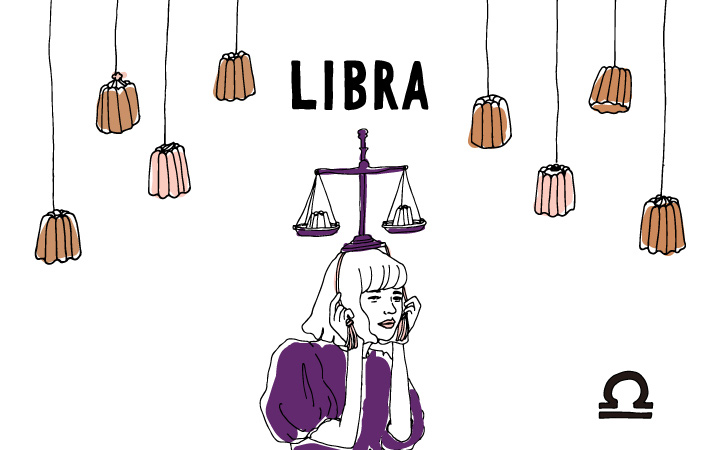食通が選ぶ、「食」の未来を考えるきっかけになる本5選
世界の美食を体験してきた食通のコラムニスト、中村孝則さんの推薦図書とともに、「食」について考えます。
おいしさの「先」を目指している外食。美食家がけん引するレストランの進化とは?

ここ10年ほど、食の流れはものすごい勢いで変化を続けています。
「美食=フランス、イタリア」という時代が長くあって、いやいや、スペインの『エル・ブリ』はすごいぞ、というところからガストロノミーの新潮流が始まり、その後、デンマークの『ノーマ』、そして今は南米ペルーの国民的人気シェフ、ガストン・アクリオと、世界の津々浦々、辺境の地にいたるまで、レストランやシェフにスポットライトを浴びるチャンスがある。
そのトレンドを牽引しているのが、私がチェアマンを務める『世界ベストレストラン50』の評議員を無報酬で引き受けてしまうフーディーズ(美食家)たち。彼らはおもしろいレストランがあると聞けば、お金と時間をかけることを厭わず、世界のどこへでも飛んで行きます。
『料理通信』編集長、君島佐和子さんは『外食2.0』で「外食は『おいしさ』の先を目指す」と書いていますが、食べたことないもの、見たことないものを求め続ける人間の欲望が、ガストロノミーを盛り上げているのです。
たとえば、『世界ベストレストラン50』のアジア版『アジアベストレストラン50』2016年度で、2年連続1位に選ばれた、タイ・バンコクのインド料理店『ガガン』。味は賛否両論、分かれますが、とにかくおもしろい。先日はコースの途中でお抹茶のセットが登場して、茶器からは真っ赤なパウダー、鉄瓶からはだしのようなものを茶碗に入れて、ばーっとお茶を点てるみたいなことをするから、何かと思ったらトマトスープ! 赤いパウダーはトマトを乾燥させたものでした。
「おいしい」「まずい」の次元ではなく、「なんだかすごいものを体験したな」という楽しみ方が食にはあって、『ガガン』では、それをおもしろがれるかどうかが問われるわけです。「おいしければ満足」という人と、「もっと楽しませて」という人。ガストロミーに対する知的な好奇心やリテラシーには、大きな格差ができていますね。
食材や生産背景、食文化へのこだわりがいっそう増している
![食材への徹底したこだわりで知られるレストラン『ブルーヒル』シェフが、10年の歳月をかけて世界中の農家、畜産家、養殖場、育種家を訪れて、現代の食のシステムが抱える問題に肉迫した一冊。持続可能な未来のための食とは?『食の未来のためのフィールドノート』著=ダン・バーバー 訳=小坂恵理 NTT出版 ¥2,600[上]・¥2,800[下](いずれも税抜)](https://precious.ismcdn.jp/mwimgs/c/1/670mw/img_c13f41e356e3b88e85656068c5473f5255744.jpg)
食材についてもそうです。たとえば、昨年期間限定で東京に出店した『ノーマ』でよく使われる、生きたアリ。私は個人的に「アリは食材として“あり”か」(笑)というのは、ガストロノミーに対する貪欲さの判断基準になると思っています。食べてみるとレモングラスのような風味で、新鮮なエビにまぶすなどするとなかなか美味。
『ノーマ』は、その絶大な影響力で北欧の食文化すら変えてしまいましたが、今やシェフは、料理を提供するだけでなく、食材や生産背景、食文化を守るといった、社会活動家のような役割も担うようになってきました。N.Y.の三ツ星シェフ、ダン・バーバーも、『食の未来のためのフィールドノート』で現代の食の問題に切り込んで話題を呼びました。
さまざまな人の視点で語られる、世界の「食」
世界中の食に関わるだれもが口をそろえて言うのが、「日本はすごい」ということ。食材、その背景の食文化、料理人、すべてのポテンシャルが高いと。
辻芳樹さんの『すごい! 日本の食の底力』は、多くの先駆者が登場する、日本の食の潮流を知るのにおすすめの一冊です。食は日本が世界と戦える、数少ない圧倒的なコンテンツだということがよくわかります。

ときに辺見庸さんの名著『もの食う人びと』で原点に回帰し、ときに平成生まれの食エッセイスト、平野紗季子さんの『生まれた時からアルデンテ』に新たな刺激を受けながら思うことは、現代は「おなかいっぱい」とか「おいしい」から進化した、食を芸術として楽しむ時代だということ。
そもそも「おいしい」とはどういうことなのでしょう。「アリはなし」だけど「生きたエビはあり」というのもおかしな話ですよね?
北欧では柑橘類が採れないので、アリを酸味として使ったのだと聞けば、風土や文化の違いと納得もできます。世界のあちこちに出かけて行って「おいしい」を考えることは、他者や、他の国を理解することにもつながる。
そう考えると、我々の食への飽くなき欲望も、平和的な交流を生む、健全なものだと思えてくるのです。
※この情報は2016年10月7日時点のものになります。詳細はお問い合わせください。

- TEXT :
- 中村孝則さん コラムニスト
公式サイト:オフィス・ダンディ・ナカムラ
- クレジット :
- 撮影/篠原宏明 文/中村孝則 構成/本庄真穂(HATSU)