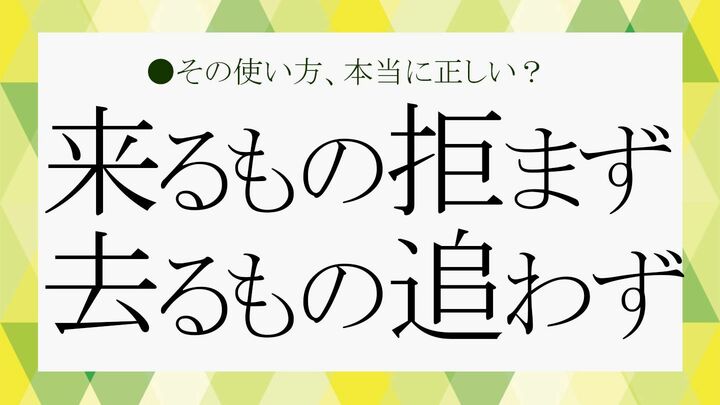【目次】
【「来るもの拒まず、去るもの追わず」とは?「読み方」と「意味」「由来」】
■「読み方」
「来るもの拒まず、去るもの追わず」は「くるものこばまず、さるものおわず」と読みます。
■「意味」
「来るもの拒まず、去るもの追わず」は「むこうからやって来る人は拒絶せず、自分から離れていこうとする人は無理に引き止めたりしない」という意味の故事成語です。「その人の自由な意志に任せる」「束縛しない」といった意味でも使われます。
■「由来」
「来るもの拒まず、去るもの追わず」は、中国戦国時代の思想家・孟子(もうし)の逸話集『孟子』(紀元前300年頃)に由来するフレーズだと言われています。孟子の弟子が盗みの疑いを掛けられたとき、孟子は「自分は弟子に関して『往(ゆ)く者は追わず、来る者は拒まず』という態度をとっているから、いろいろな人間がいてもおかしくない」と述べています。淡々として執着のない人間関係を表した言葉ですね。日本では、「来るもの拒まず、去るもの追わず」という順番で使われますが、孟子の言葉は「往く者は追わず」から始まります。
また、11〜12世紀、北宋王朝時代の文人・蘇軾(そしょく)の文章にも「来る者は拒まず、去る者は追わず」という一節があります。直接的な出典はこちらかもしれません。
■「褒め言葉」なの?
「来るもの拒まず」は、「人間としての度量の大きさ」「懐の深さ」を示す、褒め言葉として使われることがあります。一方で「去るもの追わず」のほうは、「ビジネスライクに割り切れる性格」という意味で使われることもあります。こちらは状況次第では皮肉とも取られかねませんので、少々注意が必要です。
【同じ意味になることわざ、四字熟語は?】
「来るもの拒まず、去るもの追わず」とまったく同じ意味の四字熟語はありませんが、似た意味の言葉をご紹介します。
■虚心坦懐(きょしんたんかい)
これは「何のわだかまりもない素直な心で物事にのぞむこと」という意味の四字熟語です。先入観や偏見などをもたずに「こだわりのない素直な気持ちになる」ことを強調した言葉です。
■虚心平気(きょしんへいき)
「虚心平気」の意味は「虚心坦懐」と同じで、「素直な気持ちになる」という意味の四字熟語です。実は「虚心坦懐」は、この「虚心平気」から派生し、日本で生まれた四字熟語。オリジナルは「虚心平気」だと言えますが、日本では「虚心坦懐」のほうがよく使われています。
【「英語」で言うなら?】
「来るもの拒まず、去るもの追わず」ということわざと同じように使われる英語のフレーズに、Welcome the coming, speed the parting guest.があります。これは、直訳すると、「来る客を歓迎し、去る客を送り出す」で、ホスピタリティの現場でも企業ポリシーとして掲げられます。
また、「来るもの拒まず、去るもの追わず」を素直に英訳すると[those who come are welcome, those who leave are not regretted]、直訳すると[I don’t refuse those who come, and I don’t pursue those who leave.]と表現できます。
さらに「来るもの拒まず、去るもの追わず」は、[tolerance](異なる意見や行動などを許容すること)や、〔magnanimity〕〔generosity〕(いずれも度量の大きいことを示す)という単語でも表せます。
【「言い換え」表現】
■清濁併せ呑む(せいだくあわせのむ)
「心が広く、善でも悪でも分け隔てなく受け入れる。度量の大きいこと」のたとえです。
■おおらか
「おおらか」は「心がゆったりとして、こせこせしない様子」を表す言葉です。
「来るもの拒まず、去るもの追わず」を、「心が広い」と捉えると、その「言い変え表現」としては下記のような言葉が当てはまるでしょう。
■懐が深い ■心の広い ■器の大きい ■寛容な
【「使い方」がわかる「例文」】
■1:「この勉強会は部署のしばりもないし、基本、来るもの拒まず、去るもの追わずなので、どうぞ気軽にご参加ください」
■2:「うちの会社は、来るもの拒まず去るもの追わずの社風だから、中途採用が珍しくないし、転職する人も多い」
■3:「彼はイケメンなうえに、来るもの拒まずな性格だから、あれこれと噂は多いよ」
■4:「彼女、長く付き合っていた彼と別れたみたいだけど、去るもの追わずって感じで、意外にさばさばと元気にしてるよ」
■5:「来るもの拒まず、去るもの追わずということわざは、人間味がないとか責任感がないといった意味で誤用されることもあるようだ」
【「対義語」は?】
「来るもの拒まず、去るもの追わず」の意味にぴったりと当てはまる対義語はありませんが、この言葉を「おおらか」や「こだわりがない」と捉えれば、対義語は「執着心が強い」という言葉が当てはまります。また、「心が広い」と捉えれば、その対義語としては下記のような言葉が考えられます
・了見の狭い ・心の狭い ・器の小さい ・偏狭な
***
「来るもの拒まず、去るもの追わず」は、人としての「度量の大きさ」を示す褒め言葉として使われることがありますが、その出典となる孟子の言葉を読み解くと、淡々とこだわりのない人間関係を表した、ニュートラルな言葉であったことがわかります。この点をポイントとして押さえつつ、褒め言葉として使う人の意図も理解する……これぞ「大人の語彙力」と言えるのではないでしょうか。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『デジタル大辞泉』(小学館)/『日本国語大辞典』(小学館)/『日本大百科全書(ニッポニカ)』(小学館)/『故事成語を知る辞典』(小学館)/『四字熟語ときあかし辞典』(研究社)/ 『プログレッシブ英和中辞典』小学館 :