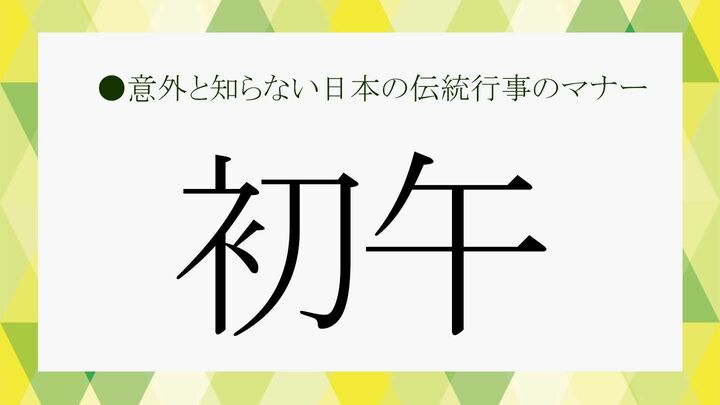【目次】
【「初午」とは?「読み方」と「意味」「由来」】
■「読み方」
「初午」は「はつうま」と読みます。「初午」の「午」を「牛(うし)」と勘違いしないようにしてくださいね!
■「意味」
「初午」は、その年の2月に巡ってくる最初の「午の日」、あるいは、「午の日」に行われる各地の稲荷(いなり)神社の祭礼を指します。では「午の日」とはなんでしょう?
子丑寅卯……と続く「十二支」の7番目が「午(うま)」。十二支獣としては「馬」になります。昔は日付を十二支に当てはめて数えていたので、12日に1度「午の日」が来ることになります。また、1年は365日か366日で、12では割り切れないので、毎年2月の最初の「午の日」である「初午」も、年によって日にちが異なります。
■「由来」
「初午」の由来は、京都の「伏見稲荷大社」にあるとされています。伏見稲荷大社は全国に約30000社あるといわれる稲荷神社の総本宮。そのため、各地の稲荷神社で五穀豊穣や商売繁盛などを祈願する祭礼が「初午」の日に行われます。
なぜこの日かというと、奈良時代の711年(和銅4年)「初午」の日に、穀物の神様である稲荷大神が、伏見稲荷大社に降臨したとされているから。ここから「お稲荷さん」でお馴染みの稲荷神社で豊作を祈る祭事が行われ、人々が参拝する習慣が始まったと言われています。また、旧暦2月は現在の3月ですが、このころは農作業を開始する時期でもあり、農神の性格をもつ稲荷と結びつきやすかったのだとも考えられます。
【何をする日?してはいけないことは?】
■何をする日?
「初午祭り」は五穀豊穣、商売繁盛を祈願するお祭りで、ここに詣でることを「初午詣(はつうまもうで)」と言います。稲荷神社では盛大に赤い幟(のぼり)が立ち、赤飯や油揚げをお供えします。稲荷神社と油揚げの関係は、稲荷大神のお使いとされるキツネの好物が油揚げであったことに由来しますよ。
■してはいけないことは?
日本全国に「初午の早い年は火事が多い」という火に関する言い伝えが多く残っています。そのため、「初午」の日はお茶を飲まない、お風呂をわかさないという地方や、消防団による見回りをする地域もあるようです。いずれも、火を扱うのを避けようとする気持ちの表れなのですね。
【お赤飯を食べるのはなぜ?「初午」の雑学】
■ お赤飯と「しもつかれ」
北関東には、「初午」をお赤飯と「しもつかれ」という郷土料理で祝う習慣があります。「初午」は農業の開始日にあたり、その年の豊作を願って赤飯でお祝いをしたのです。しもつかれは、鮭の頭とすりおろした大根やにんじん、油揚げと、節分で使った豆を酒粕で煮込んだもの。各家庭でそれぞれしもつかれをつくりますが、たくさんの家のしもつかれを食べると病気にならないと言われ、近所で持ち寄っていただくこともあるそうです。
■午前や午後に「午」が使われている理由
「午」という文字にはもうひとつの訓読みがあり、それは「ひる」。実は十二支を時刻にあてはめると、「午の刻」は正午を挟んだ2時間、午前11時から午後1時までを指します。そう、「午前」「午後」という語は、「午(ひる)」の前とうしろという意味なのです。
■「初午いなり」に「初午だんご」って!?
「初午グルメ」といえば、「初午いなり」と「初午だんご」。「初午だんご」とは、繭玉(まゆだま)に見立てた米粉のだんごのこと。蚕(かいこ)の生産が盛んな地域では、大勢に振る舞うほど「繭かき(繭から毛を除く作業)が賑やかになる」として、「初午だんご」をご近所さんに配る風習があるのだとか。これは富山県の郷土料理だともいわれています。
正月のおせち料理、七草粥、節分の恵方巻、桃の節句の菱餅(ひしもち)、端午の節句の柏餅…など、日本の伝統的な行事と結びついたものを行事食(ぎょうじしょく)と呼びますが、「初午いなり」や「初午だんご」もそのひとつ。行事食は縁起がいいとされているので、ぜひ「初午」の日には手軽に手に入るいなり寿司を食べたいものですね。
■干支についてもさくっと解説!
そもそも「干支」って何? と思っている人もいるのでは?
古代中国の天文学では、もっとも尊いと考えられていた木星が12年で天を1周することから、年ごとの木星の位置を示すために天を12等分しました。その呼称が「子(し)・丑(ちゅう)・寅(いん)・卯(ぼう)・辰(しん)・巳(し)・午(ご)・未(び)・申(しん)・酉(ゆう)・戌(じゅつ)・亥(がい)」の十二支。日本ではこれに動物の字をあて、「子(ね)・牛(うし)・虎(とら)・兎(う)・龍(たつ)・巳(み)・馬(うま)・羊(ひつじ)・猿(さる)・鶏(とり)・犬(いぬ)・猪(い)」の表記になりました。
【2025年の初午はいつ?】
2025年の「初午」は、2月6日(木)です。
2025年以降の「初午」は以下の通り。
2026年……2月1日(日)
2027年……2月8日(月)
2028年……2月3日(木)
2029年……2月9日(金)
***
「初午」の日は、一般的には特別なことをする日ではありませんが、できるものなら稲荷神社へお参りして、日々の糧に感謝したいもの。近所に稲荷神社がないという人は、自宅や職場の近くなど、行きやすい神社へお参りしてみては? たとえ「初午」と関係のない神社でも、神社詣では心が洗われるものですよ。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『日本国語大辞典』(小学館)/『世界大百科事典』(平凡社)/『デジタル大辞泉』(小学館)/『平成ニッポン生活便利帳』(自由国民社) :