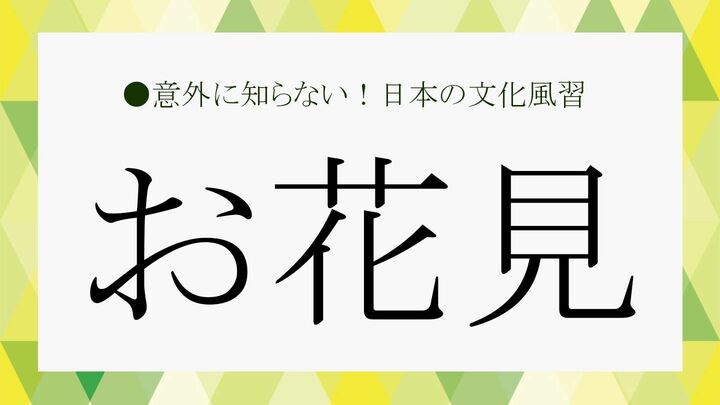【目次】
【「お花見」とは?「起源」】
■そもそも「お花見」って、何?
「お花見」という言葉から多くの人がイメージするのは、春の花、ことに「桜の花を眺めながら飲食すること」ではないでしょうか。『日本国語大辞典』でも、4つ記載されている「花見」の意味の最初に、「主として春の桜について言い、花の下で宴をはり、遊興すること」と書かれています。日本列島は南北に長く、また起伏も大きいため開花時期が一定せず、旧暦の3月3日から4月8日ごろまでの間に、全国各地で「お花見」が行われます。
■「お花見」の起源は?
「お花見」はもともと、個人の趣味や風流の行事ではなく、農事の開始に先立って、心身の汚れを取り除く物忌みを目的に、屋外に臨時のかまどを設けて飲食する行事でした。屋外での炊事が簡略化されると、家で料理したものを重箱に詰めて「花見弁当」として持って行くようになりました。
■古代・中世においては、貴族・武家の行事だった
平安時代初期からは、「花見」は宮廷貴族など貴人の遊びとしても知られ、鎌倉時代以後は武家の間でも流行したようです。当時から京都の醍醐や吉野の桜の見事さは有名で、豊臣秀吉の「醍醐の花見」は華美を極め、豪華な衣装で歌舞などの芸事をつくし、江戸時代の庶民の派手な花見の先駆けとなりました。一方、宮廷では、「花見」は節日となり、「花の宴」「花宴の節」「桜狩」などと呼ばれていました。
■江戸時代前期に一般庶民に広がった
現在、「花見」といえば、桜の花を観賞するために戸外に遊びに行くイベントを指しています。酒やご馳走を用意し、花を見ながら宴を催すことを「春の風物詩」と感じている人も多いことでしょう。このような現在のスタイルは、江戸時代、江戸や大坂、京都などの大都市を中心に発達した、庶民の花見の風俗の継承だといわれています。露地に敷物を敷いて席を設け、飲み食いをし、歌い踊って賑やかに楽しむ様子は、今も江戸時代も変わらぬ光景であったようです。
庶民に「お花見」を一気に広げたのは、8代将軍の徳川吉宗だといわれていますよ。享保元(1716)年に行った「享保の改革」の一環として、江戸郊外の飛鳥山(現在の東京・王子)に1200本余りの桜を植え、庶民向けの花見公園を開発。桜の名所として将軍自らアピールを行ったそうです。
【2025年はいつが見ごろ?】
日本気象株式会社は、3月13日に2025年第8回桜の開花・満開予想を発表しました。北海道から鹿児島までの全国約1,000か所のソメイヨシノについて、今年の開花・満開予想を行っています。
■全国的に平年並みか、平年より遅めの開花
今シーズンは全国的に平年並みか平年より遅めの開花となる地点が多くなると言われていますよ。具体的には、3月26日に東京と高知で開花がスタートし、続いて九州地方、東海地方でも開花し始める予想となっています。
2025年の主な都市の開花・満開予想日
開花予想日 満開予想日
札幌 4/27頃 5/1頃
青森 4/20頃 4/24頃
仙台 4/6頃 4/11頃
東京 3/26頃 4/2頃
金沢 4/5頃 4/11頃
長野 4/12頃 4/17頃
名古屋 3/28頃 4/5頃
京都 3/30頃 4/7頃
大阪 3/30頃 4/6頃
和歌山 3/29頃 4/5頃
広島 3/29頃 4/7頃
高知 3/26頃 4/2頃
福岡 3/27頃 4/4頃
鹿児島 3/27頃 4/6頃
■さくらの「開花日」「満開日」って?
さくらの開花日とは、気象庁が定めた標本木で5~6輪以上の花が開いた状態となった最初の日。満開日とは、標本木で約80%以上のつぼみが開いた状態となった最初の日を言います。観測の対象は主にソメイヨシノです。ソメイヨシノは江戸末期からはじまる品種で、九州から北海道の石狩平野あたりまで植栽されているといわれています。ソメイヨシノはエドヒガンとオオシマザクラの交雑種です。ソメイヨシノが生育しない地域では、ヒガンザクラ、エゾヤマザクラを観測します。
【全国の有名な「お花見」名所】
日本列島は南北に長いため各地の気温に差があるうえに、桜には野生種を含め200を超える品種があるといわれています。日本各地で開催される桜祭りや桜のお花見スポットをご紹介します。
■弘前公園(青森県)
今年は4月19日~5月5日に開催される「弘前さくらまつり」。広い公園に、まるで薄桃色の霞がかかったような光景は圧巻。観光舟に乗れば、散った桜の花弁が水面を埋め尽くす「花筏 (はないかだ)」も見られます。
■高田城址公園(新潟県)
日本三大夜桜のひとつと言われる高田城址公園の桜。約4000本の桜が咲き誇り、ぼんぼりに照らされた美しい桜とライトアップされた高田城三重櫓が堀の水面に映える様は圧巻。
■身延山久遠寺(山梨県)
久遠寺は、鎌倉時代に日蓮聖人によって開かれたお寺で日蓮宗の総本山です。境内には「全国しだれ桜10選」にも選ばれた樹齢400年の古木をはじめ多数のしだれ桜が楽しめます。
■仁和寺(京都府)
関東では桜といえばソメイヨシノがメインですが、ソメイヨシノが散ったあとに見頃を迎える「御室桜 (おむろざくら)」は、江戸時代から京都の庶民に親しまれている桜です。ぽってりとした花の姿には、はんなりとした可愛らしさが。1994年に世界遺産に登録された「仁和寺(にんなじ)」では、約200本もの御室桜が咲き誇ります。
■吉野山(奈良県)
吉野山の谷から尾根を埋める桜はおよそ3万本。標高の低い下千本(吉野駅付近)から中千本(如意輪寺付近)、上千本(吉野水分神社付近)、奥千本(西行庵付近)へと花期をずらして咲きのぼる様子は壮観です。「桜まつり」は4月11日、4月12日、3月22日(土)~4月20日(日)の期間、ライトアップが行われます。
-
■高遠城址公園(長野県)
「日本三大桜の名所」に数えられることもある長野県伊那市の高遠城址公園。タイミング次第では、信州の桜スポットでは雪に覆われた白いアルプスの山々と桜の夢の競演が見られるかも。
■造幣局 桜の通り抜け(大阪府)
「造幣局の桜の通り抜け」は、明治時代から100年以上続く大阪の春の風物詩。普段は立ち入れない造幣局の道路が、桜の開花時期の 1週間限定で一般開放されます。日本全国から集められた130種類以上の桜が、約560メートルに及ぶ通路に咲き乱れる光景は、まさに桜のトンネルです。鑑賞には専用サイトから事前申し込み(先着順)が必要です。詳しくは造幣局のホームページで案内をしていますのでチェックしてみてください。
■姫路城(兵庫県)
世界文化遺産に登録された姫路城の桜は約1000本。ソメイヨシノ、シダレザクラなど約1000本の桜が姫路城の大天守や白壁に映える景色は、「さくら名所100選」(日本さくらの会認定)にもなっています。「姫路城夜桜会」(3月28日〜4月6日、18時30分~21時予定)。
【都内の「お花見」名所】
■皇居 千鳥ヶ淵(千代田区)
気象庁の予想によると、今年の東京の満開予想は3月24日。シーズンにはライトアップされ、緑道に260 本、対岸の北の丸公園に330本もの桜が咲き誇る光景には、言葉を失ってしまいそうです。皇居のお堀に沿った歩道を歩いてみてはいかがでしょうか。
■上野恩賜公園(台東区)
江戸時代からの桜の名所として知られる上野恩賜公園。桜の本数は約800本。「秋色桜」と呼ばれる清水観音堂内のシダレザクラも有名です。桜も見事ですが人出もすごいので、平日のお出掛けをおすすめします。
■目黒川の桜(目黒区)
目黒川の目黒区エリアは、池尻大橋駅付近から約4キロにわたり、約800本のソメイヨシノを中心とする桜並木が続き、中目黒駅から上流では、左右の川岸から桜がアーチ状に川を覆います。2025年は3月29日(土)・30日(日)には、「中目黒桜まつり」と「イーストエリア桜まつり」が開催され、3月19日(水)~30日(日)の日没~20時には、ライトアップが実施されます。
■国営昭和記念公園(立川市)
豊かな自然を有する国営昭和記念公園は、春になるとソメイヨシノをはじめとする、約1500本30品種の桜が咲き誇ります。また公園内の渓流広場には、絵画のように美しく植栽されたチューリップガーデン、一番広い花畑の花の丘一面に広がる真っ赤なシャーレーポピー、そして「みんなの原っぱ」の花畑では、ネモフィラや約20品種の春の花が咲き誇るブーケガーデンなど、園内全体が春色に染まります。
【何をする?何を食べる?】
「お花見」は、桜を愛でながら美味しい食事とお酒をいただき、楽しい時間を過ごすイベント。「料理やアルコールなどの飲み物は持ち寄り」であることも多いため、「何を準備するか?」はその人のセンスを問われる重要なポイントですね。ここでは「人気のお花見料理」をいくつかご紹介しましょう。
■取り分けしやすいもの、手を汚さないものが基本
コロナ禍を経て、大皿を複数人で分けていただく料理は避けられる傾向にあります。取り箸を使えばよいのですが、状況的に難しいこともありますよね。衛生面を考慮しても、「小分けされ、ひとりひとりさっと食べやすい料理」が基本と考えるとよいでしょう。
・具の種類が豊富な「おにぎり」
・巻き寿司
・サンドイッチ
・唐揚げ
・卵焼きや唐揚げなど、おかずにしてもお酒のつまみにしても美味しくて、食べやすいもの
・三色団子
・桜餅
・桜茶
当然のことですが、宴のあとは、きっちりと片付け、出たゴミは分別して持ち帰りましょう。
***
「お花見」というイベントは、日本ならではの風習です。南北に長い日本列島の地理的な特徴と、四季に恵まれた気候の恩恵を享受した、日本人独特の美意識が「お花見」という風習を育てたのでしょう。基本的に海外では、花は歩きながら鑑賞することが多く、大人数で桜の木の下に座り、しかも飲食を伴うイベントはまれなのだとか。近年では「お花見」のマナーについて話題になることも多いのですが、私たちひとりひとりが節度を保ち、「お花見」という素晴らしい文化・風習を守っていきたいものです。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料: 『日本国語大辞典』(小学館) /『デジタル大辞泉』(小学館) /『日本大百科全書 ニッポニカ』(小学館) /『世界大百科事典』(平凡社) /気象庁HP「生物季節観測の情報」(https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/index.html) /日本気象協会HP「桜開花・満開予想 2024」(https://tenki.jp/sakura/expectation/) :