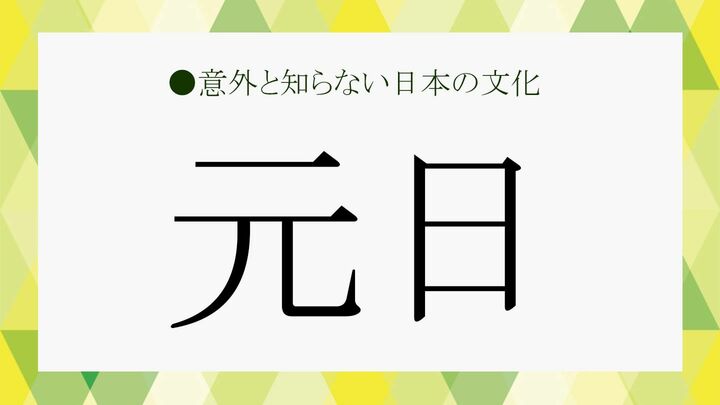【目次】
【「元日」と「元日」はこう違う!】
■「意味」
「元日」は「1年の最初の日」、つまり「1月1日」のことです。「元」という字には「いちばんはじめ」「頭」といった意味があり、「1年のいちばんはじめ=1月1日」となりました。日本では「元日」は、「国民の祝日に関する法律」で制定された「国民の祝日」でもありますね。
一方、「元旦(がんたん)」は「元日の朝」のこと。「旦」の字は、「一(地平線)」の上に太陽が現れた形をかたどっていて、「夜明け」という意味をもっています。「元日」は1月1日全体を指し、一方「元旦」は元旦は、1月1日の朝(夜明け)を指します。ここが「元日」と「元旦」の大きな違いです。
■「元日」と「元旦」。使い分けてる?
前述の通り、「元旦」は「元日の朝」を表す言葉です。ですから、「元旦の午後会おうね」とか、「元旦の朝に〜」という表現は本来、誤り。ですが、多くの人が混同して使っているのが現状です。年賀状でも、「一月元旦」と書かれているものがチラホラ。「一月」は不要ですよね。「元旦」、「元日の昼」「元日の夜」という表現であれば、間違いありません。
【結論】
・元日=1月1日(1日まるごと)
・元旦=1月1日の朝
・「元旦の午後」は本来NG
■「由来」
「元日」は本来、正月の満月の夜に、その家に福をもたらす年神さまをお迎えし、旧年の無事と豊作を感謝し、今年も同様によき年となるよう祈りを捧げる日でした。旧暦の正月15日にあたり、1873(明治6)年まで使われていた旧暦(太陰暦)の名残です。
旧暦が現在の太陽暦(グレゴリオ暦)に代わっても、この日に行われていた行事やしきたりは「小正月」として伝承され、左義長(さぎちょう/火祭り)、どんど焼き、なまはげなど、さまざまな行事が今も各地で催されています。
新年に門松やしめ飾りを門の前に飾り、鏡餅をお供えするのは、年神さまをお迎えしていた風習の名残。「明けましてめでとうございます」という新年の挨拶も、もともと年神さまへの祝福の言葉であり、人間同士の挨拶として交わすものではなかったそうです。
【元日の行事や食べ物など過ごし方】
「寝正月」という言葉もあるように、元日も含めたお正月休みは「動画を見たり、テレビのお正月特番を視聴したりしながら、家でゴロゴロ」という人も多いようです。ここでは、古くから伝わる元日の過ごし方をご紹介しましょう。
■初日の出を拝む
新しい年に幸せをもたらす年神さまは、日の出と共にやって来るとされているので、初日の出を拝むのは、とても縁起のよい元日の過ごし方。日本でいちばん早く初日の出を見ることができるのは、日本最東端にある南鳥島(東京都小笠原村)。本州では富士山山頂、そして平地では千葉の犬吠埼(銚子半島)です。冬なので日の出と言っても昇ってくるのは案外遅く、東京の2026年初日の出は6時51分です。大阪など関西では7時4~6分ごろ。初日の出がきれいに見える海岸では、けんちん汁がふるまわれるなど、新年の幕開けを祝う行事を行うところも多くあります。
人気スポットとしては、関東では東京の高尾山やスカイツリー、関西では大阪の「あべのハルカス」にある展望台がよく知られていますね。
■初詣
お正月の行事の定番といえば、「初詣」ですね。初詣では、社寺の神仏に旧年の感謝を捧げ、新年の無病息災や家内安全などを祈ります。「初詣」という言葉から、神社への参拝をイメージする人が多いのですが、お寺でもいいんですよ! 日本古来の神道には「氏神さま」という考え方があり、初詣は地域の神さまにお参りするのがよいといわれています。また、お寺なら、自分の干支の守護本尊が祭られているお寺は特に縁起がよいそうです。
■新春のごちそう
もともとおせち料理はお正月だけでなく、五節句(1月7日、3月3日、5月5日、7月7日、9月9日)などにもつくられていたハレの日の料理でした。日持ちさせる必要があったため、どちらかというと味は濃いめ。そのため、おせちを敬遠する人もいるようですが、塗りのお重に入ったおせち料理があると、食卓がパッと華やぎますよね。従来のおせちは季節の野菜や、豆腐、こんにゃく、昆布などを使った料理が中心。もともと、収穫の報告やお礼の意味を込めて神さまに供えし、大晦日にその年の神さまと一緒に食べるものとされていました。「福が重なる」といわれる重箱に詰めて保存する方法は、江戸時代に入ってからのことです。おせち料理を大晦日の夜に食べる地方も珍しくありません。
ひとつひとつの料理に意味があることもおせちの楽しいところです。例えば、黒豆はまめ(まじめ)に暮らせるように、田作りは豊年豊作を祈る気持ちを込めて、昆布は「よろこぶ」の語呂合わせ。「鯛」で「めでたい」、橙(だいだい)は代々子孫が繁栄しますようにとの願いが込められています。栗きんとんにも諸説ありますが、黄金色であることから、縁起物として加わったようです。
【年賀状に書くのは「元日」?「元旦」?どちらが正解?】
1月1日に配達される年賀状は、基本的に午前中に配達されることが多いため、元旦と書く人が多いようです。また、日本郵便は現在、1月2日の配達を取りやめています。1月1日の配達を逃すと、届くのは3日。投函が遅く、1月1日に届かない可能性が高いなら、「令和○○年正月」や、「令和○○年初春」などとしてもよいでしょう。とはいえ、現在の習慣では「元旦」や「元日」は年賀状の締めに使われる決まり文句。松の内(関東では1月7日まで。関西では1月15日までのところが多い)までに届くものであれば、「元旦」や「元日」と書くのはOKというのが、一般的な目安のようです。
***
「元旦の昼過ぎに初詣に行かない?」など、日常の会話では「元旦」と「元日」をつい混同してしまうこともありますよね。けれど、言葉の本来の意味を知り、場面に応じて使い分けられることは、大人としての教養であり、さりげない信頼感にもつながります。
同時に、周囲の言い方に過度に反応せず、柔らかく受け止められる余裕をもつことも、成熟した大人のたしなみ。正しさを振りかざすより、心地よい関係性を大切にしたいものです。
2026年の「元日」は、どんな時間を過ごしますか。忙しい日常から少し距離を置き、自分自身を整える静かな一日も、新しい一年のよいスタートになるはずです。どうぞ心身を大切に、健やかで穏やかな新年をお迎えください。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料: 『日本国語大辞典』(小学館) /『デジタル大辞泉』(小学館) /『日本大百科全書 ニッポニカ』(小学館) /『世界大百科事典』(平凡社) /『おうちで楽しむにほんの行事』(技術評論社) /『おうちで楽しむにほんのもてなし』(技術評論社) :