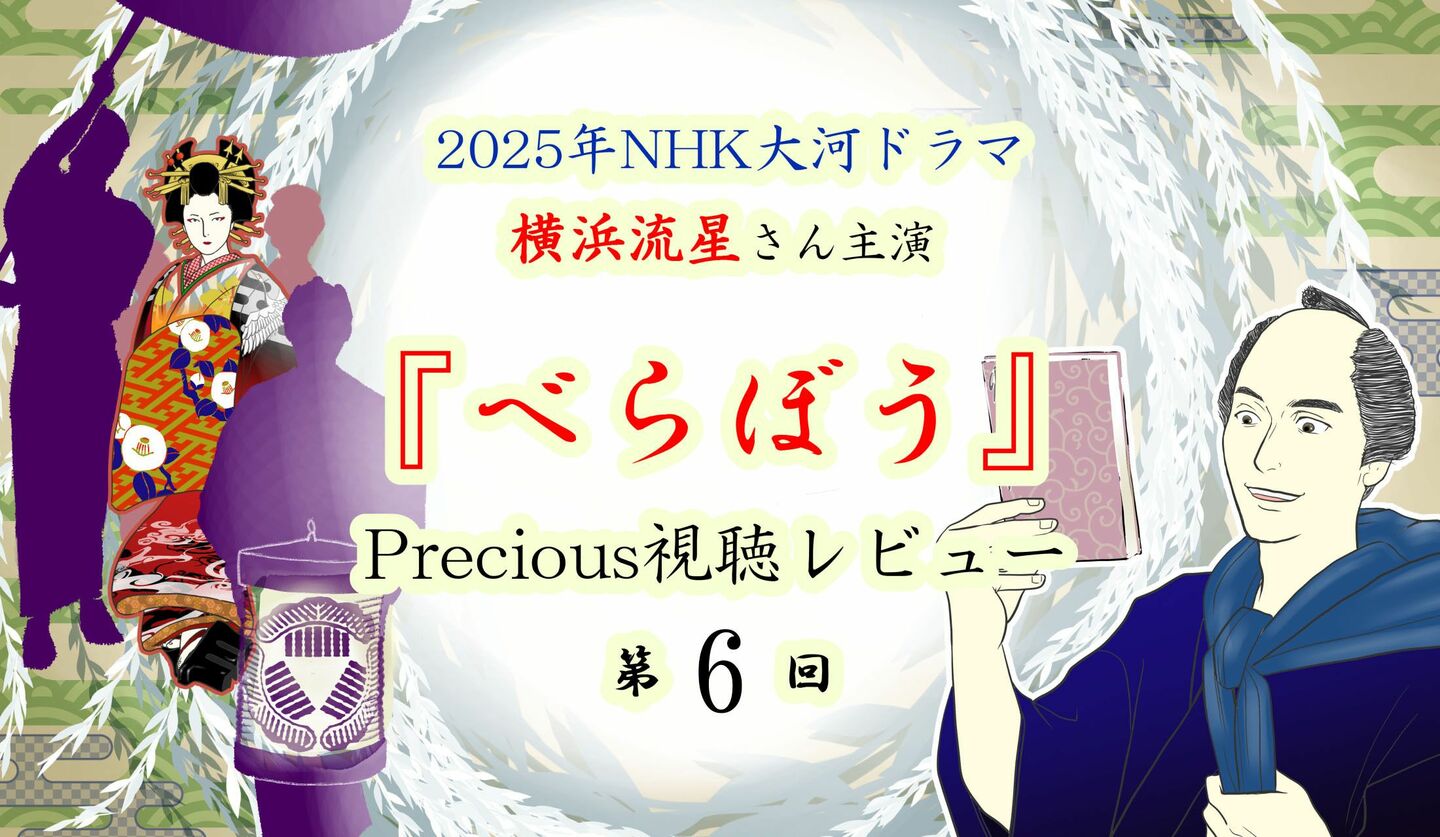【目次】
- 『べらぼう』には、現代ではほぼ見られない男性着物の魅力が満載
- お江戸のトレンドを担ったのは、町人と版元だった!
- 「金々野郎」が出現した時代背景は?
- 真っ黒な悪人も、真っ白な善人もいない、脚本の妙
- 粋な男っぷりから目が離せない!艶姿4人衆
【『べらぼう』には、現代ではほぼ見られない男性着物の魅力が満載】
大河ドラマも第6回となり、『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』の主要登場人物も大方出揃いました。ストーリー展開のおもしろさもさることながら、筆者の周りの着物民からは、「蔦重(横浜流星さん)のチラふん(チラリふんどし、ですね)姿の“いなせ”なことよ…」、「渡辺謙さんの柄物の着物の着こなしがすてきすぎて田沼意次っておしゃれだったのかもと錯覚する」「平賀源内(安田顕さん)のビジュアル再現度がすごい!」と、着物姿を絶賛する声が多数。とりわけ男性陣に注目が集まったのは、現代ではほぼ見られなくなってしまった、絞りや手描き友禅など、男性の染めの着物の多彩さに、目を奪われているからでありましょう。ということで、今回のテーマは「江戸のメンズファッション」です。当時のファッション用語とともに見ていきましょう。
【お江戸のトレンドを担ったのは、町人と版元だった!】
第6回では、鱗形屋からののれん分けを目的に、鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助さん)の元で「改(あらため/今風にいえば校閲兼エディターでしょうか)」として働くことになった蔦重。「吉原細見」の改訂に頭を悩ます彼の前を、「金々(きんきん)」にキメた若者たちが通り過ぎます。
■「金々」って?
「金々」とは、明和・安永(1764~81年)ごろの江戸の流行語です。『雛形若菜初模様』の出版は1775(安永4)年ですから、ドラマはまさにトレンド真っ只中。当世風、つまり最先端のファッションに身を包み、得意然としていることを「金々」と表現しました。「イケてる」と言われたい、「モテたい」おしゃれ男子は、「疫病本多(やくびょうほんだ)」と言われる細い髷(まげ)を結い、長い着物を引きずって歩いたのです。
■「疫病本多」とは?
「疫病本多」は、月代(さかやき/頭頂部の髪を剃った部分)を広く取り、わざと髪を減らして細くした髷を、うしろに張り出すように結ったスタイル。これは、病み上がりで髪が薄くなってしまった人のように見せるという、遊び人がとくに好んだ「攻め」の髪型でした。
■目ばかり頭巾
目ばかり頭巾とは、頭と顔全体を包み隠し、目だけを出すようにした頭巾のこと。別名「強盗(がんどう)頭巾」とも言われ、吉原では顔や身分を隠したい人が被っていました。それがおしゃれアイテムとして流行ったのです。
今風にいえば、帽子を目深にかぶり、黒いサングラスをかけて変装している人気芸能人を真似たスタイル、ですね。こういったトレンドは、当時も自意識過剰系ファッションと受け取られがちだったようで、ドラマ内で洒落者とされる次郎兵衛兄さん(中村蒼さん)も、「どっかの半可通(はんかつう)にでも教えられたのかねぇ。(吉原に)かぶって行くのが通(つう)だって」と大笑いです。
とはいえ当時、吉原では「金々」にキメた若者が「通を気取る」事態が大発生していました。「通を気取る」ということは、裏を返せば「通」に至らずということ。ドラマでも、長く引きずった自分の着物の裾を踏んづけて転んでしまったり、訳知り顔で新造(花魁付きの見習い)と花魁を間違えて花の井(小芝風花さん)をスンッとさせてしまったり。こうした、よく知りもしないのに訳知り顔をした人は「半可通」と呼ばれ、「田舎者が聞きかじりで通を気取るから…」などと、遊女たちに笑いの種を提供していたのです。
■江戸のファッションカタログ『当世風俗通』
江戸時代前期まで、衣服の装飾に贅を尽くし、その流行り廃りを享受できるのは、一部の特権階級だけでした。しかし蔦重が活躍を始めた時代、ファッションの主役は、急速に経済力をつけつつあった一般庶民、町人たちに移っていきます。そしてトレンドの発信元として人々の関心を惹きつけたのが、時流に沿った流行を収録した出版物だったのです。
『当世風俗通』は1773年(安永2年)に出版され、爆発的人気となった、おしゃれ男子向けスタイルブックです。下着から襦袢、上着に帯、キセルなどの小物まで、モテ系ファッションがこと細かく、言葉と絵で説明されていました。当然、上で紹介した「疫病本多」も紹介されています。そして、「イケてる」と言われたい、女子に「モテたい」若者たちは、こぞってこの本を読み、真似をしたのですね。
『当世風俗通』の作者は金錦佐恵流(きんきんさえる)という人物。江戸時代の作家の多くはペンネームを使った下級武士でしたが、金錦佐恵流の正体は、れっきとしたエリート藩士。実はドラマにはすでに登場済みであり、のちに蔦重のバディとなる人物なのですが…ここから先はネタバレも含みますので、また次の機会のお楽しみに。
蔦重が吉原の妓楼を回って女郎たちから集めた「金々野郎たちの逸話」は、いずれ「黄表紙」と呼ばれる本の第1号として登場してくるはず(実際には1775年の正月にはすでに出版されていたので、史実とドラマは少々違います)ですが、こちらも詳しくはまた後日。実はその作者は、『当世風俗通』の絵を描いた人なんです。くれぐれも「金々」というキーワード、お忘れなきようお願いします。
【「金々野郎」が出現した時代背景は?】
蔦重が活躍を始めた時代、政治的な実権を握った老中・田沼意次(渡辺謙さん)は、従来のコメ中心の重農主義から、商業中心の重商主義へ経済政策を転換しました。その結果、経済は拡大。一時は260年に及ぶ江戸時代のなかでも最も好景気に沸いた時代となります。『べらぼう』の舞台は、いわばそのバブル前夜。平和で好景気、世の中がどんどん豊かになっていく予感に満ちた時代…そういうとき、多くの人々が夢中になることといったら何でしょう?…そう、おしゃれと色恋ですよね。
江戸時代の町人文化は上方(かみがた/関西)の影響が濃厚でしたが、蔦重が子ども時代を贈った宝暦年間(1751〜64年)辺りから、江戸っ子独自の美意識が発達し始め、「いなせ」という新たな価値観が生まれたのです。
■「いなせ」って?
「いなせ」とはかっこよく、粋な雰囲気のこと。また、そういう雰囲気をもった男性のことを指します。漢字では「鯔背」と書き、江戸日本橋の魚河岸の若者が結っていた、魚の「いなだの背」に似せた髷の形に由来するという説が有力です。そして、当時の江戸では、“いかにも”江戸っ子らしい勇み肌の気風や容姿をもつ男性、そして、そういう雰囲気のファッションのことを「いなせ」と呼びました。
いなせな着こなしの基本は、とにかく細身に見せること。「人力」がエネルギーだった江戸時代、町には肉体労働者も多かったためか、マッチョな肉体美よりも希少価値の高い色白のやさ男がモテたのです。疫病本多が流行った背景にもそんな理由があったのかもしれません。着物も少し身幅を狭く仕立てて、スリムな男前を演出していたそう。
そして、『当世風俗通』などの大人気ぶりからもわかるように、当時、男性のおしゃれへの関心は、今とは比べものにならないくらい、強いものでした。というのも、江戸は男女の比率がかなりいびつな男社会。1721(享保6)年の男女比は男 100に対して女がわずか55 。江戸後期になるに従って男女比は均衡しつつありましたが、上流階級の男性が複数の女性を独占していたこともあり、庶民は男余りの社会で生涯独身の男性も少なくなかったのです。だから江戸では、現代以上に熱心に、女心を射止めるための努力がなされていたというわけです。
【真っ黒な悪人も、真っ白な善人もいない、脚本の妙】
さてドラマでは、「ばーっと売れて」「江戸っ子が楽しめる」青本をつくろうと、蔦重と孫兵衛があれこれアイディアを出し合います。孫兵衛の本づくりに対する熱意や愛情をしかと感じた蔦重でしたが、日本橋の中心地に店を構える大手本屋の商人、須原屋市兵衛(里見浩太朗さん)から『早引節用集』の偽板(今でいう海賊版)の話を聞き、鱗形屋が偽板に手を染めているのではという疑念を抱きます。
■『早引節用集』
『早引節用集』とは、用語や語彙を「いろは順」に集めたロングセラーの辞書のこと。人気や流行とは無関係に一定の売り上げが見込めるので、「明和の大火」(1772年。ドラマの第1回で吉原も炎上しましたね)で版木など商売道具を消失し厳しい経営状態だった鱗形屋には、喉から手が出るほど欲しい商品だったことでしょう。
鱗形屋の偽板づくりが公になれば、蔦重にとって孫兵衛に代わって版元になれるかもしれないチャンスです。須原屋に密告しようと思い立ちますが…結局、思いとどまったのは、鱗形屋の本に対する熱意や愛情は本物だったことを、知っていたから。鱗形屋も心底悪人ではない。そして疑われていて「あぶないよ」と忠告しなかった蔦重とて、清廉潔白なわけではない。最終的に鱗形屋は未来の鬼平、長谷川平蔵(中村隼人さん)によって捕らえられてしまいますが、「うまくやるってのはこたえるもんですね」と落ち込む蔦重。こんなふうに考える彼だからこそ、私たちも応援したくなるんですよね。
それにしても、見事なカモられっぷりに、SNSでは「カモ平」呼ばわりされていた平蔵さんが、キリッとした侍姿で戻ってきたのには驚きました。吉原では息で吹き払っていた「シケ(鬢がほつれてパラリと垂れた色香の素)」も封印。粟餅を「濡れ手に粟餅だ」と蔦重に差し出し、「せいぜいありがたくいただいとけ。それが粟餅落とした奴への手向けってもんだぜ」と決め台詞。視聴者が「おお、未来の鬼平が見える!」と思った直後、「いいこと言っちまったぜ」と自分に酔って薄笑いを浮かべる平蔵さん、やはりナイスなキャラクターです。
実はこの「粟餅」も、のちのち出てくるキーワードです。覚えておいてくださいね。
【粋な男っぷりから目が離せない!艶姿4人衆】
それでは最後に、粋な着物姿に注目の、艶男4人衆をご紹介。
■蔦屋重三郎のテーマカラーは緑
衣装デザインを担当している伊藤佐智子さんによると、「緑は1回では染まらない色。たやすく再現できないところが蔦重のオリジナリティ豊かな人生と重なる」というイメージから選ばれたそう。
■平賀源内の衣装は小物までおしゃれ
マルチな才能を発揮した自由人、平賀源内(安田顕さん)は、着物や帯に使われた、多様な素材やデザインが見もの。ちなみに愛用の懐紙ばさみは、源内が考案したとされる金唐革紙(きんからかわかみ)。黒一色で地紋に凝った長着など、いかにも通な装いです。ふだんは長着に羽織をはおっていますが、田沼意次を訪ねるときは袴姿になるなど、当時のドレスコードもわかっておもしろいですね。
■時代劇の大御所らしい品格にうっとり…須原屋市兵衛
須原屋市兵衛は日本橋の中心地に店を構える大手本屋の商人。演じているのは里見浩太朗さんです。里見浩太朗さんといえば、ドラマ『水戸黄門』の5代目の黄門さま。今回のドラマでも、大御所ならではの品格を備えた着物姿が眼福なのは言うまでもありませんが、「実はモード」な着こなしにも注目したいところ。
須原屋市兵衛はオランダ語が禁止されていた時代に、その翻訳本である『解体新書』を出版するほど、革新的・先鋭的な視点をもった版元でした。里見さんに伝えられた制作側のイメージは「フランスの老紳士」。格子の掛け衿に縞の長着、極細の縞の羽織と、控えめながら洒脱な着物の数々は、まさに「ボン シック(Bon chic/趣味がよくて上品)」。羽織紐にバイカラーのチェーンというセンスも見逃せません!
■『べらぼう』のおしゃれ番長は次郎兵衛さんに決定!
蔦重の義兄・次郎兵衛(中村蒼さん)は働くよりも趣味や遊びに力を注ぐタイプ。着道楽の放蕩息子で、流行りの「抛入(なげいれ)花(今でいう「生け花」ですね)」や浄瑠璃に挑戦するなど、トレンドにも敏感、という役どころなため毎回のように着替えがあり、衣装さんに「花魁役より着替えている」と言われる程だとか。ドラマでは、絞りの着物につばめの羽織、太さの異なる縞の着物と羽織の合わせなど、着物民をうならせる衣装も次々登場します。
また、セリフを言う際、「猫を抱きながら」だったり、「ぼっぺん(ガラス製の玩具。口に当てて吹くとぽんぴんと鳴る)を吹く」だったり、次郎兵衛は、当時のブームを手持ちの小道具で表現する担当も担っています。「働きすぎておかしくなっちまうから帰る」など、あちこちポンコツですが、おしゃれであることは間違いありません。当時のお金持ち町人男子の様子を味わいたい人は、ぜひ次郎兵衛に注目を!
【 次回 『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第7回 「好機到来『籬(まがき)の花』」のあらすじ】
鱗形屋(片岡愛之助さん)が偽板の罪で捕まった。この機を逃すまいと、蔦重(横浜流星さん)は今の倍売れる吉原細見をつくることを条件に、地本問屋の仲間に加えてもらう約束を取り付けます。それを快く思わないのが老舗地本問屋の方々です。西村屋(西村まさ彦さん)は、浅草の本屋・小泉忠五郎(芹澤興人さん)と別の細見をつくり、蔦重の参入を阻もうとします。細見お披露目直前まで編さんを繰り返した蔦重ですが、そこに花の井(小芝風花さん)が現れ、ある話を持ちかけて…。
※『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺』~第6回 「「鱗剥がれた『節用集』」のNHKプラス配信期間は2025年2月16日(日)午後8:44までです。
- TEXT :
- Precious編集部
- ILLUSTRATION :
- 山田シャルロッテ/新刊情報:ママトモ同志【マイクロ】 1 https://csbs.shogakukan.co.jp/book?comic_id=86946
- 参考資料:『日本国語大辞典』(小学館)/『デジタル大辞泉』(小学館)/『日本大百科全書 ニッポニカ』(小学館)/『江戸のきものと衣生活』(小学館)/『NHK大河ドラマ・ガイド べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~ 前編』(NHK出版)/『NHK2025年大河ドラマ完全読本 べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺』(産経新聞出版)/『日本髪の描き方』(エクスナレッジ)/『お江戸ファッション図鑑』(マール社)/『見てきたようによくわかる 蔦屋重三郎と江戸の風俗』(青春文庫)/『江戸の衣装と暮らし解剖図鑑』(X-Knowledge)/『一日江戸人』(新潮文庫)/『蔦屋重三郎 江戸を編集した男』(文春新書) :