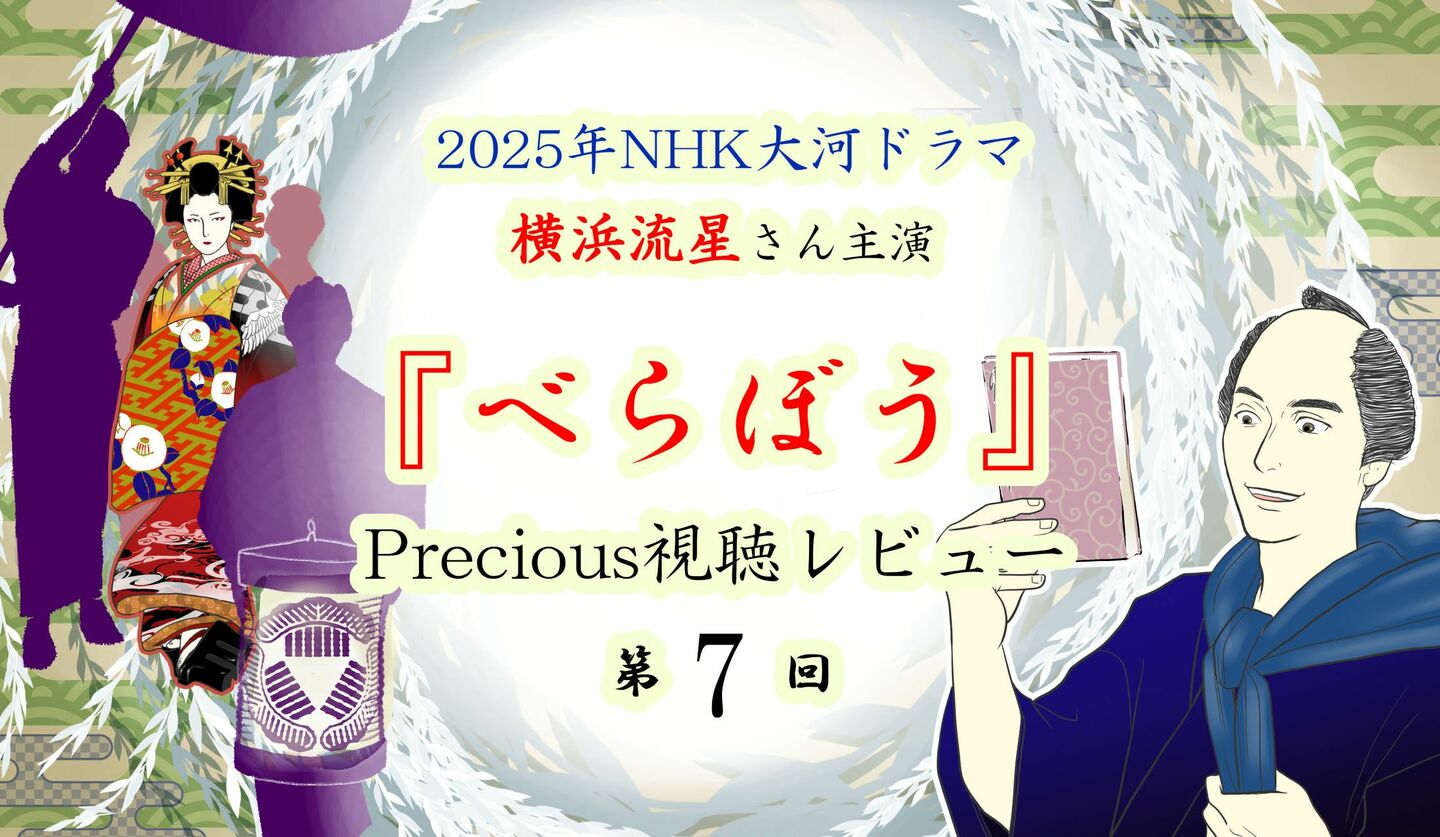【目次】
- 本格的に本づくりを始めた蔦重、「株」「版元」「問屋」などのキーワードについていけてる?
- 日本人は「本」が大好き!書物の歴史をさくっと解説
- 学術本は「書物」、蔦重が扱う娯楽本は「地本」です
- 江戸時代の出版事業の成功は「本」から「文化」の流通へ
【本格的に本づくりを始めた蔦重、「株」「版元」「問屋」などのキーワードについていけてる?】
大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』をひと言で表すなら、「江戸のメディア王・蔦屋重三郎物語」といったところでしょうか。2025年12月までの約50回の放送が予定されていて、2月16日に第7回が――ということは、すでに約7分の1が放送されているということ! 「ええっ、早い!」と感じる人も多いのでは? NHKによると「笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマ!」である本作、確かに横浜流星さん演じる蔦重のイキのよさを軸にテンポよく、物語は痛快に進んでいます。
第5回放送の「蔦に唐丸因果の蔓」で、懸命に本をつくってもその板木(はんぎ)が鱗形屋孫兵衛(うろこがたやまごべえ/片岡愛之助さん)のものになってしまうことを受け入れられない蔦重は、自ら本屋の「株」を買って「版元」になればいいのだと思いつきます。そして、本屋株を買うための知恵を得ようと、平賀源内(ひらがげんない/安田顕さん)の紹介で書物問屋(しょもつといや・しょもつどんや)の主人、須原屋市兵衛(すわらやいちべえ/里見浩太朗さん)を訪ねた蔦重。そこで本屋株の仲間に入っているのは書物問屋だけで、鱗形屋のような地本問屋に株という制度はなく、蔦重が株を買って地本問屋になる道はないと知ります。
さて、この顛末に出てきた「株」「版元」「書物問屋」「仲間」「地本問屋」は、“江戸時代の出版事情”を理解するうえで大変重要なキーワード。今回はこれらの解説と共に、江戸時代のちょっとややこしい出版事情について解説します。
【日本人は「本」が大好き!書物の歴史をさくっと解説】
日本の多くの文化や芸術は中国から渡来しましたが、書物もしかり。中国から書物が伝わって間もなくの600年代には、聖徳太子が仏教書を執筆したとされ、奈良時代には『古事記』や『日本書紀』が、平安時代には紫式部が世界初の長編恋愛小説『源氏物語』を執筆しました。これらは皇族や貴族、高僧などごく一部の特権階級の人のもの。しかも読み物を印刷する技術がなく、紙に書かれた原本を読むか、それを書写したものを読むのが一般的でした。
それを変えたのが、15世紀にドイツのグーテンベルクが発明した「活版印刷」。その技術は16世紀に宣教師たちによって日本にもたらされます。書き写すという手間なく大量に同じものをつくることができる活版印刷でしたが、日本人が使用していた文字は平仮名、カタカナ、漢字と、種類が膨大にありますね。日本語には一文字づつ組み合わせて版をつくる活版印刷より、文字を彫った板木を用いる「木版画印刷」のほうが適したというわけです。
『べらぼう』第7回で、蔦重の起死回生となる吉原本『籬(まがき)の花』の制作を手伝った小田新之助(おだしんのすけ/井之脇海さん)が、何度も何度も書き直していたのが木版画の要となる板木を彫るための「清書」です。浮世絵も木版画ですから、絵師が描くのも清書(というか下絵)。
絵でも文字でも、この清書を元に彫師が板木に彫り、摺師(すりし)が紙に刷り写して、初めて「摺り物」として完成するのです。新之助は源内と炭売りをしていた浪人(簡単にいうと武家出身の貧乏人)ですが、達筆っぷりを買われたのでしょうか。まじめに働くと読まれていたのでしょうか。
とにもかくにも、一文字ずつ書き写していた時代に比べ、木版印刷によって出版スピードは格段に上がったのです。
【学術本は「書物」、蔦重が扱う娯楽本は「地本」です】
蔦重が生まれる30年ほど前、江戸時代中期の1721年に江戸の人口は100万人を超えていたといわれています。そんな世界一の巨大都市江戸では、江戸時代後期になると5割程度の人が読み書きができたとも。当時のヨーロッパでは識字率が20%に満たなかったようなので、江戸は世界水準を大きく上回っていました。だからこそ、本をレンタルして安く楽しめる貸本業が成り立ち、蔦重も日銭を稼ぐことができたというわけです。
■蔦重が扱うのは楽しむための「地本」
蔦重が女郎屋などに持ち込むレンタル本は、「地本(じほん)」と呼ばれる娯楽本。「草紙(そうし)」ともいい、物語やハウツー本、ガイドブックなど、楽しむための本です。庶民にもわかりやすい地本は吉原でも大人気で、花の井(はなのい/小芝風花さん)やうつせみ(小野花梨さん)がいる松葉屋などで、女郎や禿(かむろ)が地本を物色するシーンがたびたび登場します。当時の地本は表紙の色でジャンルやターゲットを分けていました。
・赤本(あかほん):「桃太郎」や「猿蟹合戦」など、昔話を扱う薄赤色の表紙の本。年末に出版されることが多く、お年玉替わりに子どもに買い与えることも多かったよう。花の井がたびたび手にしている『塩売文太(しおうりぶんた)物語』も赤本で、子どものころに蔦重からプレゼントされたものでした。
・黒本(くろぼん):黒表紙の本で、歌舞伎や浄瑠璃、軍記や歴史ものを扱う大人向けの教養本。
・青本(あおほん):表紙が萌黄色(もえぎいろ/黄みを帯びた明るい緑色)で、赤本についで、黒本とともに流行。内容は黒本と同じく、歌舞伎や浄瑠璃の絵解き本。
・黄表紙(きびょうし)/世の中を風刺した大人向けの読み物。本づくり初期の蔦重が最も得意としたジャンルです。その第1号は恋川春町(はるかわこいまち)の『金々先生栄花夢(きんきんせんせいえいがのゆめ)』で、当時の世相を巧みに描写して大ヒット。『べらぼう』のサブタイトル「蔦重栄華乃夢噺」はこのタイトルを意識したものと思われます。
これらは表紙の色で分けられたものですが、吉原のガイドブックである「細見」をはじめ、遊里を舞台にした小説の一種「洒落本」や「人情本」と呼ばれる庶民の恋愛や人情の葛藤を描いた小説ジャンルなども。このあたりは、『べらぼう』で蔦重が出版人として乗ってきたころに改めて解説しましょう。
■勉強のための本は「書物」
娯楽本の「地本」に対し、学術書や歴史書、医学書、漢籍(中国の書物)などは「書物(しょもつ)」と呼ばれました。書物は主に京都で制作され、その出版業は大阪にも広まります。本屋の歴史も上方から、なのです。愛之助さんの鱗形屋も、西村まさ彦さんの西村屋も、風間俊介さんの鶴屋も、地本を扱う地本問屋。一方、里見浩太朗さんが主人を演じる須原屋は書物問屋です。
■「地本問屋」としての蔦重の才能は追い追い…
1700年代になると江戸にも多数の本屋が出現します。その多くは上方から出店した書物問屋の支店などでしたが、やがて江戸前の柔らかい内容の本を制作して卸す地本問屋が急増。そうです、「書物」は京都や大阪といった上方から運ばれてくるものですが、江戸でつくられた娯楽本は「地元でつくられた本」だから「地本」というわけ。
地本問屋は本を自ら企画し、執筆や絵の制作を依頼、でき上がった原稿を編集したのち、彫師や摺師をキャスティングして摺り上げ、製本して売る、あるいは貸本屋に卸します。地本問屋は木版印刷の心臓部である板木を所有することから「版元(はんもと)」とも呼ばれましたが、板木は売り買いも可能で、板木を所有する者は本の印刷・販売ができました。
この地本問屋が最も栄えて精彩を放ったのが、18世紀後半から19世紀半ばにかけての約100年間。のちに蔦重が経営する耕書堂は、その時代の前半のトップクラスの地本問屋だったのです。アイディアをひねり、聞き込みや取材を重ね、拝み倒して彫師に何度も修正させ…と、本づくりに情熱的だった蔦重。ビジネスパートナーである鱗形屋が海賊版制作の疑いで捕まると、自分の手中に取り込もうとする西村屋にビシッとひと言「今後は俺が版元となって細見を出します」と、地本問屋を始める宣言をしました。
■「株制度」がないなら「仲間」になればいいじゃない
書物問屋には販売権に等しい「株」という制度があり、この「株」を持たないと書物問屋にはなれません。地本問屋には株制度はありませんが、「仲間」でない蔦重は版元(地本問屋)にはなれない――ならば、俺を仲間に加えてくださいと直談判。版元の数が多くなって出版数が増え、共倒れすることを防ぐために版元の数に上限を設けるのなら、鱗形屋の検挙によってできた空席に自分が座ってもよいのでは、という理屈です。
今までの倍売れる細見をつくってみせると豪語し、吉原の親父連中にも協力を取り付けた蔦重。その情熱と活躍ぶりは、第7回放送の通りです。
【江戸時代の出版事業の成功は「本」から「文化」の流通へ】
特権階級でない一般人に出版文化がもたらされたのは、慶長年間(1596~1615年)になってからのこと。京都を発端に上方で発展した出版文化は江戸中期に江戸に広まり、上方から運ばれてくる「下り本」だけでなく江戸で「地本」を制作しました。
江戸での出版事業は、一揆や打ち壊しなどが盛んだった田沼政権の天明期(1781~1789年)に一時期停滞したものの、寛政期(1789~1801年)には復活。先行していた上方の出版界を追い越すまでに成長を遂げました。大阪では江戸制作の草紙などの地本を専門に扱う業者も現れます。文化は伝統的に西から東に流れていくものでしたが、江戸時代の出版業を通してそれが逆転。江戸の文化が上方へ、そして全国へと広まっていったのです。
そんな激動の江戸出版界のど真ん中にいた蔦重。吉原の立て直しと遊女たちへの想いは、やがて吉原のガイドブックにとどまらず、錦絵(にしきえ/多色刷りの浮世絵版画)をプロデュースし、喜多川歌麿をスター絵師に育て、謎の絵師東洲斎写楽を誕生させます。『べらぼう』が歌麿や写楽をどう描くのか。ここも本作の見どころのひとつ。今後が楽しみですね。
【 次回 『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第8回 「逆襲の『金々先生』」のあらすじ】
蔦重(横浜流星さん)が手掛けた吉原細見『 籬まがきの花』は、瀬川(小芝風花さん)の名を載せたことで評判となり、瀬川目当てに客が押し寄せ、吉原が賑わう。瀬川は客を捌さばききれず、ほかの女郎たちが相手をする始末に、蔦重も一喜一憂する。そんななか、瀬川の新たな客として盲目の大富豪、鳥山検校(市原隼人さん)が現れる。一方、偽板の罪を償った鱗形屋(片岡愛之助さん)は、青本の新作『金々先生栄花夢』で再起をかけ、攻勢に出る…。
※『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺』~第7回 「好機到来『籬の花』」のNHKプラス配信期間は2025年2月23日(日)午後8:44までです。
- TEXT :
- Precious編集部
- ILLUSTRATION :
- 山田シャルロッテ/新刊情報:ママトモ同志【マイクロ】 1 https://csbs.shogakukan.co.jp/book?comic_id=86946
- WRITING :
- 小竹智子
- 参考資料:『デジタル大辞泉』(小学館)/『NHK大河ドラマ・ガイド べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~ 前編』(NHK出版)/『蔦屋重三郎と江戸文化を創った13人』(PHP文庫)/田中優子著『蔦屋重三郎 江戸を編集した男』(文藝春秋)/伊藤賀一著『面白すぎて誰かに話したくなる 蔦屋重三郎』(リベラル新書)/安藤優一郎著『蔦屋重三郎と田沼時代の謎』(PHP新書)/山村竜也監修『蔦屋重三郎 江戸のメディア王と世を変えたはみだし者たち』(宝島社新書) :