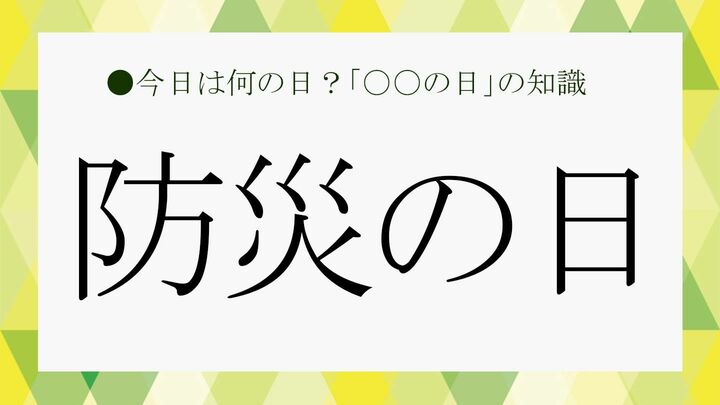「防災意識を育てる日」という記念日をご存知ですか? 東日本大震災が起きた3月11日に、私たちが日常忘れがちな防災の重要性を再認識し、家族や職場で防災について話し合い、具体的な行動を促すために設けられました。今回は「防災意識を育てる日」を中心に、防災に関する知識をまとめてお伝えします。
【目次】
【「防災意識を育てる日」とは?「意味」と「由来」】
■どんな記念日?「意味」
「防災意識を育てる日」は「3月11日」です。家族や職場などで防災について話し合い、行動してもらうことを目的に制定されました。日本で全国的な防災訓練が行われるのは、1923年9月1日に起きた関東大震災を日付の由来とする「防災の日」ですが、台風シーズンと重なることから防災訓練が中止となることもあるため、新たにこの「防災意識を育てる日」が制定されたという経緯があります。
■「誰が」決めたの?
この記念日を制定したのは、インターネットテレビやFMラジオ局を運営し、東京・渋谷の「今」と「これから」を世界へ発信する、株式会社渋谷クロスFM(Shibuya Cross-FM)です。同局ではこの日に防災特別番組を放送したり、被災地へのボランティア活動を積極的に行っています。2021(令和3)年に、一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録され、現在では同社の代表取締役社長であり、防災士でもある江﨑洋幸氏が継承しています。
■「由来」
「防災意識を育てる日」の日付は、2011年3月11日に発生した東日本大震災にちなんでいます。どの世代にとっても記憶が新しい、東日本大震災での経験を風化させないよう、震災で得た教訓を次の世代につないでいくために、この日が選ばれました。
【そのほかの防災に関連する日】
総務省統計局の「世界の統計2022」によれば、日本の国土の面積は全世界のたった0.29%です。ところが、全世界で起こったマグニチュード6以上の地震の18.5%が日本で起こり、全世界の活火山の7.1%が日本にあります。
また、全世界で災害で死亡する人の1.5%が日本、全世界の災害で受けた被害金額の17.5%が日本の被害金額となっています。このように、日本は世界でも災害の割合が高い国なのです。そのため、防災に関連する記念日は複数あります。
■3月11日は「いのちの日」でもあります
東日本大震災で失われた命の尊さを思い、命の大切さを考え、震災で学んだことを風化させることなく災害に備えようと「災害時医療を考える会(Team Esteem)」が制定したのが「いのちの日」です。災害時医療の改善を図るとともに、9月1日に防災訓練が行われるのと同様に、3月11日には健康、医療、災害時の体制などを考える機会を設けたいとの思いから制定されました。
■「おくる防災の日」も3月11日
「おくる防災の日」は、ネット販売を通じて、自然環境や人、地域に優しい社会を目指すエールマーケット(LINEヤフー株式会社運営)によって制定されました。東日本大震災の震災の記憶を忘れずに「防災用品や防災食を大切な人に贈る・送る」という「おくる防災」という習慣を、社会に根付かせることが目的です。
防災用品の備蓄保有率が向上するように、より多くの企業、団体などが自由に記念日を活かしてほしいとの想いも込められています。
■「防災の日」は9月1日
1923(大正12)年の9月1日午前11時58分、関東地方をマグニチュード7.9の大地震が襲い、死者・行方不明者14万人という大災害となりました。この日を忘れることなく災害に備えようと、1960(昭和35)年に制定されたのが「防災の日」です。
■「防災とボランティアの日」は1月17日
1995(平成7)年の1月17日に発生した阪神淡路大震災。その際、ボランティア活動が大きな力となったことから、災害への備えとともにボランティアの大切さを認識する日として、「防災とボランティアの日」が制定されました。
■「ペットも救急の日」 は9月9日
沖縄県の琉球大学地域創生総合研究棟内にある地区防災研究所が開設した、ペットBLSトレーニングセンターが制定したのが、「ペットも救急の日」です。近年、犬や猫を中心としたペットの飼育数が増加していることから、記念日を通してペットの防災や救急についての知識の普及を図り、その大切さを社会にPRすることが目的。日付は、ペットも人間と同じ家族の一員として考えることが重要との思いから「救急の日」である9月9日が選ばれました。
【2011年3月11日に発生した東日本大震災とは】
東日本大震災から14年が経ちます。記憶を風化させないために、改めてどれ程大きな災害だったのか、概要を頭に留めておきましょう。
■国内観測史上最大 マグニチュード9.0の巨大地震
太平洋側を中心に、日本列島全体が激しい揺れに襲われました。宮城県栗原市で震度7 。震度6強は宮城県、福島県、茨城県、栃木県の4県37市町村。東京23区でも最大震度5強。超高層ビルなどを大きくゆっくりと揺らす「長周期地震動」も観測され、震源から遠く離れた大阪などでも被害が出ました。九州南部や小笠原諸島でも震度1を観測。国内の観測史上最大となる巨大地震は、日本全国を揺らしたのです。
気象庁によると、マグニチュード9.0の地震は、1960年のチリ地震や2004年にインドネシア・スマトラ島沖で発生した地震などに次いで、1900年以降、世界で4番目に大きい規模の地震でした。
■継続時間3分。想定外に長い地震でした
長い継続時間も、この巨大地震の特徴でした。東北大学の地震計で観測された地震波形は、東日本大震災を引き起こした巨大地震は、過去に宮城県沖で起きた地震(1978年宮城県沖地震)と比較して、継続時間が3倍以上。断層があまりに大きかったため、大きな揺れが収まるまでに180秒(3分)程度かかりました。これは、短い時間で地震の規模を推定し、津波警報などを発表する当時の気象庁システムの想定をも上回るものでした。
■津波の高さは?
大きな被害を出した原因のひとつが、大津波です。太平洋沿岸を中心に、岩手県、宮城県、福島県、茨城県に次々と津波が押し寄せました。気象庁検潮所で確認された津波の高さは、福島県相馬市で9.3m以上、宮城県石巻市 で8.6m以上、岩手県宮古市で 8.5m以上、茨城県大洗で 4.0m。検潮所で観測できる津波の高さをはるかに超え、実際の津波の高さが観測できない事態になったところも多くあったそうです。
また国土地理院によると、津波で浸水した面積は、青森・岩手・宮城・福島・茨城・千葉の6県62市町村の合わせて561平方キロメートル。東京23区の面積のおよそ9割にあたる広い範囲でした。最大40メートルの巨大津波はなぜ起きたのか、研究は継続していますが、今も謎は残されています。
■2万人以上が犠牲に
東日本大震災では、「関連死」を含めた死者・行方不明者が2万2200人以上に上っています。東京電力福島第一原子力発電所で世界最悪レベルの事故も発生しました。
【備えておきたい防災の対策と知識】
災害は突然、襲ってくるものです。災害が発生すると、日常的な常識だけでは対処できない想定外の事態が発生するため、防災の知識こそが災害発生時や被災生活の安全性や利便性を高めます。そのため、防災に関する情報収集が重要です。
■ラップやポリ袋で洗い物が激減
被災生活を想定して、非常食を用意している人は多いですよね。でも、水の使用量が制限される災害時、食器を洗えないことが多いもの。使い捨ての紙コップや紙皿も貴重なものになります。そんなときには、食器をポリ袋で覆ってから食品を盛り付けましょう。ポリ袋とはポリエチレン製やポリプロピレン製の薄い袋のこと。最近では岩谷マテリアルの「アイラップ」の評価が高いようです。湯せんができて、解凍レンジもOK。マチ付きなので間口が広く、つがい勝手も◎。ポリ袋で食器を覆うことで、食品を盛り付けても食器が汚れません。食事が終わったら、ポリ袋をくるっと裏返すだけ。いつでも衛生的に食器を使用でき、後処理も簡単です。ラップでも代用できますよ。
また、食器そのものがない…ときにも、新聞紙や雑誌などとポリ袋を組み合わせて活用可能です。食事の際、新聞紙を箱型に折ってビニール袋をかぶせれば、お皿代わりに。新聞紙をコップの形に折り、清潔なビニール袋をかぶせればコップとしても使えます。
■懐中電灯はペットボトルでランタン代わりに
災害の発生につきものなのが、停電です。懐中電灯を用意している人も多いと思いますが、懐中電灯はスポット的な灯りなので、これだけで部屋全体を明るくするのは難しいもの。でも、ペットボトルと組み合わせることで、ルームライトにように使うことができるのです! しかも使い方は簡単! 懐中電灯を上向きに置き、その上に中身の入ったペットボトルを置くだけです。ペットボトル内で水が光を反射して部屋全体を明るく照らし、ランタンの代わりになるので、覚えておくと便利ですよ。
■ 蓄光シールを活用しよう!
蓄光シールとは、蛍光灯や太陽光などから蓄えた、光エネルギーを放出して発光する「蓄光顔料」が含まれたシールのことです。 突然の停電で慌てて行動したために、転倒して怪我をするといったアクシデントは想像以上に多いもの。部屋の出入り口や階段周辺、ドアノブ周辺などに、蓄光シールを貼っておくことで災害時役に立ちます。急に真っ暗になっても避難路を把握できるうえに、段差も確認できるため、スムーズな避難につながります。
■「ローリングストック」を意識していますか?
「ローリングストック」とは、普段の食品を少し多めに買い置きしておいて、 賞味期限を考えて古いものから消費し、消費した分を買い足すことで、 常に一定量の食品が家庭で備蓄されている状態を保つための方法です。 せっかく高価な非常食を用意してあったのに、「賞味期限切れ!」を経験したことのある人は多いはず。
もちろん、非常食を使わずに済んだことは喜ばしいことではありますが、できればムダはカットしたいもの。飲食物を備蓄する際には、定期的にチェックし、賞味期限が短いものから食事に取り入れ、新たに買い足すことで、無駄なく備蓄することができます。
■「防災バッグどこ?」という事態は絶対に避けたい!
必要な備蓄品を詰めた防災バッグは、必ず玄関横に配置しましょう。いざ災害が発生してから、押し入れに押し込んだ防災リュックを取り出すのは、想像以上の手間がかかるもの。多少見栄えは悪くても、玄関脇に防災リュック用意して、さっと抱えて外へ逃げるのがスムーズです。また、最近ではインテリアを損なわない、センスのよい防災セットも増えています。
***
東日本大震災の発生から、今年(2025年)で14年が経ちます。ひとりひとり、遭遇した条件はさまざまであっても、あのときの記憶を鮮明に持ち続けている人は多いのではないでしょうか。テレビの画面に映し出される信じられない光景……あの記憶を忘れずに、日ごろから災害に備えましょう。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『日本国語大辞典』(小学館) /『デジタル大辞泉』(小学館) /『日本大百科全書 ニッポニカ』(小学館) /一般社団法人日本記念日協会(https://www.kinenbi.gr.jp) /内閣府「防災情報のページ」(https://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h23/63/special_01.html) /国土技術研究センター「国土を知る / 意外と知らない日本の国土」(https://www.jice.or.jp/knowledge/japan/commentary09#:~:text=みましょう%E3%80%82-,外国と比べて自然災害が多い日本,%が日本にあります%E3%80%82) :