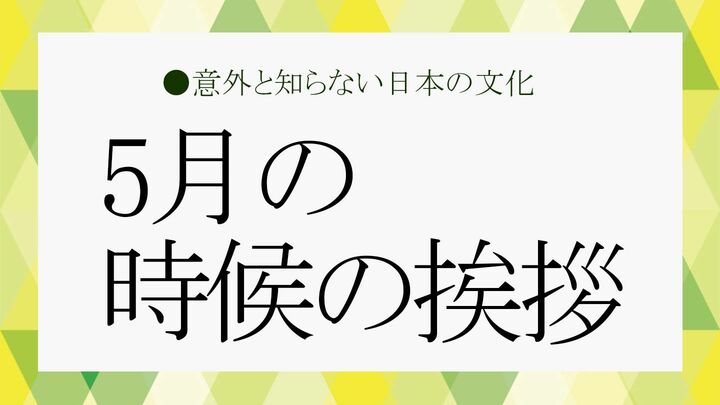【目次】
- 「時候の挨拶」とは?
- そのまま使える「5月上旬」の時候の挨拶と結びの「例文」
- そのまま使える「5月中旬」の時候の挨拶と結びの「例文」
- そのまま使える「5月下旬」の時候の挨拶と結びの「例文」
- 5月の時候の挨拶と結びの文のポイント
【「時候の挨拶」とは?】
ビジネスレターだけでなく、近況を知らせる手紙やお礼状、お祝いの便りなどの私信にも活用したい「時候の挨拶」。まずはその意味や使い方をおさらいしましょう。
■意味
「時候」は四季折々の気候や、その時々の陽気のこと。「時候の挨拶」とは、季節感やその時々の気候から感じる様子を表す挨拶です。空模様や風土、風物を表す言葉も「時候」として使えます。
■ビジネスや目上の相手には「漢語調」
時候の挨拶はざっくり分けると「漢語調」と「口語調」の2種類があり、TPOで使い分けます。
「漢語調」は短く簡潔に表現された格調高い表現のこと。かしこまった印象を与えるので、ビジネスレターやメールのほか、目上の方への私信にも使うといいでしょう。
「拝啓 青葉の候、貴殿におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます」といったように、ビジネス文書では「頭語」(「拝啓」「拝呈」など)に続く書き出しの言葉として時候の挨拶を使用します。漢語調の時候の挨拶には「春暖の候」「麗春の折」「新緑の候」「立夏の候」などがあります。
■プライベートでは「口語調」
一方、私信では、「風月麗しい季節になりました、いかがお過ごしですか」のように、やわらかな「口語調」での時候の挨拶を。プライベートで漢語調を使用すると、受け取り手に堅苦しい印象を与えたり、距離を感じさせてしまうかもしれません。
【そのまま使える「5月上旬」の時候の挨拶と結びの「例文」】
■1:惜春の候、○○さまにおかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
五月晴れの空のように皆様のお気持ちが晴れやかでありますよう、心よりお祈り申し上げます。
■2:立夏の折、ますますご清栄のことと存じます。
爽やかな風薫る好季節、貴殿のさらなるご発展を心よりお祈り申し上げます。
暦のうえでは5月5日ごろの「立夏(りっか)」までが春。5月初頭の挨拶なら、春の終わりを表す季語がふさわしいともいえ、時候の挨拶には春の終わりを表す「惜春」「晩春」「行く春」「花冷え」「暮の春」などの季語を使います。
ほかに「新茶」や「八十八夜」「蛙始鳴(かわずはじめてなく)」などもこの時期の時候の挨拶にふさわしい言葉。「蛙始鳴」は5月5日から9日ごろのことで、田んぼなどでそろそろ蛙が鳴き始めるころという意味です。「立夏」を「夏立つ」と言い換えても素敵ですね。
【そのまま使える「5月中旬」の時候の挨拶と結びの「例文」】
■1:若葉の折、皆さまにおかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます。
吹く風も夏めく季節です。貴殿のさらなるご活躍を心よりお祈りいたします。
■2:薫風緑樹のみぎり、〇〇様におかれましてはつつがなくお過ごしのことと存じます。
爽やかな5月の空のように、お気持ちもお身体も晴れやかでありますよう、心よりお祈り申し上げます。
七十二候では、5月10日から14日を「蚯蚓出(みみずいずる)」、15日から20日を「竹笋生(たけのこしょうず)」といいます。ミミズもタケノコも地上に出てくる時期というわけです。
【そのまま使える「5月下旬」の時候の挨拶と結びの「例文」】
■1:青葉の候、お障りなくお過ごしのこととお喜び申し上げます。
梅雨入り間近となりますので、十分ご自愛くださいませ。
■2:迎え梅雨のみぎり、貴殿におかれましてはますますご健勝のことと存じます。
気候の変わりやすいこの時季、くれぐれも体調にお気を付けてお過ごしください。
1年を24に分けた二十四節気は、さらに「初候」「次候」「末候」に分けられ七十二候となります。5月下旬は二十四節気で「小満」にあたり、七十二候では5月21日から25日を「小満初候」の「蚕起食桑(かいこおきてくわをはむ)」、26日から30日の「小満次候」は紅花が咲き誇る時候をさして「紅花栄(べにばなさかう)」といいます。「紅花栄よい頃合いとなりました」なんて時候の挨拶がある便りをいただいたら、紅花の鮮やかな色合いが目に浮かぶようで気持ちがあがりそうですね。
【5月の時候の挨拶と結びの文のポイント】
最後に「感じのいい時候の挨拶と結び文のコツ」を確認しましょう。
■ビジネスでは適切な「頭語」と「結語」を用いる
時候の挨拶の前に「頭語」を、結び文の最後に「結語」を用いるのがビジネスマナー。
たとえば、「拝啓 若葉の折、皆さまにおかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます。――主文――吹く風も夏めく季節です、貴殿のさらなるご活躍を心よりお祈りいたします。敬具」のようになります。
頭語と結語の組み合わせも覚えておきましょう。
・拝啓/敬具(ビジネスでも、プライベートでも)
・謹啓/謹白(対企業や対取引先や、より丁寧で相手を敬ったビジネス文書に)
■5月にふさわしい季語を用いる
5月全般に使えるもの、前半・後半、上旬・中旬・下旬など、適した季語を用いて時候の挨拶文を作成しましょう。
・5月全般:新緑の候 緑風の候
・5月前半:若葉の候、葉桜の候
・5月後半:薫風の候
・5月上旬:若葉の候、葉桜の候
・5月中旬:若葉の候、葉桜の候、立夏の候、薫風の候
・5月下旬:薫風の候、青葉の候
「候」は、「折」や「みぎり」に置き換えることができます。
■双方の環境を考慮して言葉を選ぶ
「時候の挨拶」というくらいなので季節感は重要ですが、相手との距離や環境の違いも考慮したいもの。
例えば、北海道にいる相手に沖縄の人が5月上旬に出すお礼状に「汗ばむ季節となりました、いかがお過ごしですか」とだけだったら、まだ暖房を使用している地域の人にはちぐはぐな印象を与えてしまうでしょう。
そんなときには「当方はすでに汗ばむ季節となりました。そちらは桜の開花が待たれる心弾む季節でしょうか」など、お互いの違いを示すのも上級テクです。
***
「時候の挨拶」と聞くと難しそうですが、「季節感を盛り込んだ気持ちのいい文章」を心がければ大丈夫。「拝啓/敬具」などの頭語と結語を用いれば、ぐっとフォーマルな印象になりますよ。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『和の暦手帖 二十四節気と七十二候を愉しむ』(だいわ文庫)/『デジタル大辞泉』(小学館)/『今日から役に立つ! 使える「語彙力」2726』(西東社)/『決定版 すぐに使える! 教養の「語彙力」3240』(西東社) :