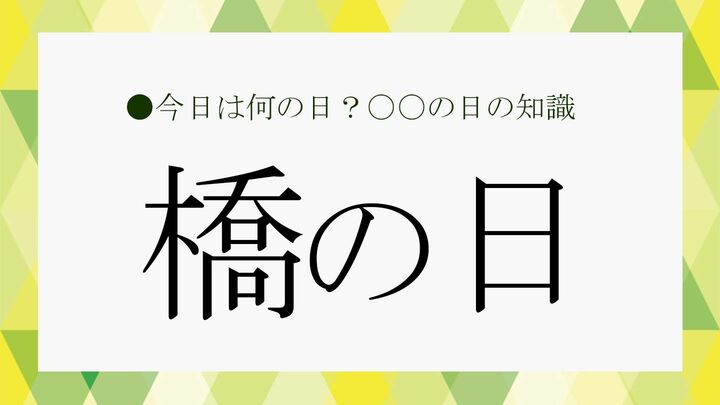【目次】
【「橋の日」とは?由来】
■「いつ」「誰が」決めたの?「由来」は?
8月4日の「橋の日」は、1985年に宮崎市在住で、宮崎「橋の日」実行委員会顧問の湯浅利彦氏が提唱した、宮崎発の啓発デーです。清掃活動や稚魚の放流といったPRイベントを宮崎市内から始め、1994年に一般社団法人 日本記念日協会から認定・登録されています。日付は「84(はし)」の語呂合わせから。
■「目的」は?
「橋の日」は、郷土のシンボルである河川と、そこに架かる橋を通して、ふるさとを愛する心と河川の浄化を図ることを目的としています。1986年に延岡市にて「第1回橋の日イベント」が実施されて以降、2015年には全国47都道府県でイベントが実施されるまでに普及し、記念日文化功労賞を受賞しました。現在、その活動は全国の都道府県に広がっています。
【ビジネス雑談に役立つ「橋」の雑学】
■「橋」の定義を知ってる?
「橋」とは、道路、鉄道、水路、パイプラインなどが、河川や湖沼、海峡、凹地や他の交通路などの上を乗り越えるために建設される各種の構造物の総称です。橋梁 (きょうりょう) とも言います。
■世界で最も古い橋は?
現在も使われている橋の中で最も古いと言われている橋は、紀元前1世紀(BC62年)に建設されたと伝えられる、イタリアの「ポンテファブリチオ(Ponte Fabricio)」です。ローマのテヴェレ川に、今から約2000年以上も前に架けられており、構造は2連の石造アーチ橋です。アーチとアーチの間には小さな穴があいていて、橋の重さを軽くしたり、洪水のときに水圧を減らしたりする役目があるそうです。

■日本最古の橋は?
長崎市にある眼鏡橋です。1634年につくられた2連の石造りアーチ橋で、橋のアーチが川面に反射することで、メガネのように見えることから眼鏡橋といわれています。

■橋には入り口と出口があるって知ってた?
橋の欄干には、必ず橋の名前が書かれています。これは「橋名板」と呼ばれていますが、ひらがなの橋名板と漢字の橋名板があることをご存知でしたか? 実はこの違いが橋の入り口と出口を示していて、入り口は漢字、出口はひらがななんです。正式には、入り口、出口というよりは、道路の起点側、終点側という意味合いとなっていて、河川名や竣工年月日をつける位置まで、ひとつひとつの場所がこと細かに定められています。
■世界一長い木造の橋は?
静岡県島田市の大井川にかかる蓬莱橋(ほうらいばし)です。全長897.4メートル、通行幅2.4メートルの木造歩道橋で、現在も農道として利用されており、貴重な歴史的土地改良施設として県内外から多数の観光客が訪れています。1997(平成9)年12月30日には「世界一の長さを誇る木造歩道橋」として、イギリスのギネス社に認定されました。「長い木=長生きの橋」、「全長897.4(やくなし=厄無し」の語呂合わせでも知られ、縁起のいい橋として人気があります。

■日本三名橋は?
諸説ありますが、一般的には東京都中央区の日本橋、山口県岩国市の錦帯橋、そして上で紹介した長崎県長崎市の眼鏡橋といわれており、いずれも江戸時代に架橋されたものです。眼鏡橋は前述の通り、日本最古の橋。錦帯橋も1674年建造で独特の形状の3連の石造りアーチ橋です。
そして日本橋は、1603年の江戸開府直後に架けられて以降、五街道の起点、江戸の表玄関として知られています。とはいえ、現在の日本橋は木製の人道橋から石造りアーチの国道橋に変わり、しかも高速道路の高架下。風景としては少々残念ですね。
***
8月4日は「橋の日」です。記念日制定から30年。節目の年である2015年に、唯一の未実施県だった滋賀県でイベントが開催され、「全国制覇」を達成しました。ふるさとの河川はいつまでも美しくあってほしいものです。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- PHOTO :
- GettyImages