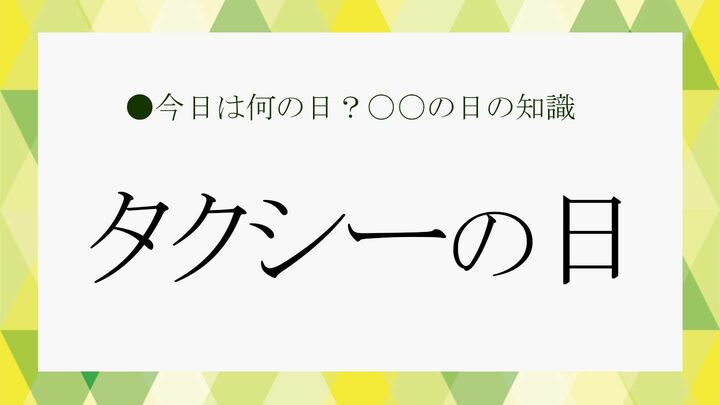【目次】
【「タクシーの日」とは?由来】
■「いつ」「誰が」決めたの?
8月5日は「タクシーの日」です。この記念日は全国乗用自動車連合会(現・全国ハイヤー・タクシー連合会)が、1989年に制定し、全国各地でキャンペーンを実施しています。
■日付の「由来」と「目的」は?
「タクシーの日」の由来は1912(大正元)年の8月5日に、日本初のタクシー会社であるタクシー自働車株式会社が営業を開始したことに由来します。
【ビジネス雑談に役立つ「タクシー」の雑学】
■「タクシー」の定義は?
「タクシー」は、英語「タクシーキャブ[taxicab]」の略称です。専用の乗り場や路上で、あるいは呼び出しにより、客の求めに応じて営業する旅客自動車運送事業の一種。タクシーという名称は世界の多くの国々で使用されています。
■日本のタクシーの歴史はわずか6台からスタートした!
日本初のタクシー会社である「タクシー自働車株式会社」は、1912(大正元)年の8月5日、麹町区有楽町(当時)の数寄屋橋付近(現在の有楽町マリオンの地点)に設立されました。当初はフォード6台でスタートし、上野と新橋に営業所ができました。
このタクシーがそれまでのハイヤー(完全予約制の運転手付きの貸し切り自動車)と異なる点は、料金算出にタクシーメーターを採用したこと。当時のタクシー料金は最初の1マイル(約1,600m)が60銭、加算料金は1/2マイル増すごとに10銭、待ち料金は5分ごとに10銭、深夜・雨天・ぬかるみ(泥濘)の際は1/4マイルごとに10銭増しとなっていました。
山手線の初乗り料金が5銭だった当時、タクシーの初乗り料金60銭はかなりの高額といえます。しかし、正確なメーター器による料金算出という目新しさから、利用者の人気を博したそうです。
■「助手席」はタクシー用語?
「助手席」が「運転席の隣の席」を指すことは、皆さんご存知ですよね。実はこの「助手席」という言葉、もともとは大正時代に生まれたタクシー業界用語だったのです。当時は着物の客が多く、乗降を手助けする人が必要でした。運転手の隣に座るその係員は『助手さん』と呼ばれ、のちに『助手席』という言葉だけが残り、一般にも広まったそうです。
■タクシーが自動ドアになったのはいつ?
現在、日本のタクシーはリアシートのドアは自動開閉するのが当たり前となっていますが、タクシー営業がスタートした当時は手動でした。手動のドアは運転手が開閉するのが一般的で、乗客の乗降時に運転手が毎回車から降りてドアを開け閉めする必要がありました。
タクシーの自動ドアが開発されたのは1950年代後半のこと。普及するまでに少々時間がかかった理由のひとつは「自動ドアは贅沢だ」という考えがあったため。タクシーの自動ドアが普及したきっかけは1964(昭和39年)に開催された「東京オリンピック」でした。日本のおもてなしをアピールするために、タクシー会社各社が自動ドアを導入。乗客へのサービス向上や運転手の負担軽減、安全対策として、普及していったそうです。
■「表示灯」の言葉の種類、いくつ知ってる?
街を走っているタクシーをつかまえたいとき、私たちは表示灯に赤く光る「空車」の文字を目安にタクシーを探しますよね。では、表示灯の言葉の種類、いくつあるかご存じですか? 正解は8つ。路上で流しのタクシーを捕まえるとき、「人が乗っていないのに停まってくれない…」と不思議に思ったことのある人は、ぜひ表示灯の種類を確認してみてくださいね。また、点灯していない場合は通常料金での実車中です。
空車:乗客がない状態
回送:乗車を受けられない状態(運転手の休憩、給油、営業終了など)
迎車:指定の場所に迎えに向かっている状態
割増:割増運賃で運転している状態(主に深夜や早朝など)
貸切:一定時間の貸し切り運賃にて乗車している状態
予約車:乗車予約を受けている状態
救援:救援事業を行うために走行する状態(買い物代行、薬の受け取りなど)
代行:タクシーが運転代行のサービスをしているとき
■タクシー深夜の料金は何時から何時まで?
深夜料金とは、通常のタクシー運賃に追加される割増料金のこと。一般的に夜間の特定の時間帯に適用されます。日本国内では、通常22時から深夜5時までの時間帯を深夜料金の対象とすることが多いのですが、地域によって適用時間、割増率が異なります。
■ビジネスパーソン必見の席次マナーは…
上司や取引先と一緒にタクシーに乗る際、どこに座るべきか迷ってしまうことがありますよね。一般的にタクシーの席順は、タクシー後部座席の運転手側が最上席とされ、次いで後部座席中央、助手席側の順となります。最下位は助手席です。
■タクシードライバーになるための資格は?
タクシードライバーとして乗務するためには、普通第二種免許が必要です。普通第二種免許取得のための試験を受けられる条件は、21歳以上で普通第一種免許を取得しており、運転歴が通算3年以上であること。あるいは、年齢が19歳以上21歳未満であっても、一定の教習を受講することを前提に、普通第一種免許等を取得していた期間が1年以上が経過していること、です。なお、公安委員会が指定した教習所の卒業生については、2年経過で受験が可能となる特例があります。
現在、東京都内のタクシー車両のほとんどすべてが、AT車(オートマ車)になっているため、AT限定普通第二種免許を取得していればOKです。また、自分のペースで仕事ができることから、年々、女性ドライバーも増えているそうです。
■タクシーに関連するほかの記念日は?
・個人タクシーの日
個人タクシーの日は12月3日。1959(昭和34)年のこの日に173名の個人タクシー第一次免許者が誕生しました。2009年、50周年を迎えたことから、一般社団法人全国個人タクシー協会が制定しました。個人タクシーを開業するには、65歳未満であること、タクシー、ハイヤー、バスなどの運転経験が10年以上(特例あり)あること、3年間など、申請日以前の一定期間無事故無違反であることなど、複数の条件があります。
・タクシーサイネージの日
タクシーサイネージの日は、4月1日。動画マーケティングを中心とした、広告事業を展開する株式会社ニューステクノロジーが、サービスを開始した2019年4月1日にちなんで制定した記念日です。
タクシーサイネージとは、タクシーの助手席のうしろなどに設置されたタブレットを通して配信される動画広告のこと。「サイネージ[Signage)」とは、建物や公共の場にある看板や標識といった意味の言葉です。
***
8月5日は「タクシーの日」です。日本のタクシーが、わずか6台からスターとしたとは驚きですね。1912年当時の山手線の初乗り運賃が5銭で、タクシーの初乗り料金は60銭だったそうですから、料金の違いは12倍。現在、山手線の最低運賃は150円(IC運賃は136円)なので、初乗り料金は1800円相当だったという計算になります。確かに高額ですね! 6台しかない稀少なタクシーは、いったい誰を乗せて走ったのでしょうか。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『デジタル大辞泉プラス』(小学館) /国土交通省「タクシーの日」(https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/press/pdf/jikou2023071901.pdf) /東京ハイヤー・タクシー協会(https://taxi-tokyo.or.jp/taxiday/index.html)/ケイサンタクシー「お役立ちブログ」(https://www.keisantaxi-2021.com/blog/) :