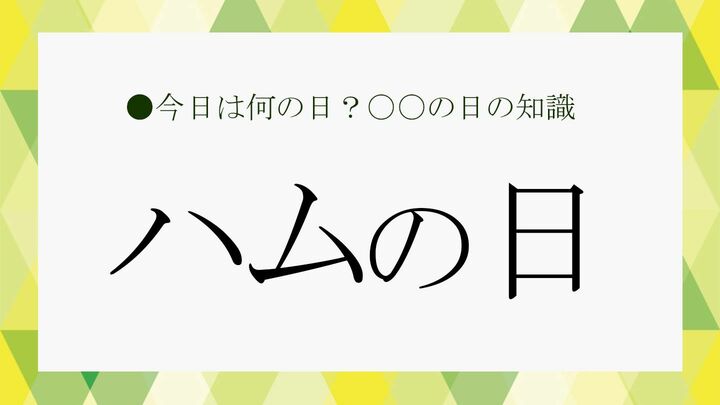【目次】
【「ハムの日」」とは?由来】
■「誰が」決めたの?
8月6日は「ハムの日」です。「ハムの日」は、ハムやソーセージ、ベーコンなどの食肉加工品を製造するために必要な資材の斡旋、製造機械のリースなどを手がける「日本ハム・ソーセージ工業協同組合」が制定しました。
■「由来」は?
日付の由来は…おわかりですよね? 「ハ(8)ム(6)」と読む語呂合わせから、です。
【ビジネス雑談に役立つ「ハム」の雑学】
■そもそも「ハム」って何?
「ハム」は、 豚肉をかたまりのまま、塩漬けしてつくられた加工食品の総称です。割合としては燻製(くんせい)したものが多いのですが、燻製していないものもあります。英語の[ham]は本来、もも肉の骨付きでしたが、現在ではボンレスハムをはじめ、ロースハム、生ハムや、そのほかの畜肉・魚肉などを使ったプレスハムもあります。
■ハムはいつからあるの?
狩猟が盛んだった時代に、肉を塩漬けすることで長く保存ができることを古代の人が知ったのが、ハムやソーセージの始まりといわれています。ギリシアでは、1000年ごろにはすでに、肉を薫煙や塩漬けにしたハムの原形のようなものが確認されており、遠征軍の携帯食として用いられていたとされています。
一方で、日本では肉食そのものが一般化したのが、明治以降のこと。そのため、ハムをはじめとする肉加工品の発達も遅く、日本でのハム製造は1872(明治5)年に長崎の片岡伊右衛門がアメリカ人ペンスニから製造法を学び、製造を開始したのが最初とされています。
大量生産されて広く一般に食べられるようになったのは、第二次世界大戦後のことです。1960(昭和35)年ごろには、一般家庭の食卓にものぼりはじめました。
■種類を簡単に説明すると…
・ロースハム……豚の肩から腰にかけてのロース肉を使ったもの
・タッソハム、ショルダーハム……肩肉を使ったもの
・ボンレスハム……もも肉を使ったもの
・ベリーハム……バラ肉を巻いてつくったもの
・生ハム……製造工程において、加熱や煮沸などの処理を行わないものを日本では「生ハム」と呼ぶことが多い
■ハムとソーセージ、ベーコンの違いを知ってる?
ハムとソーセージ、そしてベーコンは、どれも基本的には「塩漬けされた肉」。ですが、その違いは加工方法です。ソーセージは塩漬けした肉を挽肉にし、練り合わせたもの。ベーコンは塩漬けした肉の塊をそのまま燻煙したもの。そしてハムは、燻煙してからさらにボイルされてつくられます(生ハムや骨つきのハムなど、ボイルをしないでつくるものもあります)。日本に上陸したのは、ハムがいちばん早かったといれていますよ。
■「ハム」がお中元・御歳暮の定番なのはなぜ?
主な理由は3点、考えられます。まずひとつめは、ハムは加工食品の中でも賞味期限が長いものだから。賞味期限が長ければ、贈られた人が慌てて使う必要がありませんね。
ふたつめは、人に食べ物を贈る際には、好き嫌いが心配になるものですが、ハムは比較的誰からも好まれやすく、大人から子どもまで万人受けする食べ物であること。そして3つめは、加工されたハムはそのまま食べても美味しいため、切って食卓に出すだけでおかずの1品になる手軽さです。また、サラダやスープ、サンドウィッチやハムエッグ、お弁当のおかずなど、タンパク質として、幅広いメニューに使える便利な食材ですよね。
■世界三大生ハムは?
・プロシュート・ディ・パルマ
北イタリアのパルマ地方でつくられる最高級の生ハム。控えめな塩気とまろやかな味わいが特徴。10か月以上の乾燥、熟成機関を経ては製造され、パルマのロゴ入り王冠マークの焼き印が押されます。メロンのような甘味の強い果物との相性は抜群。
・ハモン・セラーノ
スペインでつくられる生ハム。「ハモン=ハム」、「セラーノ=山」という意味。寒冷な空気の中で最低9か月以上熟成され、噛み応えと強い塩気が特徴です。
・金華ハム
中国の生ハム。黒い頭で白い体の「金華豚」と呼ばれる特別な豚のみが使用され、表面にラードを塗ったあと1年以上熟成してつくられます。しっかりした塩味と固い肉質が特徴で、スープや蒸し物にして食べられます。
■「ハム」にまつわるほかの記念日は?
・生ハムの日
一般社団法人日本生ハム協会が制定した記念日です。生ハムの普及と、その美味しさと食文化をPRするのが目的。日付は、生ハムの生産が盛んなスペインの収穫祭「サン・マルティンの日」である11月11日。「サン・マルティンの日」には、豚を加工して生ハムをつくる習慣があることに由来します。
***
8月6日は「ハムの日」です。厚切りのロースハムを豪快に焼いたステーキは、手軽につくれるご馳走として人気です。ハムは加熱処理がしてあるので生焼けの心配がないのも魅力。同量の粒マスタードとマヨネーズでつくったソースを添えていただくのも、おすすめです!
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『デジタル大辞泉』(小学館) /『日本大百科全書 ニッポニカ』(小学館) /明宝ハム(https://www.meihoham.co.jp) :