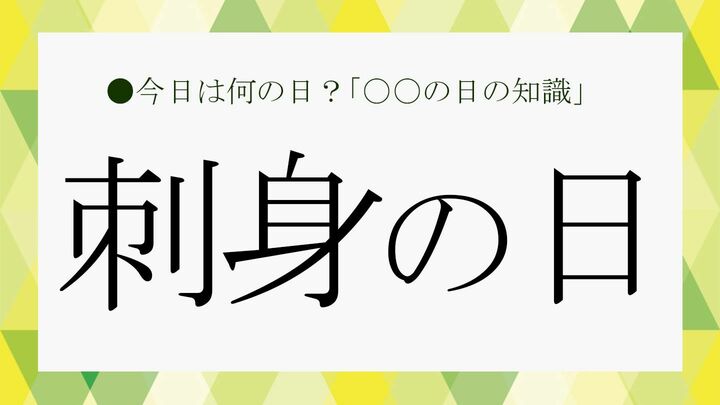【目次】
【「刺身の日」とは?由来】
■「由来」は?
8月15日の記念日として真っ先に思い浮かぶのが「終戦の日」ですよね。戦没者を追悼し、平和を祈念するこの日は「刺身の日」でもあります。
なぜ8月15日が「刺身の日」とされたのか…。日付の由来として有力なのは、室町時代に外記局官人を務めた中原康富(なかはらのやすとみ)の日記『康富記』です。1448(文安5)年8月15日に、現代と同じような刺身の描写があり、「鯛なら鯛とわかるやうにその魚のひれを刺しておくので刺し身、つまり『さしみなます』の名の起り」と書かれています。わかりやすく言うと「魚をさばいて切り身になってしまうと、魚の種類がわからなくなってしまうため、その魚のヒレを近くに刺して目印としたことが、“刺身”という名前の起源だ」ということです。この記述を刺身とゆかりのある日とし、8月15日が「刺身の日」に選ばれたのではないか…といわれています。
■「誰が」「いつ」決めたの?
「刺身の日」を誰が、いつ制定したのかについては、はっきりしたことはわかっていません。しかし、夏のこの時期になると、鮮魚店やお寿司屋さんでキャンペーンが行われたりすることから、しだいに浸透していったようです。
【ビジネス雑談に役立つ「刺身」の雑学】
■そもそも「刺身」の定義を知ってる?
「刺身」とは主に、新鮮な魚介類などを、生のまま薄く小さく切り、醤油やわさびなどをつけて食べる料理を指します。「おつくり」「つくりみ」ともいいます。魚介類のほか、馬刺しやレバ刺し、こんにゃく、ゆばなどの素材を生や冷たい状態で切って刺身として提供したものも「刺身」と呼ばれていますね。ちなみに「寿司」は、生の魚介類や発酵させた魚などを、酢飯などと一緒に食べる料理のことです。ご存知ですよね!
■「切った魚」がなぜ「刺身」と呼ばれた?
刺身という名前の由来については前述の「切り身の種類がわかるようにヒレを刺した」という説のほかに、武家社会であった当時は「(魚を)切る」という言葉が「切腹」や「縁切り」を連想指せる忌み言葉であったため、「刺す」という言葉を使用したとも言われています。
■刺身と香辛料
江戸後期から現代に至るまで、刺身と適切なつま、そして香辛料は切っても切れない関係にあったようです。1643(寛永20)年刊の料理本『料理物語』のなかではすでに、「指身」と見出しをつけて香辛料の選び方を明示しています。たとえば、「スズキは……あおず、しょうがずにてよし」、「マナガツオは……いり酒、しょうがずにてもよし」、「クジラは……うすくつくり候て、にえ湯をかけ、さんしょうみそずにてもよし」などなど。
このほか、キジ、カモなどを刺身にするには湯煮して用いることなどが明示されています。そして刺身には「あしらい」と呼ばれる添え物がつきもので、これを分類すると、けん、つま、薬味の3つに分けられます。ダイコン、キュウリ、ウド、海藻などは「けん」、葉ジソ、タデの葉、ボウフウなどが「つま」、薬味はワサビ、ショウガなどがあてはまります。
■刺身の歴史
刺身が一般に広がったのは、江戸時代の江戸だったといわれています。江戸時代の風俗などが記された類書『守貞漫稿(もりさだまんこう)』には、カツオとマグロを売る屋台の「刺身屋」が繁盛したと記されています。
実は江戸時代の中期までは、マグロは煮るか焼くか、塩漬けで食べるのが一般的でした。江戸時代後期になって、醤油漬けのマグロを生食するようになったところ、その味が評判となって刺身文化が広がり、「刺身屋」のようなお店が繁盛するようになったそうです。
このように、江戸時代にはマグロやカツオの生食が広がったのですが、当時はも完全な生ではなく醤油漬けがメインでした。冷蔵設備や冷凍技術の進歩と普及、流通の発達に伴い、日本全国で新鮮な刺身が食べられるようになったのは、明治時代以降のこと。とはいっても大正時代ごろまで、完全な生の刺身として食されたのは主にヒラメやタイのような透き通った魚で、サケやイカなどのように寄生虫がある魚は生食できませんでした。
そして、大正時代以降、冷凍技術がいっそう発達したことによって、多くの魚介類が生食できるようになり、刺身文化は大きく発展していきました。
■覚えておきたい! 「刺身」の注意点
海の幸である魚には、一定の割合で寄生虫がいるものです。必ず注意すべきは、ホタルイカや川魚のように、そもそも生食NGとされている魚種。しかし、サバやアジ、イワシ、ヒラメ、マダイなどには、アニサキスなどクドアが寄生している場合があり、食べると食中毒を引き起こします。寄生虫は加熱と冷凍で死滅するので、生で食べる場合には、いちど冷凍されたものを選ぶのが安全です。
■上手な冷凍の仕方は?
アニサキスが心配で食中毒を予防したい場合、あるいはまとまった量の魚をいただいたときなど、上手な冷凍の仕方をご紹介しましょう。
実は冷凍した魚が劣化する大きな原因は、冷凍焼け(酸化と乾燥)です。冷凍焼けを防ぐためには、できるだけ魚を空気に触れない状態で冷凍すること。たとえば、コハダなどの青魚は、さばいたあと、塩で少し身を締めてから酢につけ、ジッパー付きのプラスチックバッグなどに入れて、しっかり空気を抜くのがいちばん。お酢をちょっと多めにして、空気がない状態を作り出すのがポイントです。
解凍は、袋で密封された状態のまま20〜30秒間、表面を水に当てて流水解凍します。その後、30秒~1分おいて表面が溶けたら、中が凍っているぐらいで切って、盛り付けるのがコツです!
***
8月15日は「刺身の日」。海外では生食文化になじみのない国が多いものですが、「刺身」は世界でも群を抜いて高い衛生管理レベルを保つ日本だからこそ楽しめる料理です。特に毎日の暑さに食欲も減退しがちなこの時期、さっぱりとした「刺身」でお食事はいかがでしょう。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『日本国語大辞典』(小学館) /『デジタル大辞泉』(小学館) /『日本大百科全書 ニッポニカ』(小学館) /『世界大百科事典』(平凡社) /寿司ウォーカー(https://sushiwalker.com/feature/85725/) :