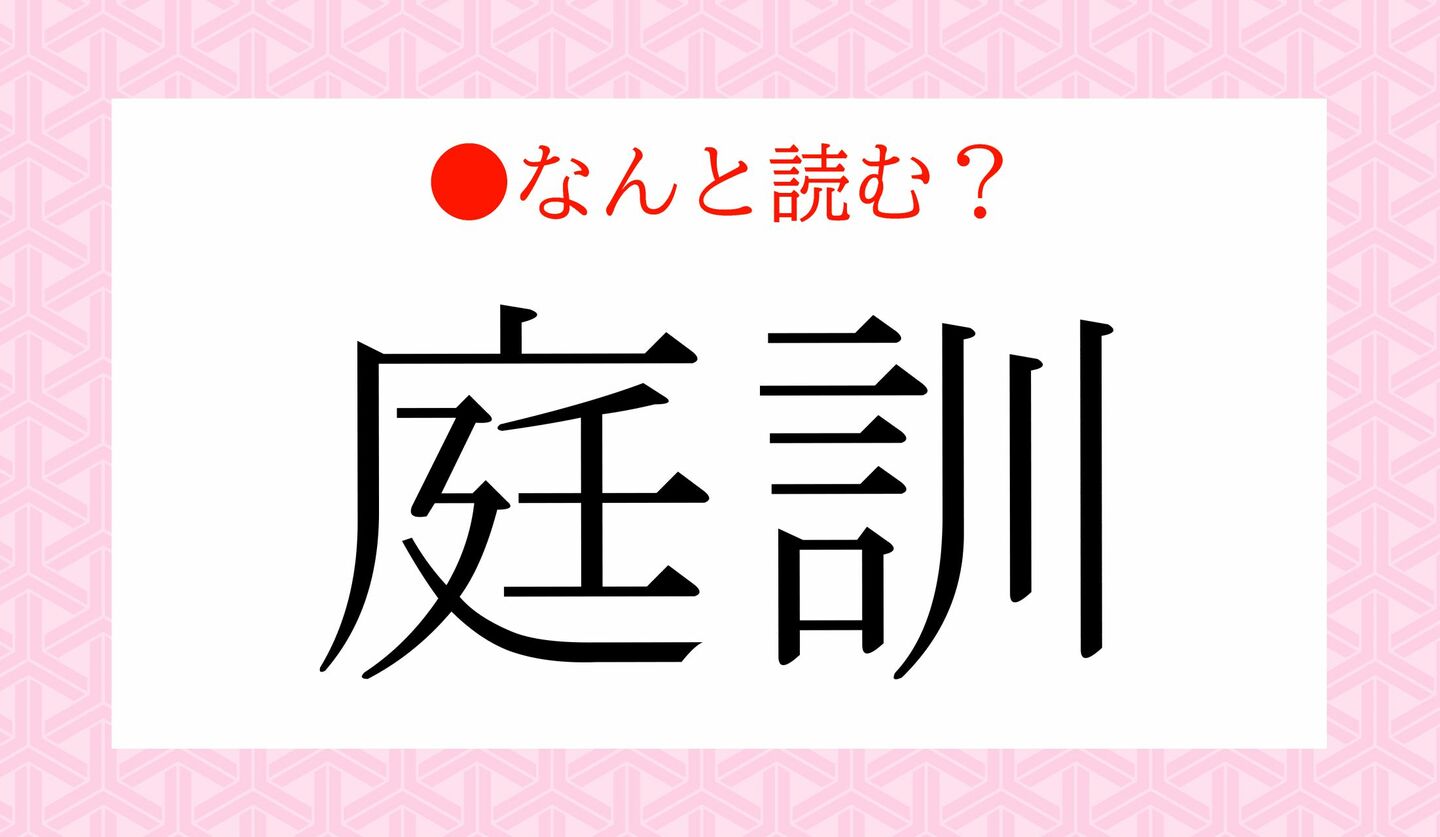「綱紀」ってなんと読む?「もうき」ではないですよ!
明日、8月25日は『川柳発祥の日』です。五七五の句でも、俳句のように「必ず季語を入れる」というルールのない川柳は、より気軽で軽妙な文芸として、現代まで親しまれていますね。
「川柳(せんりゅう)」という名称は、この文芸を確立した江戸時代の点者(連歌や徘徊を評点する職業)、柄井川柳(からいせんりゅう)の名から取られています。1757(宝暦7)年の旧暦8月25日に、彼が選者としてデビューしたことから、この日が『川柳発祥の日』といわれているのです。本日は「ルール」をキーワードに、その類語から日本語クイズを出題します。
【問題1】「綱紀」ってなんと読む?
「綱紀」という日本語の正しい読み方をお答えください。
ヒント:「国家を治める大法と細則。また、一般的に規律」という意味です。
<使用例>
「柄井川柳は、いったん綱紀を忘れてみる、というような、自由な発想を求めたのね」
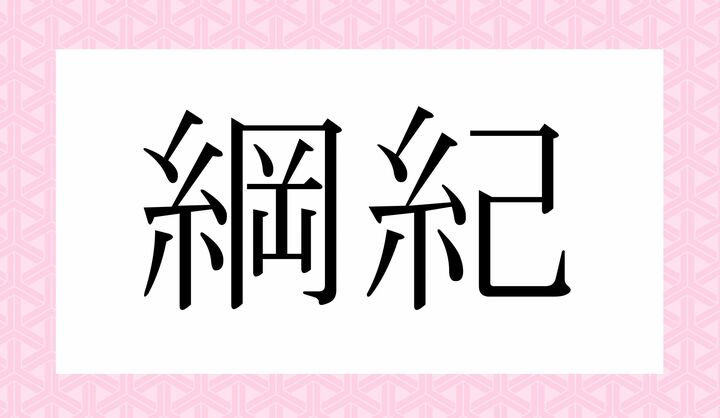
さて、正解は?
※「?」画像をスクロールすると、正解が出てまいります。
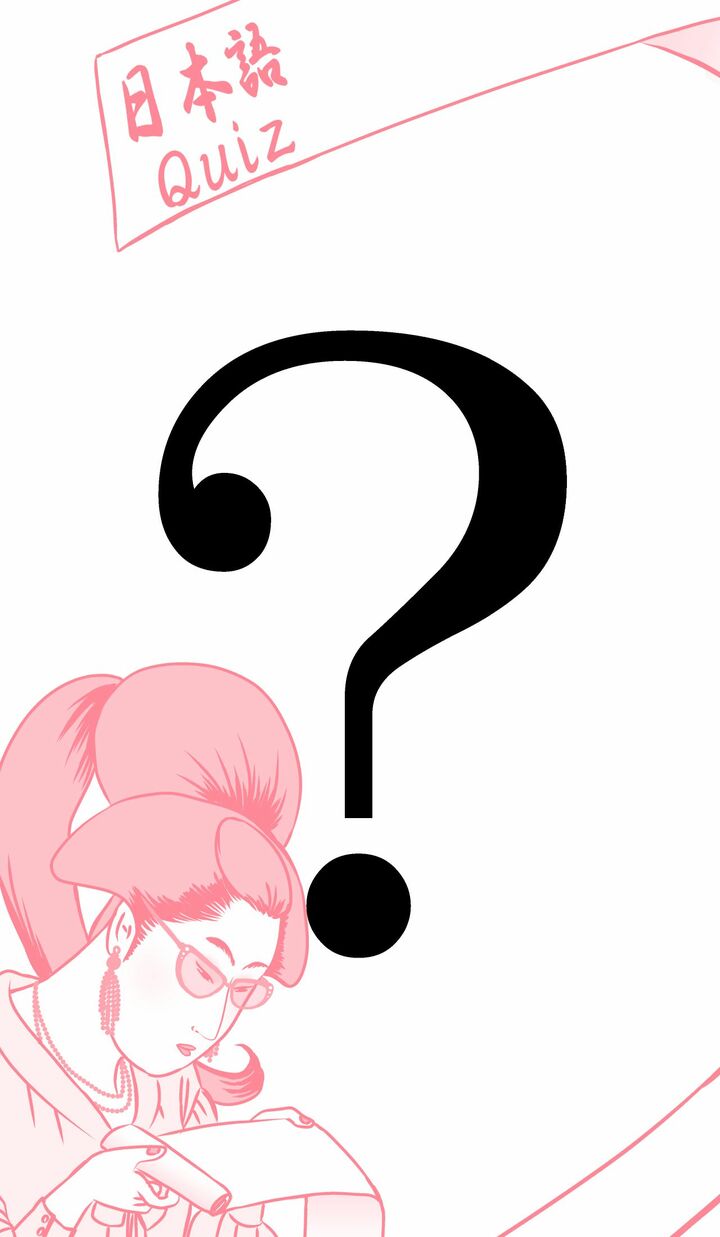
正解は… 綱紀(こうき) です。

「綱紀(こうき)」は、憲法を「大法+細則」という解釈で表現した言葉で、一般的な「規律」という意味でも使われます。「綱(コウ)」は訓読みで「つな」とう読む字ですが、この字は「網(あみ/モウ)」との混乱が生じやすいようです。誤読にご注意ください。
さて、2問目にまいりましょう。
【問題2】「庭訓」ってなんと読む?
「庭訓」という日本語の正しい読み方をお答えください。
ヒント:「家庭教育。過程での教訓」を意味する言葉です。
<使用例>
「夫婦それぞれに生家の庭訓があるので、幾度かは衝突もございました」
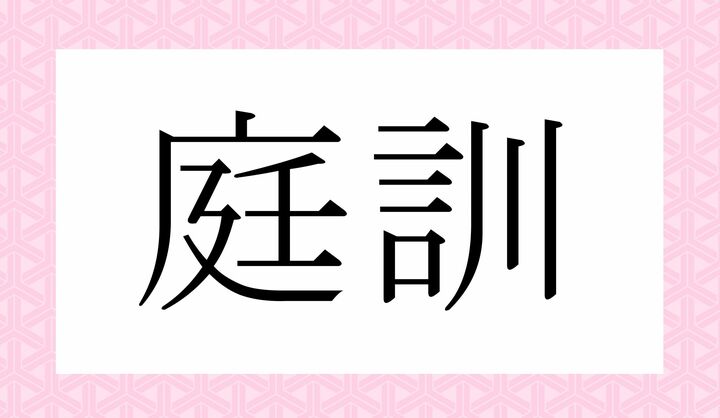
さて、正解は?
※「?」画像をスクロールすると、正解が出てまいります。

正解は… 庭訓(ていきん) です。
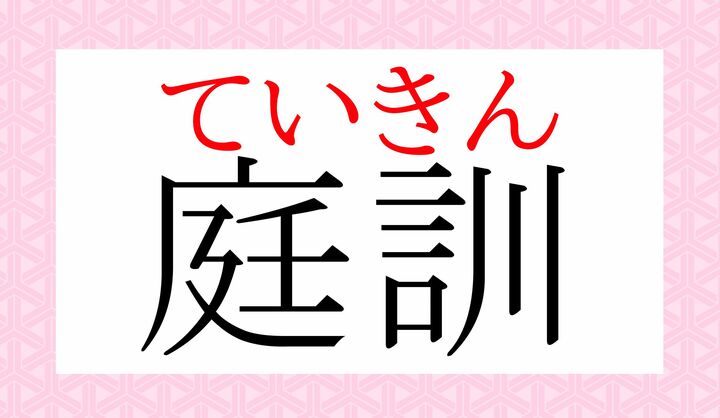
「庭訓(ていきん)」は、、もともと孔子の『論語』のなかの故事から出た熟語なので、「訓」に漢語読みの「キン」を用いるのが一般的です。「家庭教育」を意味する熟語としてポピュラーなので、読めるようにしておきましょう。
***
本日は、8月25日『川柳発祥の日』にちなんで、「ルール」をキーワードに、
・綱紀(こうき)
・庭訓(ていきん)
の読み方、言葉の背景についておさらいいたしました。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- BY :
- 参考資料:『日本大百科全書(ニッポニカ)』『精選版日本国語大辞典』『デジタル大辞泉』(小学館)/毎日新聞校閲センターX/『漢字ペディア』(日本漢字能力検定協会)
- ILLUSTRATION :
- 小出 真朱