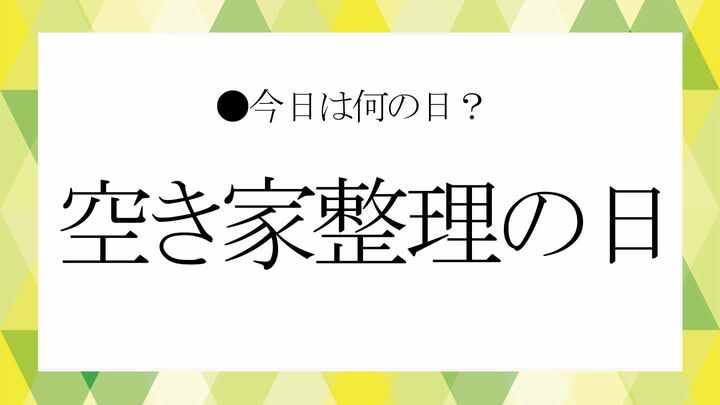【目次】
【「空き家整理の日」とは?由来】
■いつ?
「空き家整理の日」は、8月31日です。
■誰が決めたの?
「空き家整理の日」は、遺品・生前整理や就活相談等を主な業務とする株式会社ワンズライフが制定し、日本記念日協会に認定されています。
■由来
日付は8と31を「家(ヤ=8)整(セイ=31)理」と読む語呂合わせと、夏の終わりに空き家や家財の整理を考えてもらいたいという理由から決まりました。お盆休みなどで帰省した際に、実家をどう保っていくか…といった思いが生まれ、気になる時期でもありますね。
【ビジネス雑談に役立つ「日本の空き家事情」の知識】
■総住宅数の約6%が「空き家」
総務省の2023(令和5)年「住宅・土地統計調査」によると、日本全国の空き家数は900万戸と過去最多を更新。2018年からの5年間で51万戸の増加、総住宅数に占める空き家の割合も13.8%と過去最高です。空き家数は、一貫して増加を続けており、1993年から2023年までの30年間で約2倍に増えています。
空き家のうち、賃貸用や売却用の空き家、週末などに利用される別荘などを除いた空き家のことを、「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」と分類するのですが、こちらは全国で385万戸。総住宅数に対して5.9%という割合になっています。
■空き家率が高いのは西日本、低いのは都市圏
都道府県別に空き家率をみると、和歌山県と徳島県が21.2%と最も高く、次いで山梨県が20.5%です。上で説明した「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」を都道府県別にみると、鹿児島県が13.6%で最も高く、次に高知県の12.9%、徳島県と愛媛県の12.2%が続きます。空き家率は西日本ほど高くなっていることがわかります。
これに対して空き家率が低いのは、当然ながら都市圏で、東京都の2.3%が最も低く、神奈川県の3.3%、埼玉県の3.7%、大阪府の4.5%、千葉県の4.8%、福岡県の4.9%となります。
■なぜ「空き家」になってしまうのか?
「空き家」にしておく理由について、国土交通省住宅局の令和4年「空き家政策の現状と課題及び検討の方向性」から見てみましょう。
1位)物置として必要だから
2位)解体費用をかけたくないから
3位)特に困っていないから
4位)将来、自分や親族が使うかもしれないから
5位)好きなときに利用や処分ができなくなるから
6位)仏壇など捨てられないものがあるから
7位)更地にしても使い道がないから
8位)取り壊すと固定資産税が高くなるから
9位)古い、狭いなど住宅の質が低いから
10位)リフォーム費用をかけたくないから
まず挙げられる理由が、「物置として必要」というもの。また、「解体費用をかけたくない」、「労力や手間をかけたくない」といった消極的な理由のほか、「特に困っていない」という所有者も少なくありません。一方で、利活用を図ろうとしても「更地にしても使い道がない」、「住宅の質の低さ」と「買い手・借り手の少なさ」によって空き家となっているということが挙げられています。
実際に売却・賃貸を考えている所有者からは、売却・賃貸するうえでの課題として、「買い手・借り手の少なさ」、「住宅の傷み」や「設備や建具の古さ」が挙げられています。
■なぜ「空き家」は問題なのか?
住む人がいなくなった空き家の問題点を整理しましょう。まずは周辺住民や行政などに起こり得る問題点を挙げます。
-
1)周辺住民への迷惑
特に木造建築に顕著なのが建物の老朽化です。外壁や屋根材の落下、蚊やシロアリなど害虫の発生、ねずみなど害獣の住処になることも。空き家には家財道具などが残されたケースも多く、腐敗したごみの放置による悪臭も問題です。
-
2)景観や治安の悪化
放置された空き家は地域全体の景観を悪化させます。ごみの不法投棄も問題です。また、不法侵入や犯罪の温床になるなど、近隣住民の生活に深刻な影響を及ぼします。
-
3)地域社会の活力低下と財政問題
-
空き家が増えると景観が悪くなるだけでなく、地域としての活気がなくなります。自治体は空き家対策費用が増大したり税収が減少するなど、財政的な課題も大きな問題です。
-
次に、所有者や相続者側の問題点を見てみましょう。
4)建物の倒壊リスクと損害
-
老朽化が進行した空き家は倒壊の危険性が高まり、万が一倒壊して通行人や近隣に損害を与えた場合、所有者が損害賠償責任を問われることがあります。
-
5)所有者の経済的・精神的負担
空き家を処分しない限り固定資産税の支払いが発生します。また、月1回程度の見回り・草刈り・突発的な修繕なども所有者の義務。維持管理に時間的・金銭的・精神的な負担が生じます。
-
6)行政代執行と解体費用の負担
-
放置された空き家に倒壊の危険性があると判断された場合、行政代執行により解体されることがあります。この場合、解体費用は所有者の負担となります。
-
7)特定空き家指定と固定資産税の減税解除
保安上・衛生上のリスクが高い「特定空き家」に指定されると固定資産税の減税特例が解除され、税の負担が増加します。
-
***
マスコミでもたびたび報じられる空き家問題。国土交通省の調査によると当事者は「空き家を空き家のままにしておきたい」という方が多いようですが、景観や治安の悪化、悪臭や火災の誘発など、問題はその地域だけでなく社会全体に及びます。高齢化社会になるほど空き家問題は深刻化します。「空き家対策は対症療法より予防が有効」とも言われるので、「空き家整理の日」に“家の終活”について考えてみませんか?
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『デジタル大辞泉』(小学館)/『日本国語大辞典』(小学館)/一般社団法人日本記念日協会(https://www.kinenbi.gr.jp)総務省 令和5年「住宅・土地統計調査」、国土交通省住宅局 令和4年「空き家政策の現状と課題及び検討の方向性」 :