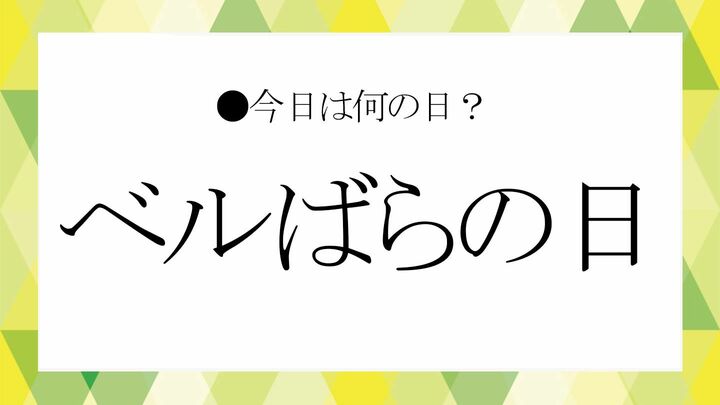【目次】
【「ベルばらの日」とは?由来】
「ベルばら」とは池田理代子さんの漫画『ベルサイユのばら』の通称。フランス革命期のフランスを舞台に、将軍の娘である主人公オスカルが、運命に翻弄されながら、自身の正義と愛に生きる姿を描いた壮大な歴史ロマン作品です。
『ベルサイユのばら』は、1972(昭和47)年4月から1973(昭和48)年12月まで少女漫画誌『週刊マーガレット』(現在の『マーガレット』集英社)に連載され、大ヒット。アニメ化、宝塚歌劇団などによる舞台化もされ、1970年代には空前の「ベルばらブーム」が巻き起こりました。
この「ベルばら」を記念した日が「ベルばらの日」です。
■「いつ」? 「誰が」決めたの?
「ベルばらの日」は8月29日です。誰が、いつ決めたのかについては、はっきりしませんが、劇場アニメを公開する東宝映画も、この日を「ベルばらの日」として広報しています。
■由来は?
日付は、1974(昭和49)年のこの日、宝塚歌劇団で『ベルサイユのばら』(通称:「ベルばら」)が初演されたことにちなみます。
【ビジネス雑談に役立つ「ベルサイユのばら」と「宝塚歌劇団」の知識】
■「ベルばら」はなぜブームになった?
『ベルサイユのばら』は、フランスブルボン朝後期、ルイ15世末期から、フランス革命が起こったルイ16世の時代(マリー・アントワネットが亡くなるまで)を描いています。悲劇の王妃マリー・アントワネットと、軍人として生きる男装の麗人オスカルという、ふたりの女性の対照的な人生を軸に、物語が展開します。
内閣府男女共同参画局のスペシャルインタビューによれば、池田理代子さんは「マリー・アントワネットの生涯を描きたい」という思いから、この作品を小学生の女の子向けに描いたそうですが、のちに「フランス革命を勉強するなら『ベルばら』を読め」とまで言われる程、徹底した歴史取材に基づいた物語は、少女たちのみならず、当時、仕事をもつ女性たちからの熱い支持を集めたのです。
というのも、1970年代といえば、女性が社会に出て働くことが今よりもずっと難しかった時代。自立を目指す女性に対し世間の目は非常に厳しかったのです。いわゆる男社会そのもののなかで、多くの少女や働く女性たちは、リベラルな考えをもち、信念をもって生きるオスカルの姿に熱狂したのですね。
また、マリー・アントワネットとスウェーデン伯爵ハンス・アクセル・フォン・フェルゼンとの恋愛や、コスプレ願望を強く刺激する美しい作画も魅力的でした。
『ベルサイユのばら』連載当時は「1ドル=301円」という時代です。海外旅行なんて夢のまた夢。ヴェルサイユ宮殿などのヨーロッパのお城なんて、テレビの旅番組でたまに見られるくらい。少女たちは、絵本の挿絵などでしか目にすることがなかった華麗な宮殿で展開される物語に、壮大なロマンを感じていたのです。
しかも当時「漫画は子どもにとって有害」という考えも強くあり、多くの親が子どもたちに漫画を定期的に買い与える、ということはまれでした。少女たちはお手伝いに励んでお小遣いを貯めたり、お誕生日などにねだったりと、苦心して手に入れた『週刊マーガレット』から「ベルばら」の連載ページを丁寧に外して、麗しい「オスカルさま」の近衛連隊長としての軍服の全身や、美しいドヤ顔のどアップなどを、透明の下敷きに挟んだりして大切に持っていました。今で言うなら、推しの写真をスマホの待ち受けにするような感覚でしょうか。
■池田理代子さんはレジオン・ドヌール勲章シュヴァリエを受賞
池田理代子さんには、2009(平成21)年にフランス政府から最高勲章であるレジオン・ドヌール勲章シュヴァリエL'ordre national de la légion d'honneur,Chevalier(名誉軍団国家勲章,騎士級(勲五等))が贈られています。これは日仏文化に貢献した、主に日本人のフランスやフランス文化への理解を高めたとの趣旨によるもの。実は池田理代子さんが実際にフランスに行ったのは、作品発表後のことだったそうです。
■「ベルばら」は宝塚歌劇団史上最大のヒット作
『週刊マーガレット』での連載が終了した翌年の1974年8月、宝塚大劇場(兵庫県)では宝塚歌劇版「ベルサイユのばら」の上演が始まりました。続く11月には東京公演が始まり、空前の「ベルばら」ブームが巻き起こったのです。1974年は、奇しくも宝塚歌劇団が60周年を迎えた年。昭和時代の「ベルサイユのばら」でキャストを務めたのは、榛名(はるな)由梨さん、汀(みぎわ)夏子さん、鳳蘭さん、安奈淳さんの4人。彼女たちは「ベルばら四強」と称され、第一次「ベルばら」ブームの立役者となりました。
シリーズはほかに「ベルサイユのばら アンドレとオスカル」(1975年)、『ベルサイユのばらIII」(1976年)、「ベルサイユのばら2001」(2001年)などのほか、2008年からは池田理代子さんが新たに書き下ろした「外伝ベルサイユのばら』が全国ツアーで上演されています。
そして、2014年には累計動員観客数500万人を記録。宝塚歌劇団史上最大のヒット作となっています。昨年2024年には、初演から50年を記念して、10年ぶりに「ベルサイユのばら-フェルゼン編-」(雪組公演)が東京・有楽町の東京宝塚劇場で上演されました。
■宝塚歌劇団の「ベルばら」ではオスカルは「男役」が演じる
漫画『ベルサイユのばら』の主人公、オスカルは将軍家の末娘で、家督を継ぐために男子として育てられた「男装の麗人」という設定。そして、幼馴染みで身分違いのアンドレと恋に落ちるというストーリーもあります。
宝塚歌劇にあまり詳しくない人は、「オスカルは男役と娘役、どちらが演じるの?」と思いますよね。…実際には、宝塚歌劇団では主人公はトップスターである「男役」の劇団員が演じるのが原則。
1974年の初演時、オスカルを演じたのは榛名由梨さん。当時月組のトップスター(当然「男役」)です。翌1975年版の花組公演(副題「アンドレとオスカル」)では、アンドレを榛名由梨さん、オスカルを安奈淳さんがダブルトップのかたちで演じています。その後も、涼風真世さん、真矢みきさん、天海祐希さんなど、今では誰もが知る女優となった当時男役の方々が演じています。
現在に至るまで「ベルばら」シリーズとして「オスカル編」「フェルゼン編」、「フェルゼンとマリー・アントワネット編」などが上演されていますが、「マリー・アントワネット編」はありません。なんならマリー・アントワネットが登場しないバージョンまであります。オスカルとアンドレの恋愛関係は「男役×男役」での演技となるので、宝塚歌劇団の作品に慣れていないと、少々戸惑うかもしれませんが、「ヅカファン」にとってはまったく違和感がないそうですよ。
■「ベルばら」三が日とは?
「ベルばら」ファンの間では有名な「ベルばら三が日」というものがあります。
7月12日・・・オスカルとアンドレが結ばれた日
7月13日・・・アンドレの命日
7月14日・・・オスカルの命日
この3日を「ベルばら三が日」というのだそうです。ちなみに、オスカルの誕生日は1755年12月25日のクリスマス。命日は1789年7月14日です。マリー・アントワネットは、1755年11月2日 オーストリア ウィーン ホーフブルク王宮で生まれ、1793年10月16日に37歳で亡くなっています。
■オスカルにはモデルが存在した!
オスカルは池田理代子さんが生み出した架空のキャラクターですが、「オスカルのモデル」になった人物がいます。それがスウェーデン人俳優のビョルン・アンドレセン。彼は、イタリア映画の巨匠ルキノ・ヴィスコンティに見出され、15歳で映画『ベニスに死す』に出演したことで、一躍脚光を浴びました。日本でも、チョコレートのCMに出演したり、日本語でレコードデビューしたりするなど、芸能活動を行っていました。池田理代子さんは2021年に公開されたドキュメンタリー映画『世界で一番美しい少年』のなかで、「大変な衝撃を受けました。この世の中に、こんなに美しい人がいる」と語りつつ、「ベルばら」の主人公・オスカルのモデルはこのビョルンだったと明かしています。
***
8月29日は「ベルばらの日」。今から51年前となる1974(昭和49)年のこの日、宝塚歌劇で「ベルサイユのばら」(通称:ベルばら)が初演されたことに由来します。この記事を読んで、改めて「ベルサイユのばら」を読んでみたくなった、宝塚歌劇団の『ベルサイユのばら』が見たくなった人もいるのでは? Netflixでは、2025年1月に公開された劇場アニメ『ベルサイユのばら』も配信されています。筆者はこれから、「ベルばら」コミックスを読み返そうと思っています!
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『ベルサイユのばら』(集英社)/『デジタル大辞泉プラス』(小学館) /内閣府男女共同参画局スペシャルインタビュー(https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2021/202201/202201_02.html) /宝塚歌劇専門チャンネル「タカラヅカ・スカイ・ステージ」(https://www.tca-pictures.net/skystage/Prgm/Detail/8125.html#:~:text=宝塚歌劇が60周年,の立役者となりました%E3%80%82) /「ベルサイユのばら展」(https://verbaraten.com) :