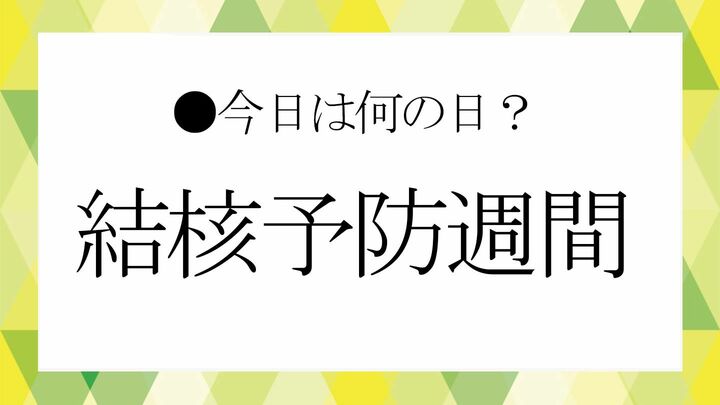【目次】
【「結核予防週間」とは?】
■「誰が」決めた?
「結核予防週間」は毎年9月24日から9月30日の一週間です。厚生労働省により制定されました。地方自治体や関係団体と共に、結核・呼吸器感染症予防に関する普及啓発を行っています。
■「目的」は?
「結核予防週間」は、マスク着用を含む咳エチケットや手洗い、換気などの基本的感染対策や予防接種の重要性など、呼吸器感染症に関する知識の普及啓発を図ることを目的としています。呼吸器感染症とは、呼吸器の病気の総称で、結核だけでなく、風邪のような軽いものから、肺炎のように命に関わる重いものまで含まれます。
【ビジネス雑談に役立つ「肺の健康」の知識】
■改めて「肺のはたらき」についておさらい!
肺は、空気中の酸素を体に取り入れ、いらなくなった二酸化炭素を外に出すはたらきをしています。鼻や口から吸い込んだ空気は喉頭(こうとう)を通り、気管に入ります。気管は左右の肺のなかに入ると、ふたつに分かれて気管支となります。気管支はさらに細かく分かれて、その先には肺胞という空気が入った小さな袋が、ブドウの房のように付いています。左右の肺は気管によってつながっています。
■生物はなぜ酸素が必要?
人間や動物が生きていくためのエネルギーづくりには、酸素が必要不可欠だからです。
私たちが口や鼻から取り込む空気の中には酸素が含まれています。特に鼻呼吸では、空気が鼻の中を通ることで、温度や湿度が調整され、さらに鼻毛や粘膜によってホコリや病原体が取り除かれます。こうして整えられた空気が肺に届き、呼吸の役に立ちます。
一方、食べ物は口から入り、胃や腸〈十二指腸、小腸、大腸〉を通るあいだに消化液によって分解され、体に吸収されやすい養分に変わります。
体内でブドウ糖などの栄養と、呼吸で取り込んだ酸素が結びついて、はじめてエネルギーが生まれるのです。
そして、エネルギーをつくる過程では二酸化炭素も発生します。二酸化炭素は体に溜まると有害なので、肺から呼吸によって体の外へ吐き出されます。
■人間は一日に何回呼吸している?
成人の平均的な呼吸の数は、1日におよそ20,000回といわれています。これが、健康な呼吸のリズムですが、私たちはほとんど無意識に呼吸しているため、普段は肺の存在を意識することはあまりありませんね。
けれども、肺がなければ私たちは生きていくことができません。肺は酸素を取り入れ、老廃物である二酸化炭素を排出することで、細胞に必要な酸素を供給し、体の代謝を支えているのです。
■肺は“体の中のフィルター”——異物を追い出す自己掃除の仕組み
肺には、鼻や口から空気と一緒に入り込むホコリや細菌などを追い出す仕組みがあります。気管や気管支の内側は粘液と細かい毛(線毛)で覆われていて、異物をキャッチすると痰として外に運び出されます。咳もその一部で、不要なものを外へ押し出す働きです。さらに、肺の奥まで入り込んだものは、マクロファージという免疫細胞が分解して処理します。
よく「肺はフィルターみたい」と言われますが、エアコンや洗濯乾燥機のフィルターと違って、汚れをキャッチするだけではありません。肺は“自分で掃除するフィルター”のようにはたらき、不要なものを外に出したり、細胞が処理したりしてきれいな状態を保とうとします。そのおかげで、肺の中は呼吸に適した環境が守られ、酸素を効率よく体に取り込むことができるのです。
つまり肺は、ただ汚れがたまるだけのフィルターではなく、痰や咳で異物を外に出し、免疫細胞で処理する「自己掃除機能つきのフィルター」なのです。
とはいえ、すべてをきれいにできるわけではありません。タバコの煙に含まれるタールや微細な粒子、PM2.5のような大気汚染物質、アスベストや鉱山・工場の粉じんなどは体外に排出されにくく、長い間に肺に沈着してしまいます。その結果、肺が黒ずんで見えたり、慢性の病気やがんの原因になることもあります。
■人間は呼吸をどれだけ我慢できる?
イタリアのシチリア島を舞台にした映画『グラン・ブルー』を観たことはありますか? この映画のモデルとなったのが、1976年に人類史上初の水深100mの素潜り記録を打ち立てた、伝説のフランス人ダイバーのジャック・マイヨール氏です。この時の無呼吸潜水時間は、実に3分40秒だったそうです。2016年にはニュージーランド人のウィリアム・トゥルブリッジ氏が、約4分半の無呼吸潜水で水深124mの素潜り世界記録を更新しました。
また、ギネス世界記録では、2015年にスペイン人のアレイクス・セグラ氏が、水中で24分3秒も息を止めるという記録を樹立しています。
■「結核」ってどんな病気?
結核は、結核菌という細菌の感染によって起こる病気で、日本でも依然として重要な感染症です。現在は減少傾向にあるとはいえ、毎年1万人前後の患者が報告されています。
症状は風邪に似てわかりにくい
結核菌は主に肺で増えることが多いため、咳・痰・発熱などの症状が風邪と似た形で現れます。しかし、初期の段階では症状がはっきりせず、目立たない場合が少なくありません。特に高齢者では、違和感があっても「年のせい」と見過ごされ、気付かないうちに進行してしまうことがあります。また、小児では、症状が出にくかったり、出ても非特異的(発熱やだるさなど)で判断が難しいことがあります。そのため進行してから発覚するケースもあり、重症化につながるリスクがあるため注意が必要です。
そして、結核は肺に限らず、全身のさまざまな臓器に広がることがあります。たとえば、リンパ節・骨・腎臓・脳などにも影響を及ぼすことがあり、これを 肺外結核 と呼びます。肺外結核は全体の2割程度とされていますが、臓器によっては重い障害を残すこともあります。
■「結核」って流行ってるの?
「結核なんて、歴史物の小説やドラマでしか見聞きしたことない」という方は多いかもしれませんが、実は毎年新たに10,000人以上の患者が発生しており、約1,500人が命を落としています。2024年には10,051人が結核患者として登録され、死亡者数は1,461人にのぼりました。
過去においては、昭和20年代まで結核は日本人の死亡原因の第1位であり、その高い死亡率や感染力のために「不治の病」「亡国の病」などと呼ばれていました。第二次大戦後、抗生物質ストレプトマイシンの普及によって治療の途が開けたこと、BCGワクチンの普及や生活水準の向上などがあり、結核による死亡者・死亡率は激減しました。
■「肺」に関係する記念日は?
・肺の日(8月1日)
・呼吸の日(5月9日)
肺の記念日も呼吸の日も、日本呼吸器学会が制定した記念日です。「肺の日」は1999年(平成11年)に、「呼吸の日」は2007(平成19)年に制定されました。それぞれ「は(8)い(1)」=肺」、「こ(5)きゅう(9)=呼吸」という語呂合わせが、日付の由来です。肺の健康についての理解を深め、呼吸器疾患の早期発見と予防についての知識を普及し、啓発することを目的としています。
***
日本では現在でも、毎年、結核によって約1,500人の方が亡くなっています。ここ数年は暑さが長引いていますが、本来「結核予防週間」の時期は、ようやく残暑もやわらぎ、秋を迎えるころ。呼吸器は外気の影響を受けやすい臓器ですから、急激な気温や湿度の変化によって負担がかかり、呼吸器感染症にもかかりやすくなります。
手洗い・うがい、そしてマスクの着用は、簡単でありながら飛沫感染や接触感染の予防に効果的で、空気感染のリスク低減にもつながります。
また、秋はブタクサなどの花粉が飛散する時期でもあり、「なんとなく体調がすぐれない…」ということもあるでしょう。つらいときには我慢せず、早めの受診を心掛けましょう。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『日本国語大辞典』(小学館) /『デジタル大辞泉プラス』(小学館) 公益財団法人結核予防会(https://www.jatahq.org) /厚生労働省「結核」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou03/index.html) /政府広報オンライン(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201509/3.html) /一般社団法人 日本呼吸器学会 /中外製薬「肺」(https://www.chugai-pharm.co.jp) :