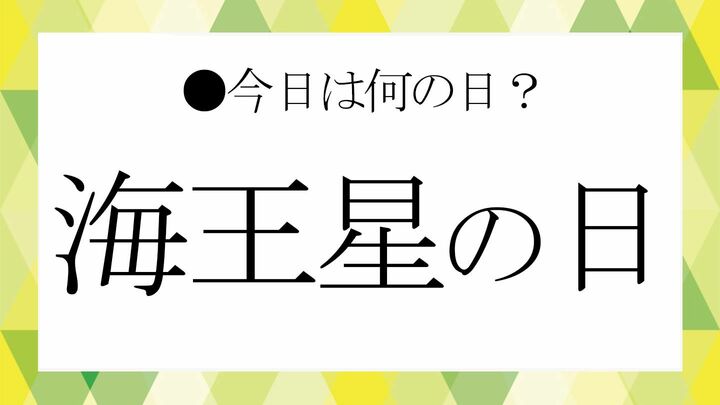【目次】
【「海王星の日」とは?由来】
■いつ?「日付」
「海王星の日」は9月23日です。2025年は秋分の日でもありますね。
■なぜこの日?発見者は誰?「由来」
1846年9月23日、ベルリン天文台で働いていたドイツ人天文学者のヨハン・ゴットフリート・ガレが、望遠鏡を使って新星「海王星」を発見したことに由来します。
1781年、天王星が発見されて以降、「天王星の軌道が天文力学(てんぶんりきがく/主にニュートンの万有引力の法則に基づいて天体の運動を理論的に研究する古典力学)に合わないのは、天王星の外側に惑星があるためだろう」と考えられており、さまざまな科学者が、この未知の惑星の大きさや軌道・位置を計算していました。
そして、フランスの天文学者のユルバン・ルヴェリエがはじき出した地点をベルリン天文台でガレが観測、新しい惑星「海王星」が発見されたというわけです。実はイギリスのジョン・アダムズも同じ地点を突き止めていたため、現在では海王星の発見者はガレ、ルヴェリエ、アダムズの3人とされています。
【ビジネス雑談に役立つ「惑星」の雑学】
■そもそも「惑星」とは?
「惑星」の定義を確認しておきましょう。
1)太陽の周りを直接回っていること
2)自己重力により球形に近い平衡形状をなすこと
3)重力作用により自己の軌道領域から他の天体を排除して主要な天体としてふるまうこと
この3つの情敬意を満たす天体を「惑星」と呼びます。2006年の国際天文学連合(International Astronomical Union:IAU)総会において、太陽系の惑星の定義が初めて決定されました。意外に最近のことでびっくりですね。
■「惑星の覚え方」が変わっていた!
「水・金・地・火・木・土・天・海・冥(すいきんちかもくどってんかいめい)」と、太陽から近い順に惑星の名前を覚えた人も多いでしょう。これは、「水星」「金星」「地球」「火星」「木星」「土星」「天王星」「海王星」「冥王星」のことですね。ところが…現在では「水・金・地・火・木・土・天・海」に。いちばん外側を回っていた冥王星が外れ、太陽系の惑星は8つになりました。
■「冥王星」はなぜ惑星から降格?
惑星の条件のうち、冥王星は(3)を満たしていません。(1)と(2)のみを満たす天体は「準惑星」とされるので、2006年より「冥王星は準惑星」となったのです。
■「惑星パレード」次回はいつ?
複数の惑星が狭い範囲に並んで見える「惑星直列」をご存知でしょうか。「惑星パレード」とも呼ばれるこの現象、次回は2026年2月28日ごろに、「木星」「天王星」「土星」「海王星」「金星」「水星」の6つの惑星に加えて「月」までも一直線上に観測できると予測されています。楽しみですね!

■各惑星の特徴をさくっと紹介
・水星/Mercury:太陽系の惑星中で最も小さく、隕石が燃えたまま衝突しするため表面に無数のクレーターが刻まれています。芸術家や作家の名前が付けられているクレーターもあり、「アクタガワ(芥川龍之介)」「バショウ(松尾芭蕉)」「リキュウ(千利休)」「ホクサイ(葛飾北斎)」「ムラサキ(紫式部)」「ウンケイ(運慶)」「セイ(清少納言)」など、日本人の名前がついたクレーターも30を超えます。
・金星/Venus:地球軌道のすぐ内側を回る太陽系の惑星で、地球に最も接近します。大きさや質量が地球と似ていることから「地球の双子星」とも。明るさは、ときに1等星の200倍以上になるので、方向がわかれば昼間の青空に肉眼でも見つけられます。
・地球/Earth:大気に囲まれ、酸素と水をもつ、現時点で生命体が繫栄する唯一の天体です。
・火星/Mars:地球のすぐ外側の軌道を回る、金星に次いで地球に接近する太陽系の惑星。太陽系の惑星としてはかなり楕円の軌道を描きます。火星のいちばんの特徴は色と明るさ。赤い火星は地球に接近するとより明るく見え、人々の注目を集めてきました。その赤い色は血や炎を連想させるため、古代から戦争や災害と関係する神やシンボルとされることが多かったようです。
・木星/Jupiter:太陽系の惑星では大きさ、質量とも最大。60個を超える衛星をもち、なかでもイタリアの天文学者ガリレオ・ガリレイが発見した「ガリレオ衛星」が有名です。
・土星/Saturn:最大の特徴は「環(わ)」でしょう。1656年にオランダのクリスティアーン・ホイヘンス によって確認されて以来、望遠鏡の発達とともに次第に詳しく観測されてきました。環は外側からA、B、C、Dの4つに分かれています。
・天王星/Uranus:大気中に含まれるメタンの影響で青緑色に見える天王星。太古より知られていた太陽からいちばん遠い惑星は土星でしたが、1781年にドイツ人のウィリアム・ハーシェルによって土星の外側に天王星が発見されました。最大の特徴は自転軸が98度も傾いていること。これにより、なんと昼間が42年間、夜が42年間続くといった極端な現象を繰り返しています。
・海王星/Neptune:地球からも最も遠くにある惑星で、光学機器でしか観測できません。太陽からも最も離れているため、公転周期が惑星の中でいちばん長く、海王星の1年は地球の164.8年に相当するとか。発見された1846年以来、海王星は太陽の周りを1回転しかしていないのです! 1回転できたのは2011年、2回転目が完了するのは2175年と予測されています。
-
***
9月23日は「海王星の日」にちなんで夜空を見上げてみてはいかが? 晴れて美しい星空が見えるといいですね。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『日本大百科全書(ニッポニカ)』(小学館)/『デジタル大辞泉』(小学館)/『情報・知識imidas』(集英社) :