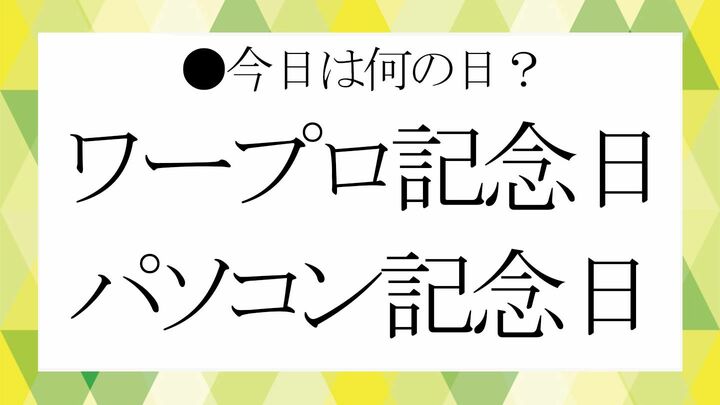【目次】
【「ワープロ記念日」「パソコン記念日」のそれぞれの由来とは?】
■「ワープロ記念日」とは?
皆さんは「ワープロ」を実際に使ったことがあるでしょうか? ワープロ使用経験の有無は、「世代がわかるエピソード」のひとつかもしれませんね! 今回テーマの「ワープロ記念日」は9月26日です。1978(昭和53)年の9月26日に、東芝が世界初の日本語ワープロ「JW-10」を発表したことに由来します。
■「パソコン記念日」とは?
「パソコン記念日(パソコンの日)」は9月28日です。1979(昭和54)年のこの日、日本電気(NEC)がパソコン(パーソナルコンピュータ)「PC-8001(PC-8000シリーズ)」を発売したことに由来します…と、言われていますが、NECの公式ホームページでは「PC-8001」の発売日は「1979年9月」としか記されていないため、なぜ9月28日が記念日として選ばれたのか、その経緯は定かではありません。
【ビジネス雑談に役立つ「ワープロ」「パソコン」の豆知識】
■そもそも「ワープロ」って何?
「ワープロ」は[word processing software(ワードプロセッサ ソフトウエア)]の略で、文書の作成や編集を行うアプリケーションソフトです。英文ワープロの発売は1964年にIBMなどによって実現しました。日本でも開発が試みられましたが、英語と異なり同音異義語が多く、多数の漢字のなかから適正な文字を選択しなければならない日本語ワープロの実用化はかなり難しいものでした。
そのなかで、世界で初めて実用レベルの日本語ワープロとされるのが、1978年に東芝が発表した「JW-10」です(出荷は1979年2月)。その後、シャープ、NEC、沖電気、富士通など多くの企業が日本語ワープロ市場に参入し、1982年には23社がワープロを販売するに至ります。以降、日本語ワープロの小型・低価格化は急速に進み、1997年には日本語ワープロの普及率は42%に達したといわれています。
■世界初の「日本語ワープロ」は超高価!
東芝が発表した日本初の日本語ワープロ「JW-10」は、幅115cm・奥行き96cm・重さ220kgというサイズ。片袖机ほどの大きさの筐体に、キーボード・ブラウン管・10MBのハードディスク・8インチフロッピーディスクドライブ・プリンターが収められていたのです。価格は630万円と大変高価なものでしたが、当時、コンピューターへの簡単な漢字入力手段はなく、英数字・カタカナに限られていました。「かな漢字変換」の開発により、書類の作成・編集が飛躍的に簡単になったのです。
■「ワープロ」って、いつまであった?
1990年代になると、インターネットの一般化やマイクロソフトによる「Windows95」の発売などにより、パーソナルコンピュータ(パソコン)及びインターネットのユーザが劇的に増加。これにより、ワープロ専用機はパソコンとの競争に敗れ、出荷台数は次第に減少します。2000年前半には、各社が相次いでワープロの生産を終了し、2000年代後半にはメーカーのサポート業務も終了してしまいました。
こうやって振り返ると、「ワープロ」が本格的に活躍したのは、1979年の登場から、その機能が「パソコン」にとってかえられる2000年代前半までの20~25年程の間だったのですね! 実際に「ワープロ」を使っていた世代は、現在のアラフィフくらいの人たちまでかもしれませんね。
とはいえ、「JW-10」などで開発された「かな漢字変換技術」と「編集技術」は、その後のパソコンや携帯電話など、日本のあらゆる情報通信分野のかな漢字入力手段として引き継がれ、今も発展を続けています。さらに、この「かな漢字変換技術」で開発された言語処理技術は、中国語や韓国語など、ほかの象形文字を扱う言語の入力技術にも大きな影響を与えました。
■「日本初のパソコン」発売前、トレーニングキットが発表されていた!
「PC-8001」が発売される3年前の1976年8月、NECは「TK-80」という商品を発表しました。「TK」はトレーニングキットの頭文字で、トレーニングの対象はマイクロコンピュータ、略してマイコンです。
価格は88,500円。当時、大卒男性の初任給平均が約9万4,300円という時代ですから、決して安くはありませんが、サラリーマンや学生でもなんとか手の届く価格でした。
「TK-80」は、コンピューターが「パソコン(パーソナルなコンピュータ)」として普及する前夜、マイコンがどのようなものなのか、どのように使えばよいのかを学び、知ってもらうための学習用トレーニングキットだったのです。基盤を中心とした半完成品を自分で動作させることで、その仕組みをよりわかってもらえるだろうという狙いもあったそうです。
■日本初のパソコン「PC-8001」とは
NECが1979年に発売した「PC-8001」は、キーボードと本体が一体化したデザインで、サイズは幅430×奥行き260×高さ80mm、重量は4kg。定価は168,000円でした。
「PC」は[personal computer(パーソナルコンピュータ)]の略で、当時は「マイクロコンピュータ」の略称である「マイコン」が一般的でした。しかし、NECは、この「PC-8001」から「パーソナルコンユータ」という名称を正式に用い、略称「パソコン」として商標登録し、一般に定着させていきました。「PC-8001」はパソコンブームの火付け役となり、PC-8000シリーズは3年間ほどで約25万台を売り上げ、同社を代表するシリーズのひとつとなりました。
■世界初のコンピューターは?
コンピューターの元祖については諸説あります。たとえば、1945年に完成した「ENIAC」は、世界初の汎用電子計算機として知られています。体積は約167㎡、重量は30トンもあり、まるで専用の建物が必要なほどの巨大さでした。
ただし「世界初のコンピュータ」が何かについては議論があります。ドイツで1941年にコンラート・ツーゼが開発した「Z3」は、リレーを使ってプログラム制御を実現した機械で、こちらを世界初のコンピュータとみなす説もあります。
■パソコンはいつからある?
世界初の「商業的に成功したパソコン」と言われるのが、1975年にアメリカのMITS社(Micro Instrumentation and Telemetry Systems)が開発した「Altair 8800」です。当時の価格はキット版で395ドル(完成品は650ドル)でした。当時、1ドル=304円の時代ですから、キットで約121,600円。大卒初任給の平均が89,300円でしたから、驚く程高価なものではなかったようですが、「組み立て式」で、操作もスイッチとランプによるもおのだったため、扱える人もかなり限られていたと考えられます。
■日本ではMac[Macintosh]ブームがパソコン普及に拍車をかけた
内閣府の調査によると、パソコンの普及率は1990年代前半までは10%台で、一部の専門家やマニアに限られたものでした。90年代後半になると急激に普及率が上昇し、2001年には半数を超えています。
そんななか、1998年に登場した「iMac G3」が大ヒット。最初は「ボンダイブルー」の半透明ボディのみでしたが、翌年以降には「ストロベリー(赤)」「ブルーベリー(青)」「ライム(緑)」「グレープ(紫)」「タンジェリン(オレンジ)」といったカラフルなラインナップが加わり、ポップなデザインからブラウン管が透けて見える斬新さで人気を集めました。
このブームによって、当時経営難に陥っていたアップルの業績は一気に回復し、同時に「パソコンを使いこなすのがおしゃれ」という時代が到来したのです。

***
今ではなくてはならないものとなっているパソコンですが、東芝が世界初の日本語ワープロを発表したのは1978年(出荷は1979年)のことでした。アルファベットを使用する英語とは異なり、同音異義語が多く、多数の漢字のなかから適正な文字を選択しなければならない日本語ワープロの実用化が、どれほど難しかったのかは想像に難くありません。
このときに開発された「かな漢字変換技術」は、やがてパソコンやスマートフォンの入力方式に引き継がれ、私たちが今享受している利便性や楽しさの基盤となりました。
しかしながら、東芝は2020年までにノートパソコン事業から完全撤退しています。時の流れ、技術革新のスピード、そして時代や文化の移り変わりを感じさせる出来事です。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『日本国語大辞典』(小学館) /『デジタル大辞泉』(小学館) /東芝レトロSeries 特別編「JW-10」#ワープロ記念日(https://www.youtube.com/watch?v=Ig74lCz_Dd4) /公益社団法人発明協会 戦後日本のイノベーション100選事務局(https://koueki.jiii.or.jp/innovation100/innovation_detail.php?eid=00060&age=stable-growth&page=keii#:~:text=1978年、東芝は自,健一によって始められた%E3%80%82) /NEC LAVIE公式サイト「NECパソコンの歴史」(https://support.nec-lavie.jp/navigate/application/history/20120828/index.html) :