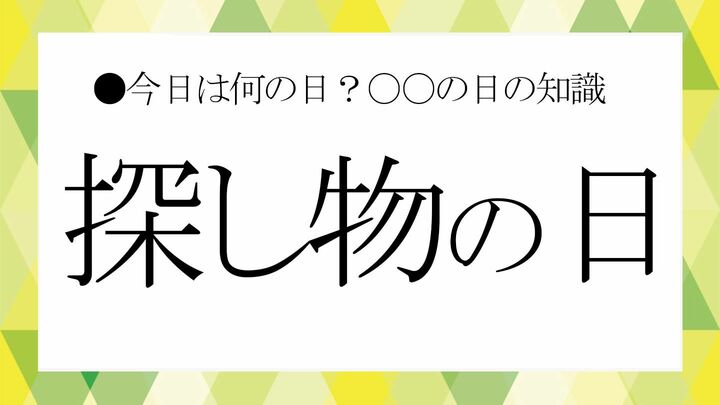【目次】
【10月4日は「探し物の日」由来は?】
「探し物の日」の日付は、NTTの電話番号案内が104番であることに由来します。「電話番号を探す=探し物」という連想から、失くした物をもう一度探してみる日とされていますが、この記念日がいつ、誰によって制定されたか等は不明です。そもそも、電話番号案内サービス『104』を知らない世代もかなり増えているかもしれませんね。
【日本人の「探し物」にまつわる雑学】
■電話案内『104』は2026年3月に終了…!
皆さんは“番号案内『104』”を利用したことがありますか?これは、局番なしの「104」に電話をかけ、オペレーターに相手の名前と住所を伝えると、有償で電話番号を教えてもらえるサービスです。NTT東日本・西日本・NTTドコモが関わっており、24時間対応だったり、携帯電話からの対応もあったりします。
かつては1989年度に利用件数が約13億回とピークを記録しました(12億8,000万回という数字を挙げる報道もあります) 。しかし、ネットやスマートフォンの普及などを背景に、2022年度には約2,000万回程度にまで激減したとされています 。また、2023年5月1日からは、104利用時の案内料がこれまでの275円から 440円( に改定されています 。
■日本人は年間◯時間「探し物」に使っている?
文具メーカー「コクヨ」が2022年にインスタグラム公式アカウント「コクヨのぶんぐ」のフォロワーを対象に行ったアンケートによると、ビジネスパーソンが仕事中に何らかの「探し物」に費やしている時間は、一日平均で約13.5分。これを年間に換算すると、実に約54時間にもなるそうです。
実はこのアンケートは2018年にも行われており、その際の結果は一日平均20分、年間にして約80時間。比較すると、この数年間で探し物にかける時間は減少傾向にあることがわかります。背景には、近年のデジタル化によって紙の資料そのものが減り、それに伴い「探し物」も減ってきたことが考えられるでしょう。
とはいえ、仕事中だけでこれほどの時間を費やしているのですから、決して軽視できません。これにプライベートでの「探し物」まで加えたら…年間でどれほどの時間になるのか、想像するだけでも恐ろしいですね。
■財布、鍵、スマホ…「いちばんなくすもの」は?
「落とし物クラウドfind」を提供する株式会社「find」は2025年、4月25日の「拾得物の日」にあわせ、全国の提携施設における落とし物の傾向をまとめた「施設別落とし物ランキング」を公開しました。
【施設別落とし物ランキング】
商業施設……1位:現金 2位:食品 3位:タオル・ハンカチ
鉄道…………1位:現金 2位:手袋 3位:スマートフォン
タクシー……1位:スマートフォン 2位加熱式たばこ 3位クレジットカード
また、紛失防止タグ「MAMORIO」を展開するMAMORIO株式会社が、10代~70代の全国男女500名を対象に実施した「家の中での物の捜索についての実態調査」によると、家の中で物をなくす回数は1か月に平均3.2回。なくしやすいと感じている物は、1位が「鍵」、2位が「スマートフォン・携帯電話」で、このふたつで約半数を占めています。
さらに、回答者の75.2%が実践している紛失対策としては、「物の定位置を決める」「定期的に整理整頓を行う」といった工夫が多く挙げられました。
「1か月に平均3.2回」という結果は、筆者にとっては意外と少ない印象でしたが、皆さんはいかがでしょうか。
■日本には平安時代から遺失物管理の役所があった?
昔の人は、落とし物をしたとき、どうやって探していたのでしょうか。実は日本には、平安時代以前にすでに「贓贖司(あがもののつかさ/ぞうしょくし)」と呼ばれる役所が存在しました。「贓贖司」は律令制下で刑部省に属していた官司のひとつで、盗品や没収品などを管理する部署です。必ずしも現在の「遺失物センター」のように落とし物を取り扱っていたかは定かではありませんが、物品の管理や処分を担う仕組みが当時すでにあったことは興味深い事実といえるでしょう。
さらに時代が下って江戸時代になると、落とし物は町奉行所に届けられるようになりました。奉行所では拾得物を記録し、落とし主が現れるまで一定期間保管。持ち主が現れなければ処分されたり、場合によっては拾い主に渡されたりすることもありました。公示の方法は「高札」や「町触れ」といった掲示・触れ回りが中心で、人々はそれを頼りに落とし物を探していたのです。
■江戸時代の「公事方御定書」とは?
江戸幕府が定めた基本法典「公事方御定書(くじかたおさだめがき)」には、拾得物の取り扱いが明記されていました。現金の場合は落とし主と拾い主が半々に分け合い、謝礼も現代より高額。さらに、持ち主が半年現れなければ拾い主の物になるなど、現在の仕組みに通じる規定がすでに存在していたのです。
この考え方は明治時代に引き継がれ、1899(明治32)年に「遺失物法」として制定されました。そして2007年には大幅に改正され、現在の遺失物制度に至っています。
■現在の遺失物の扱い
●落とし物や忘れ物をした人は…
落とし物や忘れ物をしたと思う施設、最寄りの警察署、交番・駐在所に問い合わせを。次に警察署、交番・駐在所で遺失の届出をします。拾得物の情報はインターネットで公表されているので、確認することも可能です。
●落とし物や忘れ物を拾った人は…
駅構内や鉄道の車内、デパートやストアなどの施設で拾ったものは、その施設に届けるのが基本。それ以外
の、道路などで拾った場合は、警察署、交番・駐在所に届けます。道で拾った場合は1週間以内、路上以外の駅構内やデパート内などの特定施設で拾ったときは、24時間以内に届け出る必要があります。
届け出ると、拾得者には以下の権利が発生します。
●拾った物件の時価の5~20%を落とし主からお礼として受け取る権利
●落とし主が分からない場合は3か月後に拾った物件を受け取る権利
「お礼はいりません、拾った物ももらわなくて結構です」という場合は、届け出るときに「権利放棄」が必要です。
■世界が驚愕!「日本の遺失物返還率」
日本では、「落とし物をしても高い確率で手元に戻って来る」という定評がありますが、実際に「遺失物変換率」はどのくらいなのでしょうか。産経新聞などの報道によれば、2024年に東京都内で落とし物として交番や警察署などに届けられた現金は約44億9千万円で過去最多を更新。これは毎日1200万円以上が届けられている計算になります。
そのうち、持ち主に返された現金は、約32億3千万円。物品は約136万点が変換されたとされています。
一方、拾得者に引き渡された現金は約5億7千万円、物品は約160万点でした。持ち主が判明せず、拾得者も所有権を放棄するなどした約6億6千万円は都の歳入となっています。現金に限っていえば、7割以上が持ち主の手に戻ったことになります。
また、警視庁のデータによると、2018年、東京管内においては証明書類(身分証など)等、約101万件の遺失物届が提出され、拾得届は約75万件でした。たとえば財布では9割以上が落とし主のもとへ戻るとされ、スマートフォンでも半数以上が返還されているそうです。「遺失物変換率」の高さは世界的な基準としては珍しく、日本を訪れる外国人旅行者から「日本が好きな理由のひとつ」と語られることもあります。誇らしいですね!
■「落とし物」の捜索にAIを活用!
AIを活用した落とし物管理システム「落とし物クラウド find」が注目を集めています!「find」は2023年5月に京王電鉄に正式導入されて以来、鉄道会社・バス事業者・商業施設など、多様な施設で採用が進んでいます。
使い方はシンプル。利用者が落とし物の特徴や画像を送信すると、その情報をもとに AI がデータベース内の落とし物情報と照合します。これにより、迅速かつ効率的に落とし物を探すことが可能になります。多言語入力や他施設との横断検索にも対応し、「どこで無くしたかわからない」ケースにも対応しているのが特徴です。
京王電鉄での導入後、落とし物の返却率は導入前の 8~10% 程度から約 32% にまで上昇し、約3倍となりました。問い合わせ件数も約3割減少したと報告されています。慶応義塾大学+2株式会社find(ファインド)+2 このような成果を背景に、他の鉄道会社や公共交通機関、施設への拡大が期待されています。
日本中、どこでもこのシステムが使えるようになれば、落とし物対応のストレスがぐっと減りそうですね。
***
ビジネスパーソンが仕事中に「探し物」に費やしている時間は、一日平均で13.5分。年間にすると実に54時間ものロスになるそうです。それでも日本では、落とし物の7割以上が持ち主に返還され、財布は9割以上が戻ってくるという驚異的な返還率を誇ります。
もしAIの活用がさらに進めば、この数字はもっと高まるかもしれません。「失くしたら終わり」ではなく、「探せば見つかる」社会――。世界から見ても特別なこの仕組みを、次世代にもつないでいきたいですね。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『日本国語大辞典』(小学館) /『日本大百科全書 ニッポニカ』(小学館) NTT東日本(https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20240719_01.html) /コクヨマガジン〔https://www.kokuyo-st.co.jp/mag/work/2022/02/000212.html〕 /落とし物クラウドfind(https://www.finds.co.jp/news/detail/202504241000) PRTIMES(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000211.000022173.html)(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000104939.html) /改正遺失物法(https://www.city.shimotsuke.lg.jp/manage/contents/upload/582186d6c085f.pdf) /産経新聞(https://www.sankei.com/article/20250304-YV7SAWD7RVIE5HTZGTOMFWWFOM/) /NewSphere(https://newsphere.jp/national/20200901-1/) /朝日新聞(https://www.asahi.com/articles/AST454H29T45OXIE00HM.html) :