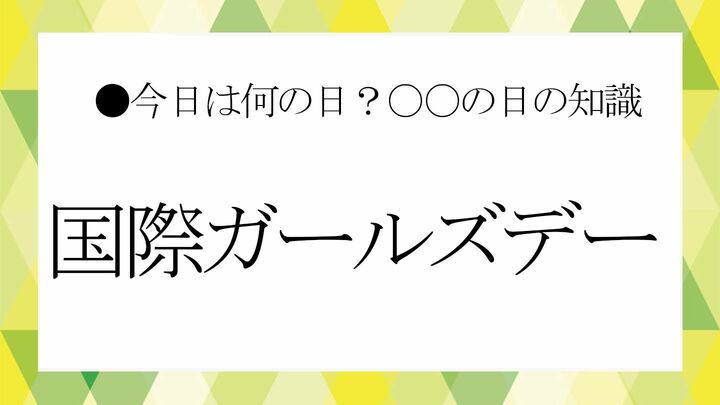【目次】
【「国際ガールズ・デー」とは?「意味」「由来」】
■意味
「国際ガールズ・デー」は国連が定める国際デーのひとつです。女の子の人権について考え、教育とエンパワーメントを推進するためのさまざまなイベントを世界各国で開催しています。エンパワーメントとは、女性が人生におけるあらゆる選択肢を“自分の意思”で選びとり、生きていくために必要な力や男性と対等に家庭内や社会の意思決定に参画する力をつけることを指します。
■いつ?
毎年10月11日です。2011年12月に国連総会で正式決定されました。初開催は2012年です。
■由来
途上国では女の子の多くが経済的、文化的な理由によって学校に通えず、10代前半での結婚を余儀なくされ、貧困の中で暮らしています。また、先進国でも女の子にはさまざまな社会的制約が存在します。けれど適切な教育と支援を受けることができれば、彼女たちの可能性は広がり、その未来は大きく変えることができます。「国際ガールズ・デー」では世界各地で女の子自らが声をあげ、彼女たちを応援するイベントやアクションが行われます。
■英語では?
[International Day of the Girl Child]と表記します。
【「女の子」の権利と世界の現状の雑学】
社会、経済、環境などが貧しい国ほど、女性、特に幼い女の子の人権が守られないのが現状です。
■「発展途上国」とは?
明確な基準はありませんが、ひとり当りの国民所得が低い国を指します。かつては「後進国」や「低開発国」などと呼ばれましたが、1960年代の初めごろから、発展あるいは経済開発が進みつつある国として、開発の途上にある国を「発展途上国」や「開発途上国」と呼ぶようになりました。抽象的に「発展途上」というより、経済や産業、技術など具体的に開発途上にあるという意味で「開発途上国」と呼ばれるほうが一般的。単に「途上国」という場合もあります。
■「後発開発途上国」って聞いたことありますか?
開発途上国の中でも、特に社会的・経済的な開発が遅れている国を「後発開発途上国」と言います。経済社会理事会の下に設置された国連開発計画委員会が設定した、ひとり当たり概(おおむ)ねGNI750ドル未満などの基準をもとに後発開発途上国と認定されているのは、2024年12月現在で44カ国。そのうちの32カ国はアフリカにあります。これらの国は、極度の貧困と膨大な対外債務に苦しみ、グローバル経済から取り残されています。
■年齢別にみる途上国の女の子
途上国での年齢別現状を知ることで、女の子の人権をより具体的に考えられるかもしれません。
・誕生から5歳くらい:途上国では望まない妊娠・出産も多く、誕生しても祝福されずに成長することが少なくありません。栄養面や衛生面など生育環境が整っておらず、乳児・幼児の死亡率は相対的に高くなります。
・6歳くらいから11歳くらい:水汲みなどの重労働から年下の子どもの世話など、教育を受けるべき時間は労働に費やされます。
・12歳くらいから18歳くらい:早すぎる結婚、妊娠・出産を強いられることも少なくありません。未婚のまま出産を迎えることも。
これ以降も、収入も発言権もないまま、地域社会から「労働力」や「労働力を生む母体」としての価値しか認められないことも…。
■学校に通えない女の子…教育の現状
過去20年間で非就学の女の子の数は39%減少しましたが、2024年時点で、世界でまだ1億2,200万人の女の子が学校に通えず、一般的な教育を受けていません。特に南アジア(インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、モルジブ、ネパール、ブータンの総称。アフガニスタンを含める場合も)の15歳から19歳までの女の子は、男の子と比べて学校や職場、職業訓練のいずれにも通っていない可能性が3倍に上ります。
■時代とともに変わるディズニーの「プリンセス像」
ウォルト・ディズニーによるプリンセス――と聞いて、白雪姫、シンデレラ、『眠れる森の美女』のオーロラ姫を挙げる人もいるでしょう。 この「ディズニー3大プリンセス」と言ってもいい作品が誕生したのは、1937年、1950年、1959年のこと。日本でいえば、昭和12年、昭和25年、昭和34年といずれもかなり昔の作品ですが、それだけ長く愛されるキャラクターであるということですね。しかし…現代の子どもにとっての“プリンセス”は『モアナと伝説の海』のモアナかもしれません。『リトル・マーメイド』のアリエルかも? 時代とともにそれらプリンセスの設定キャラクターは変化しています。
例えば、上記3作の初期のプリンセスは、いずれも受動的な女性です。幸せは結婚と共に訪れるもので、王子様の登場や、素敵な男性との出会いを健気に待つ女性が描かれました。
1989年に公開された映画『リトル・マーメイド』のアリエルは、自分の夢を叶えるために陸に上がることを決意したヒロイン。また1991年公開の『美女と野獣』のベルは、知的好奇心に満ち、困難な状況でも自分を見失わず、それを乗り越えようとする女性として描かれました。このころのディズニーのヒロインは、欲望や夢を追い求め、主体的に行動を起こすなど、時代に沿うようになります。
そして現代のプリンセスといえば、『アラジン』のジャスミン姫や『モアナと伝説の海』のモアナでしょう。ジャスミンは、望まない結婚を強いられる環境から自立しようとします。モアナは使命を果たすために大海原へ冒険に出かけます。自身の能力を信じ、強い意思を持ち、周囲に囚われず自らの道を歩んでいく姿は、とても現代的ですね。
■「国際女性デー」もあります!
3月8日の「国際女性デー」は、1975年に国連が制定したもの。1908年にニューヨークで行われた婦人参政権を要求するデモを起源とし、女性への差別撤廃と女性の地位向上を訴えます。
■日本の「女の子の日」とは?
五節句のひとつである3月3日は「女の子のための日」と言ってもいいでしょう。五節句とは、「人日(じんじつ)/1月7日」「上巳(じょうし)/3月3日」「端午(たんご)/5月5日」「七夕(しちせき)/7月7日」「重陽(ちょうよう)/9月9日」のこと。
ひな祭りの起源は平安時代中期(約1000年前)にまでさかのぼります。そのころは3月の初めの巳(み)の日に、「上巳の節句」といって無病息災を願う祓いの行事をしていました。陰陽師を呼んで天地の神に祈り、季節の食物を供え、また人形(ひとがた)に自分の災厄を托して海や川に流すのです。その当時、上流社会の少女たちの間では「ひいな遊び(人形遊び)」が流行。紙などで作った人形を使ったままごと遊びですね。紫式部の『源氏物語』では、「末摘花」や「紅葉賀」など、いくつかの章で「ひいな遊び」が登場します。
江戸初期の寛永6(1629)年に京都御所で盛大なひな祭りが催されましたが、このころから幕府の大奥でもひな祭りを行うようになったとか。この習慣は上流階級の子女から町民の娘へ、江戸や京都など都市部から地方へと大きく広がっていきました。
「人形遊び=女の子の遊び」とは限りませんが、ひな祭りの風習は現代も続いています。住宅事情などで立派な雛人形を飾る家庭は少なくなっていますが、3月3日が近くなると心躍る女性は少なくないのではないでしょうか。
***
「国際ガールズ・デー」は、女性に生まれてきたというだけでハンデを背負わざるを得ない途上国の女の子に思いを馳せる日。オンラインでのチャリティイベントなどもあるので、気になった方はぜひ調べてみてください。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『日本大百科全書(ニッポニカ)』(小学館)/『世界大百科事典』(平凡社)/『デジタル大辞泉』(小学館)/『12か月のきまりごと歳時記(現代用語の基礎知識2008年版付録)』(自由国民社)/国際連合広報センター https://www.unic.or.jp/ :