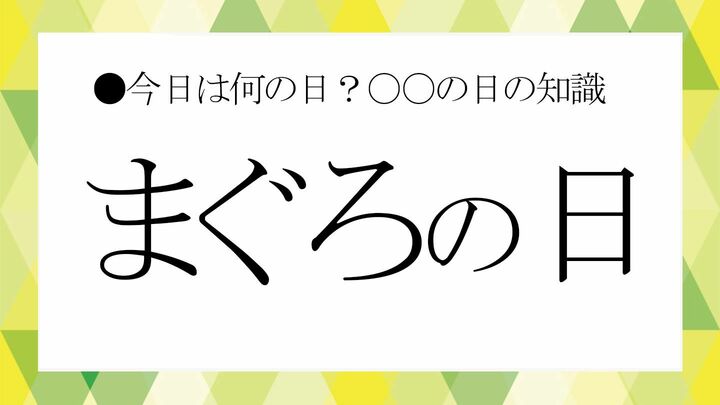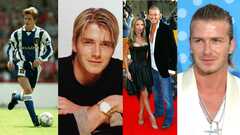【目次】
【「まぐろの日」とは?由来】
■「誰が」「いつ」決めた?
「まぐろの日」は10月10日です。鰹や鮪の漁業関係者で構成される「日本かつお・まぐろ漁業協同組合」が1986(昭和61)年に制定しました。
■「由来」は?
奈良時代の歌人・山部赤人が726(神亀3)年10月10日、聖武天皇のお供として兵庫県の明石地方を訪れた際に、まぐろ漁で栄えるこの地方を讃え、歌を詠んだとされています。『万葉集』(巻6・938段)に収められたこの歌は、日本人とまぐろの深い関わりをしのばせる歌でした。そこで、山部赤人が歌を読んだとされる日にちなみ、毎年10月10日が「まぐろの日」となりました。
■「目的」は?
全国でもっとたくさんまぐろを食べてもらうことが目的です。
【ビジネス雑談に役立つ「まぐろ」にまつわるの雑学】
■「まぐろは止まると死ぬ」ってホント?
実はこの説は「誇張された話」なんだそうです。実際には、海では常に潮が流れていいるため、止まっていられるような状況にはありません。まぐろも夜間などは速度を落として休息しますし、人間の歩く速度と同じぐらいの速さで泳いでいることもあるそうです。止まってもすぐに死ぬというわけではありませんが、まぐろは自らエラブタを動かす事ができないため、泳ぎながら口からエラの中に酸素を取り込む必要があるそうです。
■どれくらいの速さで泳ぐ?
8000kmにも及ぶ太平洋を横断することから、まぐろは時速160kmで泳ぐという説もありますが、実際の回遊時は、時速4~8kmほどで、エサを捕るときや外敵から逃れるときなどに、瞬間的に時速100キロ近く出すこともあるそうです。
■日本人はいつからまぐろを食べてるの?
岩手県陸前高田市にある縄文時代中期の太陽台貝塚からは、マグロの骨の断片が出現しています。つまり、約5000年以上の昔、縄文人はマグロを食べていたということになります。万葉の歌人・山部赤人が726(神亀3)年10月10日にまぐろの歌を詠んだことは前述の通り。日本人にとってまぐろは本当に長い間、愛されてきた魚なのですね!
江戸時代中期になると、江戸周辺で濃口醤油が広く出回るようになりました。これにより、「マグロの醤油漬け」が人気となり、消費量が一気に拡大。当時、ファーストフードとして注目を集めて始めていた握り寿司屋が目を付けたことで、いっそう人気を博しました。江戸ではもっぱた細巻きが好まれ、それも四角く巻かれたそうです。ただし、トロは見向きもされず、赤身が好まれたとか。
■冷凍まぐろをおいしく食べる方法は?
遠洋漁業で漁獲されたまぐろは、釣りたての鮮度を保つためにマイナス60度の超低温で急速冷凍されます。冷凍まぐろの鮮度を落とさずに解凍するコツは、「氷水解凍」です。手順をご紹介しましょう。
1. 凍ったままのまぐろの表面をさっと水洗いし、表面に付着している「切りカス」を洗い流します。
2. 水1リットルあたり塩40gの塩水を作り、水洗いしたまぐろをくぐらせます。こうすることで、まぐろの発色がよくなります。
3. ペーパータオルでまぐろの表面の水気をふき取り、ビニールパック等に入れ、空気を抜きます。
4. 袋の中に水が入らないよう注意しながら、氷水に1時間~1時間半くらい浸します。
5. まぐろを袋から取り出し、ペーパータオルで水気をふき取れば、解凍完了!
■天然と養殖はどう違う?
マグロには天然と養殖があるのはご存知ですよね。天然もので、日本で主に食べられているマグロは5種類。なかでもマグロの王さまといわれるのがクロマグロ(別名本マグロ)です。クロマグロは日本近海で産卵した後、太平洋へ出た後にハワイ沖を回遊し、メキシコまで行ってアメリカ西岸を北上。アラスカまで行って戻ってきます。すごい距離ですね! 赤道を越えることはほとんどなく、北太平洋を何年もかけて回遊しているそうです。一方で、南太平洋を大きく回遊しているのがミナミマグロ(インドマグロ)で、南アフリカのケープタウン沖で捕れるものが高評価なのだそう。日本近海や東南アジア沖でよく捕れるのは、メバチ、キハダ、ビンナガ(ビンチョウ)です。メバチはマグロの中で最も漁獲量が多く、冷凍ものが安定的に出回っています。
養殖には、卵から孵化したばかりの稚魚から育てるものと、卵を孵化させて育てる完全養殖の2種類があります。クロマグロ、ミナミマグロが対象で、日本では鹿児島・長崎・愛媛・高知が主な産地です。完全養殖は30年以上の研究を経て、2002年に近畿大学が成功し、「近大マグロ」として話題になりましたね!
■まぐろの部位について知りたい!
本マグロは、捨てるところがないと言われます。回転寿司でおなじみの「すしざんまい」によれば、意外と知らていない本マグロの部位でおすすめなのは、「はがしとろ」と「中落のにぎり」なのだそうです。
(1)背節上(カミ)/中トロ・赤身
マグロの場合、基本的には腹側が高価。対して、背節(背骨の上部。頭側からカミ、ナカ、シモとなる)の部位は、価格的には腹節下の次にあたります。お値打ちな部位で、中トロ〜赤身の部位となります。
(2)背節中(ナカ)/中トロ・赤身
背節上(カミ)、背節下(シモ)同様、お値打ちな部位で、中トロ〜赤身の部位です。
(3)背節下(シモ)/中トロ・赤身
こちらも中トロ~赤身に使用される部位。
(4)腹節上(カミ)/大トロ・中トロ・赤身
背骨の下部の真ん中辺りが、一般的に一番美味しいとされる部位。寿司屋で大トロと言われるにはこの部分で、マグロ自体の産地などにもよりますが、高級店の大トロはこの部分が多く使われます。
(5)腹節中(ナカ)/大トロ・中トロ・赤身
中トロと大トロの間のような存在。寿司屋で大トロ・中トロとして出てくることの多い部位。
腹節上(カミ)より脂ののりは少ないが、脂のノリが強いのが中トロとなる。
(6)腹節下(シモ)/中トロ・赤身
背骨の下部、尾びれの近く。一般的に中トロと呼ばれる部位。寿司屋で中トロとして、また割烹料理店などでよく使用される。程よい脂の乗りが特徴です。
(7)カマ
エラの下の胸びれ付近。カマトロとも呼ばれ、少数しか取れない貴重な部位で、牛肉の霜降りに似た、トロけるような味わいが特徴です。
(8)その他部位
マグロは非常に多くの部位を使用できる魚です。目周りのゼリー状の部分はDHAを非常に良く含み、トロトロして美味しい部位。ホホ肉、ひれカマ、頭肉、尾の身など様々な部分が美味しく食べられます。
■毎年高値が報道される「まぐろの初競り」。どうしてあんなに高値がつく?
2025年1月5日、東京・豊洲市場(江東区)で新春恒例のマグロ初競りが開かれ、276キロの青森・大間産が2億700万円で落札されました。これは豊洲移転後、2番目となる高値です。過去最高は、移転後初めて迎えた19年正月の初競りで、3億3360万円でした。
19年に3億3360万円で落札した「すしざんまい」によれば、超高額な競り値は、広報・PR戦略のひとつだったそうです。というのも、3億3360万で落札したマグロも、店頭では通常時の値段と変わらず提供されており、大とろ1貫398円(税抜)、中とろ1貫298円(税抜)で振舞ったそうです。1貫2万円でも原価割れするということなので、大赤字だったのは間違いありませんが、それでもPR効果は十分にあったということでしょう。
***
「まぐろの日」が、歌人・山部赤人に由来した記念日だったとは、意外ですね。最後にその由来ともなった赤人の長歌をご紹介しましょう。
天皇の 御代しらすらし 印南野の うまの原の 藤井の浦に
鮪釣ると 海人の釣舟 行き違ひ 潮焼くと 海人の釜据ゑ
浜びさし い隠り立てり 釣人の 多にあるらし 塩焼くと
海人の煙も いや立ちにけり 御民われ 生ける験あり
この浜の 清き見れば 天皇の 御代栄えむと
東なる み坂の上に 風吹けば 雲居に見ゆる
明石の浦に 舟出して 玉つくる 海人は多けむ
鰹釣る 海人は多けむ 浦見れば 楽しき浜に
年魚釣る 釣人多み 塩焼くと 海人の煙の
いや立ち渡る この浦の 名に負ふ海人の
八十(やそ)伴の 思ひつつぞ来し
我が背子が 使と言へれば
現代訳:
天皇がこの国をお治めになっているのだろう、印南野の馬(うま)の原にある藤井の浦では、
マグロを釣る漁師たちの舟が、行き交い、塩をつくるために海水を煮る釜が浜に並べられ、
浜辺には板小屋がずらりと並んでいる。
釣りをする人々もたくさんいて、塩を焼く煙もどんどん立ちのぼっている。
こうしたにぎやかな景色を見ると、私たち天皇の民が生きているかいがあると感じられ、
この浜の清らかさを思えば、天皇の御代が栄えるのももっともだと、心から思える。
東の丘の上から風が吹けば、空の彼方に、明石の浦が遠くに見える。
そこに船を出して、真珠を採る漁師もたくさんいるだろう。
カツオを釣る漁師も、たくさんいることだろう。
浦の様子を見渡すと、なんと楽しい浜だろうか。
鮎を釣る人々も多く、塩を焼くための煙が、浜全体に立ちのぼっている。
この有名な浦にちなんで、たくさんの仲間たちのことを思いながら、私はやって来た。
なぜなら――愛しいあの人の使いとして来たのだから。
自然詠の名手と評された赤人らしい、「自然の美」と「人々の営み」の描写に「天皇への敬意」を込め、最後に恋心をちらりと覗かせる、という、バランスの取れた歌とされています。のどかで美しい風景が目に浮かぶようですね。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『デジタル大辞泉プラス』(小学館) /日本かつお・まぐろ漁業協同組合(https://www.japantuna.net) /すじざんまい(https://www.kiyomura.co.jp) /『マグロはおもしろい 美味のひみつ、生き様のなぞ』 (講談社文庫) /『杉浦日向子の江戸塾』(PHP文庫) :