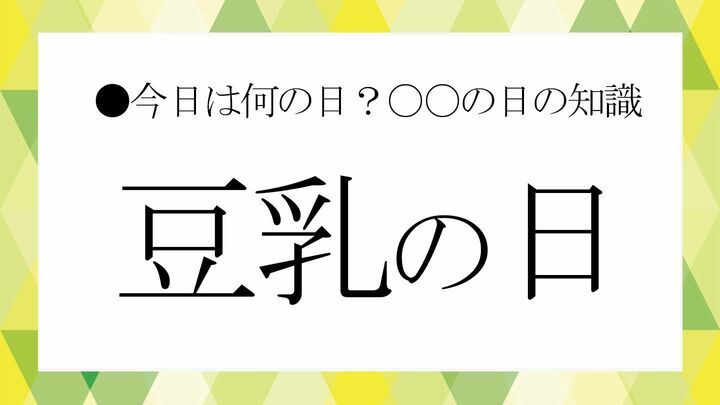【目次】
【「豆乳の日」とは?由来】
■「いつ」「誰が」決めた?
毎年10月12日は、「豆乳の日」です。日本豆乳協会が2008年に制定し、一般社団法人 日本記念日協会HPにより、認定・登録されています。
■「目的」は?
豆乳に関する知識の普及や検定試験を通じて、豆乳の効能をPRし、豆乳の消費を活発にすることを目的としています。
■「由来」は?
日付は、健康や体のケアに関心が高まる月である10月と、「とう(10)にゅう(2)」の語呂合わせから10月2日が選ばれました。
【ビジネス雑談に役立つ「豆乳」にまつわる雑学】
■そもそも「豆乳」って何?
「豆乳」とは、大豆を水につけて柔らかくしたあと、水を加えてどろどろにすり砕き、加熱して布袋で漉 (こ) したミルク状のものを指します。もともとは、豆腐を製造する際にできた副産物。タンパク質、ビタミンB1が豊富なため、栄養飲料としても広く用いられてきました。
市販品には「豆乳」「調製豆乳」「豆乳飲料」の3種の表示があります。お気づきでしたか? このうち、本来の豆乳は、丸大豆を使った「豆乳」の表示のもの。「調製豆乳」は、大豆タンパク質や粉末の加工大豆を用いたり、植物油や糖などを添加したもの。「豆乳飲料」は豆乳または調製豆乳が50%以上含まれているもので、果汁、コーヒーなどを混ぜたものです。
■豆乳の歴史を知りたい!
豆腐の歴史は古く、今から2000年前に中国で発見されたと言われていますが、日本に伝わったのは奈良時代から鎌倉時代頃とされています。同じ時期に、豆乳も「豆腐羹(一種の精進料理)」として紹介されていましたが、豆乳という名前で広く飲用されるようになったのがいつ頃からかは定かではありません。
飲み物としての豆乳は、1975(昭和50)年頃までは、もっぱらお年寄りや乳糖不耐性の幼児用の粉末主体の飲料でした。1975年前後の経済発展期になると、牛乳や肉などの栄養摂取傾向とともに、いまの豆乳商品に近い容器入り豆乳の開発、生産が盛んになり、味や品質向上の工業生産技術が革新されました。1979(昭和54)年7月に、紀文ヘルスフーズ(現キッコーマンソイフーズ)が無菌充填の紙パック200ml豆乳5種を全国販売したことに続き、岡崎マルサン や三菱化成や明治乳業やヤクルトなどの新規参入があいついで、いわゆる第一次豆乳ブームになり、1983(昭58)年には総豆乳(類)生産量12万klを記録しました。
■牛乳 vs 豆乳 どちらがカラダにいいの?
結論から言えば、飲む人の体質や飲む目的、着目する栄養成分によって異なるので、一概にどちらの方がよいとは言い切ることはできません。豆乳と牛乳に含まれる栄養価を比較してみましょう。
無調整豆乳 普通牛乳
エネルギー 44kcal 61kcal
たんぱく質 3.6g 3.3g
炭水化物 3.1g 4.8g
食物繊維 0.2g (0g)
脂質 2.0g 3.8g
飽和脂肪酸 (0.32g) 2.33g
カルシウム 15mg 110mg
鉄 1.2mg 0mg
▲出典:2020年版 文部科学省『日本食品標準成分表(八訂)準拠』
前提として大きな違いは、豆乳は大豆から絞った植物性食品、牛乳は牛の体内で血液から作られる動物性食品という点。どちらもたんぱく質を多く含む飲み物という点では共通しています。たんぱく質は豆乳も牛乳もほぼ同程度含んでいますが、豆乳の方が低糖質・低脂質のため、カロリーが低い傾向にあります。さらに飽和脂肪酸が豆乳にはほとんど含まれていないのは、豆乳が優れている点ですね。ダイエットや生活習慣病予防のためには、豆乳を選ぶとメリットが多いと言えそうです。
そのほかで着目すべき違いは、カルシウムと鉄です。これらふたつは、日本人が不足しがちな栄養素。日々の食生活の中で意識して摂る必要がありますが、カルシウムはやはり牛乳が圧勝で、豆乳の約7倍も多く含んでいます。一方、鉄に着目すると、豆乳には含まれても牛乳には含まれていないため、豆乳の方が優っていると言えるでしょう。牛乳の場合はカルシウム、豆乳の場合は鉄を、それぞれコップ1杯(200g)飲むことで成人が一日に摂りたい推奨量の約3分の1日分近くをとることができます。牛乳と豆乳、どちらが自分にあっているのかを判断して、賢くセレクトしてくださいね!
■豆乳の消費量。日本は世界第4位。1位は?
世界の豆乳市場におて、消費量第1位は中国です。人口が多いのはもちろんですが、もともと中国では豆乳が伝統的に飲まれており、大変親しまれた飲み物です。タイやベトナムでも、“肌によい”、“記憶力によい”など、機能性を訴求する豆乳が発売され、人気上昇中。近年の市場調査では、日本は世界第4位前後の消費国ですが、健康志向の強い後押しを受け、毎年拡大してきています。
■豆乳を飲むと認知症リスクが低下する?
高齢化に伴い、認知症患者の数は年々増加しています。ちょっとした物忘れが重なると、「若くて始まる認知症もあるというし…」と、不安に感じたことのある人は多いのでは? そこに朗報です。2023年10月、イギリスの研究グループによる報告によると「豆乳を飲む人は豆乳を飲まない人に比べて認知症のリスクが3割軽減される」可能性が示唆されました。豆乳が認知症リスクの低下と関係する理由については、「豆乳に含有されるイソフラボンの作用や、牛乳に比べて飽和脂肪酸が少なく不飽和脂肪酸が多いことなどが影響しているのではないか」と考えられています。
また、豆乳などの大豆製品は「大豆レシチン」という栄養素が豊富。レシチンは細胞膜の主成分で、脳神経や神経組織を構成しており、レシチンなどのリン脂質が不足すると、細胞膜が正常に働かなくなったり、コレステロールが蓄積したりすることもあります。
レシチンは、神経伝達物質を生成することで記憶力の低下や認知症の予防に効果があるとされ、動脈硬化の予防や脂質代謝の活性化効果も期待できるといわれています。アルツハイマー型認知症の原因のひとつは、脳内神経伝達物質であるアセチルコリンの量が減少すること。アセチルコリンはコリントアセチルCoAからできていますが、コリンはレシチンからできています。結果的に、豆乳を飲んでレシチンを摂取すれば、アルツハイマー型認知症の予防につながる可能性があるのです。
■豆乳の抗酸化成分に着目! 薄毛予防にも効果が期待?
老化を招く原因のひとつが、「活性酸素」による「酸化」であることは広く知られていますね。「活性酸素」とは、呼吸から取りこまれた酸素の一部が活性化したもので、細胞内での情報伝達や免疫機能の調節役として働いています。しかし、活性酸素が増えすぎると細胞を傷つけ、がん、心血管疾患、糖尿病などの生活習慣病といった病気をもたらしたり、老化、免疫機能の低下などの原因となります。そこで、「抗酸化」によって、活性酸素が体内で増えすぎないように発生を抑えたり、取り除いたりすることが大切となるのです。活性酸素は私たちの体内で常につくられていますが、活性酸素から体を守る「抗酸化酵素」の働きのおかげで、バランスを保っていられます。
豆乳は栄養価が高いことで知られていますが、特に注目すべきはその豊富な抗酸化成分です。なかでも、最も重要な抗酸化成分のひとつが、大豆イソフラボンです。
大豆イソフラボンは、エストロゲンと似た作用を持ち、細胞の老化を遅らせ、皮膚の弾力性を高めるほか、骨の健康をサポートし、更年期障害の緩和にも役立つので、特に女性の健康によいとされています。
また、大豆イソフラボンの中に含まれている「エクオール」という物質には、抜け毛予防の効果も期待できますが、日本人のおよそ半数はエクオールを体内で生成できないため、口からエクオールを摂取する必要があるのです。豆乳を飲むことで、抜け毛予防に効果が期待できるエクオールも、簡単に摂取することができますよ。「最近、老けた…?」と感じている方は、豆乳の抗酸化作用を活用してみるのもいいですね。
■「豆乳」から簡単に「手作り豆腐」がつくれるってホント?
豆腐作りを成功させるポイントは、豆乳選びです。豆乳には無調整豆乳、調整豆乳、豆乳飲料の3種類があることはお伝えしましたね。豆腐作りに適しているのは、原材料が大豆だけの無調整豆乳です。その中でも大豆固形分が高いもの、「豆腐が作れる」と書いてあるものを選ぶと間違いありませんよ。用意するものは無調整豆乳とにがり、そして電子レンジです。
【用意するもの】
・無調整豆乳・・・200ml ※よく冷やしておく
・にがり(マグネシウム濃度約5%)・・・2ml ※豆乳に対するにがりの割合は1%が目安ですが、にがりの濃度などによって豆腐の出来具合が変わります。固まらない場合は、にがりの量を調節しながらお試しください。
・耐熱性容器(マグカップでもOK)
【作り方】
1)耐熱容器に無調整豆乳とにがりを入れてよく混ぜ、ラップをかけて600Wで1分30秒加熱する。
※軽く傾けて確認し、固まっていない場合は10秒ごとに様子を見ながら追加で加熱をしてください。
2)電子レンジから取り出し、そのままラップを取らずに5分置いて蒸らす。
簡単ですね! そのまますぐに食べると、ふわトロ食感の柔らかいお豆腐に。冷蔵庫に入れて冷やすと固まって、より豆腐らしい食感になります。できたて豆腐は絶品ですよ。試してみてくださいね。
■朝はソイラテ!が新しい健康習慣
コーヒーに含まれるカフェインの作用により、朝に飲むコーヒーは目覚めを助け、体内時計を整える効果があるといわれています。さらに2025年1月、『European Heart Journal』誌におけるアメリカのハーバード大学とテュレーン大学の研究者らの発表によれば、1日中コーヒーを飲むという人は明確な健康効果が観察されなかった一方で、朝だけコーヒーを飲む人は、心血管疾患による死亡リスクが約31%低下することが実証されたそうです。
豆乳に含まれる豊富な植物性たんぱく質は、動物性たんぱく質に比べてゆっくり消化されるという性質をもっています。そのため、満腹感を得やすく、腹持ちがよいのが特長です。さらに豆乳に含まれる大豆サポニンには、満腹中枢を刺激して満腹感を与える効果があるとされています。豆乳もコーヒーも、いつ飲んでもおいしく、リラックス効果にも期待できますが、朝に飲むことでいっそう多くの健康効果が期待できそうです。そこでおすすめなのが、豆乳とコーヒーの両方のメリットを併せ持つソイラテです。朝の新習慣として、取り入れてみてはいかがでしょうか。
***
皆さんは豆乳を飲む習慣がありますか? 豆乳は飲み続けることが大切です。朝の豆乳ラテなら、とてもお手軽ですよね。無理なくおいしく、豆乳生活を続けていきましょう。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『デジタル大辞泉プラス』(小学館) /『日本大百科全書 ニッポニカ』(小学館) /一般社団法人日本記念日協会(https://www.kinenbi.gr.jp) /日本豆乳協会(https://www.tounyu.jp/tounyu-life/) :