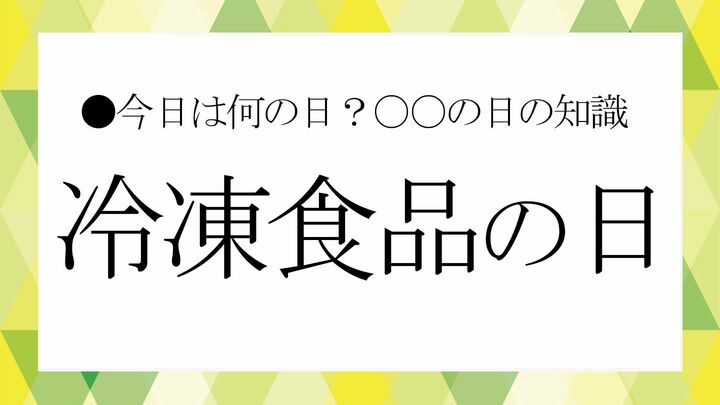【目次】
【「冷凍食品の日」とは?由来】
■「誰が」決めた?
10月18日は「冷凍食品の日」。そして10月は「冷凍食品月間」です。冷凍食品の消費拡大を目指して、一般社団法人 日本冷凍食品協会が制定しました。
■「由来」は?
10月は「食欲の秋」と言われ、冷凍(レイトウ)のトウ(10)につながること、そして冷凍食品の世界共通の管理温度である「マイナス18℃以下」から、10月18日を冷凍食品の日に、10月を冷凍食品月間に定めました。
■「冷凍食品の日」に関連したイベントは?
日本冷凍食品協会では、「冷凍食品の日」にちなみ、10月17日(金)・18日(土)の2日間限定で、「手間抜きレストラン」をオープンします。「冷凍食品は、手抜きじゃなくて、手間抜き」をコンセプトに、その日の気分で選べる冷凍食品アレンジメニューを、2日間合計1,018食分、無料で提供するそうです。
開催日時 :10月17日(金)14:00~19:00/10月18日(土)11:00~19:00
会場:サナギ新宿前イベントスペース(東京都新宿区新宿3-35-6/新宿駅東南口すぐ)
(※詳細は日本冷凍食品協会公式ホームをご覧ください)
【ビジネス雑談に役立つ「冷凍食品」にまつわる雑学】
■そもそも「冷凍食品」って何?
「食品を凍結しただけ」では「冷凍食品」と言えません。食品の安全性を確保するために定められた「食品衛生法」の施行規則は、冷凍食品を「製造し、又は加工した食品及び切り身又はむき身にした鮮魚介類を凍結させたものであって、容器包装に入れられたもの」と定義しています。日本冷凍食品協会では、冷凍食品の定義として「食品衛生法」以上に厳しい条件を定め、食の安全を守っています。
日本で販売されている冷凍食品は、「食品衛生法」の成分規格を満たす必要があります。また、冷凍食品は-18℃以下で保存されているため、保存料を使用する必要がなく、一般的に販売されている惣菜に比べると、長期間保存が可能で安全性が高い食品だと言うことができます。
■実はこんなに多い! 日本人の冷凍食品の年間消費量
冷凍食品の国内生産量は、1969年には12万7千トンでしたが、50年後の2019年には約160万トンに。なんと13倍にも伸びています。冷凍食品を積極的に「買う」頻度には個人差がありますが、2019年の日本人ひとり当たりの冷凍食品年間消費量は、過去最多の23.4kgとなっています。仮に[1食=250g]で換算すると、1年に実に94食もの冷凍食品を食べていることになるんです。「え〜? 私は冷凍食品ほとんど買わないけど…」と思った人もいるかもしれませんが、ファストフードのポテトやパティ、居酒屋の枝豆やから揚げ、社食で使われているそばやうどんの多くに、業務用の冷凍食品が使われています。飲食店では一般家庭以上に冷凍食品が重宝され、欠かせないものとなっているんですね。
■世界で最初の冷凍食品は何?
食品を凍結させて保存する方法は、エスキモーなどが天然の低温を利用し、食料を氷結させていた生活の知恵に由来しますが、人工的に低温をつくりだし、食品を凍結することができるようになったのは、16世紀になってから。最初の冷凍機は1834年にイギリスで開発され、1880年ごろにはオーストラリアやニュージーランドからイギリスやフランスへの畜肉の冷凍輸送が実用化しています。冷凍技術の進歩が促進されたのは、1900年代の第一次世界大戦後。それまでの緩慢凍結法とは違う急速凍結法が開発され、品質のよい冷凍食品がつくられるようになりました。
海に囲まれた日本での食品凍結の始まりは、魚からでした。1920年に現ニチレイ(当時の葛原商会)が北海道森町に造った冷蔵庫が、その始まりと言われています。これにより、日に10トンの魚を凍結させることが可能となり、とれたての新鮮な魚をすぐに凍結して保存し、流通させることができるようになったのです。
■冷凍すると栄養は減る?増える?意外な真実
野菜に含まれる栄養価は、冷凍と生で大きな差はありません。栄養素の中でいちばん損失しやすいものは、ビタミンCだと言われていますが、ビタミンCも野菜を急速凍結して-18度以下で保存すれば、損失は最小限にとどめることが可能です。しかも、生野菜は冷蔵保存で長期間品質を維持することは困難ですが、冷凍なら、-18度で保存すると1年間品質を保てます。ただし、急速凍結機能が付いていない家庭用の冷凍庫の場合は、凍結に時間がかかるため野菜の組織が損傷し、栄養価が落ちてしまいます。
・野菜の水気をしっかり取る
・下茹でした場合は十分に冷ます
・野菜を金属製バットに薄く広げる
上記の3つのポイントを守り、購入後できるだけ早く凍結させると、栄養価が高い状態での保存が可能です。冷凍野菜にオススメの食材ベスト3をご紹介しましょう。
1位:さつまいも
加熱調理後のさつまいもに含まれるレジスタントスターチには、血中コレステロール濃度の低下や血糖値上昇の抑制といった働きがあります。調理後に冷凍したさつまいもを食べるときに再加熱しても、レジスタントスターチの効能は変わりません。焼いたり蒸したりした後のさつまいもは冷凍保存がおすすめです。
2位:人参
人参を冷凍すると、β-カロテンが増えます。β-カロテンは体内でビタミンAとなる栄養素で、皮膚や粘膜の健康を保ちます。
3位:枝豆
枝豆は収穫後、すぐに鮮度が落ちてしまうので、できるだけ早く冷凍保存するのがベター。冷凍すれば品質は保たれますので、凍結前の枝豆を常温保存するよりも栄養価が高いというわけです。
■四半世紀以上売れ続けるベストセラー「冷凍食品ベスト5」
ミニハンバーグ(ニチレイ)
1969年発売の「ミニハンバーグ」は、発売から56年(2025年現在)という超ロングセラー商品です。発売当初はフライパン調理用でしたが、現在は「お弁当にGood!®シリーズ」のひとつとして電子レンジ調理用に。「冷めてもおいしい」冷凍食品の代表選手。
ギョーザ(味の素冷凍食品)
1972年発売。「家庭の食卓に上る頻度が高く手作りしにくいものを、家庭の調理器具で簡単に調理できるように「というコンセプトで発売されました。現在は、油と水なしでも羽根つきでパリッと焼けると評判です。
さぬきうどん(テーブルマーク)
1974年発売。本場のさぬきうどんの風味と、急速冷凍により、打ちたてのコシを閉じ込めた、冷凍うどんの中でも人気の高い商品です。発売当初は2人前入りが主流だったが、現在は5人前入りが中心に。
ちゃんぽん(ニッスイ)
1987年発売。日本初の「具付き冷凍麺」として注目を浴びました。現在は豚肉や魚介など12種類の具がたっぷりと入ったごちそう麺として定着。黄色いパッケージが目印です。
肉巻きポテト(マルハニチロ)
1991年発売。お弁当用として、油で揚げずにオーブントースターで簡単調理ができる点が人気に。現在は電子レンジ調理に変化しているほか、国産肉を使うなど素材にこだわり、子供たちからも人気なのだそう。
■賞味期限切れの冷凍食品は食べられる?
冷凍食品は長期保存できることが魅力ですが、常温の食品と同じように「賞味期限」はあります。目安は製造日から8~24か月程度とされていますが、使用されている原材料や加工方法によって賞味期限が異なるため、必ずパッケージに記載された賞味期限を確認することが大切です。「冷凍されているんだから、賞味期限切れでも大丈夫でしょ?」と思いがちですが、基本的には賞味期限を過ぎた冷凍食品は、食べないほうが賢明です。その理由は、安全性というよりも「おいしさや食感」が大きく損なわれている可能性が高いためです。
冷凍食品の賞味期限は「-18℃以下で安定して保存されていること」を前提に決められていますが、家庭用の冷凍庫は扉の開閉の頻度が高いため、温度が一定に保たれにくいのが現状です。その結果、購入した冷凍食品を家庭の冷凍庫で保管していると、少しずつ水分が蒸発したり油脂の酸化が進んだりして、風味や食感が低下していることが多いのです。
■冷凍野菜がふにゃ、べちゃっとしない加熱方法を知りたい!
冷凍庫に冷凍野菜をストックしておくと、温野菜サラダや野菜炒めなどがあっという間につくれて助かりますね! 市販されている冷凍野菜は、洗ったりカットした上で、ブランチングという加熱処理が施されているため、その後の調理が短時間で済むのが特徴。ただし、軽く加熱処理されているだけに、表示通りの加熱時間を守らないと、柔らかくなり過ぎてしまいます。ベストな状態に仕上げるために大切なのは、表示通りの加熱方法、加熱時間を守ること。そして裏技として、蒸気を抜きながら加熱をする方法がおすすめです。例えば密閉容器なら、上部に蒸気抜きの穴が開いているタイプを利用すると簡単! もしくは、耐熱袋をごく軽くしばって、レンジでチンするか湯煎して、蒸気を逃がしながら加熱するのもひとつの方法です。シャキッとした歯応えが楽しめますよ。
***
日本冷凍食品協会の「認定マーク」は、厳しい検査をクリアした、質の高い冷凍食品に対して与えられるマークです。目印は「HACCP 日本冷凍食品協会認定証」というロゴ。食卓の裏側には、技術と工夫の積み重ねがあり、冷凍食品は、“手抜き”じゃなく“知恵と選択”。この10月、「冷凍食品の日」に感謝を込めて、上手に活用してみてはいかがでしょうか?
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『デジタル大辞泉プラス』(小学館) /『日本大百科全書 ニッポニカ』(小学館) /一般社団法人 日本冷凍食品協会(https://reishokukyo.or.jp) /シンクヘルスブログ(https://health2sync.com/ja/) :