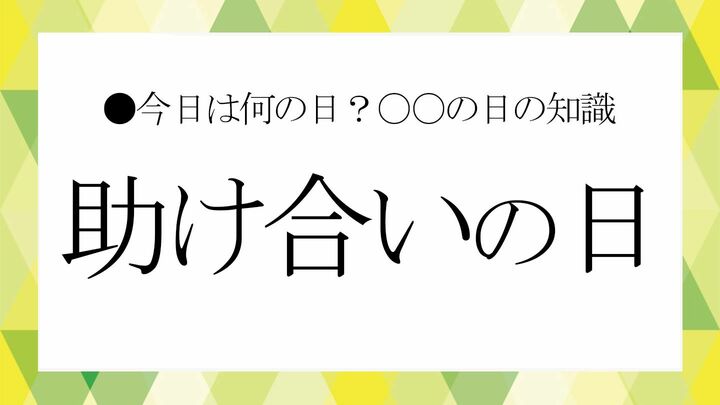【目次】
【「助け合い日」とは?由来】
■「助け合いの日」の日って?
全国社会福祉協議会が1965年に制定。日常生活での助け合いや、 ボランティア活動への参加を呼びかける日です。特別なイベントなどは行われていませんが、保険会社や介護団体などが「助け合いの日」について積極的に発信しているようです。「たすけあいの日」とも表記されます。
■いつ?
10月15日です。1965年に制定されたので、約60年前からの活動なんですね。
■全国社会福祉協議会とは?
「全国社会福祉協議会」の前身は、1908(明治41)年に「中央慈善協会」として発足した慈善事業の全国的連絡組織。生活や文化だけでなく、慈善や救済などの意識も近代化が進んだ明治期、当時はまだ政府による救貧・救護政策は乏しかったものの、篤志家(とくしか、社会事業や公共の福祉などに熱心に協力する志の熱い人のこと)や宗教家による慈善事業が盛んになっていました。個々の慈善事業が一時的なものにとどまらず、真の救済である自立を支える活動となるためには、慈善団体と慈善事業家相互の連携を図ることが重要だとし、「中央慈善協会」が発足されたのです。
その初代会長は「近代日本経済の父」などと呼ばれる渋沢栄一。今日の社会福祉の礎となる慈善事業の推進や寄付文化の振興にも、渋沢は大きな功績を遺したのです。
ちなみに…年末になると街角で呼びかけを見かけるようになる赤い羽根共同募金も、この全国社会福祉協議会によるものです。
【ビジネス雑談に役立つ「助け合い」の雑学】
■日本は「人助け指数」ワースト2位!?
イギリスに本部をもつ慈善団体Charities Aid Foundationが、2022年に発表した「世界人助け指数」。世界120の国と地域をランク付けしたものですが、日本はなんと118位という残念な結果に。これは、「寄付をしたか」「ボランティア活動をしたか」「見知らぬ人を助けたか」という問いへの回答を集計したもの。
阪神・淡路大震災や東日本大震災、2016年の熊本地震や2024年の能登半島地震など、大きな被害を伴った震災時には、災害ボランティアやさまざまな寄付が盛んに行われますが、日本人は日常的なボランティア活動や寄付の意識が薄いことの表われなのでしょうか。
■日本と海外の「ボランティア」の違い
「助け合い」や「人助け」に準ずる(と日本人は思いがちな)言葉に「ボランティア」があります。ラテン語で自由意志を意味する[voluntās(ボランタス)]が語源で、自発性に裏づけられた奉仕者や、篤志家を意味するワードです。福祉や教育などの事業では、自発的または自主的に「無償の奉仕活動をする人」を指し、自己犠牲を伴うことがその行為の基本的特性とされていました。簡単に言うと、日本では「無償奉仕という自己犠牲をともなう社会活動」がボランティアと理解されているのです。
けれど、本来は自発的に行ったことが他人の役に立っていれば立派なボランティアで、結果的に報酬を得てもボランティア。そのように認識されている諸外国では、子供から高齢者までボランティア活動をしているという意識が高いのが日本との違いです。
「自発的な行動であること」「報酬を目的としないこと」「行為の大小を問わず、社会の役に立つ活動」の3項目が揃えばボランティアなのです。
■江戸の長屋は助け合いの象徴?「向こう三軒両隣」の文化
「向こう三軒両隣」というフレーズを聞いたことはありますか? 自分の家の向かい側3軒の家と、左右2軒の隣家、あわせて5軒ほどの家と日常的に親しく付き合う、という意味ですね。
江戸時代の江戸の町では、下級武士や町人は長屋暮らしが一般的でした。長屋とは、一棟の建物を数戸の家に区切った住居建築のこと。共同の井戸や洗い場、洗濯干し場などがあるので、それぞれの生活がとても“密”でした。そんな暮らしぶりから“困った時はお互いさま”という精神が根付き、生活必需品の貸し借りや育児の共同化など自然と協力体制がとられ、共同体意識が形成されていったと考えられます。「互助=助け合い」の精神は江戸時代に確立したようです。
■助け合うだけでなく「自助」「共助」「公助」が必要です!
「助け合い」がクローズアップされがちなのは災害時ですが、日ごろから「自助」「共助」「公助」について考え、知識を持っておくことが大切です。この3者のバランスが重要とも指摘されます。
・自助(じじょ):他人に頼らず、自分の力だけで事を成し遂げること。災害時(あるいは災害想定)においては、自力(個人、あるいは家族単位)で避難できることを指します。
・共助(きょうじょ):互いに助け合うことで、物事を地域の人々で解決すること。「助け合い=共助」とも言えますね。
・公助(こうじょ):公的機関が援助すること。特に、個人や地域社会では解決できない問題について、国や自治体が支援を行うこと。
■フレイルや認知症予防にも! 「助け合い」の健康効果
実は、社会とのつながりが豊かであるほど長く健康でいられ、認知症にもなりにくいことが知られています。具体的には、週1回以上友人等と交流している人は、相対的に活動能力障害や死亡のリスクが低いのだとか。自分とは異なる背景を持つ人とのつきあいが多いほど、抑うつになりにくく、認知機能低下が起こりにくいという研究結果もあります。
また、同世代とのつながりだけでなく、同世代とのつながりだけでなく、世代間交流もフレイル予防にも効果的。「フレイル」は最近よく見聞きするワードですよね。病気ではないものの、加齢によって心と体の動きが弱くなった状態のことを指し、「虚弱」や「老化」とも呼ばれます。体力・筋力や判断能力の衰えだけでなく、外出などをする気力の低下、食生活バランスの低下など、さまざまな要素が重なって健康を損なうフレイルにも、「助け合い」は大きく関与するのです。
***
助け合いは特別なことではなく、小さな助け合いも、社会とのつながりです。10月15日の「助け合いの日」をきっかけに、ボランティア活動や災害時の自助・共助について考えてみたり、身近な人との絆を見直してみませんか?
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:社会福祉法人 全国社会福祉協議会HP(https://www.shakyo.or.jp/index.html) 東京都福祉局(https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/)『デジタル大辞泉』(小学館)/『故事俗信ことわざ大辞典』(小学館)/『現代心理学辞典(有斐閣)/日経キーワード2025-2026(日経HR) :