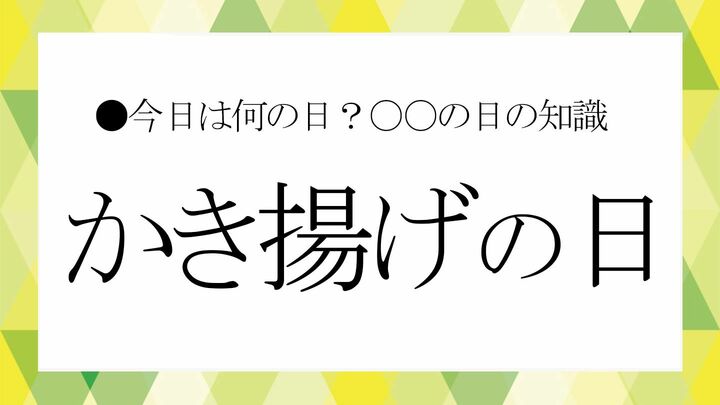【目次】
【11月4日は「かき揚げの日」由来は?】
■「かき揚げの日」とは?
さまざまな冷凍食品の製造販売を手がけ、全国の量販店やコンビニ、外食産業などに流通させている株式会社味のちぬや(本社は香川県三豊市)が制定した「かき揚げの日」。サクサクとした食感と野菜などの具材の美味しさで人気のかき揚げを、多くの人に食べてもらうのが目的です。
■なぜ11月4日?「由来」
全国製麺協同組合連合会が制定した11月11日の「めんの日」の、カレンダー上で真上(同じ曜日)に来るのが11月4日。かき揚げは、うどんやそばなどの麺類に乗せて食べることが多いので、「めんの日」の上ということで11月4日になったそうです。
■そもそも「かき揚げ」って?
かき揚げは、魚介類や野菜などを細かく切り、小麦粉などの衣でまとめて油で揚げた料理で、いわゆる天ぷらの一種です。例えば、小エビ(芝エビ)やアオヤギ(バカガイ)の貝柱、小柱を具材にしたものは、江戸前のかき揚げの代表的な具材として知られています。
てんぷらは、南蛮文化の影響を受けた揚げ物技法として日本に伝わったとされ、江戸時代初期には屋台や立ち食いそば・うどん店で気軽に食べられる“庶民の味”として広まりました。
名前の由来については、「具材をかき集めて(掻き揚げて)揚げることから ‘かき揚げ’と呼ばれるようになった」という説明が一般的です。
【「かき揚げ」のバリエーションと地方文化】
刻んだ具材を小麦粉などを溶いた衣でまとめ、油で揚げるというシンプルな調理法なだけに、さまざまなバリエーションがあります。土地の食材を使った地方色豊かなかき揚げも存在するので、その一部をご紹介しましょう。
・北海道の「札幌黄のかき揚げ」:札幌市が発祥といわれるたまねぎですが、「札幌黄(さっぽろき)」という札幌市で生まれた希少品種のたまねぎによるかき揚げが、市内の学校給食の献立に取り入れられています。
・秋田県の「じゅんさいのかき揚げ」:沼や池に自生するスイレン科の多年草植物じゅんさいは、秋田の伝統野菜のひとつ。透明な粘質物のある幼葉や葉柄の部分を食用します。独特の食感がかき揚げだとどうなるのか…食べてみたくなりますね!
・静岡県の「桜エビのかき揚げ」:生の桜エビと好みの野菜を合わせ、衣を少なめにしてカラっと揚げた「桜エビのかき揚げ」。サクサクとした食感と、桜エビの甘さや香ばしさが十分に味わえます。駿河湾は桜エビの国内水揚げ量が100%! 当地に行ったらぜひ味わってみてください。
・長野県の「魔の信州かき揚げ」:発酵・長寿を謳う長野県で、2022年に行われた発酵食コンテストでグランプリに輝いたメニュー。野沢菜と甘酒で戻した凍り豆腐を、甘酒を用いたバッター液でまとめて揚げたもの。甘しょっぱくて癖になるので“魔の”なのだそう。
・大阪の「紅しょうがのかき揚げ」:紅しょうがのてんぷらやかき揚げは、大阪では定番中の定番。色彩が乏しくなりがちな天ぷら・かき揚げのなかで、鮮やかな紅色を放ちます。ソースをつけて食べたりも(さすが大阪!)。
・鹿児島の「がね」:鹿児島の郷土料理の代表格で、揚げた姿が蟹(鹿児島弁で「がね」)に似ていることからこう呼ばれているそう。さつまいものかき揚げのことで、正月料理に用いたり、焼酎の肴やお茶請けにしたり、子どものおやつとしても親しまれています。
・沖縄の「もずくのかき揚げ」:沖縄の郷土料理。もずくのみのかき揚げが定番ですが、小エビやホタテガイの貝柱、野菜やいも類など、お好みの具材ともずくを合わせた豪華なバージョンもあります。
【家庭でサクッと作るコツ:黄金レシピ】
かき揚げも天ぷらも、揚げ上りの衣の状態がおいしさの決め手! さまざまなレシピがありますが、さくっと揚げあがる簡単で覚えやすい例をご紹介します。いずれも衣をねばつかせないことがポイント。お玉やしゃもじの上で形を整えて油に滑り込ませるほか、耐熱のクッキングシート(オーブンペーパー)の上で成形してシートごと油へ入れる方法も。クッキングシートを使う場合には、具材がおおよそ固まったら、シートを引き上げてくださいね。
■薄力粉1:冷水1
ネットのレシピサイトなどでは、衣をサクッと揚げるためのコツとして、薄力粉を冷水で溶いてバッター液(揚げ衣用の液)をつくる方法がよく紹介されています。
まず、ザルなどでふるった薄力粉を、ほぼ同量の冷水で切るように混ぜてバッター液をつくります(薄力粉カップ1/2なら冷水もカップ1/2程度)。多少粉けが残る程度でOK! 混ぜすぎると小麦粉のグルテンが形成されてねばつき、さっくり揚がりません。
また、あらかじめ具材に薄力粉少々をまとわせておくと、具材にバッター液を加えたときにまとまりやすいようです。この配分は卵を使わないので、あっさりとした仕上がりがお好みの方におすすめです。
■薄力粉大さじ4:全卵1個:冷水大さじ1.5
食材の量が多かったり、具材が大きめのときは、 衣にふくらみや厚みが出やすいたまごを使った配合がおすすめです。薄力粉大さじ4に全卵1個、そして冷水を大さじ1.5加えるレシピだと、水の量が少ないため、少し液が濃くなり、具材にしっかりと衣がつきやすくなります。
つくるたびに「衣の液が具材を包みきれているか」「揚げたときにバラバラにならないか」「サクッと仕上がったか」をチェックして、ぜひ自分流を見つけてみてください。かき揚げをつくる場合、衣がゆるすぎると具材が散らばりやすいし、濃すぎると重たい食べ応えに…。“ギリギリまとまるくらいの濃度”を目指すのがポイントです。
【ビジネス雑談で盛り上がる「かき揚げ」の雑学】
■なぜ「かき揚げ」という?
漢字では「掻き揚げ」と書きます。残った魚介や野菜の切れ端などを搔き集めて具材としたことに由来する説、具材を掻き混ぜて揚げることに由来する説、また油の中に散ったものを搔き集めてひとまとまりにするからなど、諸説あるようです。
■天ぷらそばといえば…かき揚げ?
江戸時代末期創業のそば屋のルーツをくむ、東京神田淡路町の「かんだ やぶそば」。一般的に天ぷらそばといえば大きなエビの天ぷらが乗っているものですが、「やぶそば」では芝エビのかき揚げがどんっ! しかも、そばつゆに芝エビのかき揚げのみという「天抜き」(天ぷらそばのそば抜きですね)なるメニューもあるのです。かき揚げへの自信がうかがえますね。
***
油跳ねが怖い、後片付けがめんどう、キッチンが汚れる…などの理由で、揚げ物を家庭でつくることにハードルを感じる人は少なくありません。実際、江戸時代には屋台で気軽に食べられた“庶民の味”だった天ぷらやかき揚げも、現代では「プロの技」が光るちょっとした贅沢料理として扱われることも増えました。
けれども、少しの工夫と手間を惜しまなければ、自宅でもサクサクで香ばしい“かき揚げ”を楽しむことは十分可能です。旬の野菜やエビ、小柱などを使って、揚げたてを頬張る幸せは、外食ではなかなか味わえない格別なもの。時には、家族でかき揚げを手づくりするというのも、現代ならではの「かき揚げの日」の過ごし方かもしれません。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『日本大百科全書(ニッポニカ)』(小学館)/『デジタル大辞泉』(小学館)/『デジタル大辞泉プラス』(小学館) :