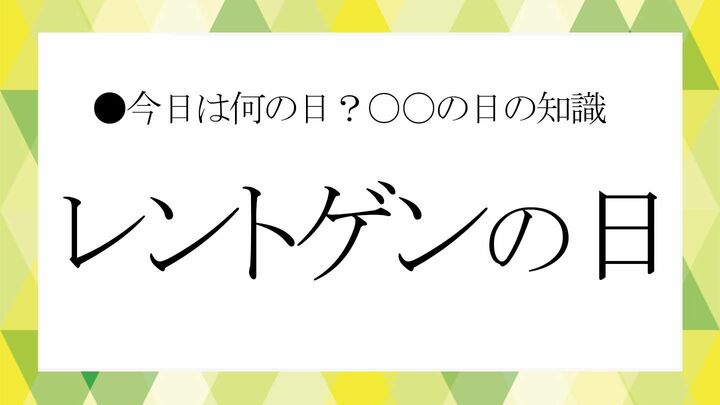【目次】
【「レントゲンの日」とは?由来】
■「何日」?
「レントゲンの日」は11月8日です。
■「由来」は?
ドイツの物理学者であるヴィルヘルム・レントゲン博士がX線を発見したのは、1895(明治28)年の11月8日。今年(2025年)でちょうど130年ということになります! レントゲン博士により発見されたX線は、医学史のなかでも最大の発見といわれており、放射線医学の歴史はここから始まりました。
■「いつ」「誰が」決めた?
2012年に、ヨーロッパ放射線学会(ESR)、アメリカ放射線医学会(ACR)、北米放射線学会(RSNA)が、11月8日を「International Day of Radiology (IDoR):国際放射線医学の日」として、国際的に祝賀することを提唱。日本医学放射線学会もこの企画に賛同・参画し、世界中から70以上の学会が参加しています。
また、この日に由来して、2003年には日本放射線技師会(現 日本診療放射線技師会)が11月2日~8日を「レントゲン週間」に制定しています。
【ビジネス雑談に使える「レントゲン」と「X線」のトリビア】
■「レントゲン=X線」だって知ってた?
物理学者ヴィルヘルム・レントゲンは、真空管に高電圧をかけて実験をしているときに、偶然、真空管の外に置かれた蛍光紙が明るく光ることに気が付きました。試しに真空管と蛍光紙の間に、1000ページもの厚さの本を置いてみても、この光は透過したのです。
そこでレントゲンは、この「いろいろな物を突き抜ける不思議な光線」に、「正体不明」という意味を込め「X線」と名付けました。レントゲンはこの功績により、1901(明治34)年に第1回ノーベル物理学賞を受賞します。当時、多くの学者は彼の発見を称え、その「不思議な光線」のことをレントゲン線と呼びました。現在でも、X線を使った検査のことを「レントゲン検査」と呼んでいるのは、この名残。放射線業務の領域では「X線検査」と呼んでいます。
■レントゲン博士が最初に撮影したものは?
答えは、レントゲン博士の、妻の手でした。このX線写真には、彼女の手にはめられた指輪がはっきりと写っています! 今では、この写真はX線の驚異的な透過能力を示す象徴となっているそうです。
■「X線」は「放射線」の一種
「X線」は私たちの体の内部を画像化する医療技術でよく知られていますが、「放射線」の一種です。放射線には、広い意味では電波や紫外線なども含まれますが、医学や科学の分野では、一般的に「物質に作用して電離を起こすほどのエネルギーをもつもの」を放射線((=電離放射線)と呼びます。
そして、放射線には、直接的な電離作用と間接的な電離作用を起こさせるものの2種類があります。医療で用いられる直接電離放射線には、電子線・陽子線・重粒子線などの荷電粒子が含まれ、直接物質にぶつかって電離を引き起こします。一方、X線やガンマ線は間接電離放射線とされ、高エネルギーの電磁波として物質に作用し、電子を弾き飛ばすことで間接的に電離を起こします。このふたつは、人の体を突き抜けるなど同じ特徴をもっていることから、広く医療の現場で、診断・治療のために広く使用されています。
■なぜ「X線」は体のなかを撮影できるの?
レントゲン博士によるX線発見後の研究で、X線は波長がたいへん短い電磁波(波長1pm~10nm)であることが判明しました。波長が短いため体を通り抜けることができ、体の部位や状態によってその通り抜け方が違うことから、体の内部の様子を撮影することができるのです。
■「CTスキャン」もX線の進化形
X線が発見されると、医療分野では診断用のX線装置が開発され、外科手術前の診断や歯科治療に利用されるようになりました。また、工業分野では、金属の欠陥検査や品質管理にX線が用いられるようになります。
1970年代になると、コンピュータ断層撮影(CTスキャン)が登場し、体の内部構造を詳細に見ることができるようになりました。現代ではデジタルX線技術が導入され、ますます画像の精度や処理能力が向上しています。マイクロX線技術やX線自由電子レーザーなど、研究用途での高度なX線技術も発展。医療、工業、科学研究の各分野で、X線の応用研究が広がっています。
■X線による被ばくリスクは?
X線は放射線の一種ですから、医療用途に使う際には放射線被ばく(医療被ばく)を伴います。とはいえ、放射線には人工的に発生するものだけでなく、宇宙線・大気中・食べ物に含まれる微量のものなど、自然放射線もあり、私たちは日常的に少しずつ被ばくしています。
がんリスクが統計的に明らかになっている線量域としては、一般に 一回あたり50〜100 mSv以上 という報告があります。例えば、ある文献では「長期・累積被ばくで100 mSvを超えるとがんリスクが上がる」という記載があります。
よって、健康診断などで行われるレントゲン検査は「非常に低い線量域」であり、一般に「安心できる範囲」であると考えられています。医師は、被ばくによる不利益と検査による利益を比較し、利益が上回ると判断される場合に放射線検査を選択しています。検査施設でも、できるだけ低線量で済むよう、照射範囲を小さくするなど、さまざまな配慮が行われています。
■「レントゲン検査」で飲むバリウム、もっとおいしくできないの?
胃や食道、腸などのX線検査(レントゲン)を受けるときに、飲む「バリウム」が苦手な人、多いですよね。バリウムを飲む理由は、消化器官のかたちや壁面を鮮明に撮影するためです。バリウムにはX線を通さない性質があるため、飲むと消化器官のかたちがはっきりと写るのですね! それにしても、もう少しおいしく飲みやすいものに改良できないのでしょうか?
実際には、バリウムも年々改良が進み、飲み干す量も昔に比べて随分減っているそうです。味も、グレープやメロン、イチゴなど、果物風味のものもありますが、それでも「おいしい!」と感じられる人は少ないかもしれません。
しかし、この「バリウムのおいしくなさ」には理由があります。実はあまりおいしいと、胃が活性化して胃酸が過剰に出てしまい、撮影に影響がでてしまうこともあるのだそうです。「おいしくないこと」にも、意味があったのですね!
***
「レントゲンの日」は11月8日です。実は日本は、世界的にみても「レントゲン検査が頻繁に行われている国」のひとつ。国民ひとり当たりの医療用CTスキャナ保有台数は、世界第1位です。医療に対するアクセスの容易さや国民皆保険制度は、日本が世界に誇れるもののひとつですね。そんな医療環境が整った日本だからこそ、ふだんの体調管理や生活習慣の見直しにも、少しだけ目を向けてみたいですね。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『日本国語大辞典』(小学館) /『デジタル大辞泉』(小学館) /『日本大百科全書 ニッポニカ』(小学館) /『世界大百科事典』(平凡社) /公益社団法人日本医学放射線学会(https://www.radiology.jp/index.html) /桐生厚生総合病院(https://www.kosei-hospital.kiryu.gunma.jp) /Yomeisyu元気通信(https://www.yomeishu.co.jp/genkigenki/trivia/110826/) :