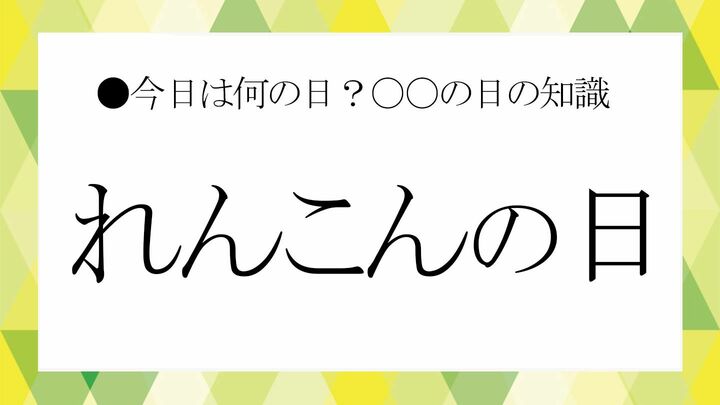【目次】
【「レンコンの日」とは?由来】
■「いつ」?
「レンコンの日」を名乗る記念日は、ふたつあります。11月8日と11月17日、どちらも「れんこんの日」なんですよ。
■11月8日は「徳島県れんこんの日」
「徳島県れんこんの日」は、徳島県のれんこんをPRするため、2012(平成24)年8月に徳島県蓮根消費拡大協議会が制定した記念日で、一般社団法人日本記念日協会により認定・登録されています。
徳島県のれんこんは、ツヤツヤとした光沢と白さが美しいと評判です。毎年年末に向かって出荷のピークを迎えますが、特に11月は出荷量が増え、品質もしっかりしている時期であることと、「1(い)・1(い)・8(は)=良い蓮」の語呂合わせから、この日が選ばれたそうです。
■ 11月17日の「れんこんの日」は茨城県発
11月17日の「れんこんの日」は、1994(平成6)年の11月17日に、茨城県で「れんこんサミット」が開催されたことに由来する記念日です。縁起の良い食べ物とされる、れんこんの消費拡大やPRを目的としています。
このように、同じ「れんこんの日」でも、県ごとに由来や意味が少し異なります。れんこんを食べるきっかけとして、どちらの日もぜひ覚えておきたいですね!
【ビジネス雑談に役立つ「れんこん」の雑学】
■そもそも「れんこん」って?
蓮根(れんこん)は、スイレン科に属する多年生水生草本、つまり蓮(ハス)の地下茎です。蓮には花を観賞する花バスと、野菜として利用される食用バスとがあり、わたしたちが一般に「れんこん」と呼んでいるのは、食用バスの地下茎が泥の中に長く伸び、先端部分に養分を蓄えて肥大した部分です。
原産地については、中国、あるいはエジプト、インドとされ、日本に伝えられたのは、2,000年以上前だと言われています。江戸時代から観賞用と食用を兼ねて栽培され、食用として本格的に栽培されたのは、明治以降のことです。 現在、日本の市場に出回っているれんこんは、明治以後に中国から入ってきた中国種と、日本在来種(明治以前に渡来したものを含む)に大別されます。
・中国種
ふっくらと太い。病気に強く収穫量が多いため、現在の主流。在来種に比べて粘り気が少なくシャキシャキとした食感が特徴。
・在来種
ほっそりと細長い。やわらかく粘り気が強いのが特徴。昔ながらのれんこんの風味が楽しめます。
■「れんこん」の名前の由来は?
蓮の花びらが落ちた後の実の部分が蜂の巣に似ていることから「ハチス」と呼び、それが略されて「ハス」となったといわれています。
■「れんこんの穴」は何のため?
答えは、「酸素を取り入れるため」です。れんこんには通常、真ん中に小さいものが1個、まわりに9個、全部で10個の穴が開いています。れんこんは「蓮田(はすだ)」と呼ばれる泥沼の中で育ちますが、穴を通して葉枝に酸素を取り込んでいるのです。つまり、穴は通気孔なのです。
■「れんこん」の収穫量ナンバーワンはどこ?
2025年に農林水産省が発表した2024年産のれんこんで収穫量が多い都道府県は……
1位:茨城県
2位:佐賀県
3位:徳島県
蓮は水生植物のため、一般的な畑では育てられません。そのため、生産しているのは全国8つの都道府県のみ。全収穫量のうち50%が茨城県で生産されています。茨城産はシャキシャキ系、徳島産はホクホク系の品種が多いそうです。
■れんこんの「選び方」は?
れんこんの収穫は冬から春先にかけて。穴が開いているため、「先が見通せる」として縁起物や祝いの料理に使われるようになりました。スーパーでれんこんを選ぶ際には、以下の点に注意して選ぶといいとされています。
・太くてまっすぐで、表面につやがあり傷がないもの
・切り口の穴が小さく穴の周囲にアクが出ていないもの
■調理する際の注意点は?
れんこんは空気にふれると黒ずむので、切ったらすぐに酢水(水1カップに酢小さじ1/2程度)に4~5分さらします。茹でるときにも、ゆで湯に酢を加えると白くきれいに茹であがりますよ。また、特有の歯ざわりを楽しむには、火の通し過ぎに注意が必要です。
■「保存方法」は?
湿らせた新聞紙で包んでからビニール袋に入れる、もしくはラップで包んで、10℃以下で保存しましょう。冷蔵庫なら野菜室がベスト。
■「長期保存」するなら?
「長期」といってもおいしく保存できる目安は1か月です。酢水にさらして水気を拭き取り、使いたい形に切ってからジップロックなどの保存袋に入れて、冷凍庫に。
■れんこんの栄養価は?
栄養的には糖質が主成分で、ほかにはビタミンC、ビタミンB1、パントテン酸、カリウムなど。れんこんのビタミンCはでんぷんに守られているため、茹でても壊れにくいのが特徴。ポリフェノールの一種であるタンニンも含まれています。
■れんこんを使った料理は?
料理としては、煮しめやきんぴら、精進揚げの具、あえもの、酢ばす、すしの具など、れんこんを使ったレシピはバラエティ豊か。すりおろしたれんこんにデンプンなどのつなぎを入れて蒸したり、揚げたりすることも。独特のシャキッとした歯ごたえが好きな人は多いのでは?
熊本地方の郷土料理として知られる「からしれんこん」は,卯の花(おから)を混ぜた「からしみそ」を穴(通気孔)に詰め、小麦粉とソラマメの粉を合わせて溶いた衣をつけて油で揚げたものです。
***
「徳島県れんこんの日」を制定した徳島県蓮根消費拡大協議会では、県産れんこんの魅力を広く発信するため、さまざまなPR活動を行っています。その一環として、JA全農とくしまの公式ホームページでは、れんこんを使った美味しいレシピも公開されていますよ。たとえば、体が温まる「蓮根のすり流し味噌汁」や、徳島名産のすだちを使った「れんこん団子のすだち鍋」、サクサク食感が楽しい「蓮根の肉巻き天ぷら」など、この時期につくりたい料理がバリエーション豊かに紹介されています。
れんこんにはポリフェノールの一種、タンニンが含まれています。タンニンは鉄と結びつくと黒く変色してしまう性質がありますので、見た目も美しく調理するには、鉄製のフライパンや鉄鍋は避けたほうがよいでしょう。加熱時間に注意して、シャキシャキとした食感を楽しんでくださいね!
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『世界大百科事典』(平凡社) /一般社団法人 日本記念日協会HP(https://www.kinenbi.gr.jp) /JA全農とくしま(https://www.zennoh.or.jp/tm/) /JAグループ茨城アモーレ(https://www.zennoh.or.jp/ib/amore/) /農林水産省「作況調査(野菜)」(https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_yasai/) /KAGOME「[れんこん]栄養や選び方、保存や下ごしらえ、切り方などまとめ」(https://www.kagome.co.jp/vegeday/yasai/lotus-root/) :