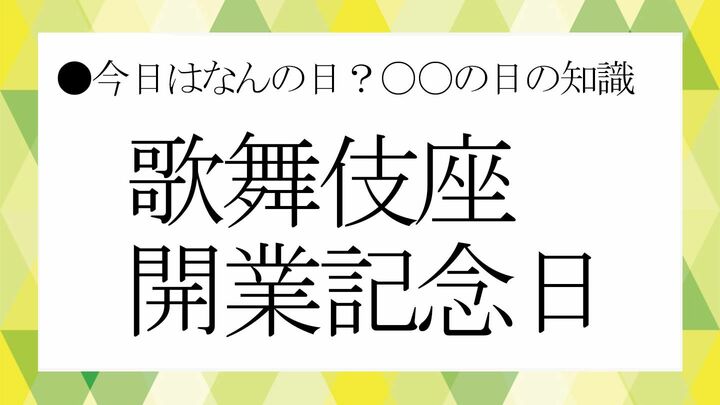【目次】
【「歌舞伎座開業記念日」とは?「由来」】
「歌舞伎座開業記念日」は11月21日です。1889(明治22)年の11月21日に、東京の木挽町(こびきちょう/現在の東銀座)に歌舞伎座が開場したことにちなんで制定されました。この地に歌舞伎座が誕生してから今年(2025年)で136年ということになりますね。
実は木挽町にはもともと、江戸時代から存在した江戸三座のひとつ、森田座(のちの守田座)があり、それが1841(天保12)年の「天保の改革」の際に、浅草に移転されていました。木挽町に再び歌舞伎座が戻ってきたのが、半世紀後の1889(明治22)年だったのです。この経緯から「木挽町」という町名は、「歌舞伎座」の呼称としても親しまれるようになりました。
【歌舞伎座の変遷〜どんな建物だった?】
そもそも、木挽町に歌舞伎座を建設する流れが生まれた背景には、1887年、外務大臣・井上馨の邸宅で開催された「歌舞伎の天覧劇」があります。
この天覧劇では、初日に天皇陛下、二日目に皇后陛下、三日目に国内外の高官、四日目には皇太后陛下を迎えるという、極めて格式高い外交イベントでした。
文明開化で西洋文化が怒涛のように流れ込むなか、政府は「日本が世界に誇れる伝統芸能とは何か」を模索していました。そのなかで、西洋のオペラに対抗しうる総合芸術として“歌舞伎”が再評価されるようになります。
この天覧劇が追い風となり、“庶民の娯楽”だった歌舞伎は、明治の知識層や政府から文化的価値を認められ、やがて福地桜痴らによって歌舞伎座建設の構想が本格化。ここから、現代につながる「伝統芸能としての歌舞伎」の歴史が形づくられていきました。
■第一期:1889(明治22)年11月~1911(明治44)年7月
初代の歌舞伎座は、劇作家でありジャーナリストとして活躍した福地源一郎氏が、自分たちの理想、日本一の大劇場を目指して建造しました。外観は洋風、内部は日本風の3階建て檜造り、客席定員1824人、間口十三間(23.63m)の舞台をもつ劇場で、今も歌舞伎座の座紋として知られる鳳凰丸は、このときから用いられています。
■第二期:1911(明治44)年10月~1921(大正10)年10月
老朽化した第一期の建物の土台と骨組を残し、純日本式の宮殿風に大改築したのが、第二期歌舞伎座です。正面車寄せは唐破風造りで、銅葺きの釣庇(つりひさし)に左右の平家も破風造り、また、内部の正面大玄関は格の鏡天井、観客席は高欄付きの総檜造りで、二重折上げの金張り格天井でした。1921年10月、漏電により焼失してしまいます。
松竹創業者の大谷竹次郎が歌舞伎座の経営に携わるようになったのはこの頃です。
■第三期:1924(大正13)年12月~1945(昭和20)年5月
第二期建物の焼失後、すぐに劇場再建工事は開始されましたが、1923(大正12)年9月1日の関東大震災の被災で工事は一時中断。翌24年3月に再開され、同年12月に大殿堂が竣工しました。
設計を担当したのは岡田信一郎氏。奈良朝の典雅壮麗に桃山時代の豪宕妍爛の様式を伴わせた意匠で、鉄筋コンクリートを使用した耐震耐火の日本式大劇場でした。正面大屋根の高さは100尺(約30m)に達し、全椅子席に冷暖房完備、舞台間口は15間で廻り舞台の直径60尺(約18m)、照明設備はアメリカとドイツから取り寄せるなど、内容外形ともに日本一を誇りましたが、昭和20年5月に空襲を受け、外郭を残して焼失しました。
■第四期:1950(昭和25)年12月~2010(平成22)年4月
株式会社歌舞伎座が設立され、戦禍を受けた第三期の建物の基礎や側壁の一部を利用して改修、1950年12月に第四期の歌舞伎座が竣工しました。 設計は吉田五十八氏によるもの。外観は戦前の歌舞伎座を踏襲し、奈良及び桃山の優雅な趣はほぼ再現され、同時に近代的な設備が取り入れられました。客席数は、桟敷、一幕見を含めて約2000席、舞台間口15間(約27.6m)、廻り舞台の直径60尺(約18m)、大小合わせて4か所のセリがあり、平成14年2月14日「登録有形文化財」に登録されました。
■第五期:2013(平成25)年4月~
私たちが今、目にしている第五期歌舞伎座は、三菱地所設計と隈研吾建築都市設計事務所による共同設計です。第三期からの意匠の流れを踏襲、第四期の劇場外観を極力再現して竣工しました。破風屋根の飾り金物や舞台のプロセニアムアーチなどの部材を再利用する一方、建物構造や舞台機構で最新技術が取り入れられ、文化施設また高層のオフィスタワーも併設した建物として生まれ変わりました。座席数は1,808席(幕見席96席を除く)、どの席からも花道が見られ、また舞台寸法は第四期と全く変わらないものの新たに大ゼリを追加、劇場内にもエスカレーターやエレベーターが設置されました。オフィスビルが併設され、歌舞伎座と歌舞伎座タワーをあわせて「GINZA KABUKIZA」という名称で呼ばれています。

【ビジネス雑談に役立つ歌舞伎座と歌舞伎のトリビア】
■歌舞伎の起こりは?
元を辿れば「歌舞伎」という表記は実は当て字なのですが、歌(音楽)と舞(舞踊)、伎(伎芸)をそれぞれ意味し、日本独自の様式的演劇の特質を表現しているため、今日では広く定着しています。
そもそもの起源とされるのは、江戸時代よりも前、遊女と共にその風俗が注目された「かぶき者」です。
かぶき者というのは、傾く(かぶく)者、つまり乱暴狼藉をする者を意味し、天正(1573〜92)ごろから流行語となって、並外れて華美な身なりをしたり、異様な行動をする者などを指す言葉となりました。
なかでも、17世紀初頭に京都の四条河原で「かぶき踊り」を披露して評判となったのが出雲阿国(いずものおくに)。阿国は“歌舞伎の創始者”として現在も語り継がれており、彼女が行った舞踊パフォーマンスが、のちの歌舞伎の原型になったとされます。
しかし、やがて幕府は「風紀が乱れる」という理由で、女性の歌舞伎(女歌舞伎)を禁止。これに代わって、若い男性が演じる「若衆歌舞伎」が流行しました。しかし、こちらも同様の理由で禁止されることに。結果、成人男性のみが演じる「野郎歌舞伎」へと発展。これが現在の歌舞伎につながるスタイルであり、役者=男性、女性の役は男性が演じる“女方(おんながた)”の文化が確立されるきっかけとなりました。
■「歌舞伎座」と「歌舞伎」の違いは?
「歌舞伎」は、日本を代表する伝統芸能のひとつ。音楽(歌)、舞踊(舞)、演技・技巧(伎)から成る総合舞台芸術で、江戸時代から400年以上続く「劇場文化」です。
対して 「歌舞伎座」 は、東京・東銀座にある 歌舞伎専門の劇場 を指す固有名詞。明治22年(1889年)に初代が開場して以来、現在の第五期まで継承されている、歌舞伎上演の中心拠点です。
また、大阪府上本町にある 「新歌舞伎座」 は、名称が似ていますが役割は異なり、歌舞伎に限らず
・演劇
・ミュージカル
・歌謡ショー
・バラエティ公演
など、多様なステージを上演する“大衆劇場”として知られています。
つまりまとめると:
■歌舞伎(KABUKI):日本の伝統芸能・舞台芸術のジャンル
■歌舞伎座(Kabukiza Theatre):東京にある“歌舞伎を上演するための劇場”としての施設名
■新歌舞伎座:歌舞伎専用ではない大阪の劇場名
という明確な違いがあります。
■歌舞伎役者って何人いるの?
現在、歌舞伎を職業として行っている歌舞伎俳優(=歌舞伎役者)は、およそ300人前後といわれています。その多くが「松竹株式会社」と専属、または専属に準じる形で契約し、松竹の主催する公演に出演しています。
松竹は日本の商業演劇界を代表する企業で、直営の歌舞伎劇場を4つもっています。
■東京:「歌舞伎座」(かぶきざ)
■東京:「新橋演舞場」(しんばしえんぶじょう)
■京都:「南座」(みなみざ)
■大阪:「大阪松竹座」(おおさかしょうちくざ)
これらの劇場を中心に、歌舞伎公演は全国で年間を通して開催されています。
なお、しばしば誤解されがちな点として、松竹の歌舞伎公演は税金で運営されているのでは?というものがあります。実際はそうではありません。世界的に見ても、伝統文化を民間企業が自立的に運営し続けている例は非常にレア。松竹は明治期以降、歌舞伎の保存と興行を商業ベースで成立させてきた、世界でも特異な存在なのです。
また、歌舞伎俳優の多くは「名跡(みょうせき)」と呼ばれる家名を継承する家系で、若いころより長い修練を積むため、世襲・家の芸が文化の重要な軸となっています。
とはいえ、現在では家柄に限らず、研修制度(歌舞伎俳優養成所・歌舞伎研修など)を経てデビューする俳優さんも一定数おり、間口は緩やかに広がっています。
■歌舞伎の舞台、「花道」は観劇の華
歌舞伎の舞台を象徴する存在といえば、「下手(しもて/舞台に向かって左側)」から客席へ向かってまっすぐ伸びる「花道」です。花道は、演目によって お城の廊下・海辺・山道・街道 など、さまざまな風景に見立てられる「物語世界と客席をつなぐ通路」として機能します。
花道の中ほど、舞台側から数えて七割・三割の位置にあたる七三(しちさん)は、俳優さんが見得(みえ/動きを止めて決めるポーズ)を切ったり、感情のピークを表現したりする、非常に重要なポイントです。
また、七三付近の床下には、せり上がり装置「すっぽん」(正式には「花道七三のセリ」)があり、妖怪・幽霊・悪役・法力を使う人物などが不意に現れる演出で頻繁に使われます。この「すっぽん」からの登場は歌舞伎の名物のひとつです。
花道の奥(客席側の突き当たり)には 「揚幕(あげまく)」 があり、俳優が出入りする場所として使われます。「シャリン」という独特の音を立てて幕を開閉することもあり、舞台転換の緊張感を演出します。
演目によっては花道を使用しないケースもありますが、使用される演目では、花道両脇の席は役者が手の届くほど近くを通るため、息づかい、衣装の質感、匂い立つような“役者の体温”まで感じられる特等席といえるでしょう。
一方で、花道のすぐ左側の席(下手側・通称“どぶ席”)は、
・花道の役者が背中を向けることがある
・花道に立つ役者が視界を遮り、正面舞台が見えづらい
という理由から、やや敬遠されがちなことも…。チケットを取る際は、花道との距離・角度を確認して選ぶのがおすすめです。
■歌舞伎の音楽は?
歌舞伎のチラシや筋書に、「竹本(たけもと)連中」「長唄囃子(ながうたはやし)連中」「常磐津(ときわず)連中」「清元(きよもと)連中」などと書かれているのを見たことがありますか? これらはすべて、芝居や舞踊に欠かせない歌舞伎音楽を演奏する専門家のグループ(=連中)の名称です。
「竹本」とは義太夫節のことで、三味線に合わせながら物語の情景や人物の心情を語る「語り物(浄瑠璃)」。歌舞伎の芝居部分を支える力強い語りとして、江戸後期以降、舞台には欠かせない存在です。
「長唄」はメロディに乗せて唄われる叙情的な音楽で、特に舞踊演目では中心的役割を担います。
「常磐津」「清元」も浄瑠璃の一種ですが、
・常磐津 → 力強く、芝居心のある語り
・清元 → 艶やかで情緒的、色気のある音色
と、それぞれに特色があります。
これらの音楽は、
・舞台袖の黒御簾(くろみす)の中
・舞台上の囃子座
・場面転換時の効果音
など、さまざまな場所で演奏され、歌舞伎の世界観を立体的に支える「もうひとつの主役」といえる存在です。
■歌舞伎の象徴「チョン!」という音は?
芝居の幕開きや幕切れ、舞台転換など、舞台進行の合図として「チョン!」あるいは「チョン、チョン、チョン…」などと、客席に響きわたる拍子木の音は「柝(き)」と呼ばれます。進行のタイミングを知らせる“本柝(ほんぎ)”と、幕を引く合図などに使われる“揚幕柝(あげまくぎ)”の2種類があります。
また、役者が見得(決め姿の瞬間)をするとき、重要人物が登場する足音、物が落ちたときなどのアクセントとなる音が「ツケ」。上手(かみて)の端でこの音を出す人を「ツケ打ち」と言い、俳優と呼吸を合わせてタイミングよく打ち、舞台の緊張を生み出します。
■歌舞伎の幕、何種類知ってる?
歌舞伎の舞台で最もよく目にする幕が、黒・柿・萌葱色の三色縦縞からなる 「定式幕(じょうしきまく)」。江戸歌舞伎の象徴で、右から左へスッと引かれるのが特徴です。
そのほかにも、
■浅葱幕(あさぎまく):水色一色で、幻想的な場面や場面転換に用いられる。
■黒幕(くろまく):舞台全体を黒一色で覆い、背景を見せたくないときや、転換作業を客席から見えないように隠すための幕。舞台を一旦“無”の状態に戻す役割。
■道具幕:山・海・田園などの背景が描かれた幕。場面の説明や雰囲気づくりとして使用される。
■消し幕(けしまく):黒幕とは違い、舞台上の小道具・装置・演者が退場した後の“部分的な片付けや処理”をすばやく行うための幕。必要な部分だけを一瞬で隠し、次の場面へスムーズにつなぐための実務的な幕。
■霞幕(かすみまく):演奏者(下座音楽)を隠すほか、霧・霞などの視覚的効果を表現するために使われる。
など、演目や演出意図に応じてさまざまな幕が使い分けられています。
■第五期歌舞伎座の竣工前後に起きた出来事
2010年に第四期歌舞伎座が取り壊され、第五期への建て替えが始まった時期には、歌舞伎界では複数のニュースが続きました。偶然ではあるものの、同時期にさまざまな出来事が重なったことで、多くのファンが歌舞伎界の行く末を案じた時期でもあります。
・五代目中村富十郎さんの逝去(2011年1月)
・七代目中村芝翫さんの逝去(2011年10月)
・四代目中村雀右衛門さんの逝去(2012年2月)
・市川染五郎(現・十代目松本幸四郎)さんの舞台事故(2012年)
・十八代目中村勘三郎さんの急逝(2012年12月)
・ 第十二代市川團十郎さんの逝去(2013年2月)
これらは偶然の重なりとはいえ、歌舞伎界にとって大きな転換点となった期間でした。第五期歌舞伎座が竣工した2013年は、ファンにとっても「新時代の幕開け」として強い印象を残しています。
■歌舞伎出演者はどこで養成されている?
映画『国宝』をご覧になりましたか?『国宝』は、任侠の一門に生まれた主人公(吉沢亮さん)が、父を亡くしたのち、上方歌舞伎の名門である花井半二郎(渡辺謙さん)に引き取られ、才能を見出されて歌舞伎の世界へ飛び込む物語です。御曹司である俊介(横浜流星さん)との関係を通じて、歌舞伎界の「血(筋)」がテーマとして描かれています。
ご存知のように歌舞伎の公演では、主演や主要な役は、歌舞伎役者を家業として行ってきた、いわゆる梨園に育った幹部役者が務めています。でも、舞台は主役級の役者さんだけでは成り立ちません。
台詞が少ない役、立ち回り、背景を支える役者を総称して「三階役者」「三階さん」と呼びますが、歌舞伎界では古くから身分制度がはっきりしており、三階さんが大スターへと上り詰める道は非常に狭いのが現実です。とはいえ、脇を支える俳優が不足すると歌舞伎の上演自体が難しくなるため、その育成は「歌舞伎存続の要」とも言えます。
そこで、こうした構造を支えるために、国立劇場(国)が主体となって若い俳優の養成を行う制度が1960年代以降整備されました。
俳優だけでなく、
・竹本(義太夫節)
・鳴物(太鼓・笛などの囃子方)
・長唄(三味線と唄)
など、舞台音楽を担う人材も同様に育成されています。
その成果として、2022年時点では、歌舞伎俳優の約3分の1が国立劇場の養成所出身に。中には人気が出て、大役を任されるようになった俳優もいます。この養成事業には国費が投入され、伝統芸能を未来へつなぐ重要な基盤となっています。
■「歌舞伎」を英語で説明すると?
歌舞伎は、「アニメ」「漫画」「盆栽」「寿司」「天ぷら」「かわいい」「カラオケ」「絵文字」「こたつ」「温泉」など、日本語の発音でそのまま伝わる(国際語化している)日本語同様、「Kabuki」で伝わります。
では、海外の方に「What exactly is Kabuki?」と聞かれたら、何と答えればいいでしょうか。海外から来た観光の方の東京案内をされているツアーガイドの方に教えてもらいました。
Kabuki is a classical form of Japanese theater that began in the early 1600s. It blends dramatic storytelling with music, dance, and highly stylized acting.
The stage features unique elements such as a revolving platform and the hanamichi, a walkway that extends into the audience for dramatic entrances.
Kabuki plays fall into three main categories:
・Historical dramas(samurai stories and legendary events)
・Domestic plays(everyday life and emotions of ordinary people)
・Dance pieces(performed to narrative music)
All roles—including female characters—are performed by male actors using elaborate makeup and precise movement techniques.
It is considered one of Japan’s most important traditional performing arts and is still performed regularly at the Kabuki-za Theater in Tokyo.
【直訳】
歌舞伎は1600年代初頭に誕生した日本の伝統演劇で、物語・音楽・舞踊・様式化された演技が融合した芸能です。
舞台には、回り舞台や観客席へ伸びる花道など、歌舞伎特有の装置が使われます。
演目は以下の3つに分類されます。
・歴史物:(武家や伝説の物語)
・世話物:(町人の日常のドラマ)
・所作事:(語り物に合わせた舞踊劇)
主人公、悪役、女形などすべての役を、男性俳優が化粧と所作で演じるのが最大の特徴です。 現在も東京の歌舞伎座で定期的に上演されており、日本を代表する伝統芸能として世界的に知られています。
***
芝居の幕開きに響く「チョン!」という拍子木の鋭い音——その瞬間に満ちる、高揚感と緊張感。日本の伝統芸能が何世代にもわたって受け継がれてきた“時間の気配”を、身体の内側で感じられる瞬間でもあります。
「歌舞伎座開業記念日」は、単なる記念日ではなく、私たちが今のビジネス社会で失いがちな“教養の軸”をそっと取り戻す日と言ってもいいのかもしれません。
歌舞伎は、長い上演時間や独特の形式を理由に“ハードルが高い”と感じられがちですが、その分、一度触れると得られるものは想像以上に大きいもの。物語の背景にある歴史、様式美、役者の技、そして舞台装置の緻密さ——忙しい日常では味わえない「思考の深呼吸」の時間がそこにはあります。
映画『国宝』をきっかけに、歌舞伎へ再び関心が集まっている今こそ、自分の知的好奇心をアップデートする絶好のタイミング。久しぶりに歌舞伎座のチケットを予約してみませんか?一幕ごとの美意識と職人技は、きっとあなたの感性に新しい刺激をくれるはずです。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『日本国語大辞典』(小学館) /『デジタル大辞泉』(小学館) /『日本大百科全書 ニッポニカ』(小学館)/『プログレッシブ和英中辞典』(小学館)/『江戸のきものと衣生活』(小学館) /『世界大百科事典』(平凡社) /歌舞伎座「歌舞伎座史料館」(https://www.kabuki-za.co.jp/siryo/) /歌舞伎公式総合サイト歌舞伎美人(https://www.kabuki-bito.jp) /伝統文化ジャパン(https://denbunjapan.com/kabuki/kabuki_knowledge.html) :