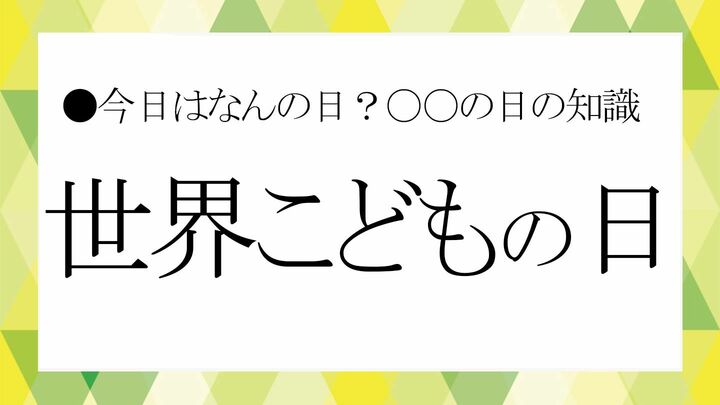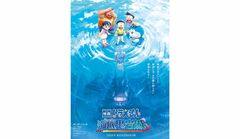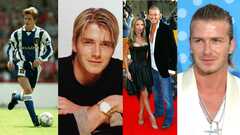【目次】
【「世界こどもの日」とは?なぜ11月20日なの?】
■目的
「世界こどもの日」は、世界の子どもたちの相互理解と福祉の向上を目的として、1954年に国際連合(国連)によって制定されました。世界共通の課題や問題について人々の関心を高め、解決に向けた取り組みを促すため、国連などの国際機関が制定した記念日「国際デー」のひとつです。
■なぜ11月20日?
1959年11月20日、国連総会で「子どもの権利宣言」が採択されました。「子どもの権利宣言」とは、子どもの権利を保障するための国際文書。しかしこれには法的拘束力がなかったため、1989年11月20日に「子どもの権利条約」に引き継がれ、より実効性のある条約となりました。
これによって世界中で子どもの保護への取り組みが進み、多くの成果が生まれています。この条約を守ることを約束している締約国・地域の数は196。世界で最も広く受け入れられている人権条約なのです。
■何をする日?
毎年の「世界こどもの日」には、子どもの権利の認識向上と子どもの福祉の向上を目的として、世界中で子どもたちが主体となって参加する催しが行われます。「子どもの権利条約」にうたわれている権利の実現に向けて取り組むことはもちろん、子どもたち自身が、自分たちのもつ権利について知り、学び、声を上げていくことがとても大切です。
たとえばNHK(Eテレ)ではユニセフ(国連児童基金)の協力のもと、2022年に「ツバメ 世界こどもの日プロジェクト」をスタート。翌年「スゴEフェス」と名称を変更し、さまざまな番組を放送しています。また、世界中の子どもの権利が守られることを目指して、ユニセフがロゴに掲げる「for every child~すべての子どものために」のメッセージを見ることもあるでしょう。
■「子ども」は何歳まで? どんな存在?
「子ども」とは、原則として18歳未満のすべての人を指します(子どもの権利条約第1条に基づく定義)。
「子どもの権利条約」は、子どもが“守られる対象”であるだけでなく、“権利をもつ主体”であることを明確にしました。年齢に関わらず「ひとりの人間としてのさまざまな権利」を認めるとともに、「保護や配慮が必要な子どもならではの権利」も定めています。
「生きる権利」や「成長する権利」「暴力から守られる権利」「教育を受ける権利」「遊ぶ権利」「参加する権利」など、子どももおとなも人間として持つべき権利は同じです。この条約が採択されてから、世界中で多くの子どもたちの状況は改善につながってきています。
【日本の「こどもの日」とどう違う?】
■「こどもの日」とは?
日本の国民の祝日のひとつである5月5日の「こどもの日」。子どもの人格を重んじ幸福をはかるとともに、母に感謝する日でもあります。
五節句のひとつ「端午の節句」でもありますね。「端午」は5月の最初の午(うま)の日のこと。古代中国伝来の行事が江戸時代に武家の習俗と結びつき、男児の誕生を祝い、健やかな成長を祈念する日となりました。
「桃の節句」とも呼ばれる「上巳の節句」である3月3日は女児の、「端午の節句」は男児の、というイメージがあるかもしれませんが、いずれも邪気を払って健やかな成長を願うもので、本来男女の区別はありません。
こども家庭庁は「こどもの日」から1週間を「児童福祉週間」と定め、児童福祉理念の普及や啓発のための事業や行事を行っています。
「世界こどもの日」と日本の「子どもの日」の違い
5月5日の「こどもの日」は国民の祝日で休日になりますが、11月20日の「世界こどもの日」は休日ではありません。いずれも目的は子どもの健やかな心身の実現ですが、「世界こどもの日」は子どもの権利について、より明確に言及しているといえるでしょう。
【今、子どもたちを取り巻く現実など…】
■日本は豊かな国ではない!?「子どもの貧困」
日本における子どもの貧困の現状は、「見えにくい」「公になりにくい」と言われています。これは日本人の気質にもよるようで、親や子どもに自身が貧困であるという自覚がなかったり、自覚があっても周囲の目を気にして支援を求めにくい、地域の目が届きにくい、といった要因も関係しているようです。
厚生労働省によると、日本の子ども(17歳以下)の貧困率は11.5%(2021年の調査)。約8.7人に1人の子どもが貧困状態にあるといわれています。
家庭が相対的貧困(所得の中央値の半分に満たない状態)にあることで、健やかな成長に必要な生活環境や教育の機会が確保されず、下記のような環境下におかれる子どもが少なくありません。
・栄養バランスのとれた食事は学校給食でしか食べられない。
・高校や大学、専門学校に進学したいが、経済的な理由で諦めている。
・将来への希望をなくし、学ぶ意欲をなくしている。
・子どもだけでいる時間が長く、保健衛生などの知識や生活習慣が身につかない。
・他者とのつながりが少なく、社会的に孤立している。
住む家がない、食べるものがない、衛生環境が劣悪など、生きていくうえで最低限必要な生活水準が満たされていない状態を「絶対的貧困」と言い、そのような状態が「貧困」だと考えがちですが、上記のような状態も「健やかな成長」を妨げるもの。「これらも“貧困”であり、改善する必要がある」と自覚、認識することが大切です。
■子どもの人口が減ることの意味を考えよう
2022年の出生数(概数)は77万747人で、統計開始以来はじめて80万人を下回りました。
少子化が叫ばれて久しいものの、抜本的な対策や長期的な効果はまだ見えにくい状況です。
日本の0歳から14歳までの年少人口の割合は年々低下していて、一部の推計では2050年ごろには全人口の1割前後まで落ち込むとされています。
また、2020年10月時点で、20代の人口は40代人口の3分の2程度。子どものいる世帯は2022年時点で約992万世帯、全世帯の18.3%でしかありません。5世帯のうち、子どもがいるのは1世帯にも満たない——日本にはそんな現実があるのです。こうした状況が続けば、将来の働き手はさらに減ります。AIなどの躍進により、効率化は図られるでしょうが、長寿大国といわれる日本。現役世代が高齢者の生活を支えるという仕組みは、大きな見直しを迫られるでしょう。
***
「世界こどもの日」は、遠い国の問題を眺める日ではなく、“自分の足元から、次の世代との関わり方をアップデートするための日”と言えるのかもしれません。子どもの貧困や少子化は、日本社会のサステナビリティそのものに直結するテーマです。ビジネスの現場で日々意思決定を行う私たち大人にとっても、それは「誰かが解決してくれる課題」ではなく、自分のキャリア観、お金の使い方、そして時間の投資先を見つめ直すきっかけになり得ます。たとえば、
・寄付やクラウドファンディングを通じて、子ども支援のプロジェクトを応援する
・本やイベントを通じて、子どもの権利について学び直す
・自社の事業や仕事のスキルを、次世代のためにどう活かせるか考えてみる
——そんな小さな一歩も、視座の高い大人にとっては立派な「ソーシャル投資」です。
「世界こどもの日」をきっかけに、子どもの貧困や少子化などについて改めて考えたり調べたりしてみてはいかがでしょう? そして、ビジネスリーダーである自分だからこそできる関わり方を、このタイミングで一度ゆっくりデザインしてみる——。それが、未来の社会と、自分自身のキャリアの両方を豊かにしていく一歩になるはずです。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『デジタル大辞泉』(小学館)/『日本大百科全書(ニッポニカ)』(小学館)/政府広報オンライン( https://www.gov-online.go.jp/ )/公益財団法人 日本ユニセフ協会( https://www.unicef.or.jp/ )/こども家庭庁( https://www.cfa.go.jp/top )/外務省( https://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html) :