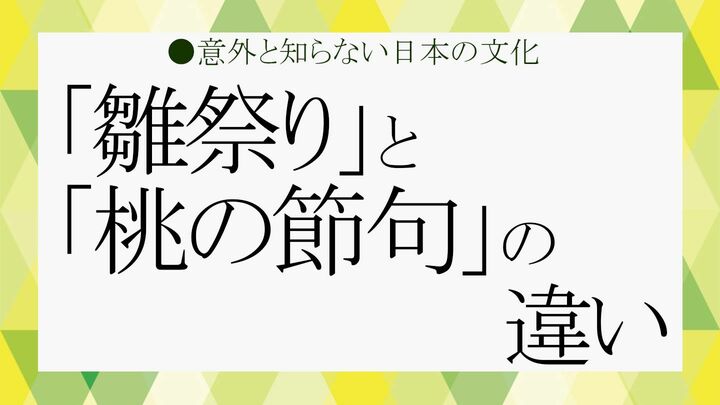今年も「ひな祭り」の季節となりました。暦の上だけでなく、お内裏様に降り注ぐやわらかな陽ざしは、まさに春の訪れを感じさせますね。今回は「ひな祭り」と「桃の節句」をおさらい。その由来や目的、ひな祭りが桃の節句と呼ばれる理由についても解説しますよ。「ひな祭り」にちなんだ行事食についても解説していますので、ビジネスの合間の雑談ネタとして、ぜひご活用くださいね!
【目次】
【「ひな祭り」と「桃の節句」の違いは?「意味」と「由来」】
■「ひな祭り」の「意味」と「由来」、「歴史」
現代では、一般的に「女の子ための行事」として認識されている3月3日の「ひな祭り」。でも、もともとは、そうではありませんでした。「ひな祭り」の由来は、「五節句(ごせっく)」のひとつ、「上巳(じょうし)の節句」です。
まずは「五節句」から説明しましょう。
古代中国では、季節の節目となる日を「節句」と定め、次の季節を無事迎えられるよう、お祓(はら)いやお清めの行事・儀式を行う風習がありました。この風習は、奈良時代ごろには日本に伝わっており、取り入れられるようになりました。とはいえ、春夏秋冬がはっきりしているうえ、稲作を中心とした生活リズムを培ってきた日本は、季節の変わり目となる大切にしたい節句がたくさんになって、すべてを行うとなるとたいへん。そこで、江戸幕府が節句を5つに絞り、公的な行事や祝日として「五節句(ごせっく)」を定めたのです。
五節句は、1月7日の「人日(じんじつ)の節句」、3月3日の「上巳(じょうし)の節句」、5月5日の「端午(たんご)の節句」、7月7日の「七夕(しちせき)の節句」、9月9日の「重陽(ちょうよう)の節句」の5つ。なかでも、3月3日の「上巳の節句」は、川で身を清めたり、宮中で宴席を催すなどして災厄を祓う中国の習わしと、「禊祓(みそぎはらい)」の思想や「人形(ひとがた)」を流す日本の伝統文化が融合し、これがのちに雛人形を飾る「ひな祭り」となったといわれています。つまり、「ひな祭り」は、けがれ・災いを人形(ひとがた)に移し、払おうとする風習が起源です。
■「桃の節句」の「意味」と「由来」、「歴史」
では、「桃の節句」とは何でしょう? 『デジタル大辞泉』によれば、「桃の節句」とは、「3月3日の節句。上巳の節句。雛祭り。桃の日」と説明されています。「桃の節句」と呼ばれたのは、「上巳の節句」の季節に桃の花が咲いていたことや、古代中国では邪気払いとして桃の花を清酒に浸した「桃花酒(とうかしゅ)」が飲まれていたためといわれています。
■「ひな祭り」と「桃の節句」の違いは?
結論から言えば、「ひな祭り」と「桃の節句」は、どちらも3月3日に行われる行事であり、呼び方の違いはありますが、同じ行事を指しています。ただし、厳密に言えば、「桃の節句」は、川で心身の穢れを流し、厄を払うという風習に由来し、「ひな祭り」は、日本の一部の地域で行われていた流し雛(お子さまの無病息災を願い、川に紙の人形を流す行事)に由来すると言われています。
どちらも川に関連した行事であり、厄払いや無病息災を祈念することが共通点。長い歴史のなかで、女の子の健康を願うお祝いという意味で、同義語になっていったようです。
【「ひな祭り」と「桃の節句」の食べ物など】
■「ひな祭り」「桃の節句」にはさまざまな伝統食が!
日本には、「季節の節目に食べるとよいとされる物」がたくさん存在します。それらは「行事食」と呼ばれ、それぞれに意味をもっています。
「ひな祭り」「桃の節句」に由来する伝統食のなかから、代表的なものをご紹介しましょう。
・ちらし寿司
「ひな祭り」といえば、ちらし寿司を連想される方も多いはず。でも実は、「ひな祭り」とちらし寿司に、特筆すべき因果関係はありません。とはいえ、華やかに彩られた具材には意味があります! まず、主な具材として用いられる海老には「腰が曲がるまで長生きしますように」、れんこんには「将来の見通しがいい」、豆には「健康で、まめに働き、まめに生きる」、そしてシイタケには「元気・壮健を願う」などの願いが込められているんですよ。
・菱餅
菱餅とは、赤色・緑色・白色の餅を3段に重ね、菱形に切ったものです。諸説あるものの、赤色には「魔除け」、緑色には「長寿や健康」、白色には「清浄」という意味があると 割れていますいわれています。ちなみに菱餅が菱形になったのは江戸時代から。3色になったのは明治時代からといわれています。そして、赤にはクチナシ、緑にはヨモギが混ぜられ、あの色となっています。はクチナシ、ヨモギ、共に邪気を払うといわれている薬草です。
・蛤(はまぐり)のお吸い物
こちらの由来は、平安時代の貴族が行っていた「貝遊び」。二枚貝であるハマグリは、対となる貝殻以外とは、ぴったりと合いません。そのことから、夫婦円満の象徴として「一生一人の人と仲良く添い遂げるように」という願いが込められ、蛤のお吸い物が食されるようになったといわれています。
・ひなあられ
ひなあられは、「ひな祭り」の代表的なお菓子ですね。甘い関東風に対し、関西風は醤油や塩を効かせた味付けが特徴的です。ご存知でしたか? 一般的なひなあられには、「赤・緑・黄・白」の4色が付いており、それぞれが四季を表しています。「四季を通して。娘が幸せでありますように」と願う気持ちが込められています。
・白酒(しろざけ)
古代中国で上巳の節句に飲まれていた、桃の花びらを酒に浸した「桃花酒」。桃は邪気を払う仙木であり、また、桃が百歳を表す「百歳(ももとせ)」に通じることから、桃花酒は薬酒としても飲まれていました。日本では江戸時代より、3月3日の「ひな祭り」には、桃花酒に代わって「白酒(しろざけ)」が飲まれるようになりました。その理由は、大蛇を身ごもってしまった女性が白酒を飲んで胎内の大蛇を流したという説や、老舗酒屋が桃花酒の代わりに白酒を売り出したという説がありますよ。
■桃の花を飾る、その意味は
春の雰囲気を感じさせる桃の花は、ひな祭りのシンボルにもなっている季節の花。「桃花酒」同様、魔よけや厄除けとして、女の子が健全に成長することを願い、上巳の節句に飾られたとされます。
【ビジネス雑談に役立つ「雛祭り」「桃の節句」豆知識】
■「ひな祭り」や「ひな人形」の「ひな」ってどんな意味?
そもそも、「ひな」にどんな意味があるのか、ご存知ですか?
「雛(ひな・ひひな・ひいな)」には、「実物より小さいもの、幼いもの・一人前でないもの、かえって間もない小さな鳥の子、紙や土でつくった人形に着物を着せたもの」などの意味があります。
平安時代の貴族の女児の間では、紙で作った男女対の小さな人形(にんぎょう)を遊具とし、宮中の夫婦の暮らしなどを模した「雛遊び」が人気でした。雛遊びは、上巳の節句に限った遊びではなかったのですが、上巳の節句の祓いの人形(ひとがた)と結びついて、現在の「お雛様」の原型が誕生します。
本来、人形(ひとがた)は水に流して邪気を払うものでしたが、時代を経て人形(ひとがた)も雛遊びの人形(にんぎょう)もどんどん立派になっていき、雛人形として祭壇に飾られるようになります。そして、江戸幕府が上巳の節句を五節句と定めたことから、雛遊びがひな祭りとして定着していったとされています。
■ひな人形を飾る時期・片づける時期、タイミングは?
一般的には、2月中旬の立春を過ぎたころ、節分の豆まきで厄払いをしたあとあたりが、雛人形を飾り始めるベストのタイミングとされています。遅くとも、ひな祭りの1週間ほど前には飾り始めるのがいいそうです。とはいえ、雛人形を飾る時期は、地域や家庭などによってそれぞれですね。
片付けのタイミングにも、諸説あるようです。「3月3日を過ぎたら早く片付けるべき」という説は、「厄災の身代わりになってくれた雛人形は、早々に仕舞ったほうがいい。身代わりとなって邪気を吸い取ってくれた雛人形を長く飾っていると、その邪気から婚期が遅れてしまう」という考え方が由来。また、「3月3日を過ぎても飾っておくべき」という説は、本来のひな祭りは旧暦の3月3日、今でいうと4月上旬の行事になるところから、3月末日や4月中旬あたりまでひな人形を飾っておくべき、というものです。
最終的には、それぞれ個人の都合に合わせて、無理のないタイミングでひな人形を愛でるのが一番です。
■ひな人形の種類には、どんなものがあるの?
男女一対を基本とする雛人形。その種類を大きく分ければ、「衣裳着(いしょうぎ)人形」と「木目込(きめこみ)人形」のふたつになります。
・衣裳着人形
人形と衣裳をそれぞれにつくり、仕立て上げた着物を着せ付けたものを「衣裳着人形」といいます。人形は、一般的に頭と胴体を別々に作成します。胴体を先に作ったあとに、頭を取り付けたらできあがりです。
・木目込人形
桐粉(桐の粉と糊を混ぜたもの)や木で作られた人形に溝を堀り、そこにヘラで布を入れこんで、衣装を着ているように仕立てた人形を「木目込人形」といいます。溝に布を入れこむことを「木目込む(きめこむ)」ということから、そのような名称になったとされています。
■ひな人形の名前を知ってる?
ひな祭りに飾るひな人形には、それぞれに名前と役割があります。今回は、古来から縁起の良い数字とされる七を用いた七段飾りを例に、人形をご紹介しますね。段数の増減により、人形の種類が増えたり減ったりすることもありますよ。
・内裏雛(だいりびな)
七段飾りのいちばん上に座る、ひと際目を惹く豪華なひな人形です。正式名称は「男雛(おびな)」と「女雛(めびな)」。通常「女雛」は十二単を着ているものが多いのも特徴です。
・三人官女(さんにんかんじょ)
三人官女とは、内裏雛に仕える侍女の人形。行儀や和歌・漢文などのたしなみがあるとされています。三人官女の左右の人形が持っているのは、「長柄(ながえ)」という長い柄のある酒器です。「銚子」ともいい、現代でも結婚式の三三九度に使われるものです。
・五人囃子(ごにんばやし)
能楽の囃子方(はやしかた)を模した子ども姿の五人囃子は、元気な子どもに育つようにと応援する音楽隊です。向かって右から、謡、笛、小鼓、大鼓、太鼓を持っています。
・随身(ずいじん)
「ずいしん」とも読む内裏雛のふたりを守る役目の彼らは、右大臣(向かって左側、若者)・左大臣(右側、老人)に分かれ、いわば現代のボディーガードともいえるでしょう。
・仕丁(しちょう)
内裏雛の雑用係にあたる従者の仕丁(じちょう)。それぞれに表情豊かな顔立ちであったり、さまざまな小道具(ほうき、ちりとり、熊手など)を持っています。
***
これでもう、「ひな祭り」と「桃の節句」についての基礎知識はばっちりです! 行事の意味や由来を理解することで、より味わい深い「ひな祭り」が過ごせるのではないでしょうか。お雛様と桃の花を前に、のんびりちらし寿司とお酒を楽しんでみるのも、大人のたしなみのひとつですね!
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『デジタル大辞泉』(小学館) /『おうちで楽しむにほんの行事』(技術評論社) :