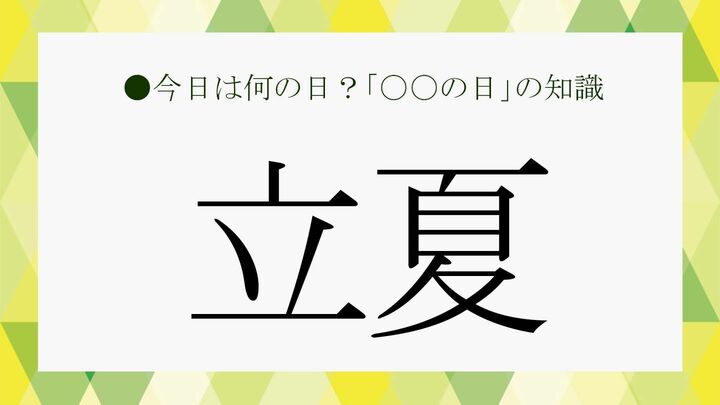「立夏を迎え、どことなく夏めいてきました」などと、季節の挨拶文に使われる「立夏」。毎年5月6日頃にあたり、この頃から暑さは日に日に増し、本格的な夏へと向かっていきます。ちょうど田植えの時期にも重なりますね。今回は「立夏」について、その意味や言葉の使い方、「初夏」との違いなどを解説します。
【目次】

【「立夏」とは?「読み方」や「意味」】
■「読み方」
「立夏」とは「りっか」と読みます。「たつなつ」ではありません。
■簡単に言うと…「意味」「由来」
「立夏」は二十四節気のひとつで、夏の兆しが見え始める頃、夏の始まりという意味です。「立」は「立案」「立法」などにも使われるように、「つくる」「新たに始める」という意味があり、二十四節気では「立春」「立夏」「立秋」「立冬」を指して「四立」と呼び、それぞれ「季節のはじまり」を表しています。
■「立夏」っていつ?
二十四節気とは、古代中国でつくられた季節の区分法です。黄道(地球から見て太陽が移動する天球上の経路)を基準に、1年を24等分して気候の推移を示すので、各節気の期間は約15日。「立夏」といった場合、立夏に入る日を指す場合と、「立夏」にあたる期間を指す場合があります。期間としては太陽暦(現在使われている暦)の5月6日頃から約15日間を指し、「立夏」から「夏至」を経て「立秋」(8月7日頃)の前日までが、暦の上での「夏」にあたります。「夏も近づく八十八夜」と歌われる唱歌『茶摘み』に出てくる「八十八夜」は立春から数えて88日目にあたり、5月2日頃。まさに「立夏」の直前。「夏も近づく…」と言うわけです。
太陽の軌道は一定ではないため、「立夏」をはじめとした二十四節気の日付は固定されておらず、毎年国立天文台暦計算室により定められます。2024年の「立夏」は5月5日。期間で言うと5月5日から5月19日までです。ちなみに二十四節気では、「立夏」の前は「穀雨(こくう)」。穀物を潤す雨が降る頃という意味で、「立夏」の次は「小満(しょうまん)」。万物が生長し天地に満ち始める頃というという意味になります。
【「使い方」がわかる「季節の挨拶」3選】
「立夏」という言葉を日常で目にするのは、手紙の冒頭、季節の挨拶ではないでしょうか。
■1:「立夏を迎え、どことなく夏めいてきました」
■2:「立夏を迎え、暦の上ではもう夏となりましたが、いかがお過ごしでしょうか」
■3:「立夏の候、皆様におかれましてはお元気にお過ごしと存じます」
「立夏の候」は、「夏の始まりを感じさせる季節になりました」という意味の時候の挨拶です。挨拶として使えるのは、毎年、立夏から小満の前日までの15日間程度です。
【「初夏」との違いは?】
「立夏」が二十四節気のひとつであることに対して、「初夏」は和の暦(陰暦)での夏の呼称です。和の暦では「夏」は4月から6月。太陽暦の5月から7月にあたり、夏のはじめである5月を「初夏」、半ばの6月を「仲夏」、夏の終わりの7月を「晩夏」と言います。つまり、二十四節気における「立夏」(5月6日頃)から「小満」を経て、次の「芒種(ぼうしゅ)」の前日(6月5日頃)までが「初夏」にあたります。
【「立夏」に「旬」を迎える食べ物は?】
■筍(タケノコ)
二十四節気の各節気をさらに3つにわけて、詳細な季節の変化を表現するのが「七十二候(しちじゅうにこう)」です。七十二候における「立夏」の終わりは「竹笋生(たけのこしょうず)」と言って、筍が生えてくる時期を指し、筍が旬を迎える時期です。土佐煮や若竹煮などの煮物、筍ごはんやオイスター炒めなど、さまざまな筍料理で旬を味わってみてはいかがでしょうか。
■そら豆
そら豆やグリーンピースなどの豆類も「立夏」の時期が食べ頃。スーパーマーケットなどでそら豆を買うときは、艶があり、鮮やかな緑色をしたものを選ぶのがポイントです。さやごと焼いたり、そら豆ご飯にするのも美味しいですね。
■鰹(かつお)
「立夏」に旬を迎える魚といえば、やはり初鰹でしょう。鰹の旬は、春と秋の2回ありますが、春から初夏にかけて獲れる鰹を「初鰹」と言います。初鰹はあっさりとした味わいが特徴で、タタキで味わうのがおすすめです。ちなみに秋に獲れるのは「戻り鰹」です。
■新じゃが
「新じゃが」とは、「男爵」や「メークイン」といったじゃがいもの品種ではなく、春から夏にかけて収穫されたじゃがいものこと。意外(?)なことに、新じゃがはビタミンCを多く含んでおり、なんとレモンと同等のビタミンC量。ビタミンCは風邪予防など免疫力を高めるほか、美肌を目指すために必要不可欠な栄養素です。じゃがいもの栄養は皮に近い部分にありますが、皮が薄く、皮ごと食べられる新じゃがはその点でもオススメです。
【「立夏」の「反対」は?】
二十四節気で「立夏」の対極にあるのは「立冬」です。現在使われている太陽暦の11月7日頃にあたります。
【「英語」で言うと?】
「国立天文台」の「こよみ用語解説」英語版によれば、「立夏」は「Beginning of Summer」と説明されています。同様に、「立春」は「Beginning of Spring」、「立秋」「立冬」も同様です。
***
「立夏」は「夏の始まり」とはいえ、気温が高くても湿度が低いので、爽やかで過ごしやすい時期と言えます。気候も安定しているので、ゴールデンウィーク終盤にあたる「立夏」の頃は毎年、お出かけに最適な時期ですね。ただしご承知の通り、紫外線も日ごとに強くなりますから、対策は怠りなく。ビタミンCが豊富で、この時期旬を迎える新じゃが料理に、舌鼓を打ってはいかがでしょうか。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:/『日本大百科全書 ニッポニカ』(小学館) /『心が通じる 手紙の美しい言葉づかい ひとこと文例集』(池田書店) 国立天文台「暦Wiki」https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/wiki/B5A8C0E12FC6F3BDBDBBCDC0E1B5A4A4CEC4EAA4E1CAFD.html「こよみ用語解説」https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/faq/24sekki.html.en :