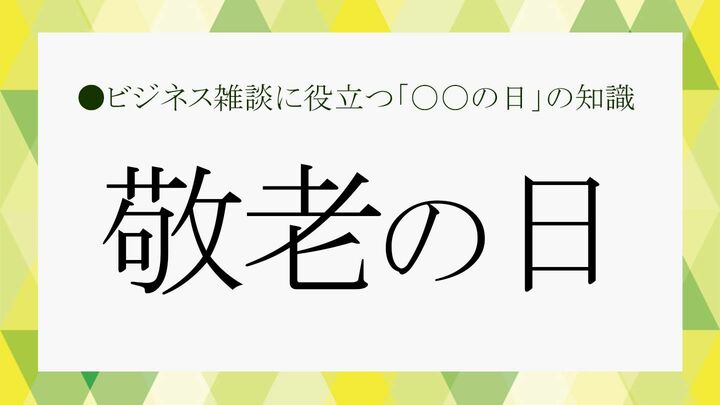【目次】
【「敬老の日」と「老人の日」何が違う?「由来」】
■「敬老の日」とは?
日本では「国民の祝日に関する法律(祝日法)」によって「国民の祝日」が設けられ、これを「休日とする」と定められています。2025年現在「国民の祝日」は年間で16日あり、「敬老の日」は1966(昭和41)年の「祝日法」改正により追加制定された祝日です。政府広報オンラインによれば、その趣旨は「多年にわたり社会に尽くしてこられたお年寄りの方々に感謝するとともに、老後の精神的な安定を願うため」と説明されています。
■2025年の「敬老の日」はいつ?2026年はシルバーウイークに!
「敬老の日」は9月の第3月曜日です。2025年は9月15日が「敬老の日」にあたり「国民の休日」になるので、9月13日(土)と9月14日(日)と「敬老の日」で3連休になる、という人もいるでしょう。制定当時の「敬老の日」は9月15日と固定日付でしたが、2001(平成13)年の「祝日法」改正により、2003年から9月の第3月曜日に変更になりました。従って2024年は9月16日でしたし、来年2026年は9月21日が「敬老の日」となります。
そして、ご存じの通り、9月23日は「秋分の日」で「国民の休日」です。2026年の9月22日は火曜日で平日ですが、「祝日法」の規定により、2026年の「敬老の日」と「秋分の日」の間(はざま)になり、22日も祝日扱いに! 2026年は、19日の土曜日から23日まで5連休という企業や教育機関は少なくないでしょう。2026年の9月には、いわゆる「シルバーウイーク」がやってくる、というわけです。
■「敬老の日」の由来
「敬老の日」は、飛鳥時代に聖徳太子が四天王寺に悲田院 (ひでんいん) という救護施設を設立したと伝えられる日に由来する、という説がありますが、直接の起源は、1947(昭和22)年、兵庫県多可郡野間谷村(現在の多可町)の村長が提唱した「としよりの日」だとされています。「老人を大切にし、年寄りの知恵を借りて村づくりをしよう」と、農閑期の9月15日に敬老会を開いたことが評判となって全国に広まり、1964年からは「老人の日」と呼ばれ、全国各地で敬老行事が行われてきました。
■「敬老の日」と「老人の日」の違いは?
一方、「老人の日」とは、老人福祉法によって定められた記念日です。「敬老の日」とは違い、「老人の日」は日付が9月15日と決まっています。また、9月15日から9月21日までは「老人週間」と定められています。「老人の日」の趣旨は、「老人が自らの生活の向上に努める意欲を促す」というもの。お年寄りに元気で長生きしてもらうという考え方は「敬老の日」と同じですね。
【お祝いをするのは「何歳」から?何をする?】
■何歳からお祝いする?「対象者」「年齢」は?
「敬老の日」って「何歳くらいの人を対象にお祝いすればいいの?」と、迷ったことはありませんか? バスや電車など、交通機関で席を譲る際に「相手に気を悪くされないかな?」と気遣ってしまう気持ちとよく似ていますね!
「敬老の日」で祝う対象者の年齢は特に定められてはいませんが、 一般的には、対象者に孫が生まれ、その孫がある程度成長したころに、「孫から祖父母へ」お祝いをするケースが多いようです。
孫のいない高齢者も少なくない現代ですが、老人福祉法における「高齢者」の定義である65歳以上を目安にお祝いする家庭が多いよう。家庭をもたない高齢者は、「社会が私を祝ってくれている」と思えばよいのではないでしょうか。
■具体的には何をする?
趣旨は「多年にわたり社会に尽くしてこられたお年寄りの方々に感謝するとともに、老後の精神的な安定を願うため」ですから、何をしなくてはいけないということはありません。感謝の気持ちを伝える手段としてメッセージカードや贈り物をしたり、食事会をしたり、旅行に行ったり…など、方法はさまざま。特別なことをしなくても、会いに行ったり電話で話したりなど、普段できないコミュニケーションをとるだけで当人は嬉しいものでしょう。
【プレゼントの選び方や値段の「相場」など豆知識】
■プレゼント選びに迷ったら…
贈るのも贈られるのも気軽な飲食品はいかが? 外れがないのがクッキーの詰め合わせや和菓子、アルコールなどでしょうか。また、ちょっと高級な肉や鰻、海産物など、日常よりワンランク上の食材をプレゼントするのもいいですね。ポイントは「そのまま食べられるもの」、あるいは「焼くだけ」「温めるだけ」など、手間のかからないものをセレクトすること。もちろん「量より質」を重視して!
■金額の相場は?
年齢や関係性(自分の祖父母とは限りません)によって…というところでしょうか。子どもなら数百円やお金のかからない方法もアリですし、学生なら「お小遣いやアルバイト代をちょっと貯めた」程度の数千円が、相手の負担にならないのでは? 社会人であっても、年齢や収入に応じて無理のない範囲で考えてみてください。「敬老の日の出費が痛い…」と感じてしまう金額は本末転倒。「プレゼント選びが楽しかった」「一緒に食事や旅行ができて嬉しかった」と思える金額が、あなたにとっての相場です。
■プレゼントは「物」だけとは限りません
まだまだアクティブに動ける方なら、日帰り温泉や「はとバス」的な日帰りツアーに連れていってあげるのもおすすめです。とはいえ、外に連れ出すだけがプレゼントだとは限りません。ゆっくり話す時間を取ってみたり、電話をかけるだけでも喜んでもらえるでしょう。まずは、お互いに負担にならない小さなことから始めてみては?
■ほかに「長寿の祝い」には何がある?
敬老の日以外にも、年齢の節目に行う長寿のお祝いがあります。いくつかご紹介しましょう。
・還暦(かんれき)
数え年で「61歳」の別称、つまり満年齢60歳を指す言葉が「還暦」です。生まれてから60年で、十二支と、「甲・乙・丙・丁・戌・己・庚・辛・壬・癸」の十干を組み合わせた、60種類の干支が一巡し、生まれた年の干支に還ります。このことから、長寿を感謝し祝う行事となりました。赤いちゃんちゃんこを着る風習でおなじみですね。赤には魔除けの意味があり、生まれた年と同じ暦に還る(赤ちゃんに還る)意味から、ちゃんちゃんこを着るようになったそうです。
・古希(こき)
古希は70歳のことで、中国の唐時代の詩人、杜甫が詠んだ「曲江詩」の一節、「人生七十古来稀(じんせいしちじゅうこらいまれなり)」が由来となった言葉です。70歳まで生きる者は少ないという意味があり、「古稀」とも書きます。魔除けの意味をもつ紫色が祝いの色です。
・喜寿(きじゅ)
「喜寿」は77歳にあたります。「喜」という漢字の草書体「㐂」が、七十七に見えることからきた言葉で、「喜びの字の祝い」「喜の字の齢」とも呼ばれ、「古希」同様、紫色で祝います。地域によっては紫色のちゃんちゃんこや頭巾や扇子、座布団などをプレゼントすることもあるようです。
・米寿(べいじゅ)」
「米寿」も「喜寿」同様、漢字を由来とする言葉です。88歳、またその長寿の祝賀のことで、別名「米(よね)の祝い」。これは「八十八」の字画を詰めると「米」に通じることからきています。お米にちなみ、「金茶色」や「黄色」の贈りものがよいとされていますよ。
・白寿(はくじゅ)
「白」の字は、百から一を取ったものであるところから、99歳、またそのお祝いを指して「白寿(はくじゅ)」と呼ぶようになりました。テーマカラーはもちろん「白」です。
・紀寿(きじゅ)または百寿(ひゃくじゅ)
100歳を迎える方へのお祝いが、「紀寿」と「百寿」です。1世紀が100年であることから「紀寿」、または100を漢字で書いて「百寿(ひゃくじゅ、ももじゅ)」とも呼ばれます。ちなみに2024 年に「紀寿」・「百寿」を迎える方は、1924年(大正13年)生まれの方です。「白色・桃色」の贈りものが縁起がよいとされています。
***
65 歳から「高齢者」の粋に入る…とはいえ、現代の60代はまだまだ元気! 企業などの定年は多くが60歳を基準にしていましたが、最近では65歳定年や、いきなり70歳定年というところも。厚生労働省も「高年齢者雇用安定法の改正」により、定年の引き上げや定年の廃止、再雇用制度や勤務延長制度の導入など、さまざまな方法で高齢者が働ける環境を整えることを推進しています。いずれにしても高齢者を敬う日である「敬老の日」、あなたの周囲の高齢者に思いを寄せてみてくださいね。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料: 『日本国語大辞典』(小学館) /『デジタル大辞泉』(小学館) /『日本大百科全書 ニッポニカ』(小学館) /『12か月のきまりごと歳時記(現代用語の基礎知識2008年版付録)』(自由国民社) /政府広報オンライン(https://www.gov-online.go.jp/) /厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/index.html) :