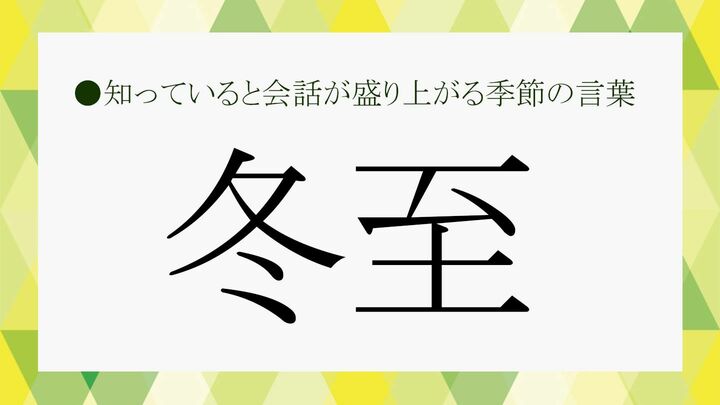【目次】
【冬至とは何?意味と読み方】
■「読み方」
「冬至」は「とうじ」と読みます。
■「意味」
「冬至」は二十四節気のひとつです。太陽の中心が冬至点を通過する日で、毎年12月21日ごろにあたり、本格的な寒さを迎える時期。北半球では一年中で昼がいちばん短く、夜がいちばん長くなる日として知られていますね。
【なぜ冬至は「重要な日」とされた? 由来と背景】
■なぜ「冬至」が重要視された?
「冬至」は、一年のうちで最も昼が短く、夜が長くなる日です。言い換えれば、この日を過ぎると少しずつ日照時間が伸びていくということ。このような観点から、世界各地では、古くからこの日を「太陽が力を取り戻す日」「再生や希望の象徴」また「太陽の誕生日」として意識するようになったのです。
■「由来」は?二十四節気をおさらい!
「冬至」は二十四節気のひとつです。二十四節気とは、もともとは古代中国の暦法で、1年を24等分して気候の推移を示すもの。各節気の期間は約15日。例えば、「冬至」といった場合、「冬至」に入る日を指す場合と、「冬至」にあたる期間を指す場合があります。
二十四節気のなかで重要な節目となるのが、「二至二分(にしにぶん)」と呼ばれる、春分、夏至、秋分、冬至の4つです。
春分と秋分は、昼と夜の長さが同じになることはご存知ですよね? 夏至は昼の時間が最も長く、冬至は昼の時間が最も短くなります。それぞれの季節の始まりを告げる立春、立夏、立秋、立冬の4つを「四立(しりゅう)」と呼び、二至二分と四立をあわせたものが「八節(はっせつ)」。この八節を3つの節気に分けたものが二十四節気となります。
つまり、「冬至」は季節の大きな転換点であり、農耕社会での季節管理における大きな節目でもあったのです。
■暦を正す「基準日」だった
冬至のように「1日の長さが最も短くなる日」は、暦の基準点としても重要でした。太陽の動き(天文学的現象)は、暦を作る上うえで、もっとも客観的で普遍的な基準となります。
■「一陽来復」
「一陽来復」は紀元前数世紀の中国で生み出された「易」の占いから出た言葉です。「冬の厳しさが最高潮に達すると、やがて春が訪れる」ことを表し、 ここから「冬至」を意味するようになりました。転じて、「不運が窮まると、やがて幸運が訪れる」という意味にもなります。「冬至=一陽来復」として、「これからよい方向に向かう吉日」とする考えが日本にも広まりました。
【日本の伝統行事】
■「ん」のつくものを食べる
「冬至」には、縁起を担いで「ん」の付くものを食べるという風習があります。これは「運盛り」と呼ばれ、運を呼び込めるといわれています。運盛りのなかでも「ん」が2回つく食べものを「冬至の七種(ななくさ)」といいます。
「南京(なんきん:かぼちゃ)」
「蓮根(れんこん)」
「人参(にんじん)」
「銀杏(ぎんなん)」
「金柑(きんかん)」
「寒天(かんてん)」
「饂飩(うんどん、うどん)」
以上7つが、「冬至の七種」です。なかでも「南京(かぼちゃ)」は有名ですね!
■小豆を食べる
古くから、赤は邪気を祓う色だといわれています。そして、冬至に赤い小豆を食べて邪気を払う、という目的で、小豆を使った冬至粥、小豆とかぼちゃを煮た「いとこ煮」を食べる習慣もあります。
■ゆず湯に入る
「冬至」の日、柚子(ゆず)の実を入れて沸かす「ゆず湯」に入る風習は、江戸時代のころから始まったといわれています。ゆず湯は「冬至湯」とも呼ばれ、ゆずの強い香りで邪気を払い、体を清めることで運を呼び込むと考えられていました。
また「柚子=融通」「冬至=湯治」といった語呂合わせから、「ゆず湯に入って、融通よく暮らしましょう」という説もあるようです。融通よく、というのは、ちょっと意味がわかりにくいですが、「融通」という言葉がもつ「金銭の都合をつける」「ものごとを滞りなく進める」といった意味から、無病息災で、という思いが込められていると考えられます。
ゆず湯には血行促進作用や温浴効果があるといわれているため、風邪予防のサポートのほか、爽やかな香りでリフレッシュ効果も期待できますので、日頃の疲れを癒したい方にもおすすめです。
【冬至の食べ物 栄養学的意味は】
■冬至かぼちゃは風邪予防に効果的
昔から、体調を崩さないため、また、運気を高めるため、冬至に食べるかぼちゃのことを「冬至かぼちゃ」と呼んでいます。かぼちゃはビタミンAやカロチンといった栄養素が豊富なうえに、長期保存が可能。冬の風邪や脳血管疾患予防に効果があるといわれています。
■「いとこ煮」の栄養価は?
小豆とかぼちゃを煮た「いとこ煮」は、かぼちゃのビタミンAと小豆のたんぱく質で栄養バランスも抜群。また、小豆にはサポニンなどのポリフェノールやカリウム、食物繊維などが豊富です。サポニンは小豆の苦味成分で、抗酸化作用で体内の活性酸素を抑制するほか、血流を改善するため、冷え性対策に有効です。
また、血糖値の上昇を抑えたり脂肪の蓄積を改善するとされています。余分な水分を流してくれるため、むくみ解消にも役立ちます。ミネラルの一種であるカリウムは、体内の余分なナトリウムを排出したり、利尿作用によりむくみを解消してくれます。さらに食物繊維を摂ることで腸内環境が改善され、便秘や肌荒れの解消、体内の老廃物の排出などに役立ちます。ほっこりした甘さが心も和ませてくれる「いとこ煮」は、寒い夜にぜひ食べてほしい一品です。
【2025年の「冬至」はいつ?日の出・日没・日照時間】
■「日付」は?
2025年は、12月22日(月)の18時21分が「冬至」です。また、二十四節気の期間でいえば次の「小寒」(2026年1月5日)の前日まで続きます。
■「日の出」「日の入り」の時間、「日照時間」は?
冬至の日の出や日の入りは、何時ごろになるのでしょう? それぞれの年や地域によっても違いがありますが、2025年の冬至である12月22日は、東京の「日の出」が6時47分、「日の入り」が16時32分で、日照時間は約9時間45分です。冬至を境に、昼がいちばん長い「夏至」に向かって昼の時間が長くなっていきます。
ちなみに、2025年の「夏至」は6月21日(土)。東京の日の出は4時25分、日の入りは19時00分で、日照時間は約14時間35分でした。「夏至」と「冬至」では、昼の時間に5時間弱も差があるのですね。日が短く感じられるはずです!
【世界で祝われる「冬至」の行事】
世界には、「冬至(最も昼が短く夜が長い日)」を祝う行事や祭りがあります。共通のテーマは「太陽の再」「生命の循環」。地域ごとの文化や信仰・歴史によって、さまざまなスタイルで表現されています。
■北欧の「ユール祭」
北欧では冬至祭りである「ユール」がクリスマスの起源と考えられ、現在でもクリスマスのことをユールと呼んでいます。ユールの祭りで燃やされる薪には魔力が宿るとされ、冬至を境に太陽が夜の闇に勝るよう輝きを助ける薪とされていました。樹木信仰が強かったドイツでも、ユール・ログの樫の木は「モミの木」へと替えられていきます。冬至の祭り「ユール」はクリスマスと融合して、モミの木がクリスマスツリーとして飾られるようになったのです。
■中国の「冬節、交冬」
中国では周の時代から「冬至大如年(冬至は春節(新年)にも匹敵する程大切な行事)」といわれており、宮廷はもちろん民間でも大切にされ、祭祀の行事が行われてきました。餃子(北部)や湯円(タンユェン/南部)を食べ、祖先を祭り、家族で団欒し、春の訪れと新たな始まりを祝う伝統行事です。
■イランの「ヤルダ・ナイト」
「ヤルダ」とは、「一年で最も夜が長い日=冬至の夜」を指す行事名です。イランのほか、アフガニスタン、トルクメニスタン、アゼルバイジャン、タジキスタンなどペルシア文化の影響がある地域でも祝われています。イランには古くから、冬至が最も暗い夜である一方で、「太陽が生まれる夜」と捉え、光が暗闇に打ち勝つ象徴として祝い、家族で夜を明かして語らい、祈りや詩の朗読を楽しんだ歴史があります。
***
師走に入り、昼の時間がどんどん短くなってくると、本格的な冬の到来を感じますね。これが「冬至」の季節です。血行促進や温浴作用が期待できる「ゆず湯」や「冬至の七種(ななくさ)」「冬至かぼちゃ」などで、風邪や体調不良を予防し、健やかな新年を迎える準備としてください。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料: 『日本国語大辞典』(小学館) /『デジタル大辞泉』(小学館) /『日本大百科全書 ニッポニカ』(小学館) /『世界大百科事典』(平凡社) /『四字熟語ときあかし辞典』(研究社)/国立天文台「東京(東京都)のこよみ」(https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/dni/dni13.html) /ベル・フルール「12月 冬至とブッシュ・ド・ノエルとクリスマス」(https://school.belles-fleurs.com/2024/11/2412column/#:~:text=冬至の祭りユールは,ド・ノエル」なのです%E3%80%82&text=また、クリスマスツリーが初めて,を願ってお過ごしください%E3%80%82) /北京観光「冬至の節気│中国では伝統的な行事である冬至の風俗習慣と行事食」(https://japan.visitbeijing.com.cn/article/47Jv3iMH3nG#:~:text=冬至と言えばなんと,も食べてみてください%E3%80%82) /公益社団法人 日本国際民間協力会「イランの紹介 “~冬至について~” -Introduction of Iran “the winter solstice”」(https://kyoto-nicco.org/projectblog/afghanistan160310) :