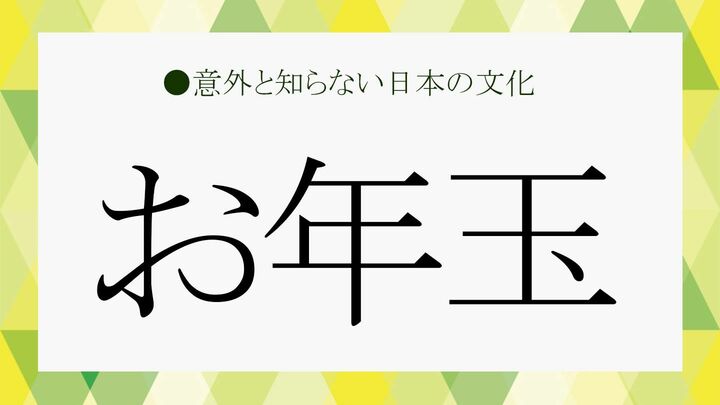子どものころ、新年を迎えるたびに楽しみにしていたのが、「お年玉」でしたよね! 両親や親戚の方などからいただいたあと、こっそり袋の中身を確認する時のドキドキを覚えている人も多いでしょう。今回は「お年玉」について、その由来や歴史のほか、「誰に、いつまであげればいいの?」といった素朴な疑問にお答えします!
【目次】
【お年玉の「由来」と「歴史」】
お正月には、子どもたちが家族や親戚からお年玉をもらう習慣があります。現在では「お年玉」は、新年を祝う贈り物や、主に子どもに贈る金品を指して使われていますが、もともと、どんな由来や歴史がある言葉なのでしょうか?
■「由来」
「お年玉」の由来は、「御歳魂」という言葉からきています。これは「その家に福をもたらす年神さまの賜物(たまもの)」を意味し、元旦に各家庭に降りてくる年神さまが、恩恵や祝福としてお与えくださったご加護が「お年玉」という言葉に変化していったといわれています。また「年神さまの魂」が「お年玉」の由来になったとする説もあるようです。
■「歴史」
現在、「お年玉」と言えば「お金」を連想しますが、もともとは、なんとお餅でした。「御歳魂」は、正月に歳神さまをお迎えするためにお供えした丸い鏡餅のことを指していたのです。これは「魂」の象徴であり、同時に生きる力、気力を象徴するものでした。その丸餅をくだいて家族や使用人に分け与えることで、一年分の力を授かり、これからの一年を無事に過ごせるよう祈ったのです。
この習慣が、お正月に訪れた家族や親戚、友人の子どもなどに、お餅だけではなく品物やお金で「お年玉」を渡す習慣に変化していったと考えられています。始まった時期については諸説ありますが、江戸時代には庶民にも浸透していたといわれています。現金を渡すことが主流になったのは、高度経済成長期だった昭和30年ごろのからのようです。同時に、贈る相手ももっぱら子どもになったといわれています。
【お年玉は「誰」に「何歳まで」あげるもの?】
自分が子どものころは、当たり前のように受け取っていたお年玉ですが、大人になった今、「誰に」「いつまで」お年玉をあげるべきなのか、決めかねている人は多いのではないでしょうか。
■お年玉は「誰に」どこまであげる?
お年玉をあげる対象は、「お正月に直接顔を合わせる(親戚の)子どもには全員」と考えている人が多いようです。兄妹や親せきの数が多い家庭では、なかなか痛い出費になるかもしれませんね。とはいえ今は、お正月に親族全員が集まるという家のほうが、少数派なのかもしれません。
■「何歳」まで、あげるべき?もらうべき?
お年玉をあげるのは、子どもが高校を卒業するころまでと考える人が多いようです。これには、民法の改正によって、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたのも影響していると思われます。とはいえ、「勉学が本分である学生の間はお年玉をあげる」という考えもあるので、何歳まであげるかは、各家庭の判断、対象となる子どもとの関係性次第。一概に「○歳まで」と決めるのは難しいですね。
【お年玉の「金額の相場」は?】
「○歳の子どもにはいくらあげるのが適切なの?」という問題も、切実ですね。金額の相場について、マーケティング・リサーチの株式会社インテージが2023年12月に実施した「2024年お年玉調査」の結果を以下にご紹介します。
[ポイント]
・来年のお年玉を渡す予定の人は全体の46.8%。渡す人の予算総額は平均25,099円で前年比106%の増加。
・相場(1人に渡す金額)は、昨年に比べ減少。小学生未満「1,000円以下」、中学生「3,000円超~5,000円」など。
・渡す方法は「現金(手渡し)」が9割と大多数、「スマホのキャッシュレス決済」は1%未満で前年と大きな変化なし。
・もらう側は「スマホのキャッシュレス決済」を4人に1人が希望。
1人に渡す金額として、それぞれの学齢で最も多かった金額は以下の通りです。
・小学生未満「~1,000円」(44.9%)
・小学1~3年生「1,000円超~3,000円」(50.3%)
・小学4~6年生「1,000円超~3,000円」(40.9%)
・中学生「3,000円超~5,000円」(49.1%)
・高校生「5,000円超~10,000円」(48.8%)
・大学生・専門学校生・短大生「5,000円超~10,000円」(67.7%)
注目すべきは、「もらう側」の希望です。「スマホのキャッシュレス決済でもらいたい」という人は27.4%にのぼり、理由のトップは「普段スマホのキャッシュレス決済を使っていて便利だから」(66.7%)でした。4人に1人以上が電子マネーの送金を希望しているのですね。とはいえ、実際にキャッシュレス決済を利用しているのは、全体の1%未満。選択しない理由としては、「現金の方がもらったという実感がわく」(41.0%)がトップでした。
【お年玉に贈与税がかかるってホント?】
国税庁によれば、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」に関しては、贈与税はかからないとされています。お年玉は「年末年始の贈答」に含まれると考えられるため、一般的な常識の範囲内であれば贈与税はかかりません。では、お年玉に贈与税がかかるのは、どんなケースが考えられるでしょう。
■110万円超は要注意!
贈与税は、1人の人が1年間(1月1日~12月31日)にもらった財産の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた残りの額に対して課税されます。1年間にもらった金額の合計額が110万円を超える場合、もらった側が贈与税の申告を行わなければなりません。お年玉の金額が110万円になることは一般的にはないと思いますが、お年玉以外にも贈与されたものがあり、合計額が110万円以上になるなら、納税の申告が必要となります。
例えば、「祖父から100万円、祖母から20万円」を贈与された場合でも、贈与合計額は110万円を超えるため、贈与税の対象になります。受け取った側の年齢は関係ないことにも注意が必要です。贈与した相手が生まれたばかりの赤ちゃんでも、支払い義務が発生する可能性もあるのです。
■贈与税がかからないお年玉のあげ方
では贈与税がかからないようにお年玉をあげるには、どうしたらいいでしょうか?
あげ方1:お年玉は相場の金額にする
一般的なお年玉の金額の範囲であげるのが、いちばん安心ですね。
あげ方2:生活費や教育費としてあげる
生活費や教育費に必要なお金を贈与された場合は、贈与税の対象になりません。ですから、もし一般的なお年玉の相場よりもずっと高額を渡すなら、生活費や教育費として使うといいかもしれません。
あげ方3:年末と年始に分けて贈る
贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの期間にもらった合計金額をもとに計算します。ですから、もし高額のお年玉をあげるのなら、12月中と1月に分けて渡すという方法もあります。
【ビジネス雑談に役立つ「お年玉」の雑学】
■お年玉をあげる・もらうのにふさわしい日にちは?
お年玉の由来となっている年神さまが降りてくるのは、元旦です。従って、お年玉をあげるのにふさわしい日は、元旦と考えていいでしょう。とはいえ、1月1日に親戚に会うとは限りませんし、いつまでにあげなければいけないといったルールはありません。元旦にこだわるなら、遠く離れた親戚などの場合、現金書留を利用して、元旦前に親元に届ける、という手もあります。
■ポチ袋の用意がなかったらどうする?
お年玉に関するマナーとして、「ポチ袋に入れて渡す」ことは、皆さんご存知ですよね。ポチ袋の表には渡す相手の名前を書き、裏に自分の名前を書くのが一般的です。想定外のケースも考えられますので、年末年始はポチ袋を余分に用意しておくと安心です。万が一、お年玉を渡したほうがよいシチュエーションでポチ袋の用意がなかったら…ティッシュペーパーでもよいので、必ず何らかの紙や布で包んで渡すのがマナーです。その際、失礼を詫びるひと言葉を添えるといいですね。
■ポチ袋にお札を入れるときの注意点は?
ポチ袋には、できれば新札を入れて用意するのがマナーです。忙しくて新札を用意できなかったら、手持ちのものでできるだけきれいなお札を選んで。お札を折って入れる際には、お札の肖像が内側に入るように左から右に三つ折りにします。硬貨は、製造年月が書いてある裏側を下にして入れるのが、正しい入れ方です。
ちなみに、2024年の銀行・郵便局の窓口の営業日は、12月30日(月)まで、12月31日(水)から1月5日(日)までは休業となります。
■NGマナーはある?
お年玉は、目上の人から目下の人に渡すもの。そのため、子から親に渡すのは本来、失礼にあたります。どうしても渡したい場合は「お年賀」として渡すのがスマートですね。では、上司や先輩のお子さんに対してはどうでしょう。この場合には「お年賀」としてお菓子を持参したり、Amazonなど各種ギフト券やプリペイドカード、デビットカードなどを現金代わりにあげるという方法も。図書カードも、親の立場からすればうれしいですね。
***
子どものころ、お年玉をいただくのはお正月の楽しみのひとつでした。近年では「合理的」ということで、親戚同士、お年玉のやり取りはなし、という取り決をするケースもあるようですが、それもなんだか味気ないし、大人の事情に巻き込まれる子どもが少々気の毒です。お年玉は、子ども達の健やかな成長を願う思いを込めて贈るもの。日本の習慣のひとつとして、伝えていきたいものです。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料: 『日本国語大辞典』(小学館) /『デジタル大辞泉』(小学館) /株式会社インテージ「2024年お年玉調査」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000220.000036691.html) /国税庁『No.4405 贈与税がかからない場合』(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm) :