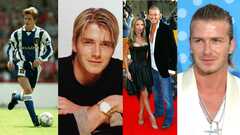【目次】
不安に思うことの99%は起きない
「医師の目」で答える「不安」と上手に生きる心構え
恐れを抱く対象が明確なものが「恐怖」で、対象が明確でなく漠然としたモヤモヤが「不安」です。何に対して違和感や恐れを抱いているかわからないから、考えるほどに不安が広がっていくのです。そんな不安をますます増大させているのが「情報」だと私は思っています。今年80歳になる私からすれば、人々の不安の絶対量は、今も昔もたいして変わりません。けれども、不安をあおるような「情報」があまりにも多すぎる。
世界情勢から、著名人はもとより、一般人の超・個人的なあれこれまで…、見なくてもいいこと、知らなくてもいいことが、世に溢れています。確かに、シャットダウンしたくても、無意識に目の前を流れてしまうほど、今の時代は情報社会かもしれません。でも、まだ足りない、もっと知りたい…と、人々は自ら情報を求め、情報に飢えているような…そんな気さえします。つまり、自ら「不安」をかき集めているように思うのです。だったら、最初から情報なんて集めないことです。
だいたい、この世の中は知らなくていいことばかりです。知らないからって死ぬことはありません。もちろん、知って得する情報もありますが、知りすぎる不幸もある。他人は他人、私は私。人はみんな違うんです。最初から競わない、羨まない、攻撃しない。
「人生、なんとかなる」んです。そう思えたもんが勝ち!みんなまじめすぎるんですよ。皆さん、最初から、パーフェクトに42・195キロのフルマラソンを走りきろうとしすぎです。とりあえず、遅くてもいいから、あの角まで行こう。そう思って角を曲がったら、別の景色が見えてちょっと気分が変わる。そうしたら、あとちょっとだけ走ってみるかとなって、また次の角まで行ってみる。介護も老後も、それくらいの心もちでいいんです。「そこの角まで」の繰り返しが、結果として今、続いている人生です。過去でも未来でもなく「今ここを生きる」こと。少し気が楽になるでしょう?
不安を感じたら、なんでもいいから「集中」できることをやってください。買い物でも、ゲームでも、海外ドラマ鑑賞でも、とにかく夢中になって“考える”ことから一旦離れること。私の場合はゴルフですが、目の前の小さな球が気持ちよく弧を描いて飛んでいくことだけに集中します。スコアも考えない、競わない。これが大事。
とにかく、不安から逃げるんですよ、考えちゃいけません。よく、気分転換に筋トレや水泳、瞑想、サウナなどを挙げる人がいますが、例えば筋トレなら、筋肉の動きだけに集中できる上級者ならいいですが、それらは結局、自分と向き合う時間です。よけいなことを考えてさらに不安になってしまう。雑念を振り払うことは、凡人には難しいのです。それから、聞き上手の仲間をもつのも有効です。声に出して話すことで、思考が整理され悩みが明確になります。
不透明な時代ですが、頑張りすぎず、無理しすぎず「今日一日を凌ぐ」くらいの気構えで、ね。

あなたの「不安」に寄り添いたい…「情報を集めすぎない、不安に思うことの99%は起きません」医師・大塚宣夫さん
強運を身に付ける習慣【2選】
あなたは自分のことを運がいいほうだと思いますか? もし現時点では自信をもって「YES」と答えられなくても、実はちょっとした日々の心がけで強運体質になることは可能なのです。しかも、その方法はたったのふたつ! 五輪メダリストや甲子園球児などのメンタルコーチを務める飯山晄朗さんから、トップアスリートが実践している強運を身に付ける習慣について教わりました。
【1】「だからこそ」を口癖にする

「強運を身に付ける最も手っ取り早い方法は、使う言葉を変えること。よく言われているように、言霊の力は絶大です。私たちの脳は、知らず知らずにうちに使っている言葉の影響を受けています。つまり、ポジティブな言葉を使えば使うほど、脳がプラス思考になって強運体質になれますし、逆に、ネガティブな言葉ばかり使っていると、脳にどんどん負け癖がついてしまうのです。
一流アスリートのインタビューで『必ず勝つ』『圧倒的な結果を出す』など、強気な発言を耳にすることが多くないでしょうか。プラスの言葉には、自分を鼓舞するともに勝負強さを培う効果もあります。ですから、私たちも強運を身につけたいなら、『でも』『だって』『どうせ』をはじめとするマイナス言葉はなるべく慎まなければなりません。
とはいえ、自分の口癖というのは、一朝一夕には矯正できないもの。禁句にしようにも、ついついマイナス言葉が口を出てしまうことはあると思います。そうした場合に、『あーまた言っちゃった』と自己嫌悪しては、ますますマイナス思考になるという悪循環に陥りかねません。そこで、おすすめの方法は、ネガティブな言葉を発してしまったときには、そのあとに『だからこそ』というフレーズを付け加えること。
たとえば、私がメンタルコーチを務める競泳の小堀勇氣選手は、大舞台になると緊張して実力を発揮しきれないという悩みを抱えていました。その悩みに『だからこそ』を付け加えると、『緊張してまわりの選手のことが気になってしまう。だからこそ、落ち着いてまわりが見える』とプラスに転じることができたのです。
強運フレーズ『だからこそ』は、もちろん職場でも使えます。たとえば、何かミスをやらかして上司から厳しく叱られた場合、ただ落ち込むのではなく、『ミスしてしまった。だからこそ仕事の精度を上げるためにどうすればいいのか?』など、不快な出来事を自分のスキルアップにつなげることが可能です。このように、『だからこそ』と言い切ってしまえば、その前にどんなにネガティブな発言をしていても、それが無効化されて、脳が勝手に前向きな言葉をたぐりよせようとします。『だからこそ』は強運を身に付けるための魔法のフレーズのようなものなのです」(飯山さん)。
ネガティブな口癖を直そう、ポジティブな言葉を使おう、と心がけてはみたものの、長続きしなくて「やっぱり自分はダメだ」と自己嫌悪に陥ったことのある人は多いのでは? 自分の言葉遣いを無理に直そうとするのではなく、「だからこそ」というワンフレーズを差し挟むだけならとても簡単! これなら挫折することなく、プラス思考と強運を身に付けることができそうですよね。
【2】明るい表情をつくる
「脳は、何か思ったり考えたりするという“入力”よりも、言葉を発したり体を動かしたりという“出力”のほうを強く記憶するという性質をもっています。だからこそ、プラスの言葉を使うことが強運を身に付けるのにもってこいなのですが、同じく出力作業として、明るい表情をつくることも効果的です。
そもそも、運がいい、運が悪いとはどういうことか。“運”は訓読みすると“運ぶ”となることからわかるように、運とは自分がつくり出すというより、誰かがもってきてくれるものなんです。たとえば、スポーツ選手について考えてみると、どんなに才能に恵まれていても、それを開花させられなければ宝の持ち腐れですよね。他方で、ずっと無名だった選手が、あるコーチとの出会いをきっかけに急に頭角を現すというケースもあるものです。
つまり、運がいいかどうか、成功するかどうかというのは、結局は、人との縁がカギを握っているのだといえます。では、どうすればそんな幸運な出会いに恵まれるのか? 答えはシンプルで、成功をもたらしてくれる強運な人に自分を見つけてもらうこと。そして、強運な人の目に留まるために、強力な武器となるのが笑顔です。
類は友を呼ぶ、と言われるように、強運な人は強運な人同士で引き合います。逆に、終始つまらなそうな表情でいると、同じように不平不満だらけの人ばかりが集まって、ますます運が下がってしまうことでしょう。強運な人に出会いたければ、まず内心はどうあれ明るい表情をつくること。自分がどんな表情をしているのかは自分では気づきにくいものなので、積極的に鏡を見てチェックするのもおすすめです。
もし、どういう表情がいいのかわからない場合、自分にとって『あの人は運がよくて自信に満ち溢れている、オーラがある』と憧れる人物を研究して、とことん真似するのもいいでしょう。直接の知り合いではなく、芸能人などでもOKです。特に、女性の場合、メイクや髪型によって大きく印象が変わるので、こうした形から入る作戦は非常に効果があります。ぜひ見た目だけでも運がいいように見えるように、いろいろ工夫してみましょう」(飯山さん)。
自分を取り巻く人間は、自分を映す鏡のようなもの。もし、自分は人間関係に恵まれていない、自分のまわりには何だか冴えない人物しかない……というふうに感じているのであれば、それは他ならぬあなた自身の魅力がその程度ということかもしれません。
強運の人を引きせて、自分の運気をアップさせるべく、明るい表情を努めましょう。
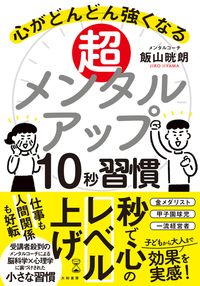
一流アスリートが実践してる!「強運を身に付ける」たった2つの習慣
どんな逆境でもモチベーションを保つ方法【6選】
五輪メダリストや甲子園球児への指導も行っているメンタルコーチの飯山晄朗さんによれば、一流のアスリートたちは決して腐ることなく、“次”を見据えて粛々と自己鍛錬に励んでいるとのことです。人間の真価は順風満帆のときよりも、困難を迎えたときそこそ問われるもの。モチベーションが低下しかけている人たちにとって、彼らのメンタルコントロール術は大いに参考になるのではないでしょうか?
【1】自分にとって究極の目標は何か考える

「甲子園に行きたかったのに……と落胆している選手には、『君はなぜ甲子園出場を目指していたの?』『どういう自分になっていたいの?』と問うています。
プロ入りを目指す生徒。野球は高校で終わりにするつもりの生徒。その中間的存在として、大学生や社会人になってからも野球を続けたい生徒……。人によっておかれた状況はさまざまですが、目標を深堀していくと、甲子園はあくまで手段であって、それ自体が目標ではないことに気付く瞬間があるのです。
たとえば、ある生徒には『やりきった充実感を得たかった』という動機がありました。やりきった充実感を得るのは、甲子園でなければできない、というわけではありません。
そのことに気づけば、『では、甲子園以外でどうすれば充実感を得られるのか?』『自分はどういうときに充実感を得ているのか?』という問いを立てることができ、突き詰めて考えていくと、徐々に自分のやるべきことが見えてきます」(メンタルコーチ、人財教育家 飯山晄朗さん)。
ビジネスの世界でも、「このプロジェクトを成功させたい」という表面的な目標の背景に「こういう自分になりたい」という動機があり、何が何でもそのプロジェクトでなければ……ということはないのでは? 計画などが頓挫してモチベーションが低下している人は、「なぜ自分はそれをやりたかったのか?」について、一度腰を据えて考えてみましょう。
【2】自分を取り巻く他者の存在を意識する
「自分は一体、何を目指していたのか、究極の目標を考えるときの手がかりとして、自分を取り巻く他者の存在を意識することは有効です。人間は、“自分がどうしたいのか”と意識が自分にばかり向いていると、どうしても視野が狭くなってしまいます。また、自分の喜びのためだけだと、逆境や壁にぶつかったときに、モチベーションの限界を迎えやすいのです。ですから、モチベーションの限界を感じたときには、家族や友人など自分の身近な人たちの存在を思い浮かべてみましょう。
たとえば、野球強豪校の3年生のこんなエピソードがあります。甲子園中止といっても、1年生、2年生ならば『今年がダメでもまた来年』と思えますが、3年生の彼にとってはもう“次”がない。失望した彼が再起するきっかけは後輩の存在でした。自分がなぜ甲子園を目指していたのか。そう考えたときに、彼は『甲子園で活躍している姿を後輩たちに見せたかった』という思いに気付いたのです。
野球を通して、人に何かを伝えたい。それが真の目的であれば、甲子園出場の道が閉ざされたからといって、腐っているわけにはいきません。残りわずかな高校生活の中で、少しでも後輩に何かを託したい、野球部に貢献したいという強い気持ちから、彼の部活動への取り組む姿勢が変わりました」(飯山さん)。
あなたの目標は自分のだけのものではなく、誰かを幸せにするためのものではないでしょうか? 心が折れそうなときは、あなたにとって大切な人の笑顔を思い出しましょう。
【3】自分の思いを自由に書き出す

「詳しくは後述しますが、モチベーションが下がったときには、自分のやりたいことについて人に話すのもおすすめです。ただ、人に話すためには、ある程度、自分の考えがまとまっていることが前提となります。ですから、人に話す前に、まずは自分の思いを自由に書き出しましょう。
これは自分のために行う作業なので、どのように書くかこだわる必要はありません。誰かに見せるものではありませんから、『コロナの影響で、この先どうなるのかわからなくて不安だ』や『もう何もかも投げ出したい』など思い切り弱音を吐いた次の瞬間、『自分は絶対に●●を成功させる』と根拠不明な宣言をしてもいい。
実際にやってみると、『やりたくない』と『やりたい』が混在するなど、支離滅裂な内容になりがちですが、まったく問題ありません。自分で書き出して心の動きを可視化し、自分の中にある矛盾に気づき受け入れることこそが、この作業の目的です。また、成功するには否定的な言葉をあまり使わないほうがいい、とよくいわれますが、この作業ではネガティブな言葉をどんどん書き出しても構いません。
ただ、ひとつだけ守ってほしいルールがあります。それは、最後は必ず『だから明日から~~する』と前向きな宣言でしめくくること。実は、脳には最後に出力した言葉を強く記憶する、という性質がありますので、どれだけネガティブな言葉を書き連ねても、最後の宣言しだいで脳をプラス思考に上書きすることができます。
『明日から~~する』の宣言内容は、大それたことではなく、すぐに実践できる小さな一歩が望ましいです。宣言したことをコツコツと実践して、『自分はできる!』というモチベーションを上げていきましょう」(飯山さん)。
【4】何でもいいからまず「1」を積み上げる
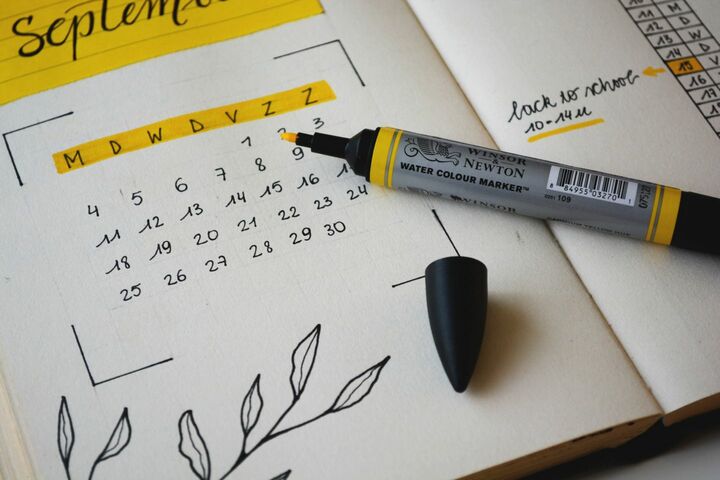
自分の気持ちを整理したうえで、「明日から~~する」と宣言し、それをコツコツと実践していく。たしかに、自己肯定感やモチベーションアップにつながりそうですが、万が一、宣言通りに行動できなかった場合、「やっぱり自分はダメなんじゃないか」と自己嫌悪に陥り逆効果にもなるおそれも……。
「自分で設定した『明日から~~する』を遂行できなくても、自分を責める必要はありません。できなかった原因は、気合や根性、能力不足など自分側ではなく、『明日から~~する』という設定のほうにあるのだと、割り切りましょう。自分では小さな一歩のつもりが、実は欲張りすぎていたのかもしれないし、そもそも気持ちが整理できておらず、自分が本心からやりたくないことを設定していた、という可能性もあります。
ですから、なぜできなかったのかにフォーカスするのではなく、どうすればできるようになるのか、そもそも自分は何をしたいのか、もう一度、自分に向き合って気持ちを自由に書き出して、最後に『だから明日から~~する』と宣言しましょう。
そして、翌日、宣言したことを実践する。できなかったら、また自分と向き合って『だから明日から~~する』と再設定する。そうやって、自分がやり続けられることを見つけていけば、必ず小さな一歩が積み重なっていくでしょう」(飯山さん)。
【5】自分がやりたいことについて人に話す
「モチベーションが下がっているときは、スポーツにしろ仕事にしろ、自分がやりたいことについて、人に話すのもいいでしょう。
というのも、脳は入力(思い・イメージ)よりも出力(言葉・動作)を信用する性質があるからです。頭の中で『やる気を出さなきゃ』とひたすら念じ続けるよりも、『自分はこんなことをやりたい、こんなふうになりたい』と言葉に出して人に伝えるほうが、よほどモチベーションアップ効果があります。
たとえば、コロナ自粛期間中、多くのアスリートが無料レッスン動画などを公開していました。あれは、視聴者のためというだけでなく、自分自身のためという意味もあったのではないかと思います。
レッスン動画を公開するからには、視聴者にその競技の魅力をアピールする必要がありますが、そのためには出演するアスリートは無気力な姿など見せられません。視聴者の気分を盛り上げるために、前向きな言葉で語ったり、楽しそうに競技に取り組んだりしているうちに、視聴者の誰よりも出演者のアスリートこそがモチベーションアップしたのではないでしょうか。
このように、ポジティブな姿勢で人に話すことにはメリットがありますが、ただ相手は誰でもいいわけではないので要注意です。たとえば、自分のやりたいことを話した結果、『何、そんな夢みたいなこと言っているの』『そんなことよりもっと大事なことがあるでしょ』など、腐すようなことを言われたらガッカリですよね。
話してみて、自分が元気になったり、何かヒントを得られたりする相手を選びましょう。もし、身近に適任がいないなら、プロのメンタルコーチやカウンセリングを受けるのも一考です」(飯山さん)。
【6】気持ちの整理がつくまで休む

「モチベーションを保つには、目の前の目標の先にある真の使命を見極めることが大切ですが、そうはいっても目標が消えてなくなると、すぐには気持ちの整理がつかないもの。どうしてもやる気が起きないときは、しばらく休むのもいいでしょう。
というのも、モチベーションが低い状態で、無理に自分を奮い立たせようとしても、“やらなきゃ、やらなきゃ”と気持ちが焦るばかりで、ストレスをためこむことにしかならないからです。
たとえば、芸能人でも一定期間、活動休止するケースはよくありますよね。一旦、普段の仕事を離れて冷静に自分を見つめ直すことで『やっぱり自分はこれがしたい』と情熱が再燃するかもしれないし、まったく別の自分の可能性を見出すこともあるかもしれない。
ただし、気持ちの整理がつくまで、といってもある程度は期限を切らないと際限がなくなります。1週間、1か月、あるいは何か節目となるイベントまで、と腹を決めて、休止期間を設けましょう」(飯山さん)
逆境でも心が折れない!一流アスリートが実践する「モチベーションを保つ方法」6選
ストレスに強い人が何気なくやっている習慣【8選】
【1】適度にからだを動かす

仕事のできる人は健康への意識が高く、忙しい合間を縫ってスポーツジムに通ったり、ジョギングを習慣化したりしている人が少なくありません。実は、このように適度にからだを動かすことは、ストレスマネジメントにも役立っているとのこと。
「ストレスというのは、例えると風船に圧力がかかっているような状態です。破裂を防ぐには、中の空気を逃がしてやる必要があります。その方法の1つが、適度にからだを動かしてストレスのエネルギーを外に出すこと。じっとしたままだと、ストレスの圧がかかり続けて、いずれ心身のバランスを崩すことになりかねませんが、からだを動かすことで、一種のガス抜きができるのです」(日本心理教育コンサルティング代表、カウンセラー 櫻井勝彦さん)。
デスクワークの人は、長時間座り続けることで、知らず知らずのうちにストレスを溜めこむおそれもあります。ときどき外に休憩に出たり、職場内を歩き回ったり、それも難しければ、せめて自分の席で伸びをするなど、からだを動かすことを意識的に行いましょう。
【2】嫌なことがあったら人にしゃべる
「ガス抜きの方法として、からだを動かす以外には、人に話すというのもおすすめです。風船の空気孔をきつく縛っていて、空気の逃げ場がないと、ちょっと圧をかけただけですぐに破裂してしまいますよね。ストレスがかかったときは、なるべくためこまず、人に話してしまいましょう」(櫻井さん)。
【3】お笑い番組を見る

何かストレスのかかる出来事があれば、できるだけ自分にとって楽しいことに触れて、気分を紛らわしたいもの。そうした娯楽のなかでも、お笑い番組は、単なる気晴らしになるだけではく、ストレスマネジメントと意外に深い関係があるとのことです。
「笑うという行為は、ストレス発散になるだけでなく、免疫力向上にもつながるといわれています。笑うための手段は、いろいろありますが、中でもお笑い番組は特におすすめです。というのも、お笑い芸人のかたは、ご自身の失敗や不幸話を自虐ネタとして笑いに昇華させています。そういう姿勢は、ストレスマネジメントにおいて非常に重要なんですね。
自分にとってネガティブな出来事について、くよくよ悩むのではなく、笑いに変えてしまう。そういう思考パターンを見習えるという点でも、お笑い番組はストレス対策として有効でしょう」(櫻井さん)。
【4】物事がうまくいかないときは、行為に焦点を当てて原因を考える
どんなに有能な人でも、失敗をゼロにすることはできません。物事がうまくいかないとき、どのように対処するかにも、ストレスマネジメントの秘訣があるようです。
「失敗したり不幸に見舞われたりしたとき、ストレスを溜めやすい人というのは、自分を全否定しがちです。たとえば、恋人に振られたときに、『自分に魅力がないからだ』などと捉えてしまい、ストレスの逃げ場がなくなります。
他方、ストレスに強い人の場合、『今回は、自分の行為の何がいけなかったのだろう?』と考えます。このように、自分全体にダメ出しするのではなく、行為に焦点を当てると、『自分のあの発言が相手を傷つけたのではないか』→『自分の感情を伝えたいときは、こういう言い方をしよう』と改善点が見えてくるので、過度の落ち込みを防ぐことができます」(櫻井さん)。
【5】日々、新しいことにチャレンジする

「ストレスの原因の1つとして、変化が挙げられます。たとえば、引っ越しや異動・転職、あるいは、結婚・出産といったおめでたいことであっても、何か新しい事態に直面すると、ストレスを感じてしまうものなのです。このように、人は変化に反応しやすい生き物ですが、変わり映えのない日常をずっと送り続けていると、ますます変化に対するストレス耐性が弱まります。
ですから、ストレスに強くなるには、1日1個、1週間に1個でもいいので、何か新しいことにチャレンジしましょう。今までやったことのないことに積極的に触れることで、変化に柔軟に対応する力が身につき、ストレス耐性も高まります。新しいことにチャンレンジ……といっても、難しく考える必要はありません。たとえば、ランチのお店を新規開拓する、普段食べないメニューを注文する、あるいは、会社帰りにいつもとは違う経路を使ってみるなど、ちょっとした変化を楽しみながら、経験することをおすすめします」(櫻井さん)。
【6】複数のフィールドをもつ

「家は柱が多いほど倒れにくいですが、人間も同じです。自分を支えるものが多いほど、ぐらぐらせずに精神が安定します。逆に、自分にとって心の拠り所が1つしかない人は、そこに問題が生じた瞬間、一気にストレスで崩れてしまうおそれがあって危険です。たとえば、会社一筋の人は、仕事がうまくいかないと、それだけで自分の存在意義が脅かされるように感じて、多大なストレスを受けます。また、恋愛するとのめりこんでしまう人は、相手との関係がちょっとぎくしゃくするだけで、この世の終わりのように感じがちです。
自分にはこれしかないと決め打ちするのではなく、仕事でもプライベートでも自分の居場所を複数つくっておきましょう。そうすれば、ある1つの分野でエラーが生じても、他の分野でリカバリーがきくので、ストレスに押しつぶされずに済みます」(櫻井さん)。
あなたには、「これが私の生きがい!」といえるものがいくつありますか? 自分の心のよりどころを増やすためにも、前項でご紹介した“日々新しいことにチャレンジする”という習慣は、重要かもしれませんね。
【7】瞑想の習慣をもつ

「学校でも社会においても、思考力を高めることはよいことだとされ、『もっとよく考えなさい』などという指導が行われていますが、実は、現代人は余計なことを考えすぎる傾向があります。たとえば、『ああなったらどうしよう』と先のことを悩んだり、『あのときこうしておけば』と過去の失敗を悔んだり、頭のなかであれこれ考えてしまうこともストレスを悪化させる原因です。
こうした考えすぎによるストレスを防ぐには、意識的に脳を休める習慣が大事だと思います。1日に1回、数分間でいいので、呼吸に意識を向けて、敢えて頭を空っぽにする時間をとりましょう。いわば、“考えないトレーニング”をするのです。考えることが習慣化している現代人にとって、これはなかなか難しく、何も考えまいとしても、ついいろいろ雑念は浮かんでしまうと思います。ただ、そこで自己嫌悪せず、何事も始めはうまくできなくて当たり前だととらえて、まずは毎日“何も考えない時間”を設けてみてください」(櫻井さん)。
【8】何事にも感謝する
「人は生きている限り、何かとアンラッキーなことは避けられませんが、その出来事をどう捉えるかがストレスに強い人と弱い人の分かれ目です。たとえば、新しくできたレストランに期待していたのに、いざ訪れてみたら料理がおいしくなかった。こんなとき、『残念』『ついていない』と落ち込むのが通常の反応ですが、ストレスに強い人は、ただネガティブな感情だけで終わらせるのではなく、『でも、健康で外食できることはありがたいことだな』などと、物事のよい面にも目を向けようとします。
これに関連して、私の知っているある料理人さんのエピソードをひとつ、ご紹介します。彼は、厨房で怒号が飛び交うような大変厳しい環境で働いているのですが、一度、『なんで平気なの?』と尋ねたところ、彼は『怒られるのは当たり前だから』と答えたんです。
怒られるのを過度に恐れていたら、ビクビクと上司の顔色をうかがって、精神的にまいってしまいます。そこを、彼のように『怒られるのは当たり前』とフラットにとらえたり、あるいは『怒ってもらえることで成長できる』と前向きにとらえたりすれば、ストレスを最小限に抑えることができるのではないでしょうか」(櫻井さん)。
これでストレス耐性アップ!ストレスに強い人が「何気なくやっている習慣」8選
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- PHOTO :
- gettyimages