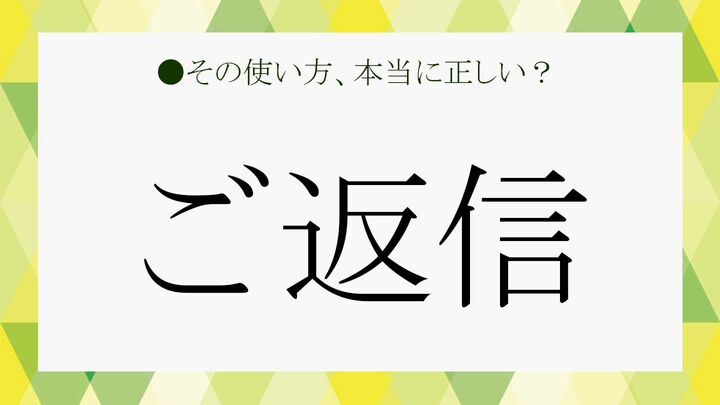【目次】
【誰に対する敬語表現?「ご返信」の「意味」】
「ご返信」の「ご(お)」は、語を丁寧にすることで結果的に動作の相手を立てる働きをする敬語表現です。例文で見てみましょう。
〈例文1〉部長からご返信を頂戴した。
〈例文2〉部長にご返信を差し上げた。
どちらの文も「返信」に「ご」をつけることで、相手に対して敬意を示しています。〈例文1〉では「部長からいただいた返信」を丁寧に言い、〈例文2〉では「部長に差し上げる返信」を丁寧に表現しています。
「自分の行為に“ご”をつけるのはおかしいのでは?」と思う人もいるかもしれませんが、「差し上げる」といった謙譲語と組み合わせることで、全体として相手を高める表現になるため、まったく問題ありません。
【「使い方」がわかる「例文」】
「ご返信」は接頭語を用いた敬語表現です。一般的によく使われる「ご返信ください」も、「くれる」の尊敬語である「くださる」を用いた丁寧な表現ですが、「ください」が命令形であるため、人によってはやや強く響き、「指示」と感じられる場合があります。
そのため、特に目上の方や社外の方に対しては、
「ご返信くださいますようお願い申し上げます」
などとより丁寧な形にしたり、
「お忙しいところ恐縮ですが」などのクッション言葉を添えたりするのが適切です。
■「ご返信」が「相手からの返信」である場合
・「お忙しいところ誠に恐縮ですが、ご返信くださいますようお願いいたします」
・「この度は丁重なご返信をいただきまして、ありがとうございました」
・「恐れ入りますが、ご返信をお待ちしております」
・「こちらのメールはご報告となりますので、ご返信いただくには及びません」
■「ご返信」が「自分からの返信」である場合
・「部内で検討したうえで、改めてご返信いたします」
・「こちらのアンケートには、いつまでにご返信すればよろしいでしょうか」
・「部内の意見を急ぎとりまとめ、後日メールにてご返信いたします」
【ビジネスでは「ご返信」と「お返事」どちらを使う?】
『デジタル大辞泉』によると、「返信」は「返事の手紙やメールを送ること。また、その手紙やメール」、「返事」は「呼びかけに対して答える言葉」「返答の手紙。返信。返書」と定義されています。
つまり、「はい」など口頭での答えを別にすれば、「返事」と「返信」はほぼ同じ意味で使われています。ただし、印象としては「ご返信」の方がフォーマルで、「お返事」はややカジュアルなニュアンスになります。
そのため、ビジネスシーンでは「ご返信」を用いるのが一般的であり、適切だと言えるでしょう。
【「類語」「言い換え」表現】
■お返事 ■ご回答 ■ご返答
「返答」とは、「問いに対して答えること。また、その答え」を意味します。「お返事」と同様に問いかけへの答えを表しますが、「ご返答」の方が改まった響きをもち、ビジネスや公式の場でよく使われます。
「ご回答」は特に質問やアンケート、問い合わせに対する答えに用いられる表現です。
したがって、日常会話では「お返事」、ビジネス文書では「ご返答」や「ご回答」といった表現を使い分けるのが自然です。
【「英語」で言うと?】
ひとことで「ご返信」に完全に対応する単語はありませんが、「返信」は[reply]や[response]で表現できます。
■「ご返信」が「相手からの返信」である場合
「ご返信をありがとうございます」を英訳してみましょう。
・Thank you very much for your reply.
・I appreciate your response.
■「ご返信」が「自分からの返信」である場合
・I will reply to your message as soon as I can.(できるだけ早くご返信します)
・We will send you our feedback as soon as we get back to the office.
(社に戻り次第、メールにてお返事させていただきます)
「feedback」は意見や感想を伝える場合には適切ですが、単にメールに返事をするなら「reply」や「response」がより自然です。
***
「ご返信」の「ご」は、「相手からの返信」であっても「自分からの返信」であっても、いずれも相手に敬意を示すための接頭語であることが、ご理解いただけましたか? ほかにも「ご相談」や「ご案内」「ご説明」なども同様です。言葉についての知識を深めることで、自信をもって敬語を使いこなしてくださいね!
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『デジタル大辞泉』(小学館)/『敬語マスター まずはこれだけ三つの基本』(大修館書店) :