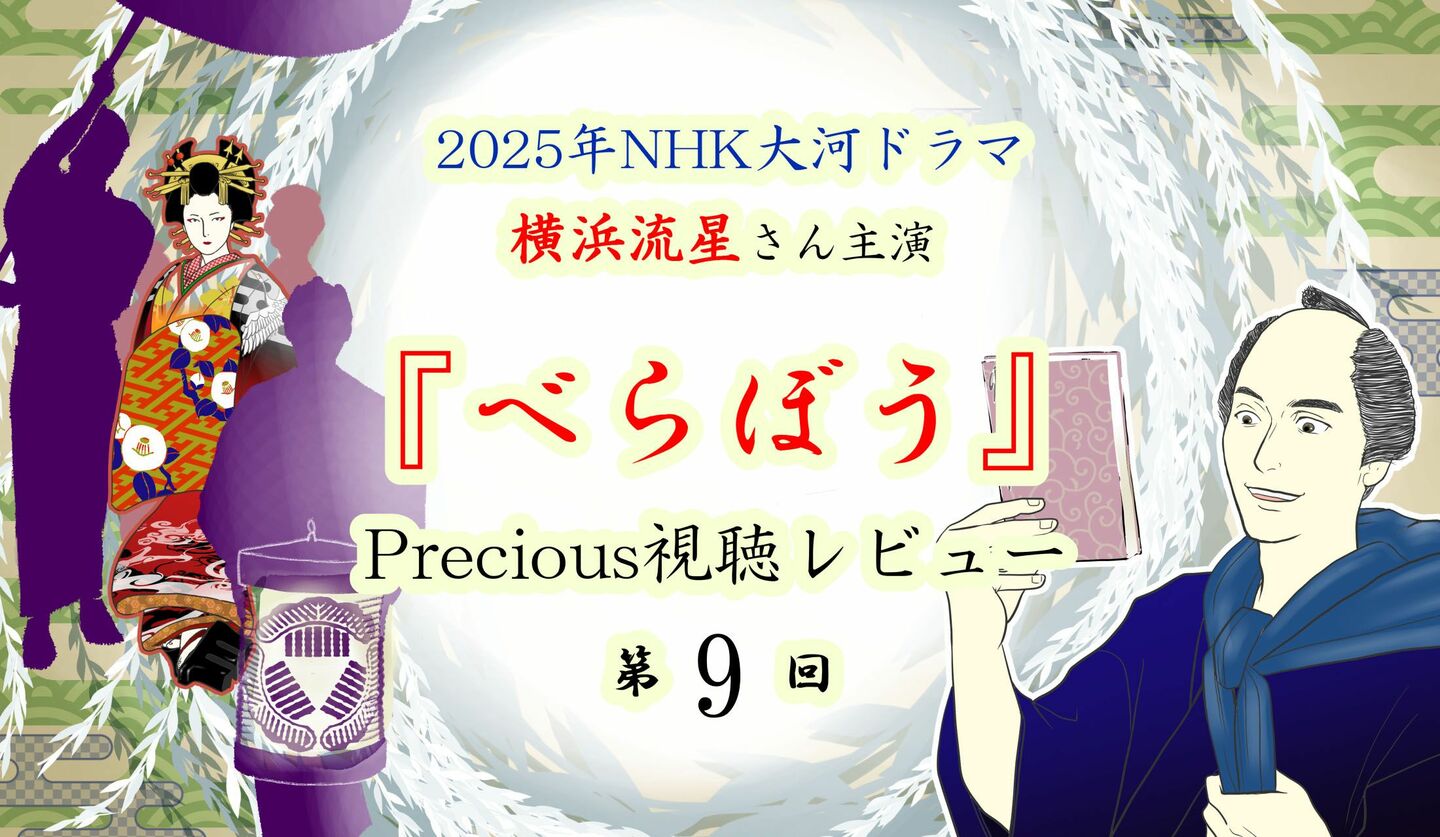【目次】
- これまでのあらすじ
- 明確な階級制度で成り立つ女郎屋
- 格付け最上位は「花魁」?「太夫」?
- 「花魁」までの道のりは遠かった!
- 次回『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第10回 「『青楼美人』の見る夢は」のあらすじ
【これまでのあらすじ】
大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』は、天下泰平、文化隆盛の江戸時代中期を舞台に、親なし金なしの蔦重こと蔦屋重三郎(横浜流星さん)が、その企画力とプロデュース力で「江戸のメディア王」にのし上がっていく物語です。第9回は、市中の本屋連中と決裂したことで悩むなか、瀬川(小芝風花さん)に対する自分の気持ちにようやく気付いた蔦重の告白にドキドキさせられましたね。
吉原にかつての賑わいを取り戻したい、そこで生きざるを得ない女たちに少しでも幸せになってほしい――この想いが熱血漢蔦重の生きる源です。それを誰よりもわかっている花の井は、永久欠番的な名跡だった「瀬川」を継ぐことを決意し、蔦重がつくる『吉原細見』の価値を爆上げ!
第8回の大きな見どころは、美しく豪勢に着飾った花の井の五代目瀬川襲名の花魁道中でした。小芝さんは公式サイトのインタビューのなかで、襲名前と襲名後では花魁道中の歩き方を変えていると発言。高下駄を履いた脚を大きく外側に回す「外八文字(そとはちもんじ)」という独特な歩き方は自主練の成果、小学3年生から中学2年生までフィギュアスケートをしていた小芝さんの鍛えられた体幹のたまものでしょう。
NHKの大河ドラマは、人気俳優だけでなく勢いのある新人から味のある中堅、そして大御所俳優まで、毎回バラエティに富んだ豪華俳優陣が見どころのひとつですが、本作『べらぼう』でのいちばんの注目俳優は、蔦重の幼馴染みで女郎屋松葉屋の看板花魁、瀬川を演じる小芝風花さんだとSNSでも評判です。小芝さんはすでに主役を張れる女優ですが、女郎として生きるしかない定めを受け入れている強い眼差し、きっぷの言い口回し、切ない気持ちを表す表情や仕草…どれをとってもグッとくると、その評価は急上昇! 今回はそんな小芝さん演じる花魁や遊女について解説します。
【明確な階級制度で成り立つ女郎屋】
遊女とは、いわゆる「春を売る」女性のこと。「女郎」「浮かれ女(め)」「遊び女(め)」「傾城(けいせい)」「遊君(ゆうくん)」などとも呼ばれました。そして、遊女を抱えた店を「女郎屋」「遊女屋」「妓楼(ぎろう)」などといい、それらが集まる吉原は、江戸時代に幕府公認で営業した唯一の遊郭。江戸市内の性的秩序を維持するため幕府が特定の遊郭(吉原)に売春権を与え、女郎屋は幕府の後ろ盾がある金貸しから融資を受けて営業、その収益の一部は幕府に納められました。
1617(元和3)年に現在の日本橋で開設したのが吉原遊郭の始まりで、1657(明暦3)年の大火でこの遊郭は被災、浅草の外れに移転した「新吉原」が幕末まで繁栄します。『べらぼう』の舞台はこの「新吉原」というわけです。
【格付け最上位は「花魁」?「太夫」?】
■遊郭の華「花魁」
高級遊女の代名詞が「花魁(おいらん)」です。美貌や芸事に優れているだけでなく、教養や品格も備わっていなければ花魁にはなれず、蔦重が働く「駿河屋」のような引手茶屋の紹介がないと花魁とは遊べません。女郎屋で、舞踊や、三味線、茶道、華道、書道、囲碁、和歌詠みなど、あらゆる芸事や教養を仕込まれる遊女たち。そのなかでひと握りのとびきりの遊女が、太夫や花魁と呼ばれたのです。
当然、花魁と遊ぶには相当な金額がかかります。しかも初回は単なる顔合わせ。豪勢な食事や芸者による宴が催されますが、花魁は客の隣に座っているだけで口も利かないのが吉原のしきたりでした。第9回で、鳥山検校(とりやまけんぎょう/市原隼人さん)が初めて瀬川花魁を呼んだ席で、盲人である検校に瀬川が本を読み聞かせたのは異例中の異例だったのです。
花魁の語源は、女郎屋で生きる幼い女児たちが、姉格の遊女を「おいらの太夫(たゆう)でありんす」と言うところを省略して「おいらん」と呼ぶようになったのが始まりという説が。「太夫」とは、歌舞伎や浄瑠璃などの芸能に秀でた人の敬称です。江戸時代初期に、京都の四条河原などで遊女が歌舞伎を披露していた時期があったことから、すぐれた遊女を太夫と呼ぶようになったとか。吉原でも、江戸初期は高級女郎を「太夫」と呼んでいました。
また、尾っぽを使ってだます狐や狸とは違い、手練手管で遊客をだます(持ち上げていい気分にさせる)ことから「尾がいらない」という意味で「尾いらん」「おいらん」となったともいわれています。
■「花魁」にもランクがあった
第9回に登場した松の井(久保田紗友さん)は、「呼出」という立ち位置の花魁です。「呼出」とは、張り見世を行わず、客からの指名で茶屋に出向く花魁のこと。彼女は「松葉屋」のナンバーワンで、後輩たちの衣装代などの面倒もみています。勢いは瀬川に劣るとも、長年松葉屋を支えてきたベテラン遊女。クールでかっこよく、蔦重など外の人間にもおもねることのない松の井、今後どう活躍するのか楽しみです。
【「花魁」までの道のりは遠かった!】
■女郎屋で働く最下位は「禿」
瀬川が暮らす「松葉屋」にもさまざまな遊女がいます。そもそも遊郭は、貧困家庭や親がいないなどの事情から身売りされた女性たちが行きつく場所。年季が明けるか、客から身請けされると吉原生活から卒業できるわけですが、その前に病気などで亡くなったり、逃げ出す女郎も。また、無事に生きて年季が明けたとしても、遊郭を出て暮らすすべをもたない遊女も少なくありませんでした。
そんな将来を案じてしまうのが、幼い「禿(かむろ)」。10代前半までの少女で、遊女見習いとして姉さん女郎たちの身の回りの世話をするのが仕事です。本人たちはまだ客をとりません。
■遊女としての第一歩は「振袖新造」
姉さん女郎に学び、さまざまな芸事や教養を身につけるなど勉強にいそしみながら成長する禿。彼女たちも13歳から15歳くらいになると「振袖新造(ふりそでしんぞう)」と呼ばれる新米遊女になります。自室はまだもてず雑居暮らしで、客をとる際には「まわし部屋」を使用しました。姉女郎に属し、姉女郎が忙しい際にはその代わりを務めることも大切な仕事。将来有望と見込まれた禿は、初めて客をとる際に「突き出し」という花魁道中のような華やかなデビューを飾りました。
■「部屋持ち」から「座敷持ち」へ
「振袖新造」の時期を経ると、まずは居室(自室)で客をとる「部屋持ち」と呼ばれる遊女に一段格が上がります。そこで人気が出て優良客をたくさんとれるようになれば「座敷持ち」に。居室とは別に、宴席のための専用座敷をもてるようになるというわけ。瀬川の妹分であるうつせみ(小野花梨さん)は座敷持ちの遊女です。
座敷持ちのなかでトップクラスが「花魁」と呼ばれるわけですが、瀬川のようなトップ花魁の下(2番目に格の高い遊女)は昼も夜も揚代が3分(さんぶ。現代の価値で7~8万円)と高額を稼いだため、特別に「昼三(ちゅうさん)」と呼ばれました。
■年季が明けても「番頭新造」「遣り手」として吉原で…
年季が明けても身寄りも行く場所もない遊女は吉原にとどまり、女郎屋の「番頭新造」という役目に就くことも。花魁の世話をするだけでなく、まだ一人前とはいえない振袖新造や禿の教育係のような役目を担い、女郎屋のこまごました厄介事を片付けたりもしました。
さらに年を重ねると、遊女を監督・監視する「遣り手」に。ただでさえ自由の利かない吉原で始終監視されていては窮屈なため、遊女たちからは煙たがられる存在だったはず。第9回で瀬川を見張っていたのが遣り手のまさ(山下容莉枝さん)です。「おまさ目を光らせ候 しばらくあハざるやうにいたすべく候」と、瀬川は短い文(ふみ)を貸本に忍ばせ、窮地を蔦重に伝えましたね。蔦重にまとわりつく振袖新造のかをり(稲垣来泉さん)のお目付け役の志げ(山村紅葉さん)も、「大文字屋」の遣り手です。
身を粉にして働き、大名客と政治の話ができるほどの教養を身に付け、諸芸に長けた江戸の教養人であったともいえる吉原の遊女たち。『べらぼう』に見る瀬川をはじめとする花魁や遊女の心意気やふるまいは、私たちも学ぶべき点があるかもしれませんね。
【次回『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第10回 「『青楼美人』の見る夢は」のあらすじ】
瀬川(小芝風花さん)の身請けが決まり、落ち込む蔦重(横浜流星さん)。そんななか、親父たちから瀬川最後の花魁道中に合わせて出す、錦絵の制作を依頼される。調査に出た蔦重は、自分の本が市中の本屋から取り扱い禁止になり、捨てられていることを知る。一方、江戸城では、意次(渡辺謙さん)が家治(眞島秀和さん)から、種姫(小田愛結さん)を自分の娘にして、将来は家基(奥智哉さん)と夫婦にする計画を告げられる。発言の裏には家基のある考えがあった…。
※『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺』~第9回 「玉菊燈籠恋の地獄」のNHKプラス配信期間は2025年3月9日(日)午後8:44までです。
- TEXT :
- Precious編集部
- ILLUSTRATION :
- 山田シャルロッテ/新刊情報:ママトモ同志【マイクロ】 1 https://csbs.shogakukan.co.jp/book?comic_id=86946
- WRITING :
- 小竹智子
- 参考資料:『NHK大河ドラマ・ガイド べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~ 前編』(NHK出版)/『初めての大河ドラマ べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~歴史おもしろBOOK』小学館)/『蔦屋重三郎の生涯と吉原遊郭』(宝島社)/『大河ドラマ べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~蔦屋重三郎とその時代』(宝島社)/『デジタル大辞泉』(小学館) :