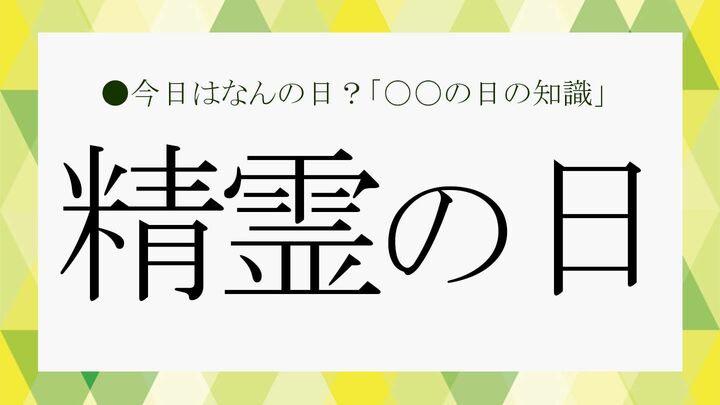【目次】
【「精霊の日」とは?「読み方」「意味」】
■「読み方」
「精霊の日」は「しょうりょう-の-ひ」と読みます。
一般的に「精霊」は「せいれい」と読みますが、「精霊(せいれい)は、シルフ(風の精霊)やウンディーネ(水の精霊)に代表されるように、ファンタジー作品などで自然界の力や要素を象徴する存在として描かれています。
一方、「精霊の日」の「しょうりょう」は、日本の古神道的な意味で、「死者の霊魂」や「みたま」を表す言葉です。
■「いつ」?
「精霊の日」は3月18日です。
■「意味」
3月18日は、日本最古の歌集である『万葉集』を代表する柿本人麻呂、そして女流歌人である和泉式部と小野小町の命日として言い伝えられていることから、日本特有の記念日である「精霊の日」となりました。
【柿本人麻呂とは】
柿本人麻呂は『万葉集」を代表する歌人であり、三十六歌仙のひとりです。生没年や経歴は不詳ですが、その主な作品は689~700(持統3~文武4)年の間につくられており、皇子や皇女の死に際しての挽歌や、天皇の行幸に供奉しての作品が多いことから、歌をもって宮廷に仕えた宮廷詩人であったと考えられ、天武、持統、文武天皇の三代に渡り活躍したとされています。
人麻呂作と明記された歌は『万葉集』のなかに長歌16首、短歌61首を数え、ほかに《柿本人麻呂歌集》の歌とされるものが長短含めて約370首に及びます。質量ともに『万葉集』最大の歌人といえます。
「あしひきの 山鳥の尾のしだり尾の 長々し夜をひとりかも寝む」
鎌倉時代に完成した「百人一首」にも、柿本人麻呂の歌は選ばれています。「山鳥の尾の、長く長く垂れ下がった尾っぽのように長い夜を、(私が思う人にも逢えないまま)独りさびしく寝るのだろうか」と、独り寝の寂しさを、山鳥の長い尾でリズミカルに表現した歌です。
【小野小町とは】
小野小町といえば、平安時代前期の女流歌人であると同時に、絶世の美女の代名詞として語り継がれる存在です。しかしながら、その生没年は不詳で、多くの謎に包まれた存在です。六歌仙、三十六歌仙のひとりでもあります。
「小町」という名前についても、宮中の局町に住んだことによるという説をはじめ、諸説あります。王朝女流歌人の先駆者で、和歌の宮廷文学としての復興に寄与しました。その歌は恋の歌が多く、情熱的で奔放な中にも現実を回避した夢幻的な性格をもち、哀調を帯びていると言われています。
「花の色は 移りにけりな いたづらに 我が身世にふる ながめせしまに」
「ぼんやりと物思いにふけっているうちに、長雨のせいですっかり色あせてしまった花のように、私自身の姿も衰えてしまった……」。百人一首に収められた小野小町の歌は、儚い世を歌った無常観がストレートに表現されています。
【和泉式部とは】
「恋多き女性」として伝えられる和泉式部。生年は987年ごろ、没年は不詳ですが、紫式部より少し年下で、昨年、2024年のNHK大河ドラマ『光る君へ』でも描かれていましたね。冷泉(れいぜい)天皇の皇子である、為尊(ためたか)親王、敦道(あつみち)親王というふたりの親王との恋愛と死別の後、中宮彰子に仕えました。勅撰和歌集(天皇の命令によって集められた歌集)に247首も採られているのは、女性歌人としてはトップ。『和泉式部日記』という恋の作品も有名です。
あらざらむ この世のほかの 思ひ出に 今ひとたびの 逢ふこともがな
百人一首に収められた和泉式部の歌です。「私の命はもうすぐ尽きてしまうことでしょう。せめてあの世へ持っていく大切な思い出として、あなたにもう一度だけお会いしたいものです」。恋する気持ちがダイレクトに伝わってくる、情熱的な歌ですね!
【食べ物など精霊の日のおすすめの過ごし方】
3月18日は「春の彼岸」にも近い日であることから、「精霊の日」は偉大な歌人たちの霊魂を偲ぶ日として伝わっています。ということで、お彼岸の過ごし方について紹介します。
■2025年「春の彼岸」はいつ?
2025年の「春の彼岸」は3月17日(月)から23日(日)までの7日間です。
■「春の彼岸」のころには何をする?
「春分の日」と「秋分の日」は、太陽が真東から昇って真西に沈み、昼と夜の長さがちょうど同じになる日。「此岸(しがん)と呼ばれる「現世」と「彼岸」が最も近づく日とされ、極楽浄土があるとされる真西に沈む太陽に手を合わせ、死者や来世を偲ぶ日とされています。お墓参りをして、ご先祖様を供養し感謝を伝えられるといいですね。たとえお墓参りに行けなくても、そっと手を合わせ、心の中で感謝の気持ちを表しましょう。
と同時に、3人の精霊たちを偲んで名歌を楽しんでみてはいかかでしょうか。
■何を食べる?
春のお彼岸にいただくものといえば、「ぼたもち」が有名ですね「ぼたもち」と、秋のお彼岸にお供えする「おはぎ」、どちらももち米とあんこを使った和菓子で、現代では大きな違いはありません。昔から「小豆は邪気を払う」といわれてきたため、お彼岸にも小豆を使った料理が、お供え物として利用されてきたのです。
***
「精霊の日」である3月18日前後は、日本が一年のなかでも最も穏やかな気候を迎えるころです。桜前線の予報が気になりはじめる頃でもありますね。3人の偉大な歌人に尊敬の念を表すると共に、ご先祖様をはじめ、亡くなった方々を敬う、日本古来からの習慣を大切にしたいものです。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料: 『日本国語大辞典』(小学館) /『デジタル大辞泉』(小学館) /『日本大百科全書 ニッポニカ』(小学館) /『世界大百科事典』(平凡社) /『平安のステキな!女性作家たち』(岩波ジュニア新書) :