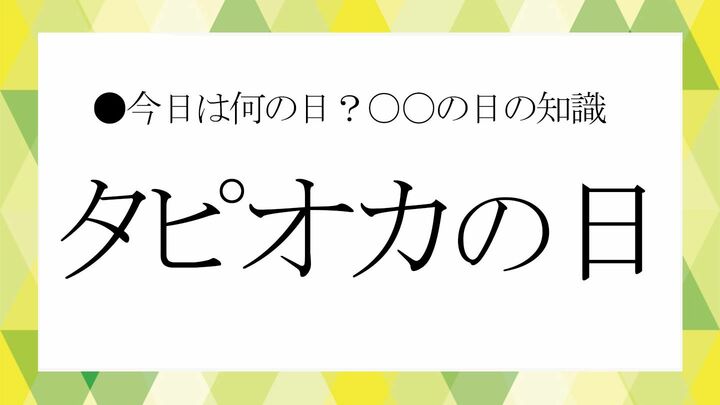【目次】
【11月9日はなぜ「タピオカの日」?その由来とは】
■「誰が」決めた?
「タピオカの日」は、ヨーグルトやデザート、チルド飲料の製造販売などを行う安曇野食品工房株式会社が制定した記念日です。日本記念日協会により認定、登録されています。
■「由来」は?
「タピオカの日」の由来はふたつ。ひとつは、台湾で人気のあった珍珠奶茶(タピオカミルクティー)を、2002年11月に安曇野食品工房が日本で初めてチルドカップ容器で製造販売したこと。ふたつめは、当時この商品の別名がQ-PON(キューポン)であったことから、「11」に「Q(9)」を組み合わせ、11月9日となりました。
【ビジネス雑談で盛り上がる「タピオカ」のトリビア10選】
■いまさら聞けない…そもそも「タピオカ」って何?
タピオカの正体は、トウダイグサ科に属する芋類の一種、キャッサバの根茎(地下に伸びる茎が肥大化したもの)からとったでんぷん。あの独特なモチモチ食感はデンプン由来のものだったのですね! タピオカは南米、北東ブラジル原産で、生産地上位は1位ナイジェリア、2位タイ、3位インドネシアと、サバナ気候や熱帯雨林気候で栽培され、主食のひとつとして食べられています。別名はキャッサバデンプン、マニオカデンプンです。
■タピオカの意外な用途とは?
タピオカはお菓子の材料になるだけではありません。料理のとろみつけに使われるほか、つなぎとして用いられています。日本でいうと、片栗粉のような存在ですね。また、意外な用途としては、紙の強度を上げるための薬剤の原料としても重要な役割を果たしているんですよ!
■名前の由来は
「タピオカ」の名前は、ブラジルの先住民のトゥピ語でデンプン製造法を「tipi'óka」と呼ぶことにちなみます。
■タピオカの製造法
まずは原料となるキャッサバを水で洗ったあと、摩砕機ですりつぶし、水中にデンプンを洗い出したら、沈殿させて集めます。このデンプンを、「水を替えて沈殿」を繰り返すか、遠心機にかけて精製し、脱水後乾燥させます。
■タピオカって、本当は何色?
飲み物のなかに入っているタピオカは黒や茶色のイメージですが、タピオカ本来の色は、白、というか透明(半透明)です。白やカラフルなものはもちろん、色のついたタピオカは、すべて着色料で着色されているんです。
■タピオカに含まれる有害成分とは?
タピオカのもともとの原料である「キャッサバ」の根には、有毒な成分が含まれていることをご存じでしょうか? キャッサバには「シアン化合物(シアン化グルコシド)」という青酸を発生させる成分が含まれており、生のままでは食べられず、日本への生食用の輸入も禁止されています。
しかし、タピオカとして食べられる状態になるまでには、「水にさらす」「加熱する」「乾燥させる」といった工程を繰り返すことで、有毒成分はきちんと除去されています。製品化されたタピオカは、純白で不純物も少なく、安全に食べられるようになっているのです。
■タピオカの栄養素は?
タピオカの原料(キャッサバ由来のデンプン)の栄養成分は、ほとんどが炭水化物です。たとえば、飲み物などに入っているタピオカの元“乾燥タピオカ真珠”では約 89 %が炭水化物、約 11 %が水分というデータもあります。
たんぱく質・脂質・食物繊維などはごくわずかで、鉄・カルシウム・カリウムなどのミネラル類も少量含まれていますが、その量は多くありません。つまり、タピオカは“もちもち食感”や“エネルギー補給”には活用できても、たんぱく質補給やビタミン・ミネラルの補完を期待するには 単体では物足りない食品と言えます。タピオカを楽しむなら、低カロリー&高栄養価な食材を上手に組み合わせて、血糖値の急上昇を抑え、エネルギーを持続的に取り入れる工夫をしましょう。
■「タピオカは太る」ってホント?
炭水化物は「糖質+食物繊維」からできています。糖質は消化されてエネルギーになるのに対し、食物繊維は消化されず、体外へ排出されるのが大きな違い。そしてタピオカに含まれる炭水化物は、100gあたり食物繊維が0.2g、糖質が15.2gと、糖質がかなり多め。白米よりも糖質の割合が多いといわれています。
糖質は消化・吸収されて身体の主要なエネルギー源となることで知られていますね。
ですから、タピオカを楽しむ際には「タピオカそのもの」だけでなく、「ドリンク全体の糖・脂・ミルク・シロップの量」も意識することが大切です。
そして気になるカロリーは、乾燥状態で100 gあたりでは炭水化物約88 gというデータもあります。茹でたタピオカでいうと、100gあたり、61kcalです。お茶碗一杯(約150g)のご飯のカロリーが約234kcalですから、「案外低い?」と思いがちですが、台湾ティーの専門カフェ「ゴンチャ」の人気メニューである「⿊糖 アールグレイミルクティー アイスMサイズ」に、タピオカをトッピングした場合のカロリーをみてみましょう。
⿊糖 アールグレイミルクティー(257kcl)+タピオカパール(128 kcal)= 385kcal
ミルクティー一杯で、ご飯一杯分の約1.6倍のカロリーとなります。ですから、タピオカを楽しむ際には「タピオカそのもの」だけでなく、「ドリンク全体の糖・脂・ミルク・シロップの量」も意識することが大切です。
■タピオカドリンクの起源は?
台湾です! 台湾では、ミルクティーにタピオカを入れて太いストローで吸い上げるという飲み方が、1980年代から流行していました。台湾中部の台中市にある「春水堂」というお店が、タピオカミルクティーの元祖と言われていますよ。
■日本でタピオカがブームになったのは、いつ?
日本では、「タピオカブームは3回あった」と言われています。
第一次ブームは1992年ごろ。当時のエスニックブームに牽引されるかたちで、「白いタピオカ入りのココナッツミルク」が流行しました。
第二次タピオカブームは2000年代の初頭。このとき流行ったのは、タピオカミルクティーです。タピオカが白から黒に変わり、同時にスプーンで食べるものからストローで飲むものに変わったのもこのころ。「タピオカの日」を制定した安曇野食品工房が日本で初めてチルドカップ容器で製造販売を始めたのが2002年ですから、同社はこの第2次タピオカブームを牽引した存在だったのですね! タピオカパールが食べやすいように太いストローが付いたのも、印象的でしたね。
そして、第三次タピオカブームは2018年ごろから。2019年には新語・流行語大賞のトップ10に「タピる」がランクイン。『現代用語の基礎辞典』にも「タピる=タピオカのドリンクを飲むこと」として掲載されました。きっかけは、LCC(格安航空会社)の就航によって海外へのアクセスが手軽になり、近場である台湾旅行の人気に火がついたこと。本場台湾のタピオカミルクティーの人気が再燃したのです。インスタ映えする、いわゆる「映えフード」として注目されたことも、ブームに拍車をかけました。「甘くないお茶」との組み合わせが生まれたのもこの頃で、紅茶以外にも緑茶、烏龍茶、ほうじ茶などと、お茶のバリエーションも広がりました。
***
モチモチとした食感が魅力のタピオカドリンクですが、正直なところダイエット中は避けておきたい飲み物です。「小さめのサイズ」で「甘さ控えめに」「ミルクの入っていないものにする」などの工夫で、カロリーを多少抑えることはできます。とはいえ、せっかくの一杯なら「好きなものをしっかり楽しんで」、そのぶん、ほかの食事でカロリーを調整するというのも、ストレスを溜めずに上手に続けられる、スマートな選択肢かもしれませんね。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『日本国語大辞典』(小学館) /『デジタル大辞泉』(小学館) /『日本大百科全書 ニッポニカ』(小学館) /『世界大百科事典』(平凡社) /『現代用語の基礎知識』(自由国民社)/一般社団法人 日本記念日協会HP(https://www.kinenbi.gr.jp) /プレジデントオンライン「街中に溢れていた「タピオカ屋」はどこに消えたのか…「一過性のブーム」でも収益を生み出す"すごい仕組み"」(https://president.jp/articles/-/80591?page=1) /日本食品標準成分表(八訂)増補2023年(https://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=2_02057_7) /ゴンチャジャパン「カロリー(エネルギー量)・カフェイン量 情報」(https://www.gongcha.co.jp/wp-content/themes/gongcha/pdf/gongcha_Allergy_Energy_and_Caffeine.pdf?1762421530) :