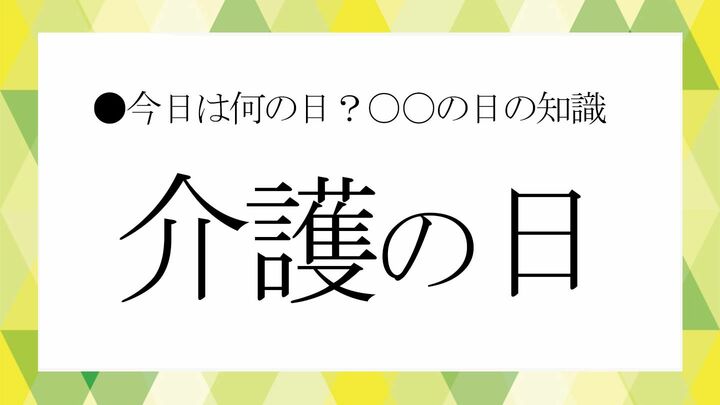【目次】
【11月11日はなぜ「介護の日」?その由来とは】
■最初に制定されたのは別の日だった
「介護の日」は、もともと2005年に「がんばらない介護生活を考える会」が、自身の会の発足日にちなみ、9月25日を記念日として制定しました。しかし、その3年後の2008年に、厚生労働省がより多くの国民に介護について関心を持ってもらうことを目的に、11月11日を新たに「介護の日」として正式に制定。この動きを受けて、同会も、「介護の日」の日付を11月11日に日付を変更しました。現在では、国民全体が介護について考える日となるように、全国各地でシンポジウムやイベント、啓発活動などが行われ、介護の重要性について理解を深める日として広く知られるようになっています。
■日付の「由来」は?
厚生労働省では、「介護の日」制定にあたり、国民からの意見を募集する「パブリックコメント」方式が採用されました。その結果、「いい日、いい日、毎日、あったか介護ありがとう」という「介護の日」のキャッチコピーを念頭に、「いい(11)日、いい(11)日」の語呂合わせから、もっとも支持が多かったのが11月11日だったということで、この日が選ばれたのです。
【知っておきたい「介護」の基礎知識】
「介護」に対する不安を何となく感じてはいても、その現状や正確な情報を知っている人は少ないのでは? 実はキャリアがもっとも充実する40代〜60代は、 親の介護が始まるケースがいちばん多く見られる年齢層です。ほんの入り口ではありますが、「介護の基礎知識」を解説します。
■「介護保険制度」とは
介護保険制度は、超高齢社会を社会全体で支え合うために、2000(平成12)年にスタートした公的な社会保険制度です。国や地方自治体、国民が収める保険料で運営されています。介護や支援が必要な人に、費用やサービスを給付する仕組みで、介護や支援の必要性が認められると、少ない費用負担で介護サービスが受けられます。「え? 私、介護保険料なんて払ってない!」と思った人もいるかもしれませんが、介護保険制度は原則として40歳以上のすべての国民が支払いを義務付けられており、40~64歳の間は健康保険料と一緒に徴収されています。65歳以降は原則として年金からの天引きにより支払うことになります
介護保険制度の目的は、次のふたつです。
・介護を担う家族の経済的、身体的負担を減らす
・高齢者の自立を支援し、できる限り要介護状態にならずに生活できるようにする
かつての日本では「家族の介護は家族が行うべき」という価値観が主流でした。しかし、核家族化が進み、超高齢化社会に突入した現代では「家族だけで介護を行う弊害、限界」が社会問題となってきました。そうした背景から、「介護は社会全体で支え合うべきもの」として生まれたのが、現在の介護保険制度なのです。
■介護保険の利用者は2種類
介護保険の利用者、つまり被保険者は、65歳以上の者(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している者(第2号被保険者)とに分類されます。手続きは不要で、40歳になると自動的に第2号被保険者の資格を取得し、65 歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わります。
受給要件は「要介護」「要支援」の認定を受けることですが、第2号被保険者の場合、介護保険が利用できるのは、16の特定疾病が「要介護(要支援)状態の原因」と認められた人だけです。
■65歳未満でも、厚生労働省が認める特定疾病(16種類)
・がん末期
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症(ウェルナー症候群等)
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
言い方を変えれば、たとえ65歳の第1号被保険者になっていなくても、上記の疾患をもっている40歳以上の人なら、公的な「介護保険」の申請を検討してみる価値があるということです。早めの相談が、その後の生活の質にきく影響します。
■「要介護認定」とは?
要介護認定とは、介護保険制度を利用する対象者が、どれくらい介護サービスを必要としているかを判断し、数値化したものです。
具体的には、症状が軽いものから「要支援1・2」、「要介護1〜5」と、7つの区分に別れています。要介護・要支援の認定を受けることで介護保険が適用され、介護予防サービスや介護サービスを利用できます。認定基準は全国一律。住んでいる地域の市町村がその基準に沿って要介護認定を行います。介護保険は仕組みがやや複雑なので、早めに市町村の窓口や地域包括支援センターに相談するのがおすすめです。
■「要介護認定」はどうやって申請する?
「要介護申請」から「認定」までの流れは、以下の通りです。
1)窓口で申請する
2)訪問面談による認定調査を受ける
3)一次判定
4)二次判定
5)申請結果を受け取る
申請の窓口になっているのは、市区町村の担当窓口です。申請書は、役所や地域包括支援センターの窓口で入手できます。PCやスマートフォンで検索してみれば、簡単に情報が手に入りますよ。本人が窓口まで行けない場合は、家族や地域包括支援センターのスタッフ等に代行申請してもらうことも可能です。
■要介護(要支援)の認定を受けた人はどれくらいいる?
厚生労働省や内閣府の統計資料によると、2023年度(令和5年度)末時点で、介護保険の「要介護」または「要支援」の認定を受けている人は約676万人とされています(※1)。この数は今後も高齢化に伴い増加が見込まれています。
この認定者のうち、最も人数が多いとされているのが「要介護1」です。
「要介護1」の認定基準は以下のような状態です。
・立ち上がりや歩行などに部分的な介助が必要
・認知症状によって一部の動作に介助が必要
一方、40歳以上65歳未満の第2号被保険者については、特定疾病を原因とする場合に限り介護保険の対象となりますが、この年齢層の認定者数は相対的に少なく、おおよそ13万人前後とされています(※2)。
なお、第2号被保険者の中で最も多い認定区分は「要介護2」といわれています。
「要介護2」の主な基準は以下の通りです。
・立ち上がりや歩行が困難
・排泄や食事などにおいて介助が必要
・認知機能の低下があり、一部の動作に見守りや介助が必要
日本の高齢者人口は今後も増え続け、2025年には65歳以上の人口が約3,677万人となり、総人口の30%を超える見込みです(※3)。また、2040年頃をピークに認定者数もさらに増加すると予測されています。
※2:第2号被保険者の認定数については複数の推計があり、正確な統計値は年次によって異なります。
※3:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」。
■介護保険で利用できるのは、2種類のサービス
介護保険で利用できるサービスは、要介護認定の区分により異なります。大きく分けて、「要介護1~5」の人が利用できるサービスは「介護給付」。そして「要支援1~2」の人が利用できるのは「予防給付」です。
介護の入り口とも言える「要支援者」が受けられる「予防給付」は、要介護状態になることを防ぐのが目的です。日常、お世話をする家族の負担を軽減する役割もあるので、活用したいですね。
・自宅での入浴介助
・訪問看護
・自宅でのリハビリ
・デイケア(施設に通ってリハビリを受ける)
・施設へのショートステイ
■介護保険サービスの利用料は?
介護保険制度は保険料で運営されています。利用者は介護サービスにかかる費用の1割(一定以上の所得者は2〜3割)を負担することになります。ただし、介護保険サービスの利用料は、月額の上限額が区分ごとに決まっています。上限を超えて利用したサービスは、超過分が全額自己負担となります。
■「がんばらない介護」とは?
実際の介護の現場では、介護をする側もされる側も、それぞれに「頑張らなければいけない」「ちゃんとしないと」という意識を強くもってしまう傾向にあります。これは「介護を頑張ることが愛情表現」であったり「よき介護者でなくてはならない」という意識に囚われがちだから。真面目な人ほど、追い込まれてしまうのです。
でもそれでは、現状の中で自分らしく生き、人生を楽しむことは叶いません。そこで、「がんばらない介護生活を考える会」は、介護のストレスを解消させ、様々な情報を駆使しながら、精神的なストレスのない介護をするために、「頑張らない介護5原則」を提唱しています。
1)ひとりで介護を背負い込まない
2)積極的に介護のサービスを利用する
3)現状を理解し、受容する
4)介護される側の気持ちを理解・尊重する
5)できる限りラクな介護の仕方を考える
***
キャリアが充実し、「働き盛り」とも言われる40代〜60代は、仕事でも家庭でも多くの責任を抱える時期です。 そして同時に親の介護が現実的なテーマとして浮かびあがってくる年代でもあります。実際、介護が始まるタイミングがもっとも多く見られるのがこの年代です。しかも、医療の進歩により、介護期間は少しづつ長くなってきているというデータもあります。それはつまり、「介護」は一時的なサポートではなく、長く向き合っていく可能性があるライフイベントだということです。
そうしたなかで、仕事と介護の両立に悩む人が増えているのも、決して特別なことではありません。誰にでも起こり得るからこそ、いざというときに慌てないように、制度や仕組みについて少しずつでも知っておくことが大切です。「何から調べたらいいのか分からない…」というときは、信頼できる情報源を活用して、ひとつずつ確認していきましょう。心の準備は、介護を支える第一歩です。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『デジタル大辞泉プラス』(小学館) /一般社団法人 日本記念日協会HP(https://www.kinenbi.gr.jp) /厚生労働省「介護の日検討会(https://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/h0728-2.html) /明治安田ライフフィールド(https://www.meijiyasuda.co.jp/dtf/lfm/life/articles23.html) /ALSOK「介護のお役立ち情報」(https://joylife.alsok.co.jp/knowhow/archives/48) /介護のみらいラボ(https://kaigoshoku.mynavi.jp/contents/kaigonomirailab/works/commonsense/4980/) :