日本の映画が面白い!『世界の中心で、愛をさけぶ』から変わった日本映画と、ヒットを量産する裏方の苦労とは?
『シン・ゴジラ』『バケモノの子』『神様のカルテ』『いま、会いにゆきます』など、ヒットした日本映画の音楽を主導した、映画音楽プロデューサーの北原京子さん。東宝ミュージックの社員として働きながら、他社が制作する映画の音楽プロデュースも行っているそうです。
映画音楽プロデューサーというお仕事とは? 日本映画界の変革、北原さんのキャリア、センスの磨き方と女性の活躍などについて、詳しくお話をお伺いしました。

■映画「音楽」プロデューサーって、どんなお仕事?
――北原さんが携わっている「映画音楽プロデューサー」とは、どんなお仕事なのでしょうか?
わかりづらい仕事なのですが、「映画内の音楽すべて」に関わる仕事です。広い映画業界でもこの仕事をしている人は片手ほどという「まれ」な仕事です。
映画製作において、クリエーター的な仕事と、予算権利周りといった、調整の仕事の両方を行います。感性、センスにおいても、客観と主観のバランスが求められている仕事だなと思います。
映画の企画自体から携わることもありますし、すでに座組が決まっていて依頼されるなど、さまざまです。仕事内容としては、要は、イメージの立ち上げから、最終的な完成まで全部を行う仕事です。全体を作曲いただく音楽家を選定することも、重要な仕事のひとつです。
映画音楽のイメージの立ち上げから最終的な完成系まで、すべてを行う仕事
――そうすると、映画音楽全般の指揮を執るお仕事なのでしょうか?
そうですね、監督の多くは音楽に関して実作業をするわけではなく、「こういうイメージを作りたい」というものがあって、それを私たち音楽プロデューサーが「実際の音楽に置き換え、こういう方に依頼をしたら、その演出を目指せるのでは?」といった、具体的な提案をするわけです。
「主題歌」も担当します。その主題歌のためのアーティストの選定、交渉、曲作り、レコーディングにも関わります。
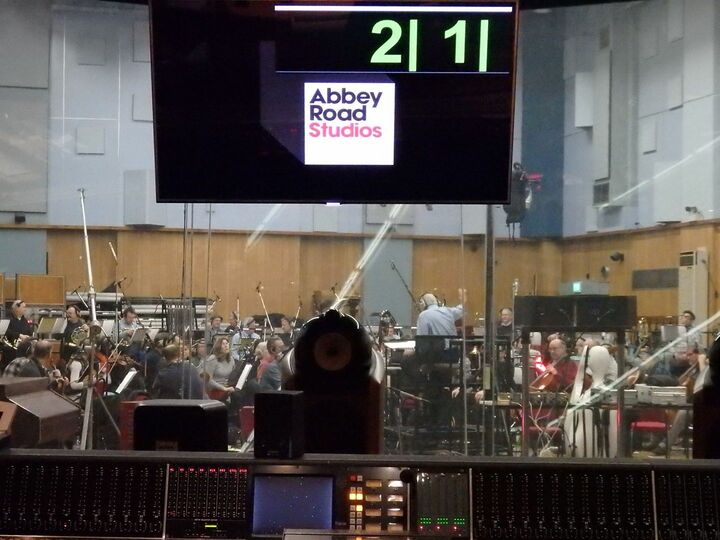
各場面の音楽(劇伴)の音楽メニュー(何分何秒何コマという、詳細な映像に対するアテ書き)も、監督や音楽家と決めていきます。その後、上がった音楽家のデモに曲のアレンジの修正・提案等のディレクションを行います。
撮影した「画」にセリフ、効果音、音楽をシンクロさせていく
――お仕事の中で、大変な局面はどこですか?
映画は、撮影、照明、録音、美術、編集、音響といった、複数の部門から成り立っています。それぞれのプロフェッショナルがいて、その舵を取っているのが、監督。撮影終了クランクアップ後、画の編集に入ります。(ここからの期間をポスプロと呼びます)
編集が終わったものを皆で観て、ポスプロ期間中、意見交換をしながら各パートは作業を進めていきます。
そうしてできあがった画に対して、音楽をレコーディング、mixをして、音楽を合わせていくという作業が行われます。撮影所内に映画館と同音響環境の大きな部屋があるのですが、そこに入って、映像に対して、セリフと、効果と、音楽をシンクロさせる「ダビング(ファイナルミックス)」という、緻密な作業を行います。
2週間くらい、監督、私たちポスプロ・スタッフがカンヅメになって、根を詰めた作業をします。数十秒のシーンを数時間かけてmixしたり、とてつもない工程の作業を踏んで、やっとひとつの映画ができあがるわけです。
私は音楽ですが、台詞は録音さん、効果は効果さんがいて、先に述べたように、それぞれのプロフェッショナルが集まって表現されたものなので、映画は「総合芸術」と言われています。

「映画館という特殊な環境で聴かれる音楽である」ことを想定した上で、音を作る
――まれなお仕事ということですが、お話を伺っていると、映画製作においてとても重要な役割だと感じます。なぜ、そのお仕事をしている方が少ないのでしょうか?
映画は、通常のステレオ環境で聞くようなL/Rとは違い、5.1chという立体音響、空間音響です。
同じ音楽でも、その音響によってL/Rで聞くものと、5.1chで聞くものはまったく違って、映画音楽というものを、劇場という環境で聴くと、音圧や音響が、観る方の映画体験に大きく影響を与えると感じます。
何となく周りで「ふわっ」と音が鳴っているとか、前から「ガンッ」とくる、とか。同じ音楽でも、聞かせ方によって、与える効果が違うわけです。テレビなどから感じられる「感度」とはまた違うんですね。特殊な環境にある映画のための音、5.1chのための音を、複雑な工程を組んで作っているのです。
最終の空間で感じる音楽をイメージして制作していく行為が楽しいです。劇場での音を先読みして作り上げていくことがこの仕事の醍醐味。それができるのが、私自身の強味かなと思っています。
最初から最後の工程すべての側面に関わり手掛ける「映画音楽プロデューサー」は、自分を含めて本当にごくわずか、ではないでしょうか。そのくらい、特殊性を求められる職なのだと思います。

――最初から最後の工程まで関わっていないと、映画としての完成度が変わってくるということでしょうか?
最初から最後の工程まで関わっていれば、作曲家やクリエーターが、「何に重きを置いて作ってきたのか?」という想いも込みで、演出に合わせた判断、可変をさせていけると思います。
客観で作業することで、それが功をなすこともありますが、やはりゼロから音を作ることに携わって、そこを知っていることと、知らずにいることでは、音楽のコアの在り方にも違いが出てくると思うのです。
実態のない抽象的なものを、いかに具体化するかが求められている
――現在の「映画音楽プロデューサー」というポジションに到達するまで、苦労されたことはありましたか?
若いころは「大変な仕事についてしまったな」と感じて、正直やめようと思ったこともありました。
毎回、同じ監督やスタッフで行われるわけではなく、同じチームで組む場合もありますが、基本は毎回スタッフが違うので、ただでさえ「初めまして」の人とコミュニケーションを取るのは神経を使うのに、実態のない「センス」というものを、具体的に落と込み合う共同作業は、とても難儀なものです。感受性的なもの、感情に左右されるものに正解はないからです。
音楽の良し悪しは、ヒットするかしないかともまた別のもので、「私にはこの曲は悲しく響く」と思っていても、誰かにとっては楽しく聞こえるかもしれない。正解があるようで、ないものです。
主観と客観が入り交る仕事なんですよね。私自身が音楽を書ける必要はないですが、当然、音楽を理解している必要があるわけです。その抽象的なものを、いかに具体的なものに書き換えて、人にわかりやすく説得できるか。
単に「これ、いいよね」だけではなく、言葉の説得が必要なこともあるんです。「ここにセリフや効果が入ってきて、そこに音楽が載ったときに、こういう演出に映る」という、細かい説明も必要になります。始めたばかりの頃は、そこに難易度を感じていました。
――北原さんのお仕事は、クリエイティブ的にゼロから最後まで立ち会い、同時に、社会的に各方面とのコミュニケーションを取って調整していくという、両方が求められているということでしょうか?
その通りですね。クリエイティブなこともするし、ソーシャル的なことも求められています。他のスタッフの舵取りなどもそうですね。

■日本映画はいつ変わった?
――日本映画は現在、興行的に成功していますか?
日本の映画産業は、今は好況ですが、私が東宝ミュージックに入社したころは、邦画というのは斜陽な時期だったんですよね。
でも2004年の『世界の中心で、愛をさけぶ』が社会現象になり、日本映画が一気に盛り上がり、映画とテレビの関係が変わりました。「映画って面白い!」となったんです。
年に1回、洋画を観るか観ないか、みたいな時代から、邦画を日常的に観るという時代になりました。興行の数字が証明していて、ヒットしていると感じる洋画より、邦画のほうが、日本では興行の数字が高かったりするんですよ。
『世界の中心で、愛をさけぶ』のヒットから、日本の映画業界が変わった
私たちの世代の多くは、欧米文化に惹かれて音楽やエンターテイメントに携わっていましたが、若い世代では「字幕を見るのが、面倒臭い」「吹き替えがいいよね」という世代の人たちもいます。びっくりしましたし、その事実を知ったときは、ちょっとショックでしたが、「今の若い人はそうなのね」と。
ある世代には、シリアスなものだけでなく「きらきら映画」と呼ばれるものもヒットしていました。ライトな感覚なものも、映画でも楽しみたいということで、映画館に観に来てくれていますね。

――若者のテレビ離れがよく聞かれますが、若者の映画離れはないのですか?
映画館がきれいなシネコンになって、映画料金の改定もあり、興行の数字は落ちてはいないです。でも、最近はアマゾンやネットフリックスなどの配信もあるので、日本の映画業界も安心してはいられないですよね。彼らは、映画でも、テレビでも、両方で楽しめるものを作っているわけです。PCで観ても映画館で観ても成立するものを作ってきています。
コロナ禍で、今後の映画の在り方は変わっていく可能性がある
――映画館はコロナ禍の影響が大きかったと思うのですが、どう思われますか?
今回の新型コロナウイルスによる影響で、映画館の在り方や、技術や文化が切り替わっていく、すごいタイミングに来ているのかなと感じています。
仮にこのまま映画館がクローズとなると(考えたくはないですが)、「自宅環境で楽しむ方法」にも進化があるかもしれませんよね。
――という事は、5.1chだけでなく、L/Rでインパクトのあるような音楽づくりをするというでしょうか?
どのみちハードは進歩していくと思うので、日常的環境でも立体音響の擬似が進化したり、例えば、昔海外で流行っていたドライブシアターなどができて、車のなかで5.1chが楽しめるようになるかもしれないですよね。
アウトドアで、「ソーシャルディスタンスを取りながら、立体音響が楽しめる」みたいなことも考えられるかも?、と空想も広がります。映画界にとって、新しい発想のチャレンジになるかもしれないですよね。
■北原京子さんのこれまでのキャリアと、これから
――北原さんは音楽にとてもお詳しいのですが、音楽を専門に学んでいらしたのでしょうか?
いえいえ、音大を出ているわけではなく、母がエレクトーンの講師だったので、小学校のときピアノを習っていたくらいです。ただ、ティーンエイジャーのころは洋楽に興味をもって、洋楽のハードリスナーかつ、アンチメジャーな、インディー派でした。今思えばそれが自分の原点かなと思います。
クラブの走りのようなところに入り浸っていて、そこで、センスのようなものを養ってきたのかもしれません。学生時代は小箱のクラブが主流で、そこから大箱のクラブができてきたのですが、その違いを身を持って体感してきました。
以前、電気グルーヴのドキュメンタリー映画を担当させていただいたことがありました。監督が『モテキ』の大根 仁さんで、非常に音楽センスの高い方なんです。
「フジロックのこの会場なら、電気グルーヴの音楽はこういう風に音が響くよな」、「このライブハウスならこういうふうに音が感じるな」、など、その音の響き方を工夫して音響を作りました。それをきいた電気グルーヴも「まるでその場にいるみたい!」と、とても喜んでくださったんです。
音楽を専門に学んできたわけではないけれど、音楽が好きという想いで進んで来たら、この道のプロフェッショナルになっていた

体験、経験が今の自信になっているし、音の定位を考えることに面白みを感じる遊んできた歴史があるから、今があるのかなと。
でも様々なテイストの作品があるので、自分が好きなロックやインディーばかりができるわけではないですから、非常にクラシカルなものなど、ジャンルレスに触れてやっていかなければいけません、
ピアノをやっていたので、まったくの音楽音痴というわけではなく、譜面も読めますが、入社したころはコンプレックスがありました。でも、入社した時の上司に「音大に行ったとか行っていないとか関係なくて、むしろセンスだ」と。
厳しい上司でしたが、「自分のセンスを信じろ、知識は要らない、お前のセンスは怖いものがある。お前からこの音楽がどうとかと言われたら、返す言葉がない」といわれたことがありました。
当時は、センスで人を説得する術を知らず、知識の説得のほうが強いと思っていたけれど、その上司の言ったようになり、今があります。

――就職先として東宝ミュージックを選んだ理由は?
1989年に東宝ミュージックに入社したのですが、実は当時、特に映画好きでもなくて、ロック一辺倒だったので、レコード会社に就職したかったのです。音楽が好きだったのですが、どんな仕事があるかわからなかったので、「音楽の仕事と言ったらレコード会社かな?」という、イージーな発想で就活しました。
でもレコード会社の方にお話を聞かせていただいたら、「レコード会社に来たからって、ど真ん中の制作の仕事ができるとは限らないよ、悪いこと言わないから、こんな業界やめておきなさい」と言われてしまいました。時代的に、あまりレコード会社が良くない時代だったのでしょう。
そんな時、たまたま「映画会社が音楽を担当する人を探しているけど、会ってみる?」というお話をいただいて、会うだけ会ってみようということだったのですが、そのまま話が進み、東宝ミュージックに入社することになりました。
――入社すぐから映画音楽に携わっていたのでしょうか?
東宝ミュージックは、ブロードウェイのミュージカルの版権を持っていたので、入社したころは、海外の要人のアテンドや、通訳をしたりしていました。やりたいこととは違ったのですが、大物アーティストとの契約に立ち会ったり、新人では経験できないような、重要なことをやらせてもらいました。

同時に、アニメ音楽のディレクターもやっていました。でも、技術は学べるけれど趣味的には違うかなと感じていたんです。
「このままこの仕事を続けていたら苦しくなるな」と思い、ある日、辞表を持って会社に行ったら、当時の社長に呼ばれて「映画やってみないか?」と言われたんです。「映画をやってみて違うと思ったらやめればいいや」と辞表をしまい、映画音楽に関わるようになりました、入社3年目くらいのときです。
映画でやっていく、と思えるようになった作品との出会い
――では、それから映画音楽に関わるようになったということですね?
最初はアシスタントとして、上司の隣で、皆が話していることを聞いているだけでした。先ほど申し上げたように、まだ邦画が斜陽時代だったので、カルチャーとしては順位が低く、監督たちも古いタイプの方が多かったように思います。
「撮影所システム」というものがあって、助監督を踏んでからでないと、監督になれないというような風習もありました。今とは監督の定義が違っていて、異業種から来て映画を撮る、ということは、許されない雰囲気の時代でした。
そんな風習の中で、エッジ―な音楽の会話など成り立つはずがないですよね。オーデナリーな音楽を好む監督も多かったですし、正直、その頃の皆の会話が、自分の心に響かなかったんです。
「困ったな」と思いながらも、知らないということに貪欲になれる好奇心があり、興味の範疇じゃなくても、わからないなりに、打ち合わせで飛び交う専門用語を拾って勉強していました。
関わっているスタッフの皆さんが長時間、議論しているのを末席で見ている中で、意見など言えませんでしたが、「自分ならこうするな」とメモを書いていたら、最終的なみんなの選択が自分の思う形になっていることが多かったんです。その時は「なんで最初からこうならないのかな?」と、ただ不思議に思っていました。
――その当時から、映画音楽プロデューサーという仕事は存在していたのですか?
黒澤作品など担当していた上司の時代には、音楽プロデューサーは、「音楽事務」という名前が付いていたそうです。クリエイティブというより、コーディネーターみたいなもので、今とは在り方が違っていたと聞いています。
――北原さんが「この仕事が好きだ」と思い始めたのはいつ頃からですか?
映画担当になって、初の1作目の作品が終わるころには少し自信が付き、2作目で突然、前面に立たせてもらう機会に恵まれました。「音楽プロデューサー補」というポジションだったのですが、そこで意見をちゃんと発言したことで、さらに自信がつきましたね。1991年公開の『超少女REIKO』という、観月ありさちゃんが主演の作品でした。
でも「決定的にこの仕事をやっていくんだ!」と決めたのは、『渚のシンドバッド』という1995年の作品に携わった時でした。
当時、ぴあと東宝が若い才能を発掘する「YES」という映画レーベルが立ち上げられ、新人監督に劇場長編作品を撮らせ、公開の機会を作るというプロジェクトがあって、このとき橋口亮輔監督と出会い、『渚のシンドバッド』が製作されました。
この作品で、自分のやりたいことが、すべてできたんですよね。元男闘呼組の高橋和也君に音楽をオファーしたのですが、彼と制作した音楽が上手く画にはまって。
その後は東宝ミュージックで、好きなサントラをリリースするインディーレーベルを作らせてもらったり、やりたいこともいろいろとやらせてもらえるようになりました。

自社以外の仕事も積極的に行う事で、自身の幅が広がっている
――北原さんが東宝ミュージックの社員でありながら、他社が作る映画の音楽も担当されているのはなぜでしょう?
ギャガさん、東映さんなど、東宝以外の仕事も有り難いことにオファーを頂き、立ち上がりから完成までのすべてをこなす仕事、それらを評価していただいているようです。「それが、のちの人間関係や会社にとっての営業になるわけだから、外の仕事もどんどんやれ」と、当時の上司が言ってくれていました。
例えば、『世界の中心で、愛をさけぶ』の監督・行定 勲さんとは、会社外の仕事で、行定さんのインディ時代の作品を依頼され、ご一緒した経験がありました、メジャー作品でもコミュニケーションがある中で仕事ができました。交流、人脈は、この仕事をしていく上でとても重要です。
東宝という大きな看板の下でやれること、東宝みたいな規模でやれば、やはり投げられるパイも大きいし、インパクトを起こせます。逆に単館系のものは、マニアックなクリエイティブの面白みにチャレンジできますが、投げるパイの限界がありますし、マンパワーでも限界があります。良質な映画であっても難しいことも多いです。
その両方が、自分にとって良い循環になっていて、二つのストリームを行き来していると、双方に有るもの、無いものが見えたりします。この動きができているのは幸せなことで、それによってバランスを取っていられると、自分で思いますね。

メジャーな映画の場合は、いい意味でより多くの方々に観てもらうためにも、わかりやすいものを作る必要があります。エッジーなものばかりや、ニッチすぎるものは響かなかったりもするからです。
映画は、企画の段階で、「どこをターゲットにするか」を考えて作られています。エッジ―で早いものが良いというわけでもないです。また、映画の中で音楽だけ尖がっていても仕方ないですよね。経験を経て、すみ分けができるようになったんだと思います。ただ、手掛ける作品には、多少のマニアックさを入れて、自分の色を出すようにしています。

現在は『シン・ウルトラマン』を制作中
――ご自身が制作に携わった映画で記憶に残る映画は?
「音楽作品」で言えば、松山ケンイチ君主演の、『デトロイト・メタル・シティ』。エネルギーを注入した作品です。また、『さよならくちびる』というアコースティックデュオのバンド映画、これも印象に残っている作品ですね。

――ライブシーンがある映画のほうが、記憶に残るということですか?
それだけ音楽にかけている時間が長いですし、撮影現場にも長く関わっているという理由もありますね。でも、音楽シーンが多いという事ではなく、先ほど申し上げた『モテキ』という大根 仁監督の、既成楽曲をちりばめた作品では、音楽をどう音響的に工夫したらいいのか、と試行錯誤しました。新しい発見があった作品で、自分でも「こういうこともできる」と更なる気づきがあった映画でした。
また、『シン・ゴジラ』もとても記憶に残っている作品です。現在、『シン・ゴジラ』の庵野秀明総監督の企画・脚本の、『シン・ウルトラマン』(監督・樋口真嗣)の制作をしています。コロナ禍で公開時期は目下調整中ですが、庵野ワールドが炸裂している作品ですので、『シン・ゴジラ』のファンの方には是非、観ていただきたい作品です!

■センスの磨き方や、女性活躍、今後の夢について
センスのアップデートは、常に数多くの作品に触れ続けること
――ところで、センスはどのようにして磨くのが良いのでしょうか?また、北原さんのセンスのアップデートの方法とは?
現在11歳の娘がいるのですが、娘を持つまでは夜遊びに行っていて、そこで常に音楽をアップデートしていました。子育てを始めてからは、自宅で海外チャンネルを流しっぱなしにすることは欠かさないですし、劇場で映画を観たり、PC上で作品を観たりしています。
好みの映画だけでなく、自分の趣味嗜好以外のものも観るようにしています。洋画、邦画関係なく、週3から4本、年間200本くらいでしょうか…もっとかな…。実は本も読みたいのですが、仕事とお母さん業で、今はあまり本は読む時間はないですね。

――人生で観た映画で影響を受けた1本を教えてください。
「IP5/愛を探す旅人たち』という映画です。大好きなガブリエル・ヤレドというフランスの映画音楽の巨匠が音楽を担当し、ジャン・ジャック・べネックス監督の映画で、イブ・モンタンの遺作です。
少年に寄り添う曲が劇中にあるのですが、なんか静かな「うゎ~」という、衝撃を受けましたね。自分が仕事をする上で、「人にこういう影響を与えられたらな」と、いつもこの映画のことを思い出して仕事をしています。自分の深いところで、常にこの作品の存在があるんです。
映画業界の女性進出の壁は、体力的なことが要因している
――日本の映画業界は、女性があまり多くないイメージがあるのですが実際はどうですか?
映画業界で女性が活躍するということは、確かにあまり多くないですよね。でも難しさを感じることはないですね。入社当時からいつも周りは男性ばかりなので、性別を意識したことはないです。でも絶対的に女性が少ないのは確かです。体力的にハードだからでしょうか。若いころは、それなりに女性がいて、でも結婚出産で辞められたりして、いつの間にか男性ばかりが周りにいます。

でも最近、現場を見ていると、若い女子の評価が高いです。肉体的にきつい職業なので、継続性が難しいのかもしれないですが、以前に比べたらだいぶ働きやすいようには変わってきているかもしれないです。
やりたいことを具現化するためには「イメージ」が大切
――好きなことを仕事にしたいという方に、アドバイスはありますか?
本当にやりたいことが明確にあれば、それを信じて進めばできないことはないと思います。「イメージ」ですね。自分の中のイメージを明確にしていると、言葉になるし具現化できるのではないでしょうか。
――では、北原さんの今後の夢は?
いっぱいあります。この数年は、アーティストプロデュースも手掛けています。若手女優で話題中の、上白石萌歌さんのadieuとしてのアーティスト・プロデュースをしています。今後は映画だけでなく、仕事の幅をもっと広げていきたいと考えています。
そして、この仕事をずっとやっていきたいな、ずっとこの場にいたいなと思っています。この仕事が大好き過ぎて、いずれ老いたときに、「この仕事ができなくなるかもしれない」と考えると今、すでに悲しいです。(苦笑)
プレッシャーやストレスも多い仕事ですが、できあがったとき、みんなで「わっ」となる、その一瞬のためにやっているのかもしれないですね。一生この仕事を続けていきたいと思っています。
※
以上、東宝ミュージックで映画音楽プロデューサーとしてご活躍されている、北原京子さんにお話をお伺いしました。
今まで何気なく観ていた映画も、北原さんのお話を伺ってから改めて観ると「映画の音楽とは、こんなにも作品に影響を与えるものなのか」と驚かされる感覚がありました。日本の映画が今後も幅広く支持され、邦画産業がますます発展していくことを願ってやみません。
北原京子さん、この度は貴重なインタビューの機会をいただき、本当にありがとうございました。

- TEXT :
- 岡山由紀子さん エディター・ライター
公式サイト:OKAYAMAYUKIKO.COM



















