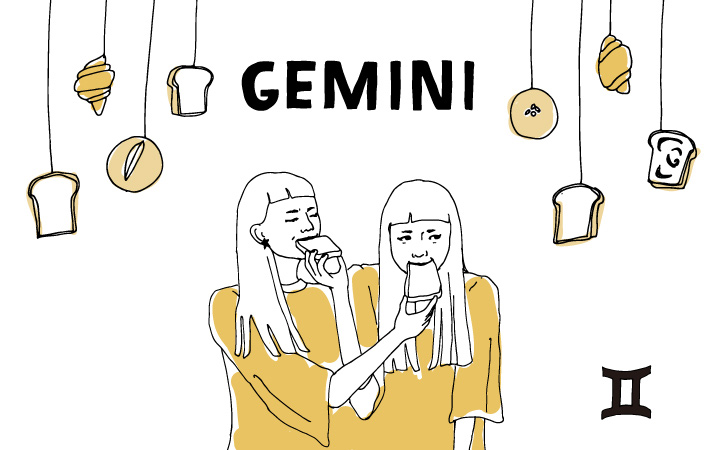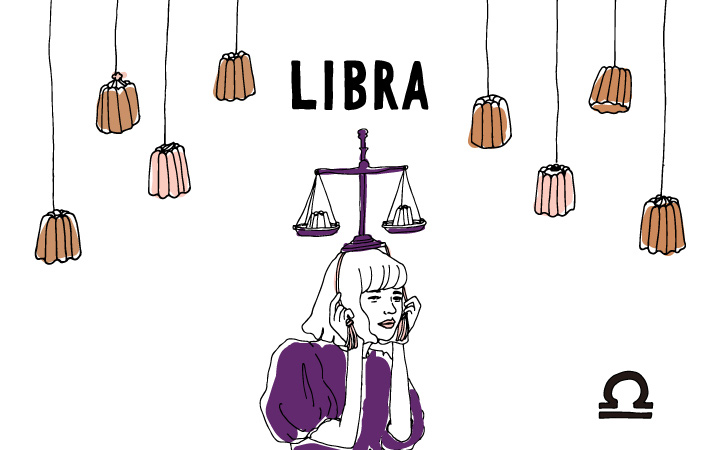ある時代、たとえば1970年代前後に背伸びした青春を送った女性なら、多かれ少なかれ心の片隅に「安井かずみ」がいるはずだ。

職業「作詞家」。『恋のしずく』や『危険な二人』などヒット曲は数え切れず。1965年『お喋りな真珠』でレコード大賞作詞賞を受賞。26才で「日本一若い作詞家」と呼ばれた。
だが、女性たちを魅了したのは、日本には珍しく湿度のない洒落た口語体の語り口だけではなく、当時としては途方もなく自由奔放な生き方にあった。

愛称ズズ。その呼び名もどこかフランス風でスノッブな匂いがする。まるで別世界の住人のような響き。
コシノジュンコや加賀まりこなど、同時代を象徴する「バッドガール」と深夜まで六本木や赤坂で遊び回る華やかな交遊のかたわらには、当時絶大な人気を誇っていたグループサウンズの人気シンガーを侍らせ、名実ともに女王のような君臨ぶり。
数多いボーイフレンド、つかの間の恋人…彼女にまつわるエピソードすべてが、フランソワ—ズ・サガンの小説を読んでいるかのような錯覚さえおぼえる、日本人離れした格好よさなのだ。格好よさとは、「スタイリッシュ」を至上とするスピリッツを貫いていたことである。
刻一刻と変容する生き生きとした’60年代から’70年代にかけて、とびきりの女の魅力とは、贅沢三昧に着飾ることではなく、高価なブランドものを身につければそれで済むのではなく、「スタイルをもつ」ことであるということを、安井かずみによって私たちは学んだ。
高度成長期のまっただなかに、それを追い越すほどのスピードで時代を駆け抜けていった、時代のミューズであったと言えよう。

戦後、すべての価値基準が崩壊するなかで育った彼女は、日本の古い価値観に囚われず、「世界の中の日本人」として生きることを選択したという。飛び抜けたセンスはさらに磨かれていった。
「(フランソワーズ)サガンが何気ない絹のシャツを着て、袖を少しまくっていた。もちろんすぐ真似た。(フランソワーズ)ドルレアックはシャンプーしたての髪をただブラッシングしただけという、自然な髪を風に揺らしていた。私は以来、美容院で髪をセットすることは決してなかった。それらパリの女達の身のこなし、仕草、雰囲気、話し方、その時々のドレスの着方、選び方をつぶさに見た、真似た」(『女は今、華麗に生きたい』大和出版刊)
なんという素直な吸収力、しなやかな直感だろう。何者にも臆することなく勝ち取っていった自由には、まず自らが選び取る選択眼と裏付ける自信があった。
「サンローラン」「キャンティ」「BMW」「アルフレックス」。アルファベットやカタカナで、キラキラ輝く言葉に彩られた彼女のライフスタイルは、まぶしすぎて実像すらよく見えず、それがまたいっそう彼女を神話的存在に押し上げた。
まだ海外旅行が珍しかった’60年代半ばに、加賀まりことふたりで、パリに3か月間も旅をしたというエピソードも、彼女をよりミステリアスに見せた。エスコートしたのは、サンローラン、トリフォー、ゴダールと言われている。本当なのだろうか? だが、もし、それがある種の伝説だったとしても、彼女の黒く縁取られた眼差しが放つ芳香の前に、サンローランさえひれ伏すかも知れないと思わせるオーラが漂っていたのは、確かである。
まだ少女だった私には、少なくともそう映った。自分が大人になって「パリ」に行き「サンローラン」で服を買い、「キャンティ」で食事するなど、夢物語でしかなかった時代の憧れの人。彼女が生きた時代は、近いようで遠い時代であった。

シャネルやサンローランの本店には自分の型紙が置いてあるなど、ファッションリーダーとしても別格であったが、それはあくまでも安井かずみの人生の一部であった。恋愛や結婚があり、それとともにファッションや食があった。
夫・加藤和彦と共著『キッチン&ベッド』という本を出したが、キッチンとベッドが生活の基本としてしっかりしているからこそ、ファッションも恋愛もある。だから日常の食やともに過ごす時間を大切に、楽しんでしまおうと言う考え方だ。とかく虚飾に映りがちなライフスタイルであったが、素朴でも本物を愛し、「お金の力」で「よい趣味を買う」など野暮の骨頂として、嫌っていたということが伝わってくる。
55才で亡くなる短い人生であったが、33冊のエッセイと4,000曲あまりを手掛けた。仕事のトップランナーとして走りながら、ブランドものに身を包んで、グラビアを飾る姿は、誰よりもエレガントでスタイリッシュだった。仕事師であり、自分の稼いだお金で贅沢をする、抜群のファッションセンス。三拍子そろった現代に連なる見事なロールモデルとして、今も輝き続けている。

- TEXT :
- 藤岡篤子さん ファッションジャーナリスト
- クレジット :
- 文/藤岡篤子 構成/渋谷香菜子