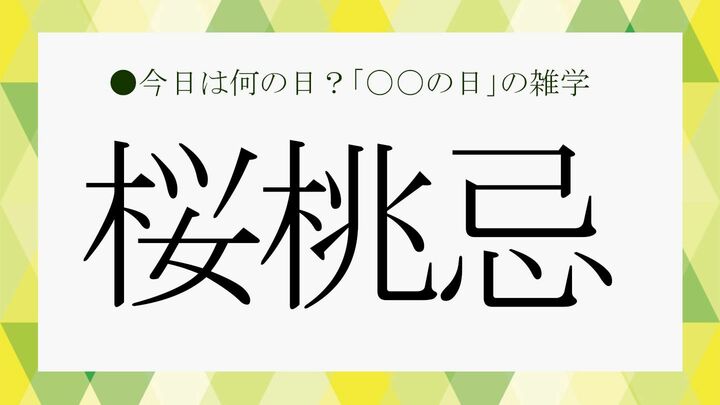「桜桃忌」をご存じですか? これは、作家、太宰治(1909~1948)の「忌日」です。「忌日」と聞いても、ピンとくる人は少ないかもしれませんね。今回は「桜桃忌」の意味や由来やほか、太宰治にまつわる雑学をご紹介します。
【目次】
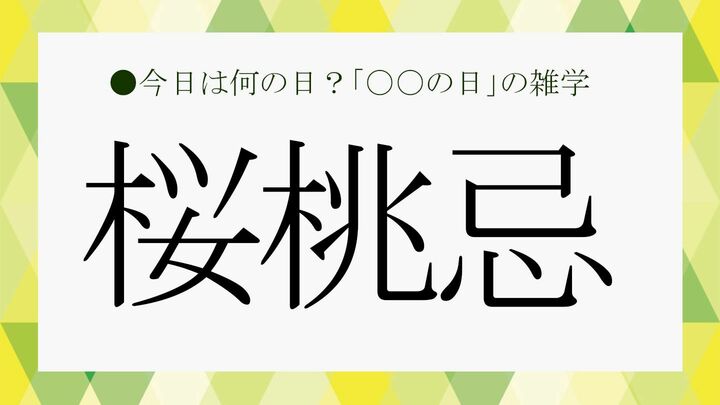
【6月19日の「桜桃忌」。「読み方」「意味」「由来」をさらっと!】
■「読み方」
「桜桃忌」は「おうとうき」と読みます。
■「意味」
「桜桃忌」は作家、太宰治の「忌日」。「夏の季語」でもあります。「忌日」は「きにち」もしくは「きじつ」と読み、「亡くなった日」を指し、「命日」とほぼ同義です。「初七日」や「一周忌」、「二十三回忌」など、「忌日」を基準とした忌日法要はよく知られていますね。「忌日」も同様で、毎年または毎月、成仏を願う仏事供養である法要が行われます。
「忌日」は「いみび」とも読みますが、こちらは「けがれを避けて慎むべき日、物忌みの日、縁起の悪い日」という意味になります。「きにち」「きじつ:とは区別して使いましょう。
■「由来」
太宰治は1948(昭和23)年の6月13日(ないし14日)に、愛人の山崎富栄と共に玉川上水で入水心中をはかりました。そして、6月19日に遺体が発見されました。その日は太宰の誕生日。これにちなみ、6月19日が「忌日」となりました。「桜桃忌」という忌日名は、太宰が死の直前に書いた短編小説のタイトル『桜桃』に由来します。毎年、6月19のこの日、太宰治が眠る東京都三鷹市の禅林寺では法要が行われています。
【ビジネス雑談に役立つ「桜桃忌」「太宰治」の雑学8選】
■「桜桃」って何だか知ってる?
「桜桃」とは、バラ科サクラ属の落葉小高木に6月ごろなる果実、つまり「さくらんぼ」のこと。太宰治が好んだ果物だったということもあり、6月19日の忌日には、太宰治の墓前に大量のさくらんぼが供えられます。
■小説『桜桃』とは?
短編小説『桜桃』は、1948年5月、雑誌「新潮」に掲載された作品です。『桜桃』は、子ども3人の子育てに疲弊する夫婦の心情が父親の目線で書かれた短編。子育てに疲れ切った父親は現実から逃げるように酒を飲み、自殺のことばかり考えて暮らしています。父ひとりで迎えた居酒屋でのラストシーンを紹介しましょう。
「しかし、父は、大皿に盛られた桜桃を、父は極めてまずそうに食べては種を吐き、食べては種を吐き、食べては種を吐き、そうして心の中で虚勢みたいに呟く言葉は、子どもよりも親が大事」(『桜桃』より)。
当時、さくらんぼは今以上にぜいたくな食べものでした。「極めてまずそうに食べて」いながら「虚勢みたいに子どもより親が大事」と呟く、という描写は、太宰治本人が、子育てと妻から逃げているという罪悪感があったからだったのかもしれませんね。。
■なぜ「忌日名」は「桜桃忌」になったの?
「桜桃忌」の名は、太宰と同郷の津軽出身で、当時三鷹に住んでいた小説家、今官一(こんかんいち)によって付けられました。「桜桃」は上述した通り、太宰の死の直前に書かれた名作の題名です。加えて、6月のこの時季に実る桜桃(さくらんぼ)の鮮烈な色が、太宰の生涯と珠玉の短編作家というイメージに最もふさわしいとして、太宰を深く知る友人たちの支持を得たそうです。太宰は『桜桃』の中でさくらんぼをこんな風に表現しています。「蔓を糸でつないで、首にかけると、桜桃は、珊瑚の首飾りのように見えるだろう」(『桜桃』より)。
■「桜桃忌」には何が行われる?
発足当時の「桜桃忌」は、太宰と直接親交のあった人たちが遺族を招き、さくらんぼをつまみながら酒を酌み交わす、いわゆる「太宰治を偲ぶ会」だったそうです。常連の参会者は、佐藤春夫、井伏鱒二、檀一雄、今官一、河上徹太郎、小田獄夫、野原一夫など。中心になったのは文芸評論家の亀井勝一郎で、昭和38年まで、当日の司会も務めました。その間に、禅林寺には、太宰治を偲ぶ十代、二十代の若者などが全国から集まるようになり、青春巡礼のメッカへとさま変りしていきました。主催も友人・知人たちから筑摩書房へ、昭和40年からは、桂英澄、菊田義孝といった太宰の弟子たちによる世話人会が引き継きました。「太宰治賞」の発表と受賞者紹介が「桜桃忌」の席場で行われたのはこのころのことです。しかし、その世話人会も1992(平成4)年、会員の高齢化を理由に解散。今年(2024年)、太宰治が亡くなってから76年となります。かつて「桜桃忌」に集った太宰ゆかりの人々の多くは故人となりましたが、その作品は今も若い読者を惹きつけ、「桜桃忌」をに禅林寺を訪れる人々はあとを絶ちません。
■ざっくり、太宰治ってどんな作家?
太宰治は青森県北津軽郡出身。17歳のころ、最初の小説を書き、作家を志します。東京帝国大学文学部仏文科に入学し、井伏鱒二に弟子入りした後、1935年に発表した「逆行」が第1回芥川龍之介賞の候補となりました。実は彼が作家として活動したのは、第二次世界大戦前から戦後にかけてのわずか15年です。この間、『走れメロス』や『斜陽』『人間失格』など、次々と作品を発表し、最期は女性と入水自殺した、自己破滅型の小説家としても有名です。太宰の自殺願望は高校生のころからと言われており、人生で5回の自殺未遂、心中未遂事件を起こしています。また、芥川龍之介と同じポーズで写真を撮る程の芥川ファンで、芥川賞受賞を熱望していました。第1回目の芥川賞に『逆行』がノミネートされた際には、賞の選考員のひとり、佐藤春夫に「佐藤さん、私を忘れないで下さい。私を見殺しにしないで下さい」と、4メートルもある巻物の手紙を送ったそうです。その後、受賞を逃してしまった太宰は、小説を酷評した川端康成に対し、「川端康成へ」という名指しの文章を雑誌に掲載。恨み辛みの言葉を並べたそうです。エキセントリックな一面が垣間見えますね。
■小説『斜陽』に元ネタがあったって知ってる?
太宰治の小説「斜陽」は太田静子の日記が基になっていたといわれています。太田静子は滋賀県の、資産家で開業医の太田家に生まれます。上京して結婚、出産しますが、子どもは生後すぐに亡くなり、離婚。その後、太宰と出会い、太宰の子を産み、育てました。当時、太宰はチェーホフの『桜の園』のような没落貴族の小説を構想しており、その題材として静子の日記を借りていました。「小説が出来たら1万円あげる」という口約束の通り、『斜陽』出版後、太宰は静子に1万円を送金しています。現在の価値に置き換えるのは難しいのですが、当時の公務員の初任給(基本給)が2,300円だったことから、ごく大雑把に100万円くらいではなかったかと推測できます。その後、何度かの養育費のほか、太宰の死後は「太宰治ノ名誉及ビ作品ニ関スル言動(ヲ傷ツケルヤウナ言動)ヲ一切ツツシムコト」という内容の誓約書(新聞・雑誌ニ談話及ビ手記発表)を取られ、その引換に『斜陽』改装版の印税10万円を渡されました。ところが、太宰の実家(津島家)からの冷遇に耐えかね、10月にはこの誓約を破るかたちで『斜陽日記』を刊行。この日記の内容に『斜陽』と重なる部分があまりに多かったため、太宰死後の捏造ではないかとの説を唱えられて悲しんだそうです。
■実は「○の○」が好きだった?
小説家の檀一雄は太宰の友人のひとりで、『小説 太宰治』を出版しています。その中のエピソードによれば、太宰治は「味の素」が大好きだったそう。
「僕がね、絶対、確信を持てるのは味の素だけなんだ」(岩波現代文庫『小説 太宰治』より)
実際、太宰の小説『HUMAN LOST』の作中にも「味の素」が登場します。「筋子に味の素の雪を降らせ、納豆と青のりとからしを添えれば、ほかに何も不足はない」程、味の素が好きだったとか。今でも、太宰のお墓にはさくらんぼと並んで「味の素」がお供えされているそうですよ。
■太宰治を主人公にした映画は?
太宰治関連の映画は数多くありますが、彼自身がモチーフとされる映画三本をご紹介しましょう。
・『人間失格』(角川映画)
2009年公開。生田斗真主演。伊勢谷友介、寺島しのぶ、石原さとみ、小池栄子、森田剛出演。小説『人間失格』を原作に、太宰治生誕100年を記念して製作された文芸大作。
・『ヴィヨンの妻 桜桃とタンポポ』(東宝)
2009年公開。松たか子、浅野忠信主演。小説『ヴィヨンの妻』が原作。『ヴィヨンの妻』は、小説『人間失格』同様、太宰による「私小説」。人気作家として世間から注目されるも、生きることに苦しみ酒や女に溺れる大谷と、放蕩を続ける夫を愛し続ける妻・佐知の姿が叙情的に描かれていきます。
・『人間失格 太宰治と3人の女たち』(松竹、アスミックエース)
2019年公開。蜷川実花監督、小栗旬主演。太宰の妻を宮沢りえ、太田静子を沢尻エリカ、最後の女性・富栄を二階堂ふみが熱演。こちらは、上の2本とは違い、太宰治本人の半生と彼を取り巻く女性との関係をモチーフに描いた作品です。
***
太宰治が生まれたのは1909(明治42)年。2009年に生誕100年を迎え、その後も「ブーム」が続いています。若者が抱える「生きづらさ」を100年前に表現していた太宰は、時代の先駆者だったのかもしれません。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『日本国語大辞典』(小学館) /『デジタル大辞泉』(小学館) 『デジタル大辞泉プラス』(小学館) /三鷹市HP「太宰治と三鷹」(https://www.city.mitaka.lg.jp/dazai/dazaitomitaka/index.html) :