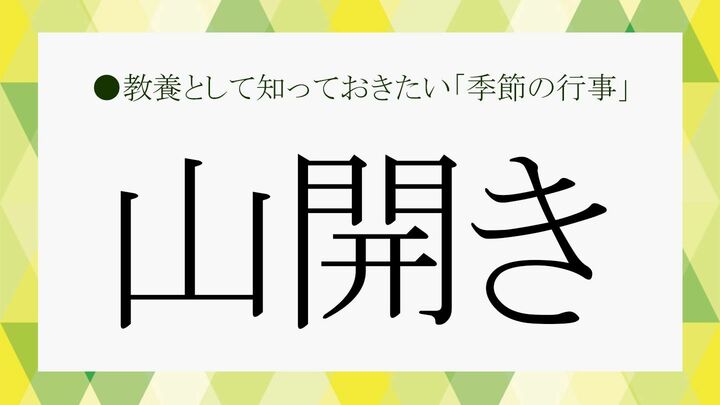【目次】
【「山開き」とは?「意味」など「基礎知識」】
■「山開き」って何?
「山開き」とは、それぞれの山を管理している地元の自治体や観光協会、山岳関係団体などが協議して、その年初めて、一般登山者に登山を許すこと。山開きの日程に考慮されるポイントは、登山道の整備具合、地域の行事との調整、例年の慣習など。富士山のように高い山や、寒い地方にある山では、雪の状況なども重要です。
「山開き」の時期が事前に決められ広く告知されるのは、山岳事故をなくし、安全に登山できるようにするためです。「山開き」の多くは夏の期間に行われ、初日には、安全を祈願してさまざまな祭事やイベントが催されます。この行事のことを「山開き」と言うこともあります。
■「山開き前」に登山はできない?
「山開き前」であっても、入山できる山もあります。とはいえ、一般の登山者に対応するための山小屋や売店が営業されてり、登山道の整備などがされるのは、「山開き」に向けて。「山開き」前の登山は、環境的には安全で快適とは言いがたいものがあり、さらに、万が一のときにも迅速な救護を受けられない場合も…。遭難リスクも高くなり、決して推奨できません。
【「山開き」の起源は?】
日本人は古来より山岳を神聖視し、神霊の宿る地としてあがめてきました。その背景には、山岳を神々との交流ができる異郷と見なし、「死霊のいる場」とする世界観があったのです。そのため、山岳は狩猟や焼畑耕作民にとっては生活空間である一方、山麓で水稲農耕を営む一般住民は立ち入ることのできない「聖なる地」とされていました。無理に入れば天狗 (てんぐ) におそわれると言い伝えられたりしましたが、江戸中期以降、各地に山岳信仰を説く集団が結成され、山頂に祀 (まつ) られている神様を拝むための登山が行われるようになりました。
この登山のために日数を決め、山を俗人に開放したのが、「山開き」の始まりです。特に初日は「お山開き」と呼ばれ、近世には、この日に信者や集団に関わる人々が山に登って御来光(日の出)を仰ぐ行事が盛んになりました。そして、最終日である「山仕舞い」を境に、山はまた山伏や僧侶たちなど修行者だけの世界に戻り、一般住民の立ち入りはできなくなったのが、今日につながっています。現在では、そのような信仰とは関係なく「安全に登山ができる期間かどうか」の目安としても、「山開き」という言葉は用いられています。
【富士山をはじめ、各地の名山の2025年の山開き】
■「山開き」はいつが多い?
ほとんどの「山開き」は、5月ごろから7月に行われます。特に、夏の登山や神社仏閣への参拝を目的とする「夏山」では、6月から7月がトップシーズン。ただし、「山開き」の時期は、地域や山ごと、さらに同じ山であっても、山頂へ向かうルートによっても時期が異なります。加えて、その年の残雪の状況や登山道の安全状況次第では、時期は前後することもあります。登りたい山がある場合は、必ず事前に、行政や山の公式ホームページなどで最新情報をチェックしましょう。
■富士山の入山ルールが強化!「山開き」もルートによって異なる
「山」と聞けば、富士山を真っ先に思い浮かべる人は多いでしょう。富士山もほかの山と同様、「山開き」の日取りは決まっています。このとき注意したいのは、富士山の「山開き」は登山ルートごとに異なるという点です。富士山の登山ルートは、登山の起点となる「登山口」によって4つに分けられており、山梨県側の「吉田口」から登るルート、静岡県側からはそれぞれ「富士宮口」、「須走(すばしり)口」、「御殿場口」から登るルートとなります。
例年の「山開き」は、山梨県側の「吉田ルート」が7月1日頃で、静岡県側の「須走ルート」「御殿場ルート」「富士宮ルート」の3つは吉田ルートより10日ほど遅い、7月10日ごろとなっています。また、「山仕舞い」はすべてのルート共通で、9月10日となっています。この期間であれば、登山ルート入口などにある休憩所やトイレ、案内所などの設備が利用できます。
●富士山4つのルートの山開きの日程
[山梨県側]
・富士山の北側から登る「吉田ルート」:2025年7月1日(火)~9月10日(水)
[静岡県側]
・富士山の東側から登る「須走ルート」:2025年7月10日(木)~9月10日(水)
・富士山の南東側から登る「御殿場ルート」:2025年7月10日(木)~9月10日(水)
・富士山の南側から登る「富士宮ルート」:2025年7月10日(木)~9月10日(水)
富士山は、2025年から入山ルールが強化され、初めて入山料(4000円)が実施されています。また、山梨県側ルート(吉田ルート)では通行予約システムを導入、ゲートを設置し、1日4000人の登山規制があります。また、静岡県側では、登山前にルールやマナーを学ぶeラーニングが義務付け。さらに、山小屋に宿泊しない場合は、午後2時から翌午前3時までの夜間規制もあります。
■北海道
ダイナミックな自然が魅力の北海道。日本百名山として知られる阿寒山群の主峰「雌阿寒岳(めあかんだけ)」の山開き「雌阿寒岳安全祈願祭」は例年6月上旬。今年は6月15日(水)に実施されました。初心者にもおすすめな「富良野西岳」は6月14日(土)、花の百名山に選ばれる「富良野岳」は6月15日(日)に山開きの登山会がありました。ロープウェイ利用でファミリーも楽しめる「有珠山(うすざん)」は例年昭和の日、今年も4月29日(火・祝)が山開きでした。
■福島県
福島県には、登山者に人気の山が数多くあります。早いところでは、今年は3月30日(日)に山開きした、白河市の「関山(せきさん)」をはじめ、多くの山々で登山客を迎え入れます。標高1700メートル、日本百名山のひとつである「安達太良山(あだたらやま)」は5月18日(日)に、燧ヶ岳・至仏山・会津駒ヶ岳のある「尾瀬」は5月30日(金)に山開きが行われました。「会津磐梯山」の民謡でおなじみ、標高メートルの活火山として有名な「磐梯山」の山開きは5月25日(日)でした。
■白馬連峰(長野県)
北アルプス「白馬連峰」の登山は、残雪や動物、高山植物などを楽しみながら歩くのが醍醐味。単独峰とは異なり、連なる連峰の稜線を歩くとまるで天空の散歩道を歩いているような気分が楽しめます。「貞逸祭(ていいつさい)・白馬連峰開山祭」は、山開きを告げる歴史ある山岳イベントです。例年5月下旬、2025年は5月30日(金)に行われました。
■西丹沢(神奈川県)
神奈川県北西部に広がる人気の観光スポット「西丹沢」。2025年の山開きは5月18日(日)でした。西丹沢には、中川沿いの各登山口のバス終点に「西丹沢ビジターセンター」という利用者のための施設があります。ここには、檜洞丸や加入道山、畦ヶ丸への登山口が集中しています。最新の登山情報が掲示され、登山道や花の開花時期情報などを尋ねることができますよ。
■福岡県
福岡県最高峰の釈迦岳をはじめ、御前岳、前門岳、文字岳、三国山、国見山、猿駈山、休鹿山など、「矢部村山系」を訪れる登山者の安全を祈願する山開きが毎年4月29日に開催されています。
【「山開き」には「何をする」?】
古くは、「山開き」の初日には、山岳信仰の信者の人々を中心に、御来光(日の出)を仰ぐ行事が盛んに行われていました。現在でも、山ごとにさまざまな行事が各地で開催され、登山者の安全だけでなく、林業など山に従事する人々の安全を祈願しています。有名な山開きの行事やイベントをご紹介します。
■富士山本宮浅間大社
富士山の山開きは盛大です。静岡県富士宮市宮町にある「富士山本宮浅間大社(ほんぐうせんげんたいしゃ)」では、今年は7月10日(木)に「開山祭」が開催されました。さまざまな式典や神事のあと、山岳救助隊による夏山救助開始式、富士山開山式典、さらに「村山浅間神社」での富士山入山式のほか、たくさんのイベントが行われ、例年通り多くの登山客が訪れました。
■北口本宮冨士浅間神社
富士山本宮浅間大社の開山祭の10日前、毎年7月1日に行われるのが、富士山吉田口登山道の起点である「北口本宮冨士浅間神社」の「開山祭」。6月30日の「開山前夜祭」と合わせて行われるこの祭事では、浅間大神様に開山させていただくことをお伝えし、富士登山者や登山道関係者の安全祈念が行われます。富士山の登山シーズン開始を告げるお祭りは、今年も無事に執り行われました。
■安達太良山(福島県)
上で紹介した福島県の「安達太良山」では、今年は5月18日(日)に山開きが開催されました。奥岳登山口で安全祈願祭が行われ、屋台のマルシェが出店。山頂では記念ペナントが配布されたり、大空コンテストが開かれたりしました。
■貞逸祭・白馬連峰開山祭(長野県)
こちらも上で紹介しましたが、北アルプス白馬連峰の山開きを告げる「貞逸祭・白馬連峰開山祭」は、白馬岳山頂に現在の「白馬山荘」を建てた松沢貞逸氏の功績を記念して、山の安全祈願をするもの。祭事と共に、白馬山案内人組合と行く「大雪渓トレッキングツアー」も実施され、県内外から多くの登山客が集まる人気の「山開き」です。今年も快晴のもと約320人が参加して、第49回の開山祭が盛大に行われたそうです。
***
「山開き」は3月末から7月に行われることがほとんど。今ではレジャー情報として活用されていますが、元々は山に神様が宿ると考える、山岳信仰に由来するものでした。トレッキングは、交通機関を使い観光地を巡る旅とは違った目線で、日本の美しい自然を堪能できるのが魅力。この夏の想い出は、自分の足で歩いて、見て、感じてみてはいかがでしょうか。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『日本国語大辞典』(小学館) /『デジタル大辞泉』(小学館) /『日本大百科全書 ニッポニカ』(小学館) /『世界大百科事典』(平凡社) /富士登山オフィシャルサイト(https://www.fujisan-climb.jp/index.html)/富士山本宮浅間大社(http://fuji-hongu.or.jp/sengen/index.html)/北口本宮富士浅間神社(https://sengenjinja.jp)/神奈川県立秦野ビジターセンター・西丹沢ビジターセンター(https://www.kanagawa-park.or.jp/tanzawavc/course.html) :