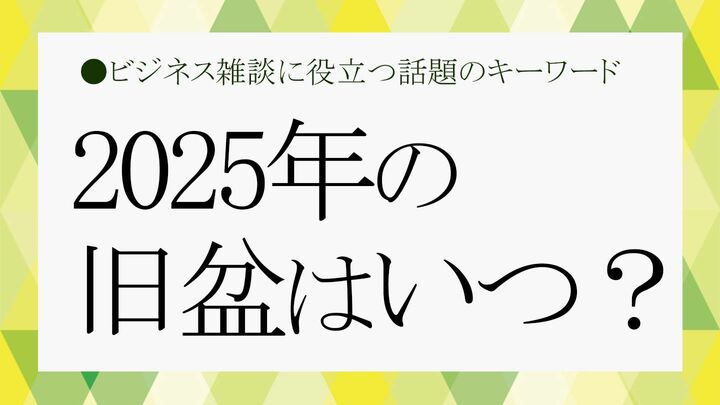【目次】
【2025年の旧盆はいつ?】
8月13日(水)から16日(土)が2025年の旧盆です。ちなみに企業などが「お盆休み」として休暇にあてる8月の「お盆」は「旧盆」をさします。つまり、一般的にわたしたちが言う「お盆」が「旧盆」ということです。
【「新盆」と「旧盆」の違い】
■「旧盆」「新盆」それぞれの「読み方」
「旧盆」は「きゅうぼん」、「新盆」は「しんぼん」と読みます。
■そもそも「お盆」とは?
「お盆」は「盂蘭盆会(うらぼんえ)」のこと。「盂蘭盆会」は、旧暦(太陰暦)の7月15日に先祖の霊を祭る仏教の行事です。現代でも、お寺で先祖供養や供養のための法要や儀式を執り行ったり、自宅でご先祖様や亡くなった家族の霊を迎えたり、お墓参りをして過ごすための期間とされています。
■旧盆とは
上でも触れましたが、8月15日ごろに行われる「お盆」が「旧盆」です。「8月盆」や「月遅れ盆」とも言います。
江戸時代までは、旧暦の7月13日から15日か16日までの3、4日間がお盆期間でした。そして、1872(明治5)年に新暦(現在採用している暦)が導入された際、カレンダー上では約30日ほど日付が前倒しなり、旧暦の7月15日(本来のお盆の日付)が新暦の8月15日にあたるため、8月のこの期間に行うお盆を「旧盆」と言うようになりました。
■新盆とは
現在の7月15日前後に行うお盆が「新盆」です。「7月盆」とも言います。
新暦を採用した明治政府のお膝元であった東京や神奈川などの都市部では積極的に「新盆」が推奨されたため、これらの地域では「新盆」が定着しました。とはいえ都市部にはさまざまな土地からの移住者も多いので、現在でもスーパーなどでは、新盆の時期と旧盆の時期の二度にわたってお盆飾りやお供えセットを販売しているようです。
■初めて迎えるお盆は「初盆」です
亡くなった方の四十九日を過ぎて初めて迎えるお盆のことを「初盆」と言います。読み方は「にいぼん」や「はつぼん」。ただし、「新盆」と書いて「にいぼん」や「あらぼん」と読ませる場合はこの「初盆」と同義です。「新盆」は読み方で意味が異なるので、しっかり認識しておきましょう。
・初盆(にいぼん・はつぼん)/新盆(にいぼん・あらぼん):四十九日を過ぎて初めて迎えるお盆のこと。
・新盆(しんぼん):新暦の7月13日から16日に行うお盆。
【沖縄の旧盆(ウークイ)はいつ?】
「旧盆」と「新盆(しんぼん)」を解説しましたが、それとは別に地域性による日程を採用している場合もあります。
■沖縄県のお盆
特徴的なのは沖縄のお盆。行事を旧暦で行うことが少なくない沖縄では「旧盆」を採用しています。
沖縄のお盆は「沖縄盆」とも呼ばれ、先祖を迎える盆の入りを「ウンケー」、中日(ちゅうにち)を「ナカビ」や「ナカヌヒ」、先祖を送り出す沖縄盆の最終日を「ウークイ」といって3日間で執り行います。
2025年の「沖縄盆」は、旧暦7月13日〜15日にあたる9月4日(木)〜6日(土)の3日間。13日がウンケー、14日がナカビ、15日がウークイとなります。
■東京都多摩地区のお盆
小金井、小平、調布、八王子など多摩川沿いの丘陵地帯は、かつて桑畑が広がる養蚕が盛んな地域でした。「東京盆」とも呼ばれていた7月中旬のお盆の時期は養蚕農家にとって繁忙期。そのため半月ほど時期をずらし、7月末から8月頭にかけて「小金井盆」を行っていたとか。現在は主流ではありませんが、7月中旬の「新盆」、7月下旬の「小金井盆」、8月中旬の「旧盆」と、お盆のための商品を3回販売する店舗もあるようです。
【「旧盆」の知識】
■「お盆」のやり方
地域や宗派によって多少の違いはありますが、一般的なお盆の内容をおさらいしましょう。
1)仏壇の掃除:日常から清浄にしておくべきですが、お盆前日までに仏壇内部までしっかり拭き掃除したり、お位牌や仏具を柔らかい布などでぬぐって清めます。
2)お盆飾りやお供え物、盆花などの準備:盆灯籠は、四十九日が過ぎて初めて迎えるお盆(「新盆」や「初盆」と言います)だけは白地(無地)を用います。また、「ご先祖さまが早く帰ってきてくれるように」という願いを込めた精霊馬と、「ゆっくりお帰りください」という意味の精霊牛をキュウリとナスでかたどったものを飾り付けたり、そうめんを供えることも。いずれも仏具屋などで揃いますが、故人が好きだった果物や菓子、花を供えるということだけでもいいでしょう。
3)初日の迎え火・最終日の送り火:「迎え火」と「送り火」には、「おがら」(皮をむいで乾燥させた麻の茎)、焙烙(ほうろく:おがらを焚くための素焼きの丸い皿)、マッチやライターなどの着火具、消火用の水を準備します。家の玄関先や庭、集合住宅ならベランダなどで行います(住居規定や地域自治体の火器扱いのルールを要確認)。新聞紙などの上に焙烙をのせ、燃えやすいよう積み重ねたおがらに火をつけます。すべてのおがらが灰になるまで火元を離れず見守りましょう。
■お盆休みが8月15日前後なのはなぜ?
8月15日前後の「旧盆」時期にお盆休み(夏季休暇)を設定する企業が多いのは、お盆の行事や墓参りのための帰省がしやすいようにとの配慮とも言えます。「新盆」時期では夏休みに入っていない学校も多く、就学児の家族がいる世帯の場合でも、8月の旧盆時期なら、休みを合わせやすいというメリットが。
わたしたちの生活を支えてくれる公共インフラ、サービス、観光業界の現場を担う方々は、なかなかお盆休みが取得しにくい現状にあります。厚生労働省が公開している「労働・休日」の主な制度には、お盆休みに関する記述はありません。つまり、お盆休み(夏季の連続した数日の休日)がないからといって、労働基準法に違反するわけではないのです。国が推奨している「働き方改革」のなかで、お盆の時期をからめて交代で休みをとったり、時期を少しずらして連休を取得できる工夫がされている企業も増えてきているようです。
***
全国から人が集まる都市部では、お盆の習慣もそれぞれです。東京だからといって、一斉に7月に行うわけではありません。帰省や墓参りなどをしない場合でも、この時期はご先祖さまへ感謝の気持ちをもって過ごしてみてはいかがでしょう。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『デジタル大辞泉』(小学館)/『日本国語大辞典』(小学館)/『12か月のきまりごと歳時記(現代用語の基礎知識2008年版付録)』(自由国民社) :