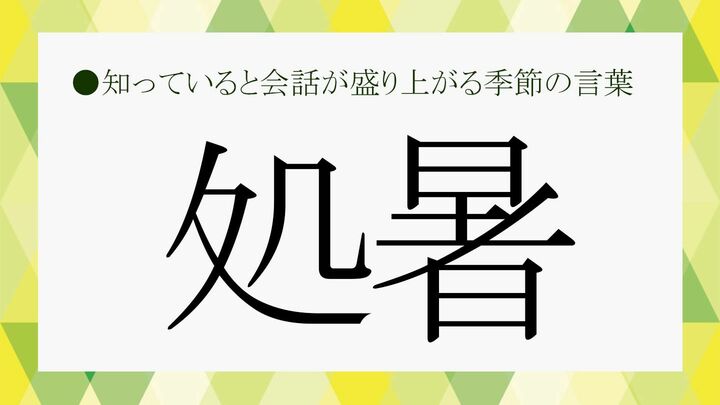【目次】
【「処暑」とは?「読み方」と「意味」、「由来」】
■「読み方」
「処暑」は「しょしょ」と読みます。
■「意味」
「処暑」は二十四節気のひとつで、太陽暦の8月23日ごろのこと。「立秋」の次の節気で、暦のうえでは秋に分類されます。「処」の文字には「止まる」という意味があり、「処暑」で「暑さが止まる」、つまり「暑さが峠を越える頃」という意味をもちます。
■二十四節気の「処暑」ってどんな日?
「処暑」は、8月23日ごろにあたり、8月中旬の旧盆を過ぎると、暑さも和らいで朝晩は涼しくなり、秋の気配が感じられるようになる…はずでしたが、近年は残暑が厳しく、まだまだ「暑さが落ち着いた」ことは実感できない時期となってしまいましたね。日本では、処暑の時期は台風に襲われることも多く、暴風や大雨に見舞われることが少なくありません。
【2025年の「処暑」はいつ?】
■「二十四節気」をおさらい!
二十四節気とは、古代中国でつくられた季節の区分法です。1年を24等分して気候の推移を示すため、各節気の期間は約15日です。例えば「処暑」といった場合、「処暑」に入る日を指す場合と、「処暑」にあたる期間を指す場合があります。
「春夏秋冬」4つの季節はそれぞれ6等分されているので、秋は8月7日の「立秋」に始まり、8月23日の「処暑」、9月7日の「白露(はくろ)」、9月23日の「秋分」、10月8日の「寒露 (かんろ)、10月23日の「霜降 (そうこう)」と続きます。「処暑」は「立秋」の約15日後で、「秋分」の約30日前ということになります。
■2025年の「処暑」はいつ?
「処暑」を含め、二十四節気の日付は固定されておらず、毎年、国立天文台暦計算室によって定められます。今後の「処暑」の日付は以下の通りです。
・2025年の「処暑」 ...... 8月23日〜9月6日
・2026年の「処暑」 ...... 8月23日〜9月6日
・2027年の「処暑」 ...... 8月23日〜9月7日
・2028年の「処暑」 ...... 8月22日〜9月6日
・2029年の「処暑」 ...... 8月23日〜9月6日
「処暑」の次に来る「白露」は、「草木に朝露がつき始める頃」。秋の気配が次第に色濃くなり、昼夜の寒暖差が大きくなる季節であるとされていますよ。
【処暑の風習とは?「過ごし方」「食べ物」】
■「処暑」の風習
「処暑」には、日本各地でさまざまな行事が行われます。なかでも有名なのが、日本三奇祭のひとつに数えられる、「吉田の火祭り」です。これは山梨県富士吉田市の北口本宮冨士浅間神社と諏訪神社のお祭りで、毎年8月26日、27日に行われます。富士山の噴火を鎮める祭礼で、正式には「鎮火祭」といいます。富士山の登山シーズンの終わりを告げるお祭りでもあります。26日夜に富士吉田市内の路上に立ち並べられた100本あまりの大松明に火を灯すことから、「火祭り」の名前で呼ばれており、国の重要無形民俗文化財に指定されています。
また、近畿地方で「処暑」の時期に行われるのは、お地蔵さんにまつわる「地蔵盆」と呼ばれる行事。京都発祥といわれ、関西地方で盛んな仏教由来の行事です。地蔵とは地蔵菩薩を指し、子供を守護する仏様です。町内のお地蔵様をきれいにして提灯を飾ったり、縁日や盆踊りが開催されたりします。
そして、富山県富山市八尾町の「おわら風の盆」も「処暑」の時期に行われるお祭りです。農作物を荒らす暴風を鎮め、五穀豊穣を願う祭礼で、立春から数えて210日目にあたる9月1日から3日間行われます。情緒豊かな踊りの芸能を堪能できるお祭りとして、観光客の人気を集めています。
■「処暑」に旬を迎える食べ物
処暑に旬を迎える野菜や果物は、さつまいもや無花果(いちじく)、ぶどうなどがあります。さつまいもには食物繊維が豊富に含まれ、便秘解消にも効果的。無花果は生で食べてもおいしいですが、ジャムやドライフルーツにしてもいいですね。傷みやすく日持ちがしないので、早めに食べきって。
そして「処暑」を迎える頃に出回り始める魚といえば、名前に「秋」の字をもち、文字通り秋の味覚の代表選手である「秋刀魚(さんま)」です。まだまだ暑さが残る時期とはいえ、秋の訪れを感じさせる食材をおいしく味わいながら、ゆっくりと夏の疲れを癒しましょう。
【「残暑の候」と「処暑の候」はいつ頃使う?】
二十四節気の「小暑」と「大暑」にあたる期間の暑い盛りに出すのが、「暑中見舞い」です。「大暑」を過ぎ、「立秋」を迎えてから出すのは「残暑見舞い」です。残暑見舞いには、「残暑の候」という時候の挨拶を添えて、「白露」の前日までに届くようにするのがマナーです。「処暑の候」を使用する期間はそれよりも短く、「処暑」から「白露」の前日までとなります。
■2025年の「小暑」から「白露」まで
「小暑」:7月7日〜7月21日 暑中見舞い
「大暑」:7月22日〜8月6日 暑中見舞い
「立秋」:8月7日〜8月22日 残暑見舞い
「処暑」:8月23日〜9月6日 残暑見舞い、処暑の候
「白露」:9月7日〜9月22日
【「処暑」を「英語」で言うと?】
国立天文台の「暦用語解説」によれば、「処暑」は [Shosho]。[End of Heat; Times when we feel less heat]と説明されています。
***
「処暑」の時期といえば、子ども時代なら、夏休みも終わりに近づいて宿題の残りが気になり始めるころですね。ここ数年、暑さが長引き、「いつまで夏なの?」といった感がありますが、「処暑」は真夏の疲れが出やすいときです。バランスのよい食事と良質な睡眠を心掛け、体調を整えつつ、食欲の秋の訪れを待ちたいものです。
関連記事
- 「芒種」とは?縁起がいいと言われるのはなぜ?2024年の日にちとビジネス雑談に役立つ知識をさくっと解説!【大人の語彙力強化塾612】
- 「こくあめ」ではありません!「穀雨」の読み方や意味、二十四節気についても!【大人の語彙力強化塾570】
- 「立夏」とは夏のこと?読み方と意味、旬の食べ物など基本事項をさくっと解説【大人の語彙力強化塾586】
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『日本国語大辞典』(小学館) /『デジタル大辞泉』(小学館) /『心が通じる 手紙の美しい言葉づかい ひとこと文例集』(池田書店) 国立天文台「こよみ用語解説」https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/faq/24sekki.html.en /『12か月のきまりごと歳時記(現代用語の基礎知識2008年版付録)』(自由国民社) :