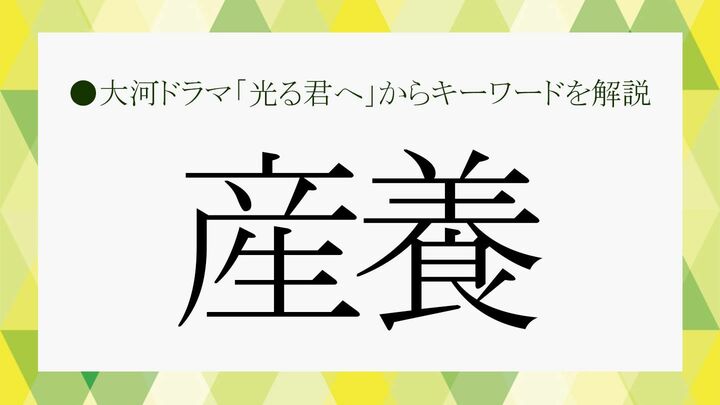医療体制が整っていない時代の出産は過酷で、いまよりもさらに母子の命が危険にさらされるものでした。そのため、無事に出産を終えたときの喜びはひとしお。平安時代、貴族たちのあいだには、出産後、多くのセレモニーが控えていました。「産養」もそのひとつで、親戚や知人達が集まり、子どもの誕生を祝うパーティを意味しています。今回は平安時代の貴族の「出産の祝賀会」である「産養」について、その基礎知識をはじめ、出産や新生児にまつわる雑学をご紹介します。
【目次】
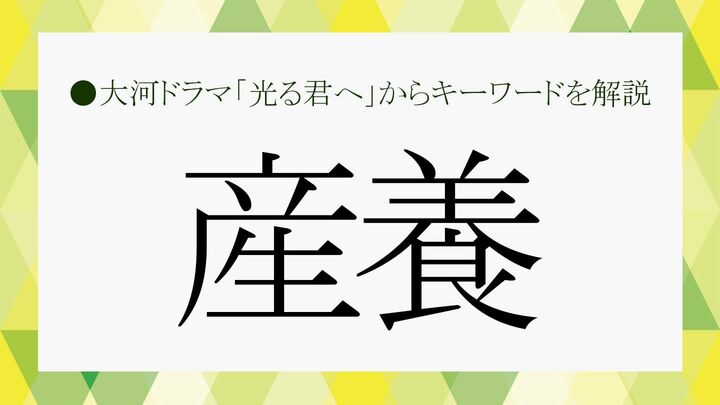
【大河ドラマ『光る君へ』にも登場した「産養」とは?「読み方」「意味」】
■「読み方」
「産養」は「うぶやしない」と読みます。「さんよう」ではありませんよ。「産養ひ(い)」とも書きます。
■「意味」
「産養」には、文字通り「子を養い、育てること」という意味もありますが、今回テーマになっている「産養」は、出産後3日・5日・7日・9日目の夜に「親戚や知人たちが集まって行われる祝宴」、つまりパーティのことです。また、その際に贈られる贈り物を「産養」と言う場合もあります。平安時代、貴族の家で盛んに行われ、「お七夜の祝い」として、今に伝わっています。
■何をする?
産養では、子どもの将来の幸せと産婦の無病息災を祈り、新生児とその母親へ、食器類数十セット込みの御膳(食事)や、産着、餅などが贈られました。主催者は子の父をはじめとする親類縁者が日替わりで務め、特に7日目の宴は最も高貴な人が担当したそうです。プログラムとしては、管楽の演奏のほか、碁(ご。詳しくは後述します)や攤(だ)などの賭けごとも行われました。『紫式部日記』には、中宮・彰子が最初の皇子(敦成親王)出産後、7日目の夜に行われた「御産養」は、朝廷が主催したと記されています。
大河ドラマ『光る君へ』の第39回では、彰子(見上愛さん)がのちに敦良(あつなが)親王となるふたり目の皇子を出産したあとに行われた「産養」の様子が描かれていました。そのシーンで、藤原道長(柄本佑さん)が「皇子さまのご誕生を寿(ことほ)いで、よき目を出したいと存じます」と、神妙な面持ちでサイコロを振っていたのが「攤」と呼ばれる行事です。詳細は不明ですが、出た目の多さを競ったと言われています。そうなるとサイコロゲームのチンチロリンのようなイメージですが、出目に占いの要素もあったようです。
【ビジネス雑談に役立つ平安時代の出産や新生児にまつわる「雑学」】
■平安時代の「出産」は死と隣り合わせの一大イベント
平安時代には、出産に際して5人にひとりの母親が亡くなったと言われています。それほど危険度が高かったのですね。当然、子どもも健康で生まれてくることは少なく、「母子共に健やか」な出産は、それだけでとにかくおめでたいものだったのです。
一般的な貴族の出産では、部屋全体を真っ白にしました。「白」には清浄、お清めの意味があったからです。お産そのものは、座ったままの座産が多かったようです。妊婦のお世話をする係の人が5〜6人はついていました。そのほかに、物の怪を退治するためのお経の声が響き渡り、悪いものを退治するために「散米(うちまき)」と呼ばれるお米が撒かれました。「弦(つる)打ち」と呼ばれる、弓の弦を引っ張って鳴らす魔除けの儀式も行われ、平安時代の出産は、かなり賑やかなものであったようです。
『光る君へ』第36回で描かれた彰子の出産シーンでも、僧侶たちの読経が響き渡る中、多くの貴族や女房たちが合掌し、物の怪が乗り移った寄座(よりまし。怨霊や物の怪を乗り移らせる人や人形)は奇声を上げ、「頭には邪気払いの米が雪のように降りかかった」と、紫式部が回想していました。
■「産養」のほかにも、平安時代の「出産後のセレモニー」ってあったの?
平安時代の出産は、母子共に死と隣り合わせ。それだけに、危険を乗り越えた出産後は、とてもたくさんのセレモニーが控えていました。ここでは、その主だったもの4つについて、ご紹介しましょう。
・臍(ほぞ)の緒
「臍の緒」は、漢字から推測できた人もいるのでは? これは「臍(へそ)の緒」を切る儀式のことです。このときへその緒を切る小刀を「竹刀(あおひえ)」と呼びました。難しい読みですね。そして、切る役目の人は、母方の近親者だったようです。『紫式部日記』には、敦成(あつひら)親王のへその緒を切る倫子(道長の妻。彰子の生母)の様子が描かれています。
・乳付け(ちつ-け)
「乳付け」は最初に乳を含ませるセレモニーです。
・御湯殿(おゆどの)の儀
平安時代の宮中や貴族におおいて、新生児の湯浴みの儀式を「御湯殿の儀」と言います。諸説ありますが、「御湯殿」は新生児に産湯をかける役割の女房をそう呼んだようです。そしてその介添え役は「御迎え湯」と呼ばれたとか。御湯殿の儀は1日2回、1週間ほど続き、儀式の最中は怨霊退散のため弓の弦を鳴らしたり、漢籍(中国の書物)を読み上げたりしたそうです。単なる沐浴というよりは、格式あるイベントだったのですね。
・五十日(いか)の祝い
「五十日の祝い」は、子どもが生まれて50日目に行う祝いの行事です。現代の「お食い初め」のルーツにあたり、平安時代に主として朝廷や貴族の間で行われました。父親か外祖父(母方の祖父)が、生まれた子に餅を食べさせる(実際には餅を入れた重湯を口に含ませるだけ)儀式が行われました。
■「産養」で行われた「碁」って?
碁は平安時代、男女問わず人気だったボードゲームです。現在の囲碁のことで、黒と白の石をマス目の上に交互に置き、広く囲ったほうが勝ち。ただの娯楽ではなく、人格などが表れる本才(ほんざい。教養)のひとつと考えられていたようで、管楽や和歌の「遊び」に加え、豪華な賞品を賭けた碁の対戦もよく行われました。碁と同じように、盤上ゲームである「双六」が庶民的な遊戯であるのに対して、碁には上品なイメージがあったそうです。文学作品に出る際には、打ち手や勝った側の身分や人柄などを暗示する小道具として使われました。
■新生児の平均的な大きさは?
現在、生まれたばかりの赤ちゃんの大きさの平均は、体重3000g、身長50cmです。厚生労働省のホームページによれば、1975(昭和50)年には3200gであった新生児の平均体重は年々少なくなり、2000(平成12)年には3050gと、さらに150g少なくなっています。
■新生児のほうが大人より「骨の数が多い」って知ってた?
大人の骨の総数は約200本ですが、新生児の骨の総数はおよそ350と言われています。理由は、骨は成長するにつれ結合していくため。一般に男性は18歳ごろ、女性は15〜16歳ごろまでに骨の融合は完了します。
***
平安時代、出産は母子共に死と隣り合わせの、一大イベントでした。そのため無事の出産は非常にめでたいことであり、だからこそ、多くの儀式で母と子の健康と幸せを祈り祝ったのです。そのイベントは、御邸(おやしき)のなかで行われる「臍の緒」から始まって「産養」まで続き、徐々に子の誕生が外部の人たちに知れ渡ることで情報公開されていきました。無事の出産はおめでたいことで、多くの人の祝意に包まれていたのです。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『日本国語大辞典』(小学館) /『デジタル大辞泉』(小学館) /『日本大百科全書 ニッポニカ』(小学館) /『平安 もの こと ひと 事典』(朝日新聞出版) /『はじめての王朝文化辞典』(角川文庫) /厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/syussyo-4/syussyo3-6.html) :