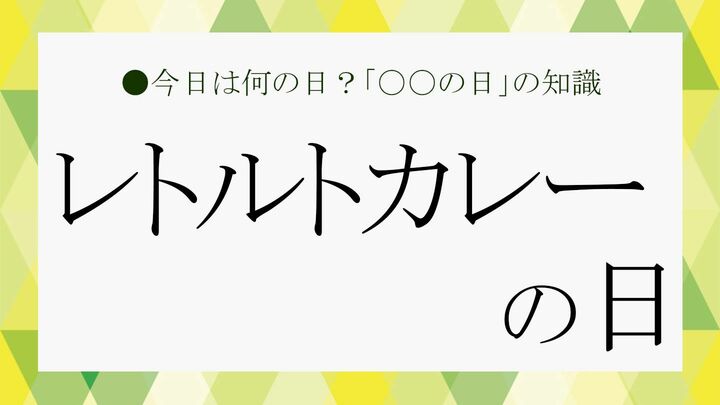2月12日は「レトルトカレーの日」だって、ご存知ですか? 記念日は語呂合わせであることが多いのですが「レトルトカレー」の語呂合わせ…ではなさそうです。ではなぜ? 今回はビジネス雑談の小ネタに使える「レトルトカレーの日」にまつわる雑学をお届けします!
【目次】
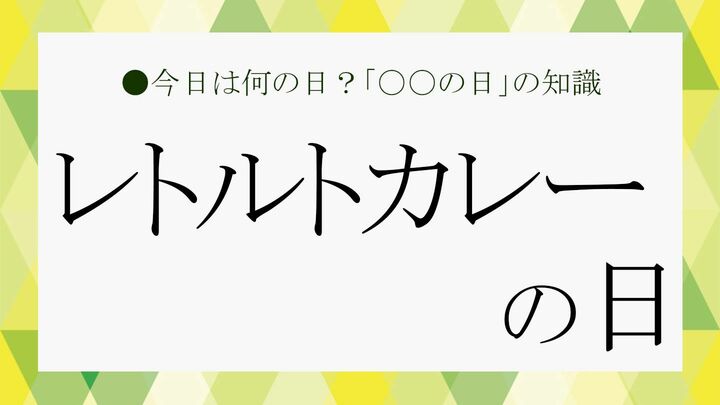
【「レトルトカレーの日」とは?「基礎知識」】
■「いつ」?「誰が」決めた?
2月12日は「レトルトカレーの日」です。食品メーカーの大塚食品株式会社が制定し、一般社団法人 日本記念日協会によって認定、登録されています。大塚食品と言えば、有名な……そう、あのカレーをつくっているメーカーです!
■「由来」は?
世界初となったレトルトカレー、「ボンカレー」が発売された日が1968(昭和43)年の2月12日。「レトルトカレーの日」は、これを記念して制定された記念日です。「ボンカレー」は今年(2025)で発売57周年!今も多くのカレーファンに愛され続けています。
【たくさんある!「カレー」にまつわる記念日】
■カレーの日
「カレーの日」は1月22日。カレーを製造する事業者の全国団体である「全日本カレー工業協同組合」が制定した記念日です。国民食と言われるまでに普及したカレーの、さらなる普及拡大を目指し、健康で豊かな食生活の実現に貢献するのが目的として掲げられています。日付は、1982年1月22日に、全国学校栄養士協議会が全国の学校給食の統一メニューとして「カレー」を提供したことにちなみます。
■ご当地レトルトカレーの日
「ご当地カレーの日」は、一般社団法人「ご当地レトルトカレー協会」が制定。全国各地にあるレトルトカレーを通して、各地域の魅力をより多くの人に知ってもらうことが目的です。日付の由来は、「カレーの日」が1月22日で「レトルトカレーの日」が2月12日であることから。1月、2月に続いて3月。さらに、22日、12日のつながりで2日として、3月2日が選ばれました。
■カツカレーの日
東京・銀座3丁目に本店がある老舗洋食店「銀座スイス」が制定したのが、「カツカレーの日」。日付は2月22日です。国民的人気メニューであるカレーライスにカツを乗せた「カツカレー」は、皆さんお馴染みですね。
カツカレーは、1948年に「銀座スイス」を訪れたプロ野球巨人軍の名二塁手の千葉茂氏のリクエストから誕生し、あっと言う間に全国に広まったそうです。「カツカレー発祥の店」として知られる同店の、記念日を通じてカツカレーのおいしさを全国でカツカレーを提供する店とともに盛り上げたいとの願いが込められています。日付は「銀座スイス」の創業日(1947年2月22日)に由来します。
■ゴーゴーカレーの日
石川県金沢市を拠点にカレー専門店「ゴーゴーカレー」を全国で展開する株式会社「ゴーゴーカレーグループ」が制定したのが「ゴーゴーカレーの日」です。カレーの魅力と食文化をより多くの人に広め、「ゴーゴーカレー」のファンとの結びつきを深めつつカレー業界全体に貢献することが目的。日付は、「ゴーゴーカレー」の1号店が2004年に東京・新宿にオープンした日であり、「ゴー(5)ゴー(5)」と読む語呂合わせから、5月5日が記念日となりました。
■クミンの日
カレーの香り付けスパイスとして普及しているクミン。この日を「クミンを使ったスパイスだけでカレーを作る日」にと制定したのはハウス食品株式会社です。日付は9(ク)と30(ミン)の語呂合わせに由来します。
■ボンカレーの日
実は2月12日は、「ボンカレーの日」でもあります。こちらも日本記念日協会により、認定、登録済みなんですよ。
【「レトルトカレー」にまつわる雑学】
■そもそも「レトルト」ってどういう意味?
「レトルト」の語源は、「加圧過熱殺菌をする釜」という意味のオランダ語です。加圧過熱殺菌とは、「熱と圧力をかけて殺菌する」ということ。そしてこの「熱と圧力」が、レトルトカレー誕生のキーワードにもなっているのです!
■大塚食品が掲げた「レトルトカレー」の絶対条件とは?
レトルトカレー開発当時、大塚食品が目標としていたのは、「一人前で、お湯で温めるだけで食べられるカレー、誰でも失敗しないカレー」の開発でした。そして、これを完成させるための絶対条件は「常温で長期保存が可能であること」「保存料を使わないこと」。 今では当たり前のように言われている安全・安心へのこだわりは、開発当初からずっと続く、変わらないものだったのですね!
レトルトカレー開発の最難関は、カレーを入れたパウチをレトルト釜に入れ、殺菌のための高温処理をすると、中身が膨らみ破裂してしまうことでした。熱と圧力の兼ね合いが難しかったのです。パウチの耐熱性、強度、中身の耐熱性、殺菌条件などのテストを繰り返し行い、試行錯誤の末、世界初の市販用レトルトカレーとして、「ボンカレー」を販売(阪神地区限定)したのが1968年2月12日。ただし、当時の「ボンカレー」は、ポリエチレン/ポリエステルの2層構造の半透明パウチであったために、光と酸素によって風味が失われてしまい、賞味期限は冬場で3か月、夏場で2か月でした。
■「ボンカレー」という名前に託された思いは?
「ボンカレー」が発売された1960年代、牛肉はとても高価なものでした。十分に確保するのが難しく「牛肉100%なんて夢のような贅沢!」と思われていた時代だったといいます。そんななか「ボンカレー」は牛肉100%にこだわり、とっておきのごちそうメニューとして食卓に提供されたのです。
「ボンカレー」というネーミングは、フランス語の[BON(よい、おいしい)]と英語の[CURRY(カレー)]を組み合わせた造語です。「おいしいカレー」という意味が込められています。
■「ボンカレー」発売当初の世間の反応は?
発売当初は半透明なパウチを使用していた「ボンカレー」。上記の通り、賞味期限も数か月と短かかったため、なかなか消費者には受け入れられず、期待されたほど、売りあげも伸びませんでした。「保存料を使わない、3分で食べられるおいしいカレーです」という説明も、「そんなはずはない」とか「腐らないのなら防腐剤が入っているのでは?」という反応がほとんど。しかも当時、外食の素うどん50〜60円の時代に、ボンカレーは1個80円。「高すぎる」というのが当時の反応だったのです。
■レトルトカレーとアポロ11号との意外な関係
もともとレトルト食品は、アメリカで開発された軍用の携帯食がはじまりでした。そして1969年(昭和44年)7月、アポロ11号が月面着陸に成功。このとき、宇宙飛行士が宇宙食としてレトルト食品を食べている映像が世界中に流れると、世界中にレトルト食品ブームが沸き起こりました。
大塚食品が宣伝用に製作した、女優の松山容子さんがボンカレーをもったホーロー看板の効果もあり、レトルトカレーは次第に一般家庭に浸透していきました。さらに1973年(昭和48年)に放送されたテレビCMが大ヒット。これはテレビドラマで大人気だった『子連れ狼』を元ネタに、落語家の三代目・笑福亭仁鶴(しょうふくてい にかく)師匠が、大五郎役の男の子に「ボンカレー」を与えるもの。「3分間待つのだぞ」というセリフは流行語にもなりました。
■レトルトカレー、「箱ごとレンジ」できるって知ってた?
「レトルトカレーは湯煎するもの」と思い込んでいませんか? 実は「箱ごとレンジ」することで、短い時間でソースも具材もムラなく温まり、おいしさもアップ。しかもお鍋に移し替えたりお湯を沸かしたりする手間がなく、洗いものも少なく済みます。しかも、湯せんするよりもエコなんです。
■「レトルトカレー」のプロが使う隠し味とは?
レトルトカレー・スープの通販を行う「NISHIKIYA KITCHENオンラインショップ」によれば、カレーの隠し味に向くベスト5は、はちみつ、味噌、赤ワイン、チョコレート、コーヒーなのだとか。使用するコツは、適切な分量を守ること。隠し味を入れすぎると、味のバランスが崩れてしまうこともあるそうです。
***
いかがでしたか? 忙しい日常で、さっと温めるだけで食べられるレトルト食品は、働く女性だけでなく、家族全員の心強い味方です。カレーに含まれるスパイスの香りは、食欲を刺激してくれますよね。美味しく時短で、ストレスフリーな毎日を!
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- 参考資料:『デジタル大辞泉プラス』(小学館) /大塚食品「ボンカレー」https://boncurry.jp /公式NISHIKIYA KITCHENオンラインショップhttps://nishikiya-shop.com/column/120?srsltid=AfmBOooD0cFYmhWb-YNEvMTQm-CNXhMRIuWd7-2r6heLvB1gkExriaIl :