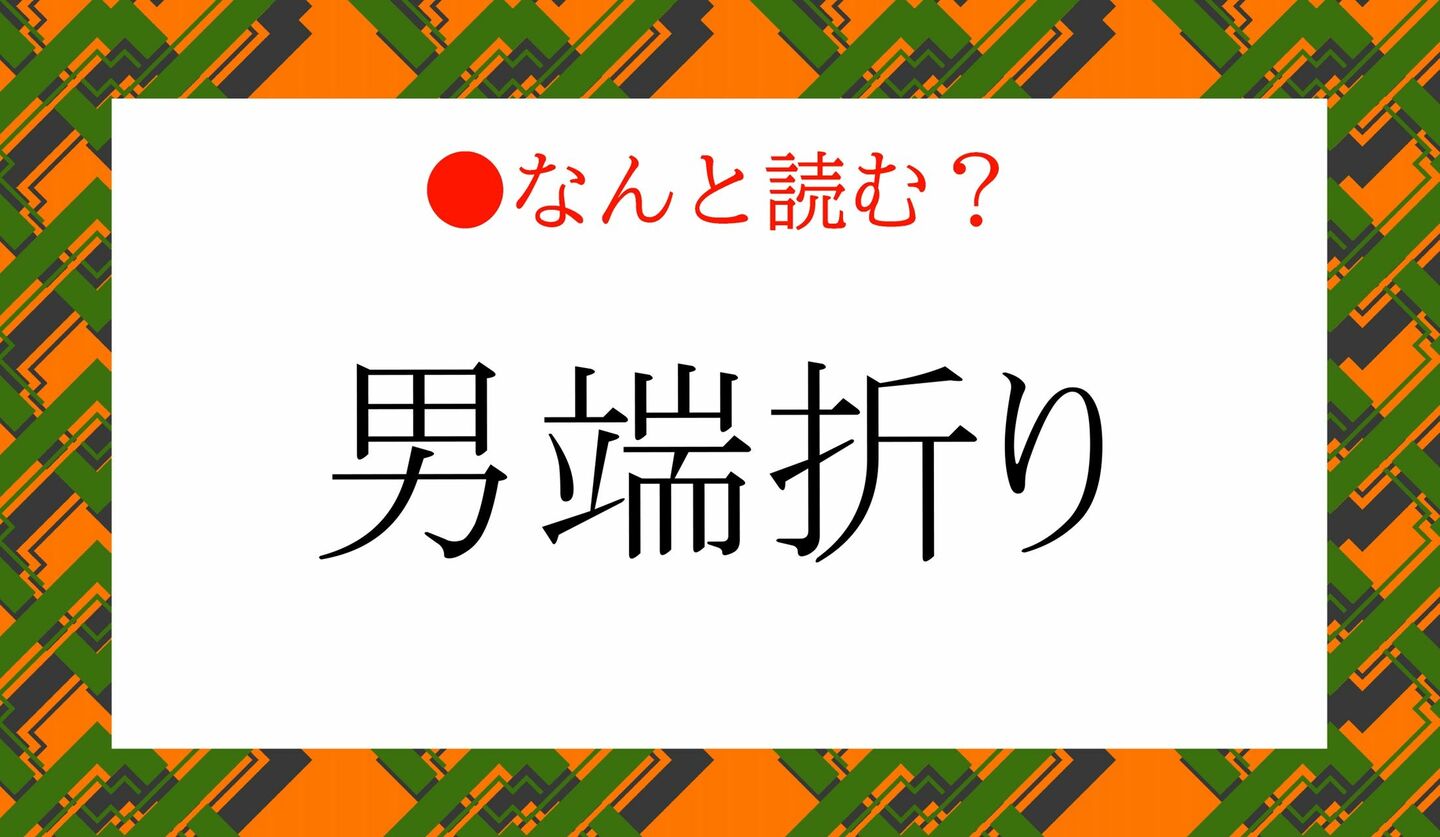「差しがね」「だんまり」「どんでん返し」…歌舞伎に由来する言葉はどれ?
明日・2月20日は『歌舞伎の日』です。1607(慶長12)年のこの日、出雲阿国(いずものおくに)が江戸城で徳川家康や大名らに、現在の歌舞伎のルーツとなる『かぶき踊り』を初めて披露した日、言われております。当時は「傾く(かぶく)」という言葉から名付けられた奇抜な舞踊から始まりましたが、多くの人々に愛され、支持されながら文化として醸成・進化し、現在の歌舞伎は、ユネスコの無形文化遺産にも登録されております。…というところで、本日1問目の日本語クイズとまいりましょう。
【問題1】歌舞伎由来の言葉はどれ?
以下の選択肢の日本語の中から、語源が歌舞伎であるものを選んでください。
1:差しがね
2:だんまり
3:どんでん返し
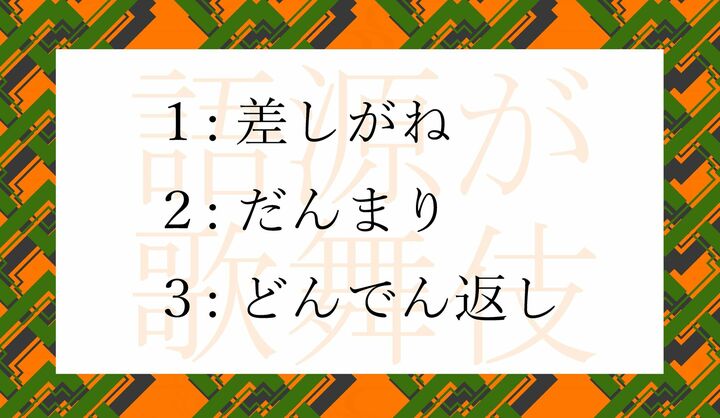
…さて、正解は?
※「?」画像をスクロールすると、正解が出てまいります。
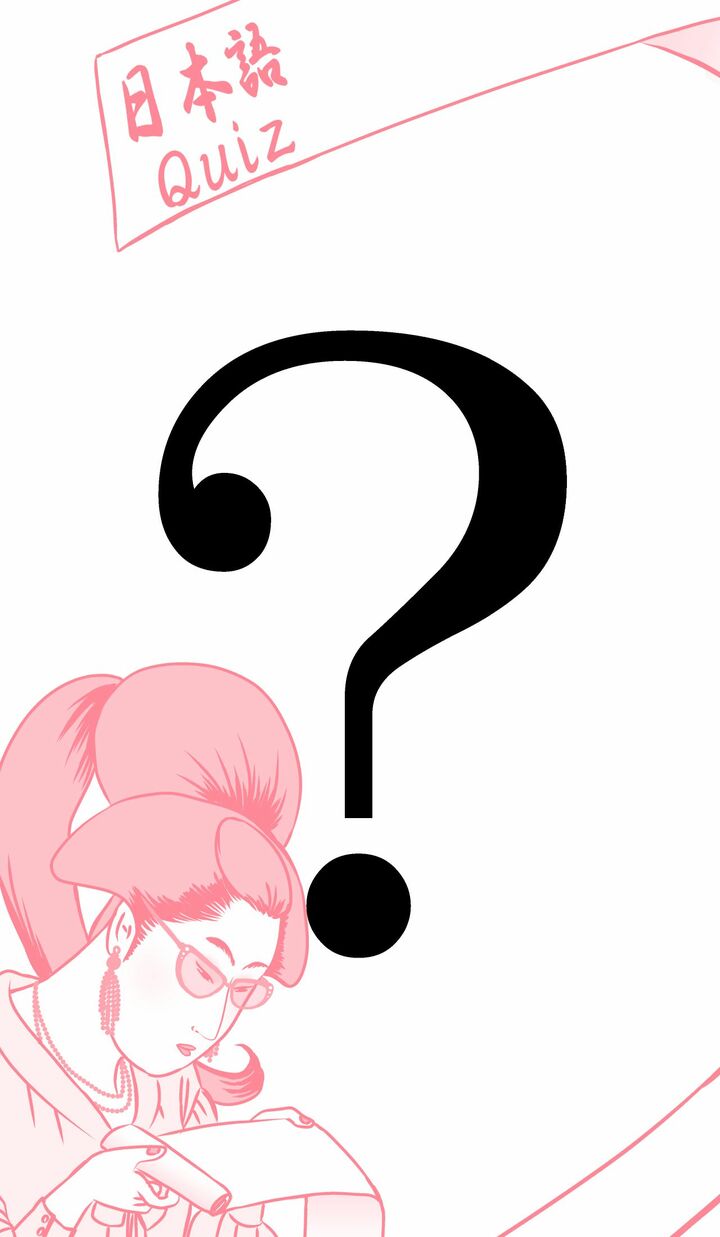
正解は… 1、2、3すべて です。
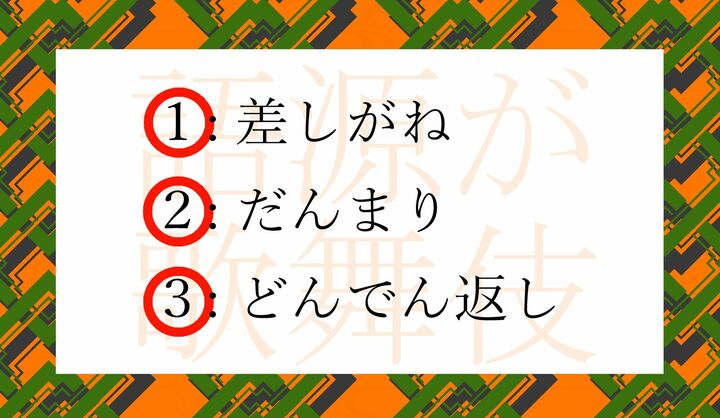
「陰で人に指図して操ること」という意味の「差しがね」という言葉は、もとは「歌舞伎の舞台で、作り物の蝶、鳥、人魂(ひとだま)などを操るための、黒塗りの細い竹竿の先端に針金を付けた道具」から転じた言葉です。
また、「ものを言わないこと」という意味の「だんまり」は、もとは「歌舞伎の演出で、暗闇のなかで登場人物が無言で探り合う様子を様式化したもの」から来ています。
そして、「話、形勢、立場などが逆転すること」という意味の「どんでん返し」は「歌舞伎の舞台装置で、場面転換に使うしかけが、どんでん、どんでん…と太鼓を叩く演出とセットで行われることが多いことから、ふたつが合わさって言われるようになった言い回し」です。日常で使っている言葉の中にも、歌舞伎の歴史が息づいた言葉がいろいろあるのですね。
さて2問目は、和服の着方に関する言葉のクイズです。
【問題2】「男端折り」ってなんと読む?
「男端折り」という日本語の正しい読み方をお答えください。
ヒント:「和服の後ろのすそをまくりあげて帯にはさむこと」です。
<使用例>
「あのエレガントな役者さんが、男端折りのいなせな魚屋を演じるなんて、おもしろい配役ね」
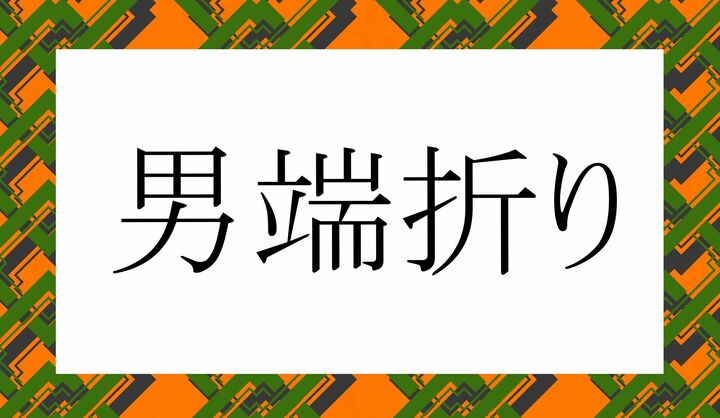
…さて、正解は?
※「?」画像をスクロールすると、正解が出てまいります。

正解は… 男端折り(おとこばしょ-り) です。
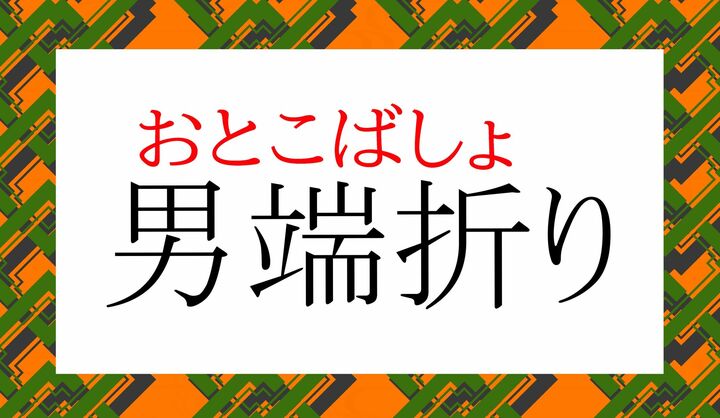
歌舞伎や時代劇の登場人物で、和服のすそをまくりあげて帯にひっかけ、ももひきを履いた足がにょきっと見えるような、ごくカジュアルな着こなし、ごらんになったことがあると思います。江戸時代の町人で、職人など、威勢のいい男性ならではの、動きやすさを追求した着方です。あの「着物のうしろのすそをまくりあげ、帯にはさんだ、市井の威勢のいい男性ならではの着こなし」が「男端折り」です。この着方をしている歌舞伎の登場人物で代表的なのは、町人で魚屋の「一心太助(いっしんたすけ)」などです。
***
本日は、2月20日『歌舞伎の日』にちなんで、
・差しがね
・だんまり
・どんでん返し
などの、歌舞伎に語源をもつ言葉や、
・男端折り(おとこばしょ-り)
の読み方、言葉の背景などをおさらいいたしました。
- TEXT :
- Precious.jp編集部
- BY :
- 参考資料:『日本大百科全書(ニッポニカ)』『精選版日本国語大辞典』『デジタル大辞泉』(小学館)/大阪府立図書館ホームページ/歌舞伎公式総合サイト歌舞伎美人ホームページ/『漢字ペディア』(日本漢字能力検定協会)
- ILLUSTRATION :
- 小出 真朱